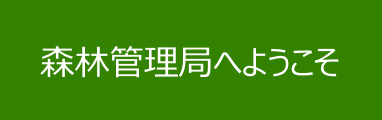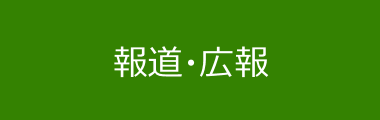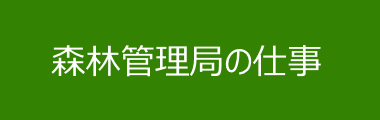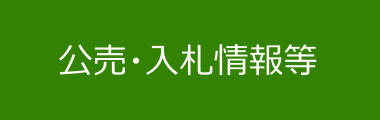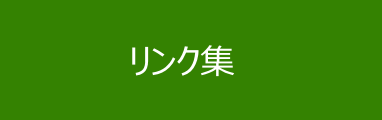中部森林技術交流発表集
平成16年度~令和5年度に中部森林管理局で開催された森林技術交流発表会の発表集をご覧いただけます。
・ 令和5年度
・ 令和4年度
| 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 1 | 森林技術 | 01 新しい林業への挑戦~クラッシャー地拵えの検証~(PDF : 1,581KB) | 北信署 | 前田賢吾 岩塚伸人 |
| 2 | 森林技術 | 02 ヒノキコンテナ苗と下刈省略の組合せによる初期保育技術の開発(PDF : 1,208KB) | 技セン | 棚橋和彦 |
| 3 | 森林技術 | 03 帯状伐採による育成複層林施業について(PDF : 1,002KB) | 木曽署 | 内藤貴幸 内田ゆき奈 |
| 4 | 森林技術 | 04 ブランド材「段戸SAN」の10年間の販売実績を振り返って(PDF : 646KB) | 愛知所 | 舟木 武 宮路 聡 |
| 5 | 森林技術 | 05 全天球カメラを活用した林況調査業務の効率化の取組について (PDF : 572KB) | 中信署 | 南坂博和 |
| 6 | 森林技術 | 06 姥ナギ沢復旧工事と緑化に向けて(PDF : 1,290KB) | 東濃署 | 星野裕太 向澤大樹 山口 元 |
| 7 | 森林保全 | 07 クマ被害の現状と新たな施業方法の考察(PDF : 1,603KB) | 飛騨署 | 川谷亮太 松井邦彦 |
| 8 | 森林保全 | 08 ブロックディフェンス設置箇所でのニホンジカ捕獲の取組(PDF : 1,053KB) | 南信署 | 井上智広 後藤伶央 |
| 9 | 森林ふれあい | 09 高山植物等保護パトロール50年の歩み(PDF : 505KB) | 富山署 | 住 裕介 太田祥平 |
| 10 | 森林ふれあい | 10 森林経営管理制度を踏まえた市町村支援について(PDF : 1,929KB) | 岐阜署 | 松下康弘 |
| 下呂市 | 小池徳一 | |||
| 11 | 森林保全 | 11 水源林造成事業地におけるくくりわなによる誘引捕獲の結果について(PDF : 999KB) | (国研)森林研究・整備機構 森林整備センター中部整備局 |
小林佳央理 清水 樹 |
| (国研)森林研究・整備機構 森林整備センター 中部整備局 津水源林整備事務所 |
小山貴則 | |||
| 12 | 森林保全 | 12 ヘアトラップを用いた木曽地域のツキノワグマの集団遺伝学的構造(PDF : 957KB) | 筑波大学大学院理工情報生命学術院博士後期課程1年 | 小井土凛々子 |
| 株式会社環境アセスメントセンター | 柳生将之 中村明日香 |
|||
| 長野県環境保全研究所研究員 | 黒江美紗子 | |||
| 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所准教授 | 津田吉晃 | |||
| 13 | 森林保全 | 13 松本市四賀地区、奈川地区における地域住民による野生動物と獣害対策に対する意識(PDF : 1,011KB) | 岐阜大学教育学部准教授 | 橋本 操 |
| 筑波大学大学院理工情報生命学術院博士前期課程2年 筑波大学大学院理工情報生命学術院博士前期課程1年 筑波大学生命環境系助教 |
佐々木悠理 原田康多 山下亜紀郎 |
|||
| 14 | 森林保全 | 14 山野草の保全遺伝学的研究:カンアオイ属ウスバサイシン節での事例(PDF : 785KB) | 筑波大学大学院理工情報生命学術院博士前期課程1年 | 新 真澄 |
| 東北大学植物園助教 | 伊藤拓朗 | |||
| 長野県環境保全研究所主任研究員 | 尾関雅章 | |||
| 東北大学植物園教授 | 牧 雅之 | |||
| 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所准教授 | 津田吉晃 | |||
| 15 | 森林ふれあい | 15 長野県木曽郡の森林経営管理制度運営における広域連合の役割(PDF : 1,169KB) | 筑波大学大学院理工情報生命学術院博士前期課程1年 筑波大学生命環境系准教授 |
江田星來 立花 敏 |
| 東京農業大学地域環境科学部助教 | 茂木もも子 | |||
| 16 | 森林ふれあい | 16 中部森林管理局と取り組む人材育成を見据えた山岳森林教育(PDF : 431KB) | 筑波大学生命環境系 山岳科学センター菅平高原実験所准教授 |
津田吉晃 |
| 17 | 森林技術 | 17 晩秋に植栽したヒノキ実生コンテナ苗の活着と状態(PDF : 795KB) | 岐阜県森林研究所専門研究員 岐阜県森林研究所森林環境部長 |
渡邉仁志 茂木靖和 |
| 18 | 森林技術 | 18 1年生ヒノキコンテナ苗の植栽初期の成長に及ぼす元肥の影響(PDF : 261KB) | 岐阜県森林研究所森林環境部長 岐阜県森林研究所専門研究員 |
茂木靖和 渡邉仁志 |
| 19 | 森林技術 | 19 モバイル型レーザを用いた幹曲線式の作成(PDF : 669KB) | 信州大学農学部4年 | 光門舞花 |
| 20 | 森林技術 | 20 携帯電話の通信圏外における通信手段確保の取組)(PDF : 935KB) | 岐阜県立森林文化アカデミー技術課長補佐兼スマート林業推進係長 | 大島愛彦 |
| 株式会社JVCケンウッド上席課長 | 田中秀樹 |
・ 令和3年度
・ 令和2年度
・ 令和元年度
・ 平成30年度
・ 平成29年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 29 | 1 | 森林技術 | 付属路の開設による効率的な生産事業への取組 | 北信森林管理署 | 西方雄一郎、岡本守 |
| 29 | 2 | 森林技術 | 自然環境に配慮したコンテナ苗による治山緑化工 | 中信森林管理署 | 帆足郁、向山剛 |
| 29 | 3 | 森林技術 | 金沢山ヒノキ林分における漸伐作業の取組 | 南信森林管理署 | 竹内智絵、源田聡子 |
| 信州大学農学部 | 松井美希子 | ||||
| 信州大学農学部助教 | 斎藤仁志 | ||||
| 信州大学農学部教授 | 植木達人 | ||||
| 29 | 4 | 森林技術 | 木曽ヒノキ天然更新補助に係る取組 ~ササ処理方法からみえてきたもの~ |
木曽森林管理署 | 早川幸治 |
| 森林総合研究所 | 酒井武、星野大介、齋藤智之 | ||||
| 木曽森林ふれあい推進センター | 黒田誠 | ||||
| 29 | 5 | 森林技術 | 多様な森林への誘導に向けたモデル林における取組 | 南木曽支署 | 南坂博和 |
| 29 | 6 | 森林技術 | 自然侵入促進工による林地復旧の取組 | 伊那谷総合治山事業所 | 佐藤義和 |
| 株式会社愛紘 | 原大吾郎 | ||||
| 29 | 7 | 森林技術 | 国有林における無人航空機の計測的活用 | 飛騨森林管理署 | 三谷果穂、本間丈瑠 |
| 29 | 8 | 森林技術 | ドローンを活用するために ~岐阜森林管理署の取組~ |
岐阜森林管理署 | 平杤潤己 |
| 29 | 9 | 森林技術 | 高標高地、遠隔地における森林整備等の課題整理 | 富山森林管理署 | 千村知博、村中健彦 |
| 29 | 10 | 森林技術 | 列状間伐がヒノキの成長に与える影響について ~樹幹解析による成長量の評価~ |
森林技術・支援センター | 三村晴彦、堤隆博 |
| 29 | 11 | 森林技術 | ササの一斉開花に伴う森林への影響について | 愛知森林管理事務所 | 野口和幸 |
| 森林総合研究所 | 齋藤智之 | ||||
| 29 | 12 | 森林保全 | 岐阜森林管理署のニホンジカ対策 ~職員の意識向上と職員捕獲の取組~ |
岐阜森林管理署 | 小原弘明、日吉晶子 |
| 29 | 13 | 森林ふれあい | 裏木曽登録ガイド制度の取組について | 東濃森林管理署 | 伊藤章代、安藤康生 |
| 29 | 14 | 森林ふれあい | 100年先の森林づくり発表会の開催 ~国・県・市が連携した地域での取組~ |
岐阜森林管理署 | 大島愛彦 |
| 29 | 15 | 森林ふれあい | 王滝村における森林・林業体験交流促進対策事業の取組について | 木曽森林管理署 | 松原正志、瀧本りりこ |
| 29 | 16 | 森林ふれあい | 長野県軽井沢町における藪刈り作業 ~官と民、都市と農村、専門家と一般住民、世代を超えた交流・協働を目指して~ |
東信森林管理署 | 下岡正幸 |
| 軽井沢西地区国有林藪刈り実行委員会 | 打越綾子 | ||||
| 29 | 17 | 森林ふれあい | 城山における生物モニタリング | 長野県林業大学校 | 南坂拓杜 |
| 29 | 18 | 森林技術 | チェーンソー伐倒作業を中心においた技術マニュアルの制作 -海外とのルール比較について- |
長野県林業大学校 | 高山亮介、藤原涼太、堀井拓人 |
| 29 | 19 | 森林保全 | 北アルプス雲ノ平における10カ年実施した官民学協働による植生復元活動について | 雲ノ平山荘 | 伊藤二朗 |
| 東京農業大学准教授 | 下嶋聖 | ||||
| 富山森林管理署 | 千村知博 | ||||
| 29 | 20 | 森林保全 | 岐阜県東白川村国有林のヒノキ人工林における水源涵養機能改善に向けた調査研究 | サントリー | 川崎雅俊、安部豊 |
| 筑波大学教授 | 恩田裕一 | ||||
| 29 | 21 | 森林保全 | シカ食害地の防除方法の比較検討について | 森林整備センター長野水源林整備事務所 | 高橋克明、池神真奈美 |
| 29 | 22 | 森林保全 | 「南信州鳥獣害対策アカデミー」による地域全体の情報共有とスキルアップセミナー | 長野県南信州地域振興局 | 久保田淳 |
| 29 | 23 | 森林技術 | 原点回帰:屋根型道に学ぶ丈夫で安価な道づくり | 岐阜県飛騨農林事務所 | 中谷和司 |
| たかやま林業・建設業協同組合 | 長瀬雅彦 | ||||
| 29 | 24 | 森林技術 | 根鉢の低いヒノキ・コンテナ苗の育苗と植栽初期の成長 | 岐阜県森林研究所 | 渡邉仁志、茂木靖和 |
| 森林技術・支援センター | 三村晴彦、堤隆博 | ||||
| 29 | 25 | 森林技術 | 1.5年生ヒノキ・コンテナ苗の育成条件の検討 | 岐阜県森林研究所 | 茂木靖和、渡邉仁志 |
| 森林技術・支援センター | 三村晴彦 | ||||
| 29 | 26 | 森林技術 | 森林路網がスギ人工林内の植物種多様性に及ぼす影響 | 信州大学大学院 | 孝森博樹 |
| 29 | 27 | 森林技術 | ヒノキ漸伐林における終伐後の林分状況と造林費の推定 -金沢山国有林を事例として- |
信州大学農学部 | 松井美希子 |
| 信州大学農学部助教 | 斎藤仁志 | ||||
| 信州大学農学部教授 | 植木達人 | ||||
| 南信森林管理署 | 藤井勝、竹内智絵 | ||||
| 29 | 28 | 森林技術 | ヒノキ人工林における枝と死節の分布特性 | 岐阜大学自然科学技術研究科 | 山本敦也 |
| 株式会社佐合木材 | 岩室宏基 | ||||
| 岐阜大学応用生物科学部 | 石田仁 | ||||
| 29 | 29 | 森林技術 | 県産材でつくる画用木炭 | 岐阜県立森林文化アカデミー | 境田夕姫 |
| 29 | 30 | 森林技術 | 赤外線センサーカメラを使用した演習林内の動物の生態調査 | 木曽青峰高校 | 磯尾ちなみ、黑澤佳苗 |
| 演習林内でのモノレール活用と、モノレールと林道の交差点の施工方法について | 木曽青峰高校 | 児野稜、坪田智大 | |||
| 29 | 31 | 森林ふれあい | 飛騨の森林から魅力発信! ~知る・学ぶ・伝える~ |
飛騨高山高校 | 谷腰怜央、岩本芽依 |
| 29 | 32 | 森林ふれあい | 教えて学ぶ森林活用 ~一膳の箸から学ぶ森林の役割や大切さの啓発~ |
長野県下高井農林高等学校 | 大平悠斗、小山竜生、佐治行喜 |
・ 平成28年度
・ 平成27年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 27 | 1 | 森林技術 | 奈良本山ヒノキ人工林天然更新試験地における施業について | 東信森林管理署 | 畠山弘一 |
| 信州大学大学院農学研究科 | 大塚大 | ||||
| 信州大学農学部助教 | 斎藤仁志 | ||||
| 信州大学農学部教授 | 植木達人 | ||||
| 27 | 2 | 森林技術 | カラマツコンテナ苗の成長調査について | 南信森林管理署 | 大溝敏哉、原田 光基 |
| 27 | 3 | 森林技術 | コンクリート構造物施工困難箇所における改良工事の取組事例 | 木曽森林管理署 | 守屋徹郎、吉越秀一 |
| 27 | 4 | 森林技術 | 7.9南木曽町豪雨災害からの復旧 ~災害直後からの経過と対応~ | 木曽森林管理署南木曽支署 | 祐成亮一、中村信吾 |
| 27 | 5 | 森林技術 | 鳶ヶ巣大崩壊地の自然再生緑化への取り組み ~鳶ヶ巣自然再生緑化戦略~ | 伊那谷総合治山事業所 | 中屋忍 |
| 有限会社エコ・プロ | 島田洋治 | ||||
| 27 | 6 | 森林技術 | 里山における山腹崩壊地の復旧について | 愛知森林管理事務所 | 佐藤義和 |
| 27 | 7 | 森林技術 | ヒノキコンテナ苗の植栽功程調査について | 森林技術・支援センター | 三村晴彦 |
| 岐阜森林管理署 | 大林誠司 | ||||
| 岐阜県森林研究所 | 渡邉仁志、茂木靖和 | ||||
| 27 | 8 | 森林技術 | 植栽後の初期成長に優れるヒノキ・コンテナ苗の育成条件の検討 | 岐阜県森林研究所 | 茂木靖和、渡邉仁志 |
| 森林技術・支援センター | 三村晴彦 | ||||
| 27 | 9 | 森林技術 | ヒノキ・コンテナ苗の活着および初期成長に及ぼす植栽時期の影響 | 岐阜県森林研究所 | 渡邉仁志、茂木靖和 |
| 森林技術・支援センター | 三村晴彦、千村知博 | ||||
| 27 | 10 | 森林技術 | 低コスト造林に向けた取り組み | 飛騨森林管理署 | 齋藤由晃、木村有子 |
| 27 | 11 | 森林技術 | 二次林及び針広混交林におけるウダイカンバの活用を目指して | 富山森林管理署 | 松原正志、古賀有紀 |
| 27 | 12 | 森林技術 | 30年を越えた本数密度実験林の比較 | 森林技術・支援センター | 千村知博 |
| 27 | 13 | 森林技術 | 人工林ヒノキ高齢木の樹幹解析結果について -赤沼田天保ヒノキ植物群落保護林の事例- | 岐阜森林管理署 | 細江将樹 |
| 森林技術・支援センター | 三村晴彦 | ||||
| 27 | 14 | 森林技術 | ヒノキ天然林における結実豊凶と小面積皆伐後の実生の消長 | 木曽森林管理署 | 久保喬之、今井 歩 |
| 27 | 15 | 森林技術 | 御岳 トウヒ・シラベ天然生林 林分成長固定試験地 ~60年間の推移~ | 森林技術・支援センター | 千村知博 |
| 27 | 16 | 森林技術 | 高齢ヒノキの樹高成長量およびそれと幹肥大成長量の関係 | 岐阜県立森林文化アカデミー教授 | 横井秀一 |
| 森林技術・支援センター | 三村晴彦 | ||||
| 27 | 17 | 森林技術 | 航空レーザーデータを活用した樹高・本数密度の把握手法の提案 | 岐阜県立森林文化アカデミー | 飯嶋郁雄 |
| 27 | 18 | 森林技術 | カラマツ天然更新林分における間伐時の生産性 | 信州大学農学部 | 松永宙樹 |
| 信州大学農学部助教 | 斎藤仁志 | ||||
| 信州大学農学部教授 | 植木達人 | ||||
| 27 | 19 | 森林技術 | 多機能な森林業への転換 | たかやま林業・建設業協同組合 | 長瀬雅彦 |
| 27 | 20 | 森林保全 | イヌワシ生息地の森林環境保全整備事業箇所における餌動物の利用状況 | 株式会社環境アセスメントセンター | 水上貴博 |
| 東信森林管理署 | 森孝之 | ||||
| 27 | 21 | 森林保全 | 南アルプス山麓におけるモバイルカリングの取組 | 株式会社野生動物保護管理事務所 | 奥村忠誠 |
| 南信森林管理署 | 谷澤功志 | ||||
| 27 | 22 | 森林保全 | ニホンジカ囲いワナによる効果的な捕獲について | 中部森林管理局計画課 | 大野裕康 |
| 株式会社ForestersPRO | 高橋聖生 | ||||
| 27 | 23 | 森林保全 | 立木利用防止シカ柵の設置試験について | 東濃森林管理署 | 佐々木伸也 |
| 27 | 24 | 森林保全 | 南木曽支署におけるニホンジカ対策の取組について -プロジェクトチームによる活動- | 木曽森林管理署南木曽支署 | 古田義一、早川 幸治 |
| 27 | 25 | 森林保全 | 長野県における野生鳥獣被害防止対策 | 長野県林業大学校 | 三石太希 |
| 27 | 26 | 森林保全 | 水源林造成事業におけるクマハギ防止対策について | 国立研究開発法人森林総合研究所森林整備センター 中部整備局富山水源林整備事務所 | 丸山慧 |
| 27 | 27 | 森林保全 | 演習林でのモノレール活用 part3 | 長野県木曽青峰高等学校 | 宮地栄多、奥野真基、中島翔太、長谷川大輝 |
| 27 | 28 | 森林ふれあい | UAV(無人航空機)を活用した調査業務の効率化について | 中信森林管理署 | 東川俊彦 |
| 株式会社クエストコーポレーション | 神戸博之 | ||||
| 27 | 29 | 森林ふれあい | 国有林を活用した「下呂の森を巡るツアー」の開催 ~地域連携の視点から~ | 岐阜森林管理署 | 河原誠二、平杤潤己 |
| 27 | 30 | 森林ふれあい | 木曽の伝統・漆に学ぶ | 長野県林業大学校 | 湯澤充尋 |
| 27 | 31 | 森林ふれあい | 材木屋が考える6次産業化 -DIYユーザー向け木材の販売の可能性の検証- | 岐阜県立森林文化アカデミー | 松葉壮平 |
・ 平成26年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 26 | 1 | 森林技術 | 飛騨地域における民国の連携の取り組み | 飛騨森林管理署 | 稲垣正紀 |
| 岐阜県飛騨農林事務所 | 中谷和司 | ||||
| 26 | 2 | 森林技術 | 欧州型林業モデル林構築の取組み | たかやま林業・建設業協同組合 | 長瀬雅彦 |
| 26 | 3 | 森林技術 | コンテナ苗植栽技術の開発・普及に向けた取組 | 中信森林管理署 | 堀内志保、青島雅俊 |
| 26 | 4 | 森林技術 | ヒノキ・コンテナ苗の植栽功程に及ぼす傾斜の影響および初期成長 | 岐阜県森林研究所 | 渡邉仁志、茂木靖和 |
| 森林技術・支援センター | 三村晴彦、千村知博 | ||||
| 26 | 5 | 森林技術 | 林業の労働災害は何故起こるのか?~事業体の災害分析からの提言~ | 岐阜県立森林文化アカデミー | 笠木遼一 |
| 26 | 6 | 森林技術 | 中規模森林所有者が行う立木の在庫管理 | 岐阜県立森林文化アカデミー | 竹川大登 |
| 26 | 7 | 森林技術 | 岐阜・愛知・富山県のスギ高齢人工林の林分構造 | 岐阜県立森林文化アカデミー | 横井秀一 |
| 森林技術・支援センター | 三村晴彦 | ||||
| 26 | 8 | 森林技術 | 老齢木曽ヒノキ天然生林における林冠木の成長に及ぼすサイズ-空間構造の影響 | 信州大学大学院農学研究科 | 齋藤大 |
| 信州大学学術研究院農学系 | 城田徹央、岡野哲郎 | ||||
| 26 | 9 | 森林技術 | 複層林の上木伐採における下木への影響調査について-舞台峠国有林のヘリコプター集材における事例- | 森林技術・支援センター | 三村晴彦 |
| 26 | 10 | 森林技術 | 漸伐作業終伐時の更新木の損傷 | 信州大学農学部 | 大塚大、斎藤仁志、植木達人 |
| 26 | 11 | 森林技術 | 木曽地域における先進的林業機械導入への取組 | 木曽森林管理署 | 依田直紀 |
| 木曽森林組合 | 大久保一彦 | ||||
| 26 | 12 | 森林技術 | トータルコスト削減への挑戦!~伐・造一貫作業システムin愛知~ | 愛知森林管理事務所 | 鈴木健二、桑原優太 |
| 26 | 13 | 森林技術 | 主索ウィンチ付きスイングヤーダと繊維ロープ導入による索張り距離の延長と集材作業の安全化・効率化 | 新城森林組合 | 白井漸 |
| 26 | 14 | 森林技術 | 伐採・造林一貫作業システムにおける繊維ロープとタワー接地型スイングヤーダ適応の可能性~伐・造一貫作業システムin愛知~ | 名古屋大学大学院生命農学研究科 | 渡辺亮介 |
| 26 | 15 | 森林技術 | 民国連携による緊急災害時の復旧対策(蕨野沢災害関連緊急治山工事の事例) | 北信森林管理署 | 小田切英市、谷口直幸 |
| 26 | 16 | 森林技術 | カラマツ製治山施設の劣化調査の結果 | 長野県林業総合センター | 山内仁人、今井信 |
| 26 | 17 | 森林技術 | 中川地区民有林直轄治山事業の概成について | 伊那谷総合治山事業所 | 立邊真悟、村田則幸 |
| 26 | 18 | 森林技術 | 安定した森林を目指して~スイスフォレスターに学ぶ、環境的にも経済的にも持続可能な森林づくり~ | 岐阜県立飛騨高山高等学校 | 今井歩、高原聖、荒井良、釜部佑太 |
| 26 | 19 | 森林技術 | 地すべりを知る~減災に向けた防災教育の提言~ | 長野県林業大学校 | 齋藤悠樹 |
| 26 | 20 | 森林保全 | 北アルプス南部地域における中信森林管理署のニホンジカ対策について | 中信森林管理署 | 小山勉、渡澤徹 |
| 26 | 21 | 森林保全 | 木曽駒ヶ岳における植生復元作業について(10年間の取組み) | 木曽森林ふれあい推進センター | 小林伸雄 |
| 東京コンサルタンツ株式会社 | 藤田淳一 | ||||
| 26 | 22 | 森林保全 | ニホンジカ対策における薬剤防除の比較試験 | 森林技術・支援センター | 千村知博 |
| 26 | 23 | 森林保全 | 七宗国有林におけるニホンジカ対策 | 岐阜森林管理署 | 加藤里実、河原誠二 |
| 26 | 24 | 森林保全 | 金華山国有林における半寄生植物ツクバネの分布と地形要因 | 岐阜大学大学院応用生物科学研究科 | 荒井亮一 |
| 岐阜大学応用生物科学部 | 加藤正吾 | ||||
| 26 | 25 | 森林ふれあい | よりよいパートナーを目指して | 名古屋林業土木協会古川支部 | 柳七郎 |
| 名古屋林業土木協会岐阜支部 | 五十君正人 | ||||
| 26 | 26 | 森林ふれあい | 遊々の森での活動を振り返って~多摩市民の森・フレンドツリー ~ | 多摩市立八ヶ岳少年自然の家 | 五味直喜 |
| 南信森林管理署 | 下城大作 | ||||
| 26 | 27 | 森林ふれあい | 竹間伐材の有効利用 | 愛知県立田口高等学校 | 稲垣純平、安藤裕路 |
| 26 | 28 | 森林ふれあい | 木育に対するマネジメント的考察~企業でも出来る木育とは~ | 長野県林業大学校 | 森円佳 |
| 26 | 29 | 森林ふれあい | 「信州 山の日」の取組について | 長野県林務部 | 井出政次 |
・ 平成25年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 25 | 1 | 森林技術 | 伐採・造林一貫作業システムについて(中間報告) | 北信森林管理署 | 森田直宏、木内重明 |
| 信州大学農学部 | 大塚大 | ||||
| 25 | 2 | 森林技術 | 治山工事における県産材コンクリート型枠合板の実証的施工について | 中信森林管理署 | 長濱健、岡庭敏夫 |
| 25 | 3 | 森林保全 | 白馬岳の山火事跡地のモニタリング調査について | 中信森林管理署 | 有賀茂 |
| 信州大学山岳科学総合研究所 | 佐々木明彦、高橋耕一、鈴木啓助 | ||||
| 25 | 4 | 森林技術 | 間伐材を利用した木製治山ダムの施工について | 南信森林管理署 | 澤口章一、中屋忍 |
| 25 | 5 | 森林技術 | 高齢級人工林ヒノキのブランド化について | 木曽森林管理署 | 黒澤友大 |
| 木曽官材市売協同組合 | 鈴木隆志 | ||||
| 25 | 6 | 森林技術 | コンテナ苗の普及に向けた取り組みについて | 木曽森林管理署南木曽支署 | 三村晴彦、吉村芙美子 |
| 森林技術・支援センター | 千村知博 | ||||
| 25 | 7 | 森林技術 | 急傾斜地における法枠工の経過と勾配緩和網の導入について | 富山森林管理署 | 竹内智絵 |
| 日本植生株式会社 | 秋田好弘 | ||||
| 25 | 8 | 森林技術 | 民国連携による市町村森林整備計画のブラッシュアップについて第一ステージ指標林の設定) | 飛騨森林管理署 | 日置順昭 |
| 岐阜県飛騨農林事務所 | 中谷和司 | ||||
| 25 | 9 | 森林ふれあい | 岐阜県恵那農林事務所と東濃森林管理署との連携 | 東濃森林管理署 | 大野裕康 |
| 25 | 10 | 森林技術 | 中部森林管理局管内における高齢ヒノキ人工林の林分構造 | 森林技術・支援センター | 早川幸治 |
| 岐阜県立森林文化アカデミー | 横井秀一 | ||||
| 25 | 11 | 森林技術 | シカの不嗜好植物との混植によるヒノキ苗の食害軽減効果の検証 | 森林技術・支援センター | 千村知博 |
| 岐阜大学応用生物科学部 | 安藤正規 | ||||
| 25 | 12 | 森林技術 | ササ生地におけるコンテナ苗を活用した更新の試み | 森林技術・支援センター | 早川幸治 |
| 25 | 13 | 特別発表 | コナラの胸高直径からシイタケ原木・薪の収穫量を推定する | 岐阜県立森林文化アカデミー | 田中一徳 |
| 25 | 14 | 特別発表 | フクシマの林業従事者が安心して働ける職場環境づくり | 岐阜県立森林文化アカデミー | 渡邉篤慶 |
| 25 | 15 | 特別発表 | 長野県西部地震に伴う御岳土石流跡地における約30年間の植生遷移 | 信州大学農学部 | 堀井涼香、北原曜、小野裕 |
| 25 | 16 | 特別発表 | 航空写真とLiDARデータを用いた岡谷市横川地区における資源量推定 | 信州大学農学部 | 本村亜紀、加藤正人 |
| 長野県林業総合センター | 戸田堅一郎 | ||||
| 25 | 17 | 特別発表 | 木曽地方三浦実験林におけるヒノキ天然更新に微地形と土壌が及ぼす影響 | 信州大学農学部 | 森本壮一郎 |
| 25 | 18 | 特別発表 | 木質成分のアルコール抽出試験~木材需要拡大への提案~ | 長野県林業大学校 | 古田啓悟 |
| 25 | 19 | 特別発表 | 狩猟サミット報告~立ち上がる若手ハンターたち~ | 長野県林業大学校 | 高津勇佑 |
| 25 | 20 | 特別発表 | 未来へつなぐ森林づくり | 岐阜県立飛騨高山高等学校 | 纐纈樹、田立達也、長本健、西野一也、杉原俊介、南英明、島本翔太 |
| 25 | 21 | 特別発表 | ニホンジカによる林業被害の対策方法を探る~枝条巻き・テープ巻きの効果の検証~ | 岐阜県立岐阜農林高等学校 | 小畑晃、後藤洋哉 |
| 25 | 22 | 特別発表 | 間伐材の有効利用~木材燃料「アツマル」の開発と普及~ | 愛知県立田口高等学校 | 寺田美里、両星達也 |
| 25 | 23 | 特別発表 | CS立体図を活用した作業路の線形の検証について | 長野県林業総合センター | 高橋太郎 |
| 25 | 24 | 特別発表 | 雪害抵抗性品種「出羽の雪」の試験導入について~富山・岐阜における事例~ | (独)森林総合研究所森林農地整備センター中部整備局 | 河原田裕二 |
| 25 | 25 | 特別発表 | 木曽ヒノキ材による超断熱木製サッシの開発 | 有限会社和建築設計事務所 | 青木和壽 |
| 25 | 26 | 特別発表 | 岐阜県東白川村国有林のヒノキ人工林における水源涵養機能改善に向けた調査研究 | サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 | 川崎雅俊 |
| 筑波大学 | 恩田裕一、小松義隆 |
・ 平成24年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 24 | 1 | 森林技術 | ナラ枯れ被害の拡大防止に向けた取組について | 北信森林管理署 | 下城大作、山口穣 |
| 24 | 2 | 森林技術 | 特殊な環境(豪雪・強酸性土壌)における緑化方法の模索(馬曲川復旧治山工事) | 北信森林管理署 | 澤口章一 |
| 国土防災技術株式会社 | 田中賢治 | ||||
| タフグリーン工法研究会 | 井野友彰 | ||||
| 24 | 3 | 森林技術 | 民間競争入札による間伐事業の取り組みについて | 横山木材有限会社 | 百瀬俊一 |
| 中信森林管理署 | 南坂博和、志賀剛 | ||||
| 24 | 4 | 森林技術 | 高山帯におけるニホンジカ被害対策について | 南信森林管理署 | 佐田有紀 |
| 長野県諏訪地方事務所 | 清水篤 | ||||
| 24 | 5 | 森林技術 | 周辺植物の侵入と定着を目的とした植生工の試験施工について | 岐阜森林管理署 | 須永道彦、可兒孝志 |
| 24 | 6 | 森林技術 | ヒノキ天然稚樹の育成過程における密度推移について | 愛知森林管理事務所 | 小川義信 |
| 24 | 7 | 森林技術 | 複層林における主伐(後伐)実施時の下層木への影響調査結果について | 森林技術センター | 早川幸治 |
| 東濃森林管理署 | 富士本亜弥 | ||||
| 24 | 8 | 森林技術 | ヒノキ、ナラ、ホオノキの混交植栽試験-中間報告- | 森林技術センター | 千村知博 |
| 24 | 9 | 国民の森林 | 「安曇野まつかわ馬羅尾高原郷土の森」協定締結を生かした村づくり-すずむしとあがりこサワラ~郷土のシンボル~自然豊かな村を目指して- | 長野県松川村 | 原勇一 |
| 中信森林管理署 | 矢部博文、鎌倉浩一 | ||||
| 24 | 10 | 国民の森林 | 台風被害跡地における景観に配慮した天然林の育成に向けて | 東信森林管理署 | 上田茉由、重松千晶 |
| 24 | 11 | 国民の森林 | 木曽谷流域における民・国連携による林業再生への取組み(准フォレスターの取組み) | 木曽森林管理署 | 市川久志 |
| 中部森林管理局森林整備部 | 渡邊修 | ||||
| 24 | 12 | 国民の森林 | 飛騨森林管理署における共同施業団地の現状と課題(高山市一色・山中山地域森林共同施業団地の実例) | 飛騨森林管理署 | 伊藤納、日置順昭 |
| 24 | 13 | 森林ふれあい | 木曽ヒノキ備林(旧出ノ小路神宮備林)案内の取り組みについて | 東濃森林管理署 | 鈴木智晴 |
| 24 | 14 | 特別発表 | 森林美学の視点からの森林経営管理 | 名古屋大学大学院 | 奥山綾菜、山田容三 |
| 24 | 15 | 特別発表 | 作業道作設時の伐根処理作業における要素作業の分析 | 信州大学農学部 | 村井秀成、齋藤仁志、植木達人、井上裕 |
| 24 | 16 | 特別発表 | ケヤマハンノキの落葉特性について | 長野県林業大学校 | 森谷周平、鳥澤京平 |
| 24 | 17 | 特別発表 | H型架線集材の現場から~高知県の事例を中心として~ | 長野県林業大学校 | 三川一 |
| 24 | 18 | 特別発表 | 演習林における野生動物モニタリング調査 | 木曽青峰高等学校 | 久保田潤也、根井悠斗、川上豪 |
| 24 | 19 | 特別発表 | 地域の里山は私たちが変える~里地・里山システムのrecovery~ | 加茂農林高等学校 | 奥田彩乃、馬場安美 |
| 24 | 20 | 特別発表 | 飛騨の里山の危機を救え!~ギフチョウの舞う開かれた里山の再生と活用~ | 飛騨高山高等学校 | 上野真義、小森大空、坂井睦、中嶋大喜、東屋憂輝、森本和也、坂下愛、踏込龍生 |
・ 平成23年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 23 | 1 | 森林技術 | 広葉樹植栽地の育成方法の検討 | 北信森林管理署 | 山口穣、岡本守 |
| 23 | 2 | 森林技術 | 植生マット伏工における在来草本類の根系発達状況について | 中信森林管理署 | 久古和貴 |
| 株式会社新日本緑化 | 木村元由輝 | ||||
| 23 | 3 | 森林技術 | 東信森林管理署管内における松食い虫防除対策の取組について | 東信森林管理署 | 田中良太、千島佑太 |
| 23 | 4 | 森林技術 | 本数調整伐における現地発生材の有効利用について | 南信森林管理署 | 中島和美、俣野篤樹 |
| 23 | 5 | 森林技術 | モデル林における「低コスト・高効率作業システム」5カ年の変遷について | 木曽森林管理署 | 市川久志、渡邊修 |
| 23 | 6 | 森林技術 | 間伐等における末木枝条の有効利用 | 木曽森林管理署 | 西方雄一郎、齋藤由晃 |
| 23 | 7 | 森林技術 | 上矢作地区における緑化工法の一考察 | 東濃森林管理署 | 野中圭太、山口元 |
| 23 | 8 | 森林技術 | 長伐期施業における樹冠長率を指標とした森林管理技術の開発 | 森林技術センター | 早川幸治 |
| 岐阜県立森林文化アカデミー | 横井秀一 | ||||
| 23 | 9 | 国民の森林 | 「檜皮の森」での活動を振り返って | 木曽森林管理署南木曽支署 | 金敏博 |
| (公社)全国社寺等屋根工事技術保存会 | 友井辰哉 | ||||
| 23 | 10 | 特別発表 | ふれあいの森より広がる地域との絆 ~段戸国有林 漁民の森林づくり活動~ | 愛知森林管理事務所 | 鈴木永江、稲垣正紀 |
| 23 | 11 | 特別発表 | ロープによる熊剥ぎ対策の効果について | (独)森林総合研究所森林農地整備センター岐阜水源林整備事務所 | 伊関仁志 |
| 23 | 12 | 特別発表 | 平成23年度高等学校初任者研修の取組 | 長野県林業総合センター | 青栁智司 |
| 23 | 13 | 特別発表 | 戸隠森林植物園の鳥類相 ~野鳥の生活型から見た年間変化~ | 長野市立柳町中学校 | 宮澤小春 |
| 23 | 14 | 特別発表 | 段戸国有林のヒノキ人工林における広葉樹の多様性について | 名古屋大学農学部 | 香坂紗由実 |
| 名古屋大学大学院 | 橋本里美 | ||||
| 23 | 15 | 特別発表 | ラジコンヘリコプターを用いた森林材積推定に関する研究~信州大学農学部構内演習林を事例として~ | 信州大学農学部 | 松尾好高 |
| 23 | 16 | 特別発表 | オーストリア林業から学ぶ | 長野県林業大学校 | 伊藤圭介、平沢公彦、堀部泰正 |
| 23 | 17 | 特別発表 | 宇宙種の発芽実験 ~宇宙農林業の可能性について~ | 木曽青峰高等学校 | 古田啓吾、片山雄太、奈良尾充弘、高木勝大 |
| 23 | 18 | 特別発表 | 「森林・林業再生プラン」が林業事業体に与える影響 ~アンケートとヒアリングを通して見えてきた林業事業体の変化~ | 岐阜県立森林文化アカデミー | 渕上英明 |
| 23 | 19 | 特別発表 | 「里山復活大作戦」 ~元気 盛り 森 プロジェクト~ | 加茂農林高等学校 | 尾﨑里沙、丹羽幸恵 |
| 23 | 20 | 特別発表 | 自分たちでつくる森づくり Part2 | 飛騨高山高等学校 | 金桶満、釜部圭太、砂田宏師、反中良太、野村拓也、中嶋大喜、松原正哉 |
・ 平成22年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 22 | 1 | 森林技術 | 希少動植物の調査手法等の検討 | 北信森林管理署 | 中澤栄貴 |
| 22 | 2 | 森林技術 | ヒノキ複層林管理手法の一考察 | 中信森林管理署 | 百瀬厚、近江隆昭、百瀬健 |
| 22 | 3 | 森林技術 | 潜在自然植生樹種による荒廃地早期復旧の取組みについて | 東信森林管理署 | 小林慶祐、中里裕貴 |
| 22 | 4 | 森林技術 | 流木等を利用した吹付工の一考察 | 南信森林管理署 | 澤口蔦夫、原浩美 |
| 22 | 5 | 森林技術 | カラマツ一般材の層積検知について | 岐阜森林管理署 | 森下佳宏 |
| 22 | 6 | 森林技術 | 植生マットを使用した未立木地解消の取り組み | 東濃森林管理署 | 北重太 |
| 22 | 7 | 森林技術 | 校倉式木製谷止工の施工について | 愛知森林管理事務所 | 向澤大樹、前田秀則 |
| 22 | 8 | 森林技術 | 愛知森林管理事務所におけるシカ防護柵設置の取組について | 愛知森林管理事務所 | 山本武郎、藤村桂 |
| 22 | 9 | 森林技術 | 人工林複層伐施業における下層木の植栽密度別生育試験 | 森林技術センター | 髙原将樹 |
| 22 | 10 | 森林技術 | 在来種を利用した法面緑化【7年経過後の結果取りまとめ】 | 伊那谷総合治山事業所 | 田中重信 |
| 日本植生株式会社 | 笹井修一 | ||||
| 22 | 11 | 国民の森林 | 松本市奈川地区における森林整備推進協定について | 中信森林管理署 | 南坂博和 |
| 長野県松本地方事務所 | 千村広道 | ||||
| 22 | 12 | 国民の森林 | 林建協働による新規林業参入者技術指導の取組み | 森林技術センター | 住裕介 |
| 22 | 13 | 森林ふれあい | 北アルプス最奥地 雲ノ平植生復元活動について~大学・山小屋との新たな協力体制~ | 富山森林管理署 | 桑原優太 |
| 東京農業大学 | 下嶋聖 | ||||
| 22 | 14 | 森林ふれあい | 戸隠高原の保全と利用のための連携 | 北信森林管理署 | 湯浅翠 |
| 長野自然環境事務所 | 丸之内美恵子 | ||||
| 22 | 15 | 特別発表 | 根羽村におけるトータル林業の取り組み | 長野県根羽村 | 大久保憲一 |
| 22 | 16 | 特別発表 | 県産材住宅における木材のライフサイクルアセスメント調査について | 長野県林務部信州の木振興課 信州木材認証製品センター 信州大学工学部建築学科浅野研究室 | 井出政次 |
| 22 | 17 | 特別発表 | 高齢ヒノキ・イチイ二段林における伝統的工芸品の原材料としてのイチイの形状の評価 | 岐阜県森林研究所 | 渡邉仁志 |
| 岐阜県モノづくり振興課 | 大洞智宏 | ||||
| 岐阜県高山市 | 小川晶子 | ||||
| 22 | 18 | 特別発表 | 強度の上層間伐実施林分における気象害発生状況 | 長野県林業総合センター | 近藤道治、大矢信次郎 |
| 22 | 19 | 特別発表 | 国有林野における地理空間情報技術を援用した植生復元事業について~北アルプス・雲ノ平を事例として~ | 東京農業大学 | 下嶋聖 |
| 22 | 20 | 特別発表 | 自分たちでつくる森づくり | 飛騨高山高等学校 | 反中良太、金桶満、釜部圭太、砂田宏師、野村拓也、松原正哉、中嶋大喜 |
| 22 | 21 | 特別発表 | 保育園との交流で始まる間伐材の利用 | 木曽青峰高等学校 | 浦野明日香、島崎志穂理、楯なつ |
| 22 | 22 | 特別発表 | 上農高校の森林への取り組みと上伊那地区の鳥獣害について | 上伊那農業高等学校 | 山川隼平、福澤亮太、川畑一樹 |
| 22 | 23 | 特別発表 | 一歩先を行くエネルギー利用inオーストリア | 長野県林業大学校 | 古川俊樹、菊原嘉晃、塚原歩美 |
| 22 | 24 | 特別発表 | 積雪地帯における林業経営の可能性を明確にする手法の検討 | 岐阜県立森林文化アカデミー | 加茂隆樹 |
| 22 | 25 | 特別発表 | 渓畔樹種の土石流緩衝機能 | 信州大学農学部 | 宮田賢 |
・ 平成21年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 21 | 1 | 森林技術 | 針広混交林への誘導について | 富山森林管理署 | 下牧幹、向山剛 |
| 21 | 2 | 森林技術 | 強酸性土壌の山腹緑化工法について | 飛騨森林管理署 | 貴田雅規 |
| 21 | 3 | 森林技術 | 木曽ヒノキ林における50年間の林分構造の変化 | 東濃森林管理署 | 鈴木賢哉、近藤美由紀 |
| 21 | 4 | 森林技術 | 除伐段階における侵入広葉樹を活用した針広混交林造成試験について | 森林技術センター | 高原将樹、藤田泰平 |
| 21 | 5 | 森林技術 | 現場仮設事務所へのソーラーシステムの導入 | 伊那谷総合治山事業所 | 帆足郁 |
| 吉川建設株式会社 | 佐々木勝敏 | ||||
| 21 | 6 | 国民の森林 | 地域に根ざした国有林を目指して~台風被害跡地復旧への取組み~ | 東信森林管理署 | 安田幸治、山口穣 |
| 21 | 7 | 国民の森林 | 地域との連携による事業展開~ニホンジカの被害対策~ | 南信森林管理署 | 野口和幸、下島聡 |
| 21 | 8 | 国民の森林 | 裏谷原生林森林環境教育の取組みについて | 愛知森林管理事務所 | 鈴木永江、千村知博 |
| 21 | 9 | 森林ふれあい | 乗鞍岳周辺におけるセイヨウタンポポ除去活動について | 中信森林管理署 | 井出崇彦 |
| 21年度グリーンサポートスタッフ乗鞍班 | 関寿治、松本徳郎、次田洋子 | ||||
| 21 | 10 | 森林ふれあい | 白馬グリーンパトロールの新たな取組み | 中信森林管理署 | 依田直紀、高岡裕大、熊谷秀樹 |
| 21 | 11 | 森林ふれあい | 地域密着の国有林づくりを目指して~ハナノキ里帰りから感じたこと~ | 木曽森林管理署南木曽支署 | 金敏博 |
| 21 | 12 | 特別発表 | 七宗国有林大径材生産展示林のスギ・ヒノキ高齢木における胸高直径と樹幹構造の関係 | 岐阜県森林研究所 | 横井秀一 |
| 森林技術センター | 早川幸治 | ||||
| 21 | 13 | 特別発表 | 森林管理におけるGPS活用について | (独)森林総研長野水源林整備事務所 | 石原祐軌 |
| 21 | 14 | 特別発表 | 信州カラマツ防火サイディングの製品開発 | 県産材販路開拓協議会(有)和建設設計事務所 | 青木和壽 |
| 21 | 15 | 特別発表 | 木質バイオマスによるカーボンオフセットシステムの構築 | 長野県林務部信州の木振興課 | 井出正次 |
| 21 | 16 | 特別発表 | 森の大切さを伝えたい!~森・水・人のつながりを目指して~ | 飛騨高山高等学校 | 熊﨑寛太、中村昴一 |
| 21 | 17 | 特別発表 | 緑地工学科の取組みと2学年プロジェクト学習 | 上伊那農業高等学校 | 小山祐樹、白鳥克弥、城島貴俊 |
| 21 | 18 | 特別発表 | 木材の精油研究~樹木の香りの商品化を考える~ | 木曽青峰高等学校 | 笹川涼太、神村一成、竹脇唯、和木一夢 |
| 21 | 19 | 特別発表 | オーストリアの森林・林業の現状 | 長野県林業大学校 | 久古和貴、源田聡子、佐藤拓人 |
・ 平成20年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 20 | 1 | 森林技術 | ウダイカンバの密度管理 | 富山森林管理署 | 城倉恵介、下牧幹 |
| 20 | 2 | 森林技術 | 浅間山麓におけるカラマツの天然更新について(中間報告)東信森林管理署 | 東信森林管理署 | 杉村智春、小須田啓 |
| 20 | 3 | 森林技術 | 地域のニーズを引き出す取組み~「郷学官」共同企画を通じた森林林業の普及~ | 南信森林管理署 | 井元幸子 |
| 信州大学農学部 | 松村泰代、細川奈々枝 | ||||
| 20 | 4 | 森林技術 | 群状択伐による木曽ヒノキの天然更新について~種子散布量と実生の消長~ | 木曽森林管理署 | 三村晴彦、栢木洋平 |
| 20 | 5 | 森林技術 | 「民国連携による「美しい森林づくりin飛騨」の取り組み | 飛騨森林管理署 | 菅野耕治 |
| 高山市 | 長沼隆 | ||||
| 20 | 6 | 森林技術 | 基本図でナビを作ろう | 岐阜森林管理署 | 影山成生、福井孝広 |
| 20 | 7 | 森林技術 | 地域・利用者のニーズに応える森づくり眺望伐開を取り入れた森林整備) | 愛知森林管理事務所 | 酒向篤憲、日比野慎也 |
| 20 | 8 | 森林技術 | ヒノキ単層林の下層植生回復試験について | 森林技術センター | 富士本亜弥 |
| 20 | 9 | 治山・林道 | 末木枝条を活かす~チップ吹付けによる自然還元への取組み~ | 木曽森林管理署南木曽支署 | 尾近茂 |
| 20 | 10 | 治山・林道 | ソイルセメントを用いた治山ダムの構築(INSEM工法) | 岐阜森林管理署 | 川本淳、山田好男 |
| 20 | 11 | 治山・林道 | 松川入地区における民有林直轄治山事業の実施状況と情報発信 | 伊那谷総合治山事業所 | 近江澤利美、帆足郁 |
| 20 | 12 | 森林ふれあい | 関田山脈を利用した信越トレイルの整備・活用について | 北信森林管理署 | 小林常正 |
| NPO法人信越トレイルクラブ | 高野賢一 | ||||
| 20 | 13 | 森林ふれあい | 赤沢自然休養林を活用した森林セラピーの取組み | 上松町 | 根井大輔 |
| 木曽森林管理署 | 湯浅翠 | ||||
| 20 | 14 | 特別発表 | 佐久地域に適合した高能率間伐材搬出システムの確立に向けた取組み | 佐久地方事務所 | 三石和久、泉川尚久 |
| 20 | 15 | 特別発表 | 森林の大切さを伝えるために~これからの森林活用法~ | 飛騨高山高等学校 | 田中良太、俣野篤樹 |
| 20 | 16 | 特別発表 | 緑地工学科の取組みと2学年プロジェクト学習 | 上伊那農業高等学校 | 保科旬哉、征矢真広、宮下大樹 |
| 20 | 17 | 特別発表 | 「森の聞き書き甲子園」に取り組んで得たこと | 木曽青峰高等学校 | 西村拓馬、椙本杏子 |
| 20 | 18 | 特別発表 | 樹皮を使った紙作りによる森林資源の活用 | 木曽青峰高等学校 | 三澤成貴、木村公良、諸原利幸 |
| 20 | 19 | 特別発表 | 巨樹巨木の森”セコイア国立公園”の森林生態 | 長野県林業大学校 | 向山剛、生駒豊文、平栃潤己 |
| 20 | 20 | 特別発表 | 長伐期複層林施業における上木間伐に関する研究 | 名古屋大学 | 小谷芙蓉 |
・ 平成19年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 19 | 1 | 森林技術 | 木曽ヒノキの集団枯損について~赤沢林木遺伝資源保存林奥千本の事例~ | 木曽森林管理署 | 三村晴彦、岡本守 |
| 19 | 2 | 森林技術 | 「飛騨でもできた」を目指し~民有林・国有林が連携した低コスト作業の取り組み~ | 飛騨森林管理署 | 川本芳光、中谷博 |
| 19 | 3 | 森林技術 | ヒノキ列状間伐実行後の状況について | 森林技術センター | 熊澤智史 |
| 19 | 4 | 森林技術 | ヒノキ2代目造林実験林について | 森林技術センター | 富士本亜弥 |
| 19 | 5 | 治山・林道 | 湧水を活用したエネルギー回収システム | 富山森林管理署 | 吉田一 |
| 19 | 6 | 治山・林道 | モリアオガエルを育てる治山ダム | 木曽森林管理署南木曽支署 | 中畑孝史 |
| 19 | 7 | 治山・林道 | 上矢作地区における緑化工法の一考察 | 東濃森林管理署 | 可兒孝志、野中圭太 |
| 19 | 8 | 治山・林道 | 愛知所における木材を利用した治山構造物について | 愛知森林管理事務所 | 萩原伸也、光坂紀治 |
| 19 | 9 | 森林ふれあい | 出前授業による地域への国有林のPRについて | 南信森林管理署 | 中村信平、南坂博和 |
| 19 | 10 | 森林ふれあい | 金華山国有林とボランティア活動について | 金華山国有林保護管理協議会 | 川瀬健一 |
| 岐阜森林管理署 | 小坂隆昭 | ||||
| 19 | 11 | 森林ふれあい | ボランティアによる木曽駒ヶ岳植生復元作業の取り組み | 木曽森林環境保全ふれあいセンター | 寺澤茂雄 |
| 19 | 12 | 特別発表 | 「PDAを持って山へ行こう!」 | 富山県林業技術センター | 小林裕之 |
| 富山県庁 | 松井俊成 | ||||
| 19 | 13 | 特別発表 | 強酸性土壌に起因する崩壊地の緑化工5ヵ年の推移 | 長野県長野地方事務所 | 田淵千春 |
| 長野県林業総合センター | 片倉正行 | ||||
| 長野県林業コンサルタント協会 | 松澤義明 | ||||
| 19 | 14 | 特別発表 | 列状間伐における列設定・測樹についての取り組み ~津水源林整備事務所の事例について~ | 緑資源機構中部整備局 | 佐々木誠 |
| 19 | 15 | 特別発表 | イヌワシ生息地の環境整備地における餌動物確保のためのノウサギの隠れ場試作設置について | 長和町イヌワシ調査グループ | 峰岸郁生、片山磯雄 |
| 19 | 16 | 特別発表 | 高齢級スギ人工林における間伐作業の事例について | 名古屋大学 | 山内美菜子 |
| 19 | 17 | 特別発表 | 森林組合における体験研修を通じての林業技術の考察 | 長野県林業大学校 | 嶋村浩香、小林明仁 |
| 19 | 18 | 特別発表 | 上農高校緑地工学科の活動 | 上伊那農業高等学校 | 唐澤一樹、宮下正秀 |
| 19 | 19 | 特別発表 | 飛騨の安らぎ空間を護るために~森林の持つ土砂災害防止機能について~ | 飛騨高山高等学校 | 井戸一隆、白川拓巳、田中有紀子 |
| 19 | 20 | 特別発表 | 林業者としてつかみたい夢~新しい視点で森林を考える~ | 飛騨高山高等学校 | 田中有紀子 |
・ 平成18年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 18 | 1 | 森林技術 | 高山植物保護パトロール35年の歩みと課題 | 富山森林管理署 | 寺島史郎 |
| 18 | 2 | 森林技術 | 白馬岳高山帯の植生復元の取り組み | 中信森林管理署 | 井元幸子 |
| 信州大学 | 田川雄之 | ||||
| 18 | 3 | 森林技術 | ニホンジカによる森林被害と対策の現状について | 南信森林管理署 | 佐野智一、宮路聡 |
| 18 | 4 | 森林技術 | ササのコントロールによる天然更新について | 木曽森林管理署 | 三村晴彦、黒澤友大 |
| 18 | 5 | 森林技術 | 地域に適応した路網整備を軸とする低コスト作業システムへの取り組み | 森林技術センター | 大林誠司、熊崎裕文 |
| 18 | 6 | 森林技術 | 初回間伐から利用可能な除伐2類段階での本数調整方法 | 森林技術センター | 藤島文博 |
| 18 | 7 | 治山・林道 | 旧御料林における砂防施設の点検調査 | 木曽森林管理署南木曽支署 | 中畑孝史 |
| 18 | 8 | 治山・林道 | 揖斐川地区民有林直轄治山事業の概成について | 岐阜森林管理署 | 萩原伸也、川本淳 |
| (財)林業土木コンサルタンツ | 児波昌則 | ||||
| 18 | 9 | 治山・林道 | アルカリ土壌地における緑化伏工技術の確立 | 伊那谷総合治山事業所 | 上西美樹、林正裕 |
| 日本植生(株) | 笹井修一 | ||||
| 18 | 10 | 森林ふれあい | 戸隠森林植物園に対する要請と展望について | 北信森林管理署 | 吉村博幸、堀内志保 |
| 18 | 11 | 森林ふれあい | 地域と連携した環境教育・環境保全の取り組み | 飛騨森林管理署 | 大西沙織、上島弘幸 |
| 18 | 12 | 森林ふれあい | 森林交流館における情報発信・普及啓発の取り組み | 愛知森林管理事務所 | 酒向篤憲 |
| 名古屋事務所 | 松田恵 | ||||
| 18 | 13 | 特別発表 | 木曽郡南部地域におけるツキノワグマによる人工林剥皮被害対策への考察 | 長野県木曽農林振興事務所 | 窪田達央 |
| 18 | 14 | 特別発表 | 環状剥皮等の乾燥に与える効果について列状間伐を実施した林分の成長特性と被害実態 | 愛知県森林・林業センター | 山本勝洋 |
| 18 | 15 | 特別発表 | 海洋深層水を利用した食用キノコ生産~栽培・加工・流通への利用~ | 富山県林業技術センター | 高畠幸司 |
| 18 | 16 | 特別発表 | 信州大学農学部環境ISO学生委員会の間伐材利用活動 | 信州大学 | 古川久実 |
| 18 | 17 | 特別発表 | 間伐強度が樹冠の降雨配分に及ぼす影響 | 名古屋大学大学院 | 藤田裕二 |
| 18 | 18 | 特別発表 | 高性能林業機械体験学習 | 長野県林業大学校 | 高原将樹、目黒雅大、峰村裕一 |
| 18 | 19 | 特別発表 | 地域と取り組む緑化活動 | 飛騨高山高等学校 | 岡崎俊輔、祐成亮一、高橋和彦、中本真人、楠翔太 |
| 18 | 20 | 特別発表 | 間伐研修とインドネシア研修報告 | 上伊那農業高等学校 | 大蔵大、西村臣司、三浦翔太、杉田治信 |
| 18 | 21 | 特別発表 | 木炭及び桧皮を培地とした溶液栽培の研究 | 木曽山林高等学校 | 下牧幹、古根春樹 |
・ 平成17年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 17 | 1 | 森林技術 | 人工林の現況調査について | 富山森林管理署 | 横井新吾、藤村桂 |
| 17 | 2 | 森林技術 | 千曲川上流域におけるカラマツ材の現状と今後の課題について | 東信森林管理署 | 田中健、井出利松 |
| 17 | 3 | 森林技術 | ササのコントロールによる天然更新について~三浦実験林帯状皆伐天然更新試験より~ | 木曽森林管理署 | 三村晴彦、谷脇雅博 |
| 17 | 4 | 森林技術 | カラマツ列状間伐の現状と課題 | 飛騨森林管理署 | 岩倉豊樹 |
| 17 | 5 | 森林技術 | 不明標解消に向けての取り組み | 岐阜森林管理署 | 影山成生、福井孝広 |
| 17 | 6 | 森林技術 | 柱適材生産のための間伐施業試験 | 森林技術センター | 熊崎裕文 |
| 17 | 7 | 森林技術 | 御岳トウヒ・シラベ林分成長固定試験地の調査結果について | 森林技術センター | 長屋和幸 |
| 17 | 8 | 治山・林道 | 在来種を利用した法面緑化工 | 伊那谷総合治山事業所 | 松井健太郎 |
| 日本植生(株) | 笹井修一 | ||||
| 綿半インテック(株) | 園原正二、今井克彦 | ||||
| 17 | 9 | 森林ふれあい | 森林バイオマス利用への取り祖み~森林ボランティア等との連携~ | 南信森林管理署 | 下平明博 |
| 上伊那森林組合 | 寺澤茂通 | ||||
| 17 | 10 | 森林ふれあい | 地元産材を生かしたまちづくり~歩いて感じるまち-木曽福島をめざして~ | 木曽町 | 古幡浩二、中谷和博 |
| 木曽森林管理署 | 木内伸夫 | ||||
| 17 | 11 | 森林ふれあい | 地域の伝統工芸と連携した森林教室の取り祖み | 木曽森林管理署南木曽支署 | 森田武士、高井宏己 |
| 17 | 12 | 森林ふれあい | 「ふれあいの森」事業を一つの基軸に | NPO恵那山みどりの会 | 柴田満、柘植昭男 |
| 東濃森林管理署 | 加地英孝 | ||||
| 17 | 13 | 森林ふれあい | 裏谷原生林における森林環境教育の実践と展望 | 愛知森林管理事務所 | 鈴木良和 |
| 17 | 14 | 特別発表 | 広葉樹等から成る保安林の調査について | 諏訪地方事務所 | 清水靖久、戸田堅一郎 |
| 17 | 15 | 特別発表 | 列状間伐を実施した林分の成特性と被害実態 | 愛知県森林・林業技術センター | 鈴木祥仁 |
| 17 | 16 | 特別発表 | 大苗造林は有効か~ササ地におけるコナラの更新作業~ | 富山県林業技術センター | 松浦崇遠 |
| 17 | 17 | 特別発表 | 粘着剤によるナラ枯損被害防除の試み | 岐阜県森林科学研究所 | 大橋章博 |
| 17 | 18 | 特別発表 | SPOT衛星を利用した木曽ヒノキの伐採照査 | 信州大学農学部 | 小川崇 |
| 17 | 19 | 特別発表 | ブナ天然林の種多様性に与える着生植物の影響 | 岐阜大学大学院 | 近藤大介、加藤正吾、小見山章 |
| 17 | 20 | 特別発表 | 緑地工学科で調査・研究していること | 上伊那農業高等学校 | 伊藤勝実、辰野起正、北原健介、伊藤健吾、中村翔、加藤将大 |
| 17 | 21 | 特別発表 | ヒノキの皮から紙作り | 木曽山林高等学校 | 坂本美由、上田晴香、岡井由佳 |
・ 平成16年度
| 年度 | 番号 | 分類 | 課題名 | 所属 | 発表者 |
| 16 | 1 | 更新・保育 | ウダイカンバの密度管理について | 富山森林管理署 | 横井眞吾、佐々木雅則 |
| 16 | 2 | 更新・保育 | ヒノキ天然更新の試験地について | 愛知森林管理事務所 | 鈴木良和 |
| 16 | 3 | 森林・林業 | 木材チップ被覆によるヒノキ根の保護について | 木曽森林管理署 | 三村晴彦、櫻井康夫 |
| 16 | 4 | 森林・林業 | ブナ坂国有林における立山スギ巨木に関する取り組み | 富山森林管理署 | 中屋健次、藤村桂 |
| 16 | 5 | 森林・林業 | 乗政ヒノキ人工林収穫試験地の調査結果について | 森林技術センター | 長屋和幸 |
| 森林総合研究所 | 細田和夫、家原敏郎 | ||||
| 16 | 6 | 森林・林業 | 高山植物等保護(グリーンパトロール)の取り組みについて | 中信森林管理署 | 寺島史郎 |
| グリーンパトロール隊員 | 波多野肇 | ||||
| 16 | 7 | 治山・林道 | 恵那山系における大規模崩壊地の復旧に向けて | 東濃森林管理署 | 高村健介、可兒孝志 |
| 16 | 8 | 治山・林道 | 高性能林業機械に対応した作業道の作設-これからの森林施業に向けて- | 森林技術センター | 熊﨑裕文 |
| 16 | 9 | 総務・地域との連携等 | 「関田トレイル」の整備と活用について | 北信森林管理署 | 平野友行 |
| NPO法人信越トレイルクラブ | 大西宏志 | ||||
| 16 | 10 | 総務・地域との連携等 | 地域伝統文化を支える森づくり-「御柱の森」における取り組み- | 南信森林管理署 | 向井明 |
| 御柱の森づくり協議会 | 宮坂源吉 | ||||
| 16 | 11 | 総務・地域との連携等 | 組織再編後における森林事務所の取り組み-地域に密着した取り組み- | 飛騨森林管理署 | 湯浅正明、銅島悟、四ッ嶽誠 |
| 16 | 12 | 総務・地域との連携等 | 城山史跡の森における地域と一体となった森林整備活動について | 木曽森林環境保全ふれあいセンタ- | 中熊靖 |
| 信州大学 | 藤澤翠 | ||||
| 16 | 13 | 特別発表 | 新しい野生きのこの栽培技術の開発-キサケツバタケ- | 愛知県森林林業研究センター | 門屋健 |
| 16 | 14 | 特別発表 | ヒノキ人工林の衰退した下層植生は間伐でよみがえるのか | 岐阜県森林科学研究所 | 横井秀一 |
| 16 | 15 | 特別発表 | GISによる地形解析技術を利用した林地生産力の推定 | 富山県林業技術センター | 図子光太郎 |
| 16 | 16 | 特別発表 | 木製法面保護工について | 長野県木曽地方事務所 | 山口真保呂 |
| 16 | 17 | 特別発表 | 森林管理計画のための機能区分の手法に関する研究-AHP階層分析法)による意思決定支援の検討- | 名古屋大学大学院 | 高根沢寛枝 |
| 16 | 18 | 特別発表 | 国有林野事業における「ふれあいの森」制度の現状と展望 | 名古屋大学 | 青木陽子、大浦由美 |
| 16 | 19 | 特別発表 | ヒノキ人工林における漸伐施業法の体系化に関する基礎的研究-東信森林管理署管内奈良本山国有林を事例に- | 信州大学 | 遠藤寛子 |
| 16 | 20 | 特別発表 | 岐阜市金華山の森林形成史 | 岐阜大学 | 今井勇一、松村学、加藤正吾、小見山章 |
| 16 | 21 | 特別発表 | 木材腐朽について | 木曽山林高等学校 | 山田修平、市川雄太、若田和幸 |
| 16 | 22 | 特別発表 | 上農高校緑地工学科の活動 | 上伊那農業高等学校 | 武田英太、竹村大志 |
お問合せ先
技術普及課
担当者:技術開発主任官
ダイヤルイン:050-3160-6548