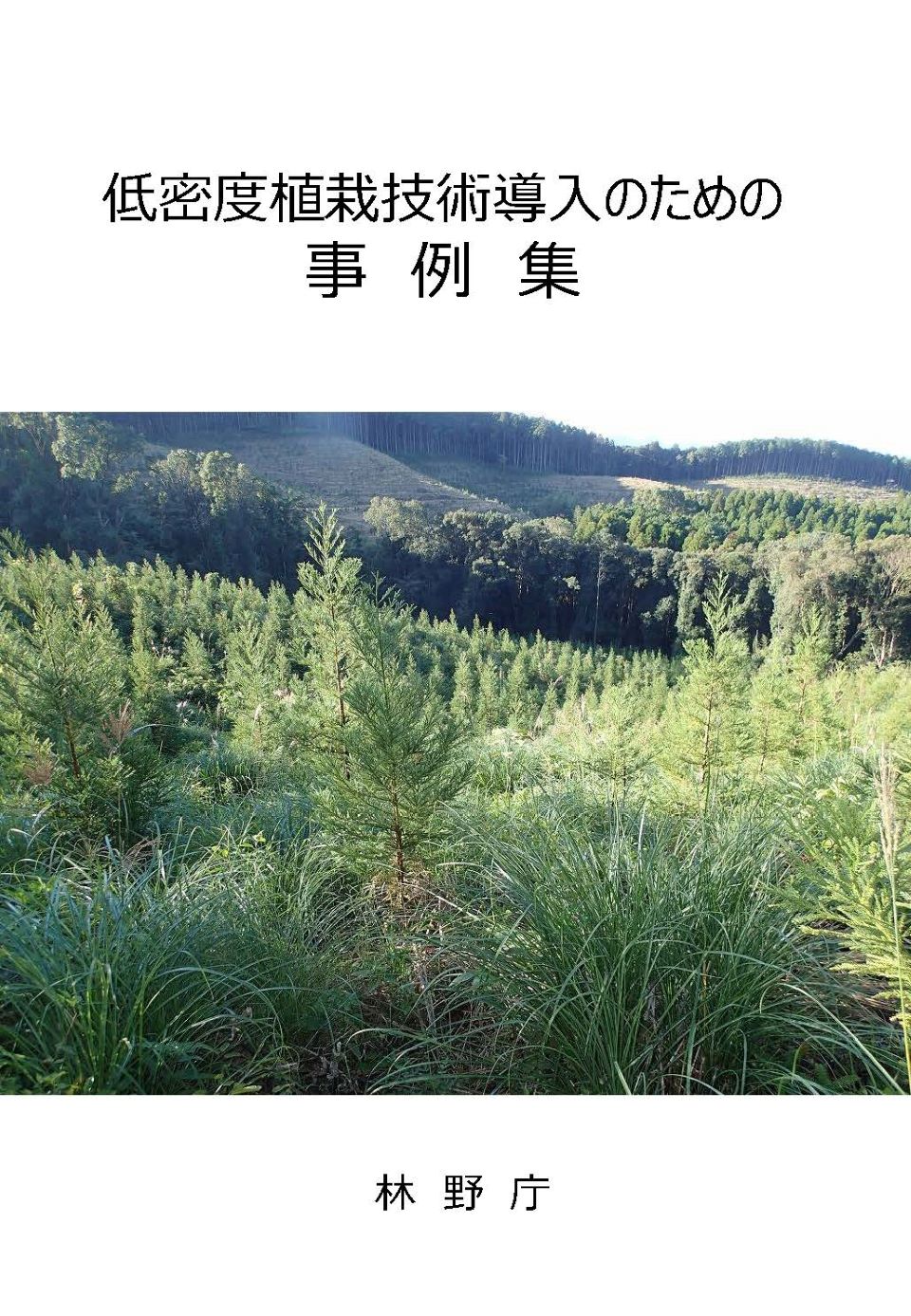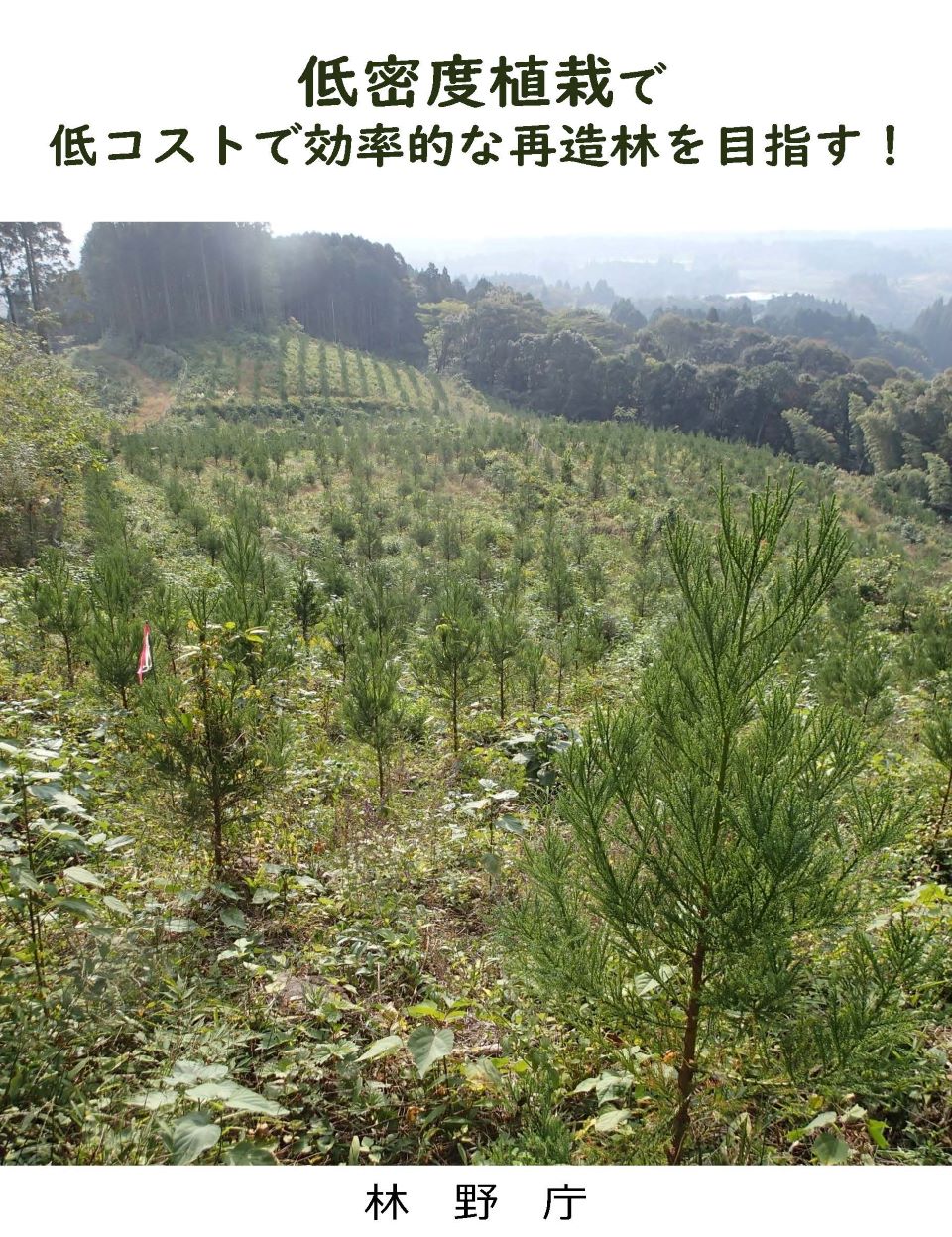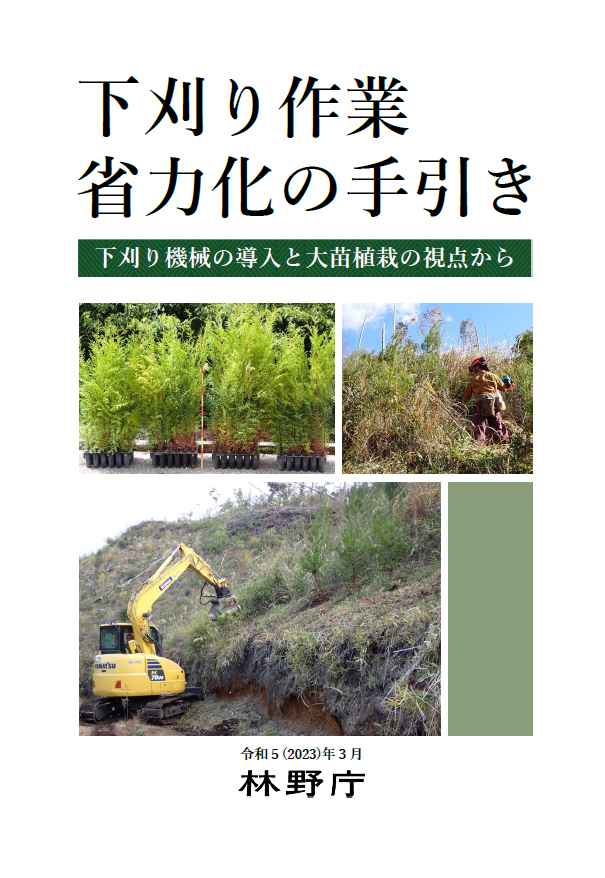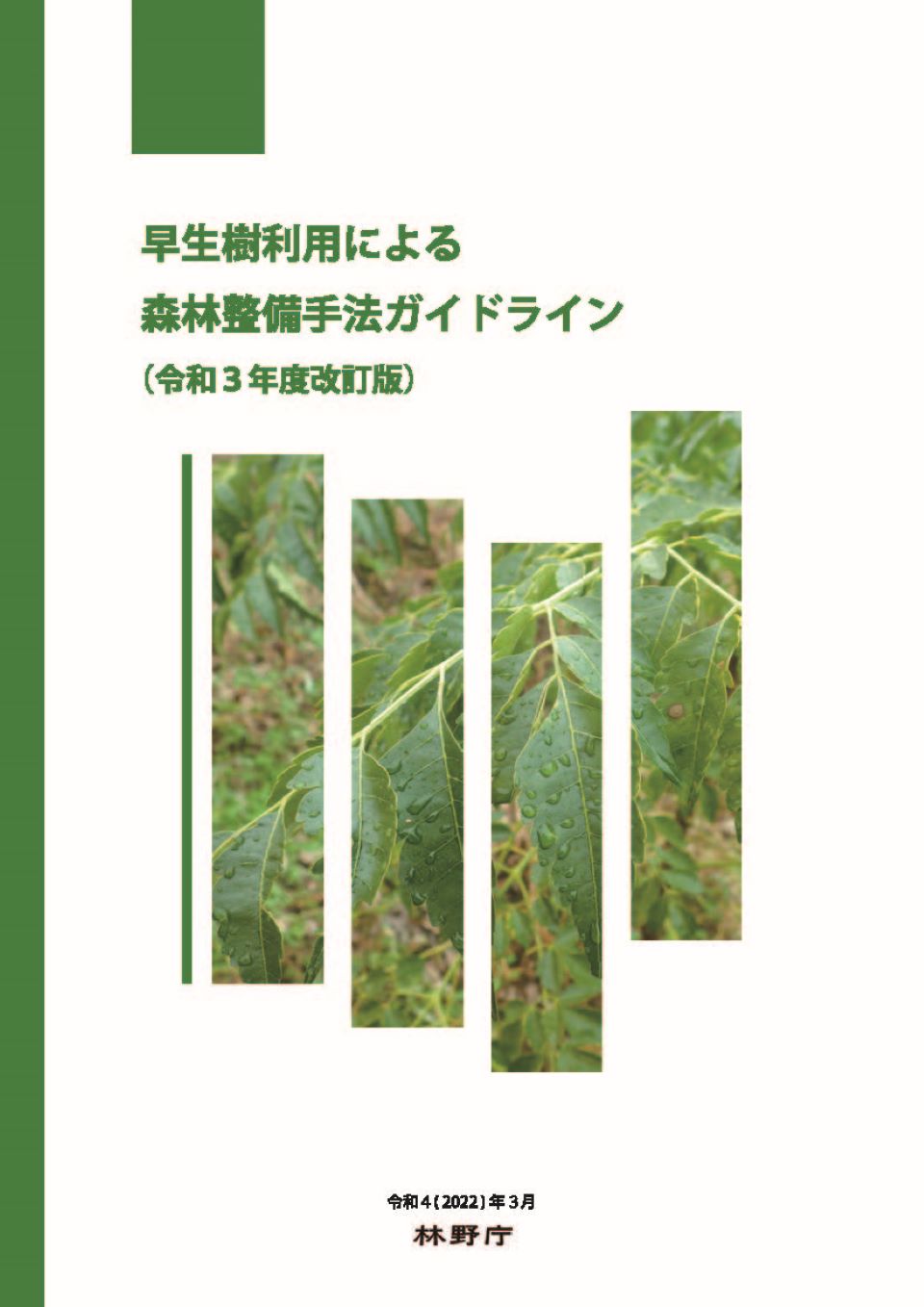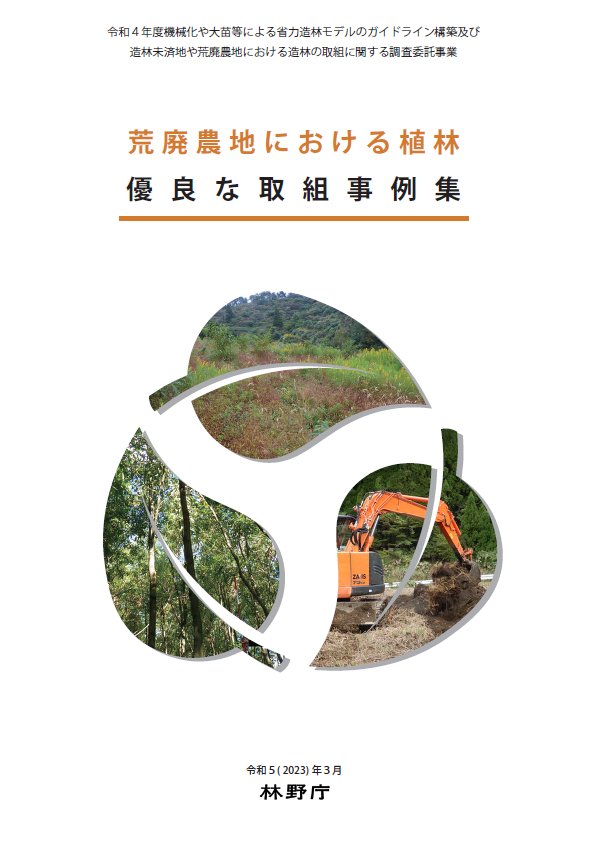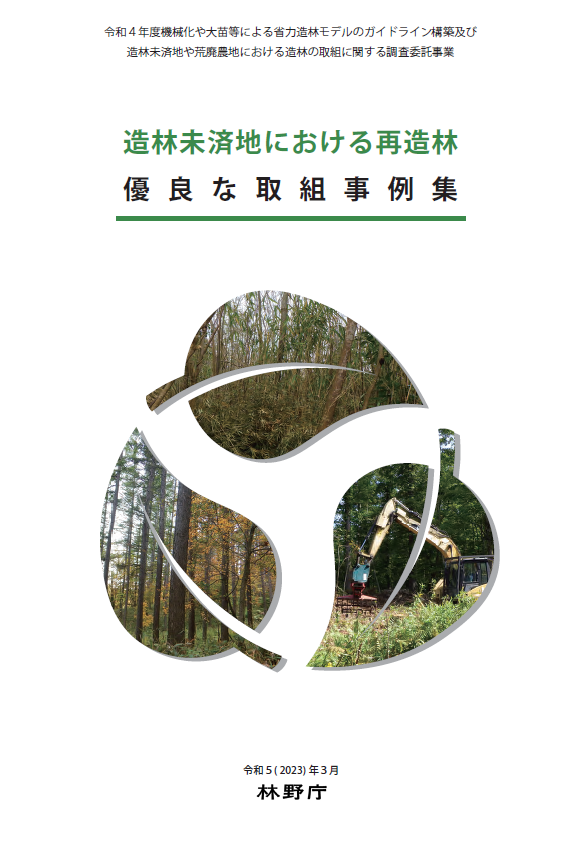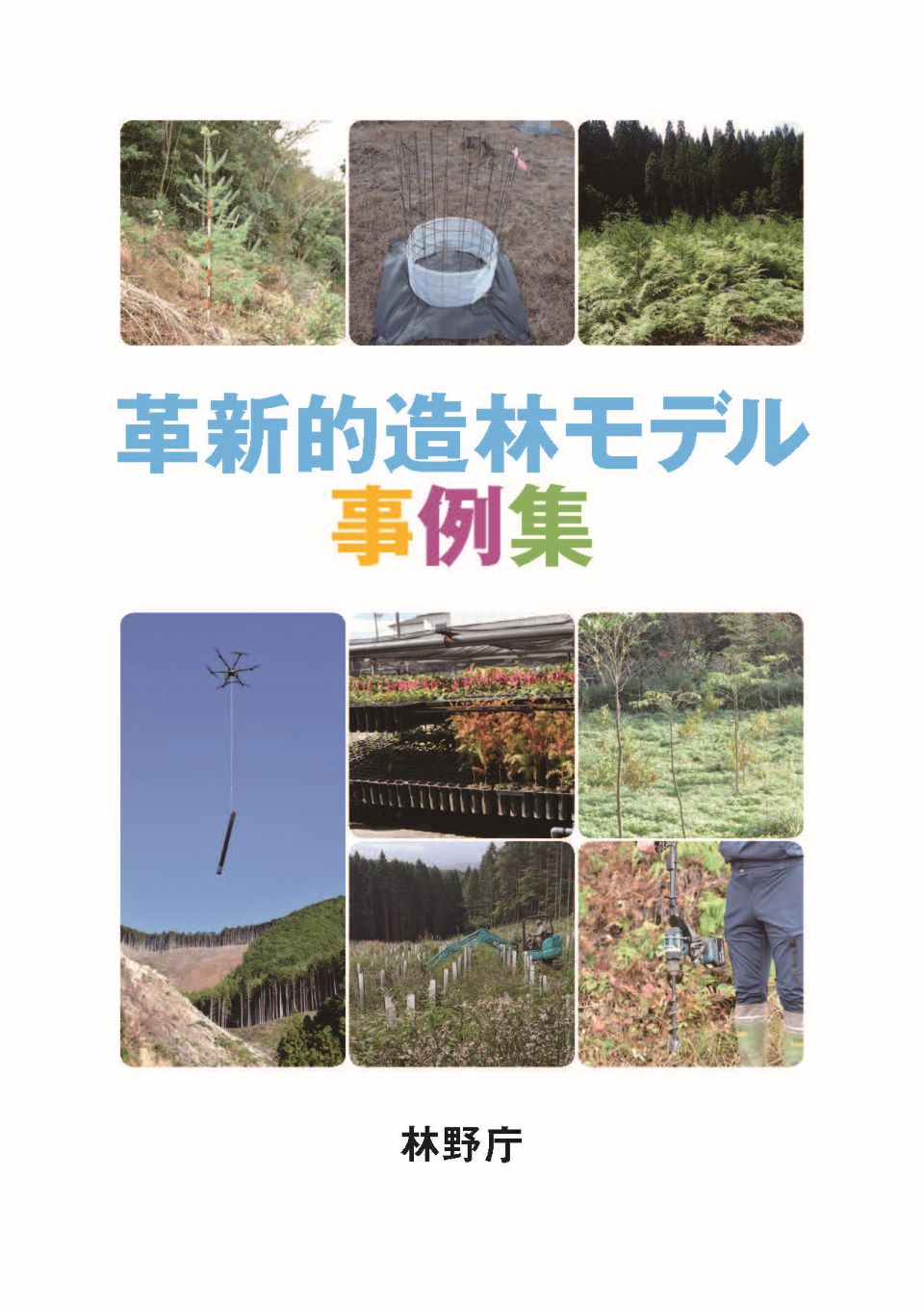造林の省力化・低コスト化について
ここでは、伐採と造林の一貫作業システムや低密度植栽、早生樹利用など、造林の省力化・低コスト化技術について、林野庁行った調査報告書やパンフレットなどの資料をまとめました。
森林整備を効率的・効果的に進めるためにお役立てください。
なお、関係法令、制度等は調査時点以降改正されている可能性がありますので、実際の事業の実施に際しては、最新の情報をご確認下さるようお願いいたします。
造林に係る省力化・低コスト化技術指針
造林の省力化・低コスト化技術の導入・普及のため、全国各地で行われた実証や取組の成果を体系的に整理し、令和6年度に長官通知「造林に係る省力化・低コスト化技術指針」及び整備課長通知「造林に係る省力化・低コスト化技術指針の解説」としてまとめました。各技術の詳しい情報はこのページをスクロールしていただくか、以下リンクからご覧ください。
また、あわせて事例集も作成しましたので、以下リンクからご覧ください。
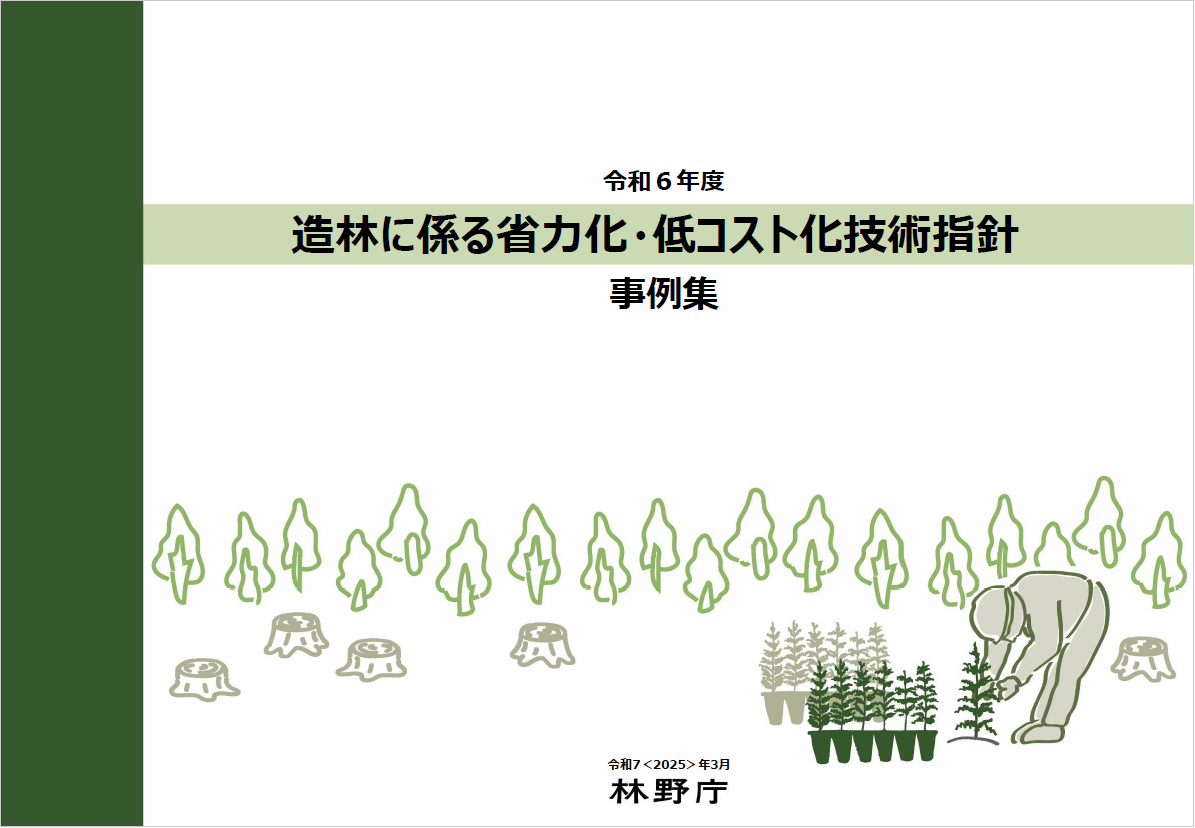
一貫作業システム
造林経費の大半を占める地ごしらえ及び植栽から下刈りまでの経費の低コスト化を進めるため、伐採と地ごしらえの一体化による低コスト造林技術についての調査を、平成26年度(2014年度)から平成29年度(2017年度)にかけて実施しました。
低コスト造林技術の導入に向けて
低コスト造林のポイントとなる「一貫作業システムの導入」、「コンテナ苗」、「下刈り回数削減」、「シカ被害軽減」及び「再造林コスト予測」について、ノウハウや留意事項等を整理しました。
低コスト造林事例集
再造林経費の削減のための低コスト造林技術の中でも、とりわけその普及が期待される『伐採と地拵えの一体化』に焦点を当て、今までそれぞれの作業を分割して実施してきたこれまでの事例と比較することで、どの程度の効果が期待されるのかを中心に紹介した事例集を作成しました。
報告書
(平成29年度(PDF : 6,032KB)、平成28年度(PDF : 10,501KB)、
平成27年度(PDF : 11,789KB)、平成26年度(PDF : 7,683KB))
伐採作業と造林作業の連携等の促進について
低コスト造林技術実証・導入促進事業等の報告書を踏まえ、平成30年(2018年)に伐採と造林の一貫作業システムのメリット等を示した整備課長通知「伐採作業と造林作業の連携等の促進について」をまとめました。
低密度植栽
主伐後の再造林を確実に実施するため、再造林の低コスト化を推進することが不可欠となっていることから、低コスト造林に繋がる可能性のある低密度植栽技術についての調査を、平成27年度(2015年度)から令和元年度(2019年度)にかけて実施しました。また、令和2年度(2020年度)から令和3年度(2021年度)にかけて実施した追跡調査の結果を踏まえ改訂を行いました。
低密度植栽のための技術指針
スギ、ヒノキ、カラマツの低密度植栽試験地を全国に設け、樹種別、地域別の植栽密度による成長状況などの違いの検証や成林の確実性、コスト削減効果、病虫獣害、下刈り終了の可否判断の基準などに関する知見を得ました。これらの知見および既存の低密度植栽試験地と既往文献情報を整理し、技術指針としてとりまとめました。
低密度植栽技術導入のための事例集・パンフレット
低密度植栽の試験地から得られた知見を基に、地域特性に応じた低密度植栽技術導入のための林業技術者向け事例集、低密度植栽における初期(植栽後5~6年程度まで)の植栽木の生育状況や初期保育コストなどについて要点を簡潔にとりまとめたパンフレットを作成しました。
本冊子が、低密度植栽を導入する一助となれば幸いです。
報告書
(令和3年度、令和2年度、令和元年度、平成30年度、平成29年度、平成28年度、平成27年度)
下刈りの省力化
下刈り機械の導入と大苗植栽による下刈り作業の省力化
林業の持続的な発展のためには、主伐後の再造林の確実な実施が不可欠です。
一方で、下刈りなどの造林作業は人力に頼る部分が多く、作業の機械化等による省力化・低コスト化の推進が重要です。
そのため、下刈り・地拵えの機械化や大苗等の活用による下刈り作業の省力化について調査を行い、手引きとして取りまとめました。
早生樹利用
多様で健全な森林への誘導や林業の成長産業化に向けて、早く大きく成長する早生樹の本格的な利用に向けた取組を進めることが重要となっていることから、早生樹による森林整備手法についての調査を、平成29年度(2017年度)から平成31年度(2019年度)に実施し、早生樹利用による森林整備手法ガイドラインを作成しました。また令和3年度(2022年度)に実施した追跡調査の結果を踏まえ改訂を行いました。
早生樹利用による森林整備手法ガイドライン
用材生産が可能な樹種のうち、各地域で植栽が進んでおり、生産目標の参考となる既存植栽地があるセンダン、コウヨウザンの2樹種について、植栽適地や密度、獣害対策等に関する調査を行い、ガイドラインを作成しました。
報告書
(令和3年度、平成31年度、平成30年度、平成29年度)
シンポジウム「エリートツリー・早生樹の展開と実践~事例から見る造林から利用まで~」
令和7年(2025年)8月にシンポジウム「エリートツリー・早生樹の展開と実践~事例から見る造林から利用まで~」を開催しました。成長に優れたエリートツリー及び早生樹の活用や省力・低コスト造林技術の一層の普及を図ることを目的として、エリートツリーや早生樹の造林から木材利用までの最新研究事例や取組事例等について、有識者の方々から御紹介いただきました。講演資料は以下のページに掲載しております。
平成31年(2019年)3月に開催された第一回のシンポジウム「早生樹・エリートツリーの現状と未来~その可能性と課題を探る~」の講演資料は以下のページに掲載しております。
その他事例集
革新的造林モデル事例集
森林施業の現場においては、林業機械及びICTの活用や低密度植栽、早生樹の導入等、効率化を進めるための各種方策が十分に普及していない状況となっています。
このため、先進的な森林施業の取組について、現地調査や森林施業に関するコンクールを開催を通じて事例を収集を行い、普及することを目的に「革新的造林モデル事例集」を作成しました。
森林づくりの新たな技術
造林コストの低減や労力の削減に向け、ドローンの活用や異分野との連携など革新的な造林技術について、調査報告書などの資料をまとめています。
以下リンクからご覧ください。
- 造林関係(ドローン等)はこちら
- 種苗関係はこちら
(参考)間伐・搬出、種苗に関する新たな技術も紹介しています。 - 間伐・搬出関係はこちら
(国研)森林研究・整備機構による研究報告等
森林総合研究所、林木育種センターの知見をまとめた報告書、マニュアル、パンフレット等が掲載されたページへのリンク集です。詳細については各リンク先に記載されている連絡先にお問い合わせください。
造林の低コスト化関係
- 「低コスト再造林に役立つ“下刈り省略手法” アラカルト」(2019年3月 東北支所発行)
- 「ここまでやれる再造林の低コスト化 ー 東北地域の挑戦 ー」(2016年2月 東北支所発行)
- 「緩中傾斜地を対象とした伐採造林一貫システムの手引き」(2016年2月 北海道支所発行)
- 「コンテナ苗を活用した主伐・再造林技術の新たな展開 ~実証研究の現場から~」(2016年3月 森林総合研究所発行)
- 「近畿・中国四国の省力化再造林事例集」(2015年3月森林総合研究所四国支所発行)
- 「低コスト再造林の実用化に向けた研究成果集」(2013年3月 森林総合研究所発行)
- 「森林・林業の再生:再造林コストの削減に向けて-低コスト化のための5つのポイント-」
(2012年11月 九州支所発行「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「スギ再造林」研究成果報告」内)
広葉樹林関係
- 「中山間地で広葉樹林を循環利用するためのハンドブック」(2019年2月 関西支所発行)
- 「広葉樹林化ハンドブック2012 ―人工林を広葉樹林へと誘導するために―」(2012年3月 四国支所発行)
- 「広葉樹林化ハンドブック2010 ―人工林を広葉樹林へと誘導するために―」(2010年12月 四国支所発行、2012年3月改訂)
- 「広葉樹の種苗の移動に関する遺伝的ガイドライン」(2011年3月 森林総合研究所発行)
獣害対策関係
- 「西日本の若齢造林地におけるシカ被害対策選択のポイント~防鹿柵・単木保護・大苗植栽」~
(2021年3月 森林総合研究所九州支所発行) - 「ツキノワグマ出没予測マニュアル」(2011年2月 森林総合研究所発行)
- 「新たなシカ管理に向けて」(2014年2月 森林総合研究所発行)
- 「林業被害軽減のためのシカ個体数管理技術の開発」研究成果集」(2014年2月 森林総合研究所発行)
- 「ツキノワグマ大量出没の原因を探り、出没を予測する」(2011年2月 森林総合研究所発行)
都道府県の研究機関等作成の資料リンク集
都道府県や都道府県の研究機関がとりまとめた資料へのリンク集です。詳細についてはリンク先に記載されている各都道府県の連絡先にお問い合わせください。
一貫作業システム
- 「よくわかる石川の森林・林業技術 No.16「低コスト再造林の進め方」」(2017年3月 石川県農林総合研究センター林業試験場発行)
- 再造林・育林の低コスト化に関する指針(2015年3月 高知県林業振興・環境部発行)
- 「岩手県低コスト再造林事例集」(2014年12月 岩手県農林水産部森林整備課発行)
低密度植栽
- ~ 資源の循環利用につながる~ 2000本植栽育林技術体系(2016年 広島県発行)
- ヒノキ低密度造林における初期保育コスト低減(2016年3月 三重県林業研究所発行)
早生樹利用
- 新たな再造林の手引き(森林再生モデル編)(2020年7月 島根県農林水産部森林整備課発行)
- センダンの育成方法H27改訂版(2015年9月 熊本県林業研究指導所発行)
低コスト造林モデル
- 青森県版スギ低コスト施業技術指針(2019年3月 青森県産業技術センター林業研究所)
- 省力的手法による主伐後の再造林の低コスト化(2018年3月 静岡県農林技術研究所森林・林業研究センター発行)
- 「スギの再造林を低コストで行うために」(2017年3月 秋田県農林水産部林業研究研修センター発行)
- 「低コスト施業の手引き ~施業方法を見直してみませんか~」(2014年3月 北海道水産林務部森林整備課発行)
その他
- 低コスト再造林に向けたコンテナ苗の利用(2017年3月 大分県農林水産研究指導センター発行)
- 皆伐施業後の森林を確実に育てるために~皆伐施業後の更新の手引き~(2015年3月 長野県林務部発行)
- 「造林未済地の解消をめざして-十勝南部の事例-」(2012年3月 道立総合研究機構林業試験場ほか 発行)
過去の調査等
森林整備革新的取組支援事業
平成18年度(2006年度)から平成22年度(2010年度)に実施した「森林整備革新的取組支援事業」の事業概要、優良事例をとりまとめた資料を、以下のサイトに掲載しております。
お問合せ先
森林整備部整備課
担当者:造林間伐企画班
ダイヤルイン:03-6744-2302