2013年7月
2013年7月28日(日曜日)
武尊GSSレポート(第4回)
  今週の巡視先は玉原湿原周辺。 今週の巡視先は玉原湿原周辺。
探鳥路からブナ平に向かう山道に、昨年は
立ち枯れ木にニホンミツバチの巣を見つけま
したが、じきに甘い物好きのクマにほじくりか
えされてしまいました。
そこでどうやらニホンミツバチ考えたようです。
今年は生きたブナの大木の割れ目に新居を
移していました。これではクマも簡単に掘り返
せない。今年は安心して蜜集めに精が出せそ
うです。

道ばたに奇妙な木の実。まるで暑さで溶けかかった丸い実が固まり
なおしたように見えますが、いくら何でもそんなことはありません。
コブシやタムシバと呼ばれるモクレンの仲間の実です。コブシは早春を
告げる花です。花は白く可憐ですが意外と実はグロテスクなんですね。

続いてはヤマブドウが実をつけていました。昨年はダメでしたが今
年は豊作です。今年の暑さは厳しいものですが、木々の実成りは全体
に良いですね。クマたち山の動物にとっては暑い夏は歓迎なのかもし
れません。

最後に見つけたこの実。ちょっと見ると先ほどの山ブドウの実と思っ
てしまいそうですが、万が一にも食べたら大変。これはウルシの実
です。 触ったりしないように注意してください。
戻った玉原湿原はコオニユリの見ごろ。あでやかなユリの花は古く
から皆さんの目に留まる花であったらしく、万葉の時代にはすでに
「百合」の名が使われています。柿本人麻呂や大伴家持の歌に「深
草百合」「さ百合花」という形で出てきます。
さほど太くもない茎に大ぶりな花を付けるので、どうも頭が重そうに
見えてしかたありませんが、あでやかな花なのに、うつむき加減に風
を受けて揺らぐ様子が清楚な美人に例えられるゆえんのようですね。
 
(武尊GSS) topへ戻る
2013年7月27日(土曜日)
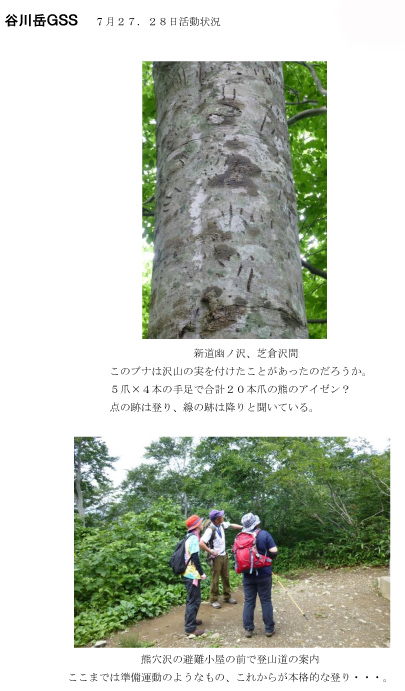 谷川GSSレポート 谷川GSSレポート
(第3回)
谷川GSSより第3回目の
レポート到着です。
谷川連峰には、そういえ
ば「新道」と呼ばれる登山
道が多数あります。吾策新
道、茂倉新道、平元新道な
どなど…。
どうやら新道とつく道は、
自然発生的な踏み分け道
ではなく、登山道とする目
的で新規開設された道を
指すことばとなっているよ
うですね。
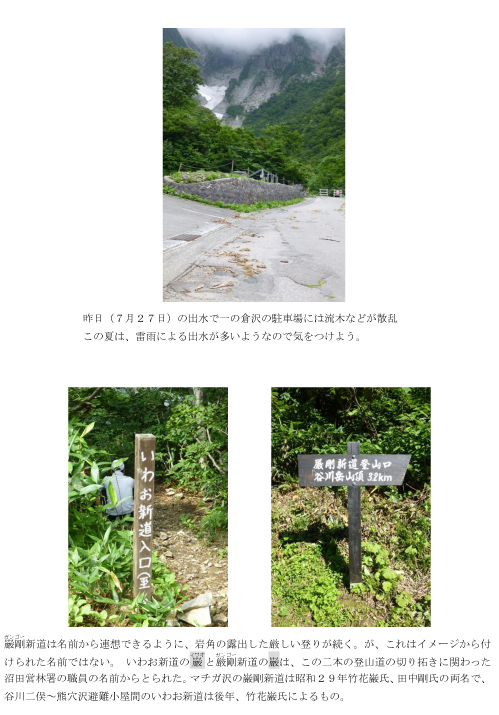

topへ戻る
2013年7月23日(火曜日)
診断書

昨年秋、大枝を落とした奥利根の「ブナ太郎」です。
管轄の水上森林官からも「ここ2、3年、みるみる葉量が減って力強さがなくなり
心配している。」と報告が来ていたところでした。
この「ブナ太郎」、奥利根の森林のシンボルなだけに、自然の成り行きにだけ任
せておくわけにはいきません。今回、樹木医の先生方にお出でいただいて現在の
樹勢診断をお願いしました。

打音による幹内部の状況把握
を行っています。
幹に腐れや空洞があるかどう
かは樹勢判断の重要因子で
す。

根元付近には穴が見つかりました。
穴入口の茶色の土のようなものは幹の
木質部分が腐って粉状に流れ出したも
のです。どうやら樹体には腐朽の進んだ
空洞があるようですね。ポールを差し込
んでみると、奥行きは80センチほどあり
ました。

このブナ太郎、公称では幹回り4.7mとなっています。 円周4.7mの直径は… 470÷円周率=約1.5m
直径1.5mのブナ太郎の根元付近の幹は、すでに半分以上が空洞となっている模様です。空洞がどの程度の高さ
ま で続いているのは、打音で推定していくのでしょう。 で続いているのは、打音で推定していくのでしょう。
もう一点、特に指摘されたのが根の状況でした。
太い主根にも腐れが入っている様子で、良くない
状態だと伺いました。
ウーム… あまり良いお話は聞くことができず、
心配は深まるばかり。ブナ太郎は照葉峡へ続く県
道のすぐ脇にあるので、樹勢の衰えだけでなく、
風倒の危険性なども指摘されれば、厳しい決断も
必要となりかねません。
8月上旬頃、診断結果をまとめて送っていただくこととしましたが、しばらく心配な日々が続きそうです。自分の健康診断の結果より見るのがいやな感じです。 踏ん張ってください、ブナ太郎!
(森林技術指導官)
topへ戻る
2013年7月21日(日曜日)
武尊GSSレポート(第3回)

GSS武尊班はオグナスキー場から前武尊山経由で沖武尊山まで往復してきました。前武尊から南を眺めると、
霞がかった墨絵の山々に目を奪われます。大きく長く榛名山、その手前には子持山、足元のとんがりは戸神山で
す。どうでしょうか?写真は一幅の日本画になっていませんか?
標高を上げるにつれて、左右の景色もだんだんと広
がりを見せてきました。これは沖武尊(山頂)直下から
見えた玉原湖。
武尊山の頂上直下には3つの池がありますが、ここ
は2番目の池。今年は全く水がありません。やはり下
界同様水不足なのか?と考えてしまいました。一方、
3番目の池に来てみると、今年はまだすっぽりと残雪
に覆われていました。雪が多かったのか?雪を溶か
す雨が少なかったのか? それでも今日の暑さには
ありがたい雪です。登りで汗びっしょりとなった体に涼しく心地よ い風が当たってくれます。ああ生き返る~。


干上がった二の池とまだ残雪に埋まる三の池
残雪の周辺にはキヌガサソウが群生していました。傘を広げたように
グルリと円を描く葉が特徴的で、非常に覚えやすい花ですね。ちょうど
今が真っ盛りの時期のようでした。
 
山頂に着くと、頭の上をアキアカネが群れを成して飛び交っていました。上昇気流に乗ってか?ずいぶん高いとこ
ろまで遠征してくるものですね。残雪の付近では雪融けとともに現れる虫を狙っているようでした。
山頂から前武尊方面を眺めると、自分たちが歩いてきた山々が並んでいました。この山々をまた戻らなければなら
ないので、今日の山頂滞在は数分だけ…。山頂には30人ほどの登山者がゆっくりとしていましたが、どうやら夕方に
は天候が崩れそうな様子、早めに気をつけて下山されるように呼びかけて記念にしおりをお渡ししました。
(武尊GSS) topへ戻る
2013年7月20日(土曜日)
 谷川GSSレポート 谷川GSSレポート
(第2回)
谷川GSSより2回目の巡視報
告です。 ずっと天気の不安定
な上越国境ですが、この日は
ガスもとれて良い巡視日和に
なったようです。


topへ戻る
2013年7月18日(木)
皇海山
 当署管内に数ある百名山。編集部の趣味 当署管内に数ある百名山。編集部の趣味
もあって?当ブログでも幾度となく御紹介し
ていますが、なぜか1山だけ全く登場してい
なかった「皇海山」。
今年、ようやく御紹介できるようになりました。
根利栗原川林道から見た皇海山(中央)
理由は林道の復旧です。足かけ3年前の夏の豪雨で不通になっていた根利栗原川林道が、この夏、ようやく全線
復旧できたのです。 登山の皆さんにはもちろん、地元関係の方々にもたいへん御迷惑をおかけしました。
 今日は定期的に実施している林道点検日。全線41㎞という長大な 今日は定期的に実施している林道点検日。全線41㎞という長大な
根利栗原川林道を点検がてら、我々も久しぶりに皇海山登山口まで
足を延ばしてみました。
 
登山・林道の安全注意標識
登山口はひっそりと静まりかえっていました。いくら百名山の登山
口とはいえ、さすがに今日は平日でしたね。それにしても久しぶりに
来てみると「登山注意」「林道注意」の看板・標識がずいぶんと増え
ていたのに驚きました。
この群馬県側の皇海山登山道、アプローチの林道だけでも深い谷あいのクネクネ道を20㎞近く走る必要がありま
すし、山が立っているので登山道も急な上り下りが続きます。実際に多くの林道車輌事故、山へ入っての遭難事故
が起こる山となっているのです。 「注意標識が多いのはダテじゃない」と理解して入山いただけますようお願いいた
します。 特に、林道については復旧したとはいうものの、もともと脆弱な地質・地形のエリアなので、最近多発する
ゲリラ豪雨などで谷が抜けたりすると、そのまま閉じ込められてしまう危険もある林道です。雨の日の入林は御法度
ですよ。
おっと…つい心配事ばかりが口をついてしまいますが、どうぞ山のルールとマナーを守りながら、皇海山を楽しんで
いただけますよう。 (署 次長)
topへ戻る
2013年7月14日(日曜日)
 武尊GSSレポート(第2回) 武尊GSSレポート(第2回)
今日はのっけからいやな報告です。
クマなどの野生動物が地面を掘った後は珍しくありませんが、
これは人間が掘り返した跡です。クリンソウの盗掘跡です。
先週はこの場所に赤い花が見ら れました。まだいくつか残って
いましたが、クリンソウは鮮やかな赤い花をつけるので心なき人
たちのターゲットになりやすいのでしょう。
どうせ持ち帰ったところで枯れてしまうのがオチでしょうに…。
今どきこんなことをする輩がいるのですね。情けない思いで巡
視をスタートしました。
こんな日はわるいものばかり見えてしまうのでしょうか? これはキハダの
木の削り跡です。キハダはミカンの仲間になるそうですが、木の皮のコルク部
分がまっ黄色になり、黄檗(オウバク)という生薬になります。とても苦い木の皮
だそうで、昔は飲みすぎで胃腸を壊したオジさんたちが苦さに耐えながらキハ
ダの皮をなめていたものです。
この削り跡、薬にしたくて削ったのか? おもしろがって削ったのか?はわか
りませんが、今のご時世、良い薬はいくらでも手に入ります。
いやな話ばかりを報告するのがGSSのお役目ではありません。
今週の玉原高原は、ツルアジサイとキツリフネがグッと目立つようになってき
ました。特にツルアジサイは、昨年、ほとんど花が見られなかったのですが、
 今年はまるで木に咲く花であるかのように見えますね。実は、樹木の生育にとってツル植物はありがたくないのですが、純粋な自然界ではこれも大切なメンバーです。 (武尊GSS) 今年はまるで木に咲く花であるかのように見えますね。実は、樹木の生育にとってツル植物はありがたくないのですが、純粋な自然界ではこれも大切なメンバーです。 (武尊GSS)

topへ戻る
2013年7月13日(土曜日)
谷川GSSレポート(第1回)

今週は谷川岳GSSから
の花の便りが届けられま
した。
山々の植物にはすでに
盛夏の装いで、実なりを
見せる木々も出てきてい
ます。
 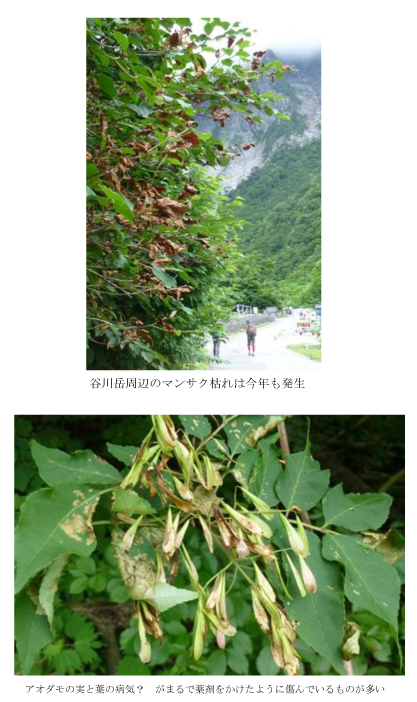
topへ戻る
2013年7月12日(金曜日)
准フォレスター研修 今年もスタートです
関東ブロック「准フォレスター研修Ⅰ-①」が7月1~5日に、同じく「林業専用道技術者研修①」が7月10~12日
に実施されました。皆様御案内のとおり、地域の森林・林業の牽引者となる人材の育成を目指した研修が「准フォレ
スター研修」であり、全国の森林管理局毎に7ブロックで開催されています。
一方「林業専用道技術者研修」も、同じく全国7ブロックで開催される、森林・林業再生に必要な路網整備の中核
となる「林業専用道」作設のスペシャリストを育成するためのものです。なお、「准フォレスター研修」は研修Ⅰと研修
Ⅱから構成され3回ずつ、「林業専用道技術者研修」は4回、それぞれ実施されることとなっております。
「准フォレスター研修Ⅰ-①」では、関東森林管理局管内の5県から県職員20名、国有林職員3名の計23名が6
班に分かれてグループワーク等様々なカリキュラムに取り組みました。研修3日目の現地実習では、時より小雨の
降るあいにくの天候の中、各班とも精力的に林内を歩き回り、発表の際には活発な意見交換が行われました。

*谷地森林事務所部内における 「森づくりの構
想現地実習」の様子
各班毎に成果を発表しました。
「林業専用道技術者研修①」には、関東森林管理局管内の11都県から都県職員10名、市町村職員4名、森林
組合職員4名、独立行政法人職員1名、国有林職員5名の計24名が参加されました。梅雨明けの猛暑の中、国有
林の既設林道を利用した現地実習では、熱中症に注意しつつも各研修生の真剣な眼差しが林道の各ポイントに注
 がれていました。 がれていました。
* 沼田森林事務所部内における「林業専用
道作設技術演習」の様子 既設道の修
正案を探りました。
各研修生の皆さんの今後の御活躍に御期待しつつ、第2回目以降の研修にも誠意を持って取り組んで参りますの
で、関係機関の皆様の御支援、御協力をよろしくお願い申し上げます。 (署 企画官)
topへ戻る
2013年7月8日(月曜日)
玉原高原 初夏のラベンダー
 玉原高原のスキー場を利用したラベン 玉原高原のスキー場を利用したラベン
ダー園が開園しました。
夏の安全祈願祭に参加した帰り道。
まだつぼみながら鮮やかなラベンダー色
を見せる花々を鑑賞させていただきまし
た。

まだまだ 全景は淡い色合いですが、
スキー場の広いスペースを使ってのお花
畑は、スケール感がありますね。
 今を盛りと咲き乱れていたのはニッコ 今を盛りと咲き乱れていたのはニッコ
ウキスゲ。満開状態がしばらく続くよう
に見えるこのキスゲの群落ですが、1
つの花が開いているのはたったの1日
だそうです。
同じ茎でも一気に開花せず、順序よく
1つ2つずつ花を開かせて受粉のチャン
スを窺うキスゲの作戦のおかげで、私た
ちもこの鮮やかな色合いを長く楽しめる
というもの。
キスゲには緑と青空がよく似合います。
(沼田 森林事務所)
topへ戻る
2013年7月6日(土曜日)
GSSによる巡視活動が始まりました
今年も例年どおり、武尊地区・谷川地区のGSS活動が始まりました。いずれも3名態勢で週末の現地を担当させ
ていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
さっそく武尊チームから報告が届いています。 
さあ今日からまた玉原巡視の日々の始まりです。
GSSとしては8ヶ月ぶりの玉原高原。まずは昨年との変
化が気になるところです。
玉原湿原に入ったところで、湿原の休憩所に設けられ
ていた案内のプレートが新しくなっていました。 実は旧
プレートは色も薄くなって何が書かれているのかよくわ
かりませんでしたので、これは良いことです。今年は多
くのハイカーの皆さんに湿原の魅力を説明してくれるこ
とでしょう。

続いてはブナ平へ回ってみると…、歩道の真上の遙か頭
上に引っかかっていた枯れ枝。昨年注意看板を立てたところ
ですが…

ありゃりゃ、冬場の雪とともに落下していてくれると良いな
と思っていたのにそのままぶら下がっています。 今年も引
き続き危険箇所ですので、ブナ平訪問の皆さん、くれぐれも
御注意ください。

今年は山の植物も例年より元気が良いというのか、色
合いの良い夏を迎えています。
例えば、昨年は実をつけなかったブナの木ですが、今
年は豊作です。ブナは大量に実をつけた翌年は実をつけ
ないので、もうひとひねりすると来年は不作ということにな
りますが、とりあえず今年は山の動 物たちの食料 が豊富 物たちの食料 が豊富
になりそうです。
ブナの実を地元では「ブナグリ」と呼びますが、どことなく
栗に似た実をつけます。地面に落ちていたブナグリを拾っ
て中身を見てみると、そろそろ 色が茶色っぽくなってきま
した。
そういえばブナの実を食べるためにクマが木の上に上っ
ていることがあるので要注意ですが、いまのところ、まだ
クマ棚と呼ばれる、クマが木の上で枝を寄せ集める大き
な鳥の巣上の枝の塊は見えません。たぶん今か今かと
時を待っていると思うのですがね。 (武尊GSS)
topへ戻る
2013年7月4日(木曜日)
玉原越え
 みなかみ町藤原の藤原ダムの近くに境界標探しに出かけたときのこと。 みなかみ町藤原の藤原ダムの近くに境界標探しに出かけたときのこと。
現地への小径を辿りながら「昔 藤原の住人はこの道を越して沼田へ出た
んだ。」という話を現場の方から教えられ、ああ これが玉原高原でよく目に
する「玉原越え」の道標の出口なんだとわかりました。
どおりで小径には昨年の落葉がそのまま積もっていて通る人もほとんどな
い様子なのに、道自体はよく踏み込まれていて忘れられた古道の趣のある
径でした。
実際使われていたのはいつ頃のことかと尋ねると「うちのばあさんは通ったこ
とがあるとと聞いたな。」とのこと。「うちのばあさんは…」という当人がすでに私
より年上なのですからかなりのものだぞ、とは感じますが具体的にピンとこな
い。戻って調べてみると…。
この玉原越の径は、当時、藤原~水上~後閑を経由する現在の国道291号線沿いの街道に比べて、直線的に沼
田方面を結ぶ道として藤原地区の人たちに利用されていたとか。そして上越線の水上駅、湯桧曽駅開業の頃には利
用されなくなっていたようです。上越線の水上開通が昭和3年(1928年)、湯桧曽を越えて新潟まで繋がったのが昭和6
年(1931年)ですからもう80年前のこと。
 もう少しネットを当たってみると、なんと昭和7年の記録が掲載され もう少しネットを当たってみると、なんと昭和7年の記録が掲載され
ていました。この方は、夜行の上越線で湯桧曽駅から夜後(藤原ダ
ム)~玉原越~発地~沼田を踏破しています。直線距離でも22~23
㎞あるコースを、日帰りで歩くのですから昔の方は本当に強かったの
ですね。
記録には「夜後から古い石の指導標に導かれ、牛の羊腸たる道を
辿る。」「行けば行くほど人跡未踏の如き荒廃した道となり、橋あれども朽ちて用なさず雑草は徒に茂って道をふさい
で、周囲は千年の老木鬱々として晝(昼)なお暗く静かなること太古のごとし」など、現在からは想像もできないような
様子が書かれています。すでに昭和7年には整備されなくなって月日が経っていたようですね。「うちのばあさん」の
時代となると100年近い昔話と聞くべきなのでしょう。
 80年以上前に利用されなくなった道にしては少々しっかり 80年以上前に利用されなくなった道にしては少々しっかり
しすぎに思えたのですが、現場の人からもう一つ教えてもら
ったのがこの場所です(左写真)。玉原越しの道が大岩にさ
えぎられて、隙間を縫って通るこの場所。すぐ左側の渓筋に
は大きな滝がかかっているのが見えました。
「ここは「クラッパギ」と名が付いている場所。」
「クラッパギ? 何のことだろう?」
「この道は伐採の馬そり道になっていたそうだが、この岩がじゃまをしてそのまま通れなかったんだな。いったん馬の
鞍をはがさなきゃならない場所なんでクラッパギだったんだそうですよ。」
「なるほど…」
 合点がいきました。一般の通行が途絶えた後、この道は運材路として馬そり 合点がいきました。一般の通行が途絶えた後、この道は運材路として馬そり
が行き来する道となっていたのです。それで現在もこのしっかりした道型が残
ったという訳ですか…。
もう今や何を調べてみてもそんな地名・呼び名は出てきません。かろうじて個
人の記憶と伝承の中に生きている呼び名なのですね。
ホンの小さな山道の記憶ですが、山の位置付けや歴史までが垣間見えるよ
うな気がしました。今度一度、玉原を越えてみなければなりません。
(中澤署長・水上森林事務所)
topへ戻る
2013年7月1日(月曜日)
おいでおいで

4年目に入ったみなかみ地区でのナラ枯れ対策。今年
もそろそろカシナガの羽化・飛翔期に入ります。
これまでの3年間は幸いと爆発的なナラ枯れ発生には
至らずすんでいるものの、確実に数十本ずつ枯死木が発
生しています。今もきっとどこかのミズナラの木の中で、
飛び出す機会をうかがっていることでしょう。
「動き出しを捕らえることが肝心」との専門家の指導を受
け、今年もこの6月末におとり丸太を被害地区の中心に設
置完了しました。このおとり丸太、あまり早くに設置しすぎ
ると丸太が乾いてしまい、カシナガにとって魅力が薄れる
ようなので、県の試験場からも適期のアドバイスをいただきながらの設置となりました。
 
頼みは誘引剤(左写真)と乾燥・日照防止のムシロ。
これで準備万端、さあいらっしゃい。
すぐ隣には県試験場が、発生予察の確認のために捕獲器も設置しています。
今日見に出かけたところ、?……らしいのが1匹、捕獲器に浮いていました。
 いよいよ来るのか? いよいよ来るのか?
(署 森林整備官(育成担当))
topへ戻る
+先月の記事へ+
|
![]()
![]()