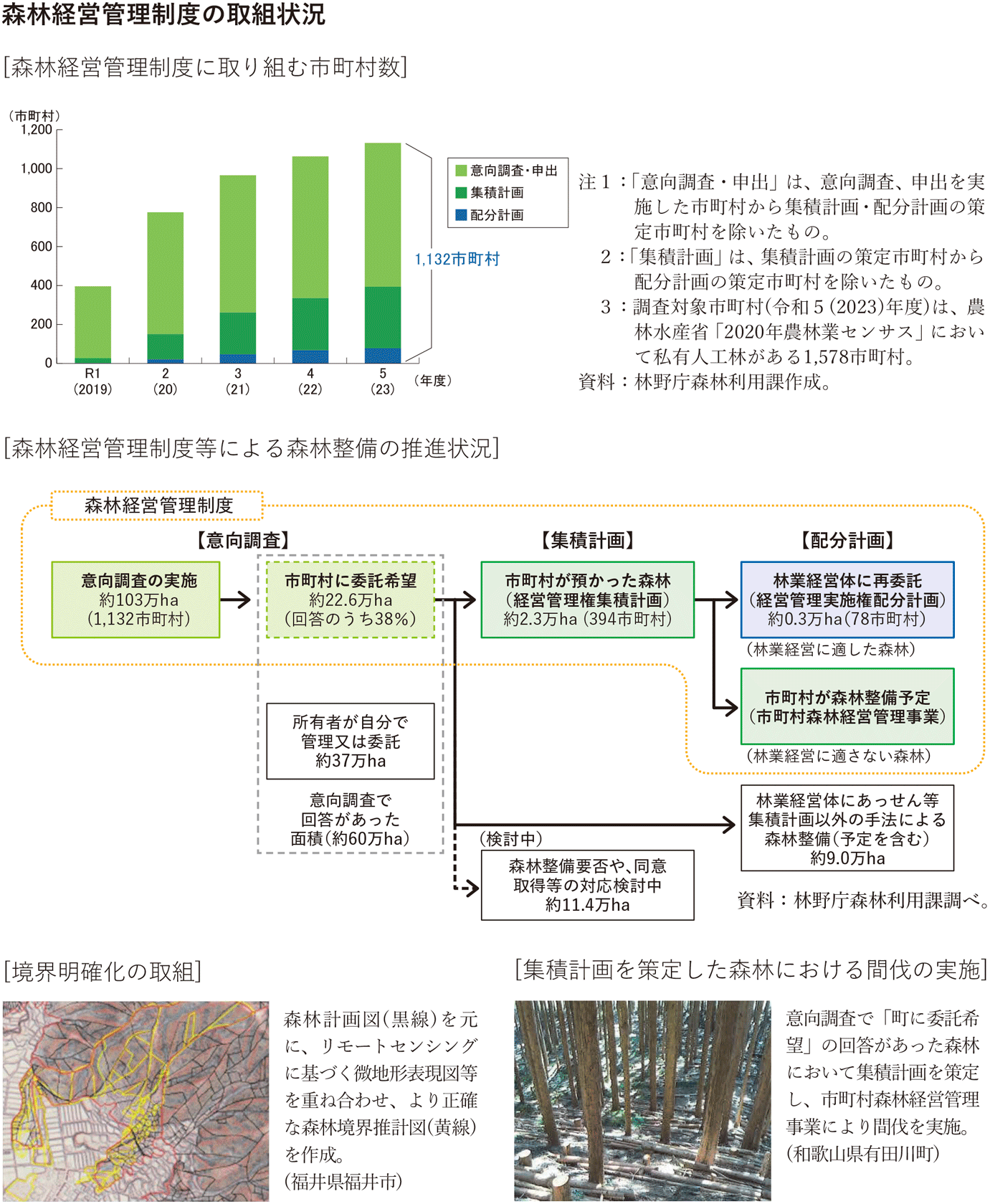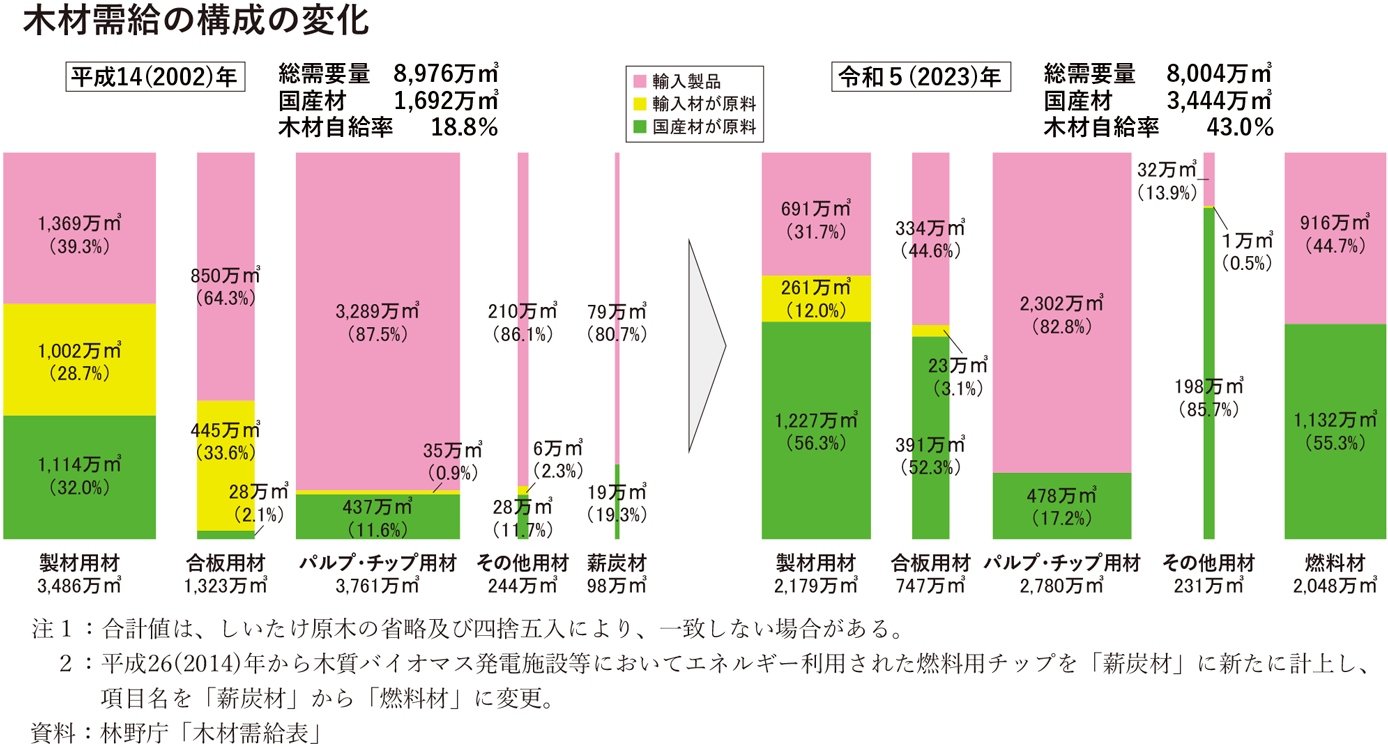第1部 トピックス
2.「林業職種」の技能検定がスタート ~「林業技能士」の誕生~
5.プラスチックを代替するバイオマス由来素材「改質リグニン」の今後の展開
1.森林経営管理制度5年間の取組成果




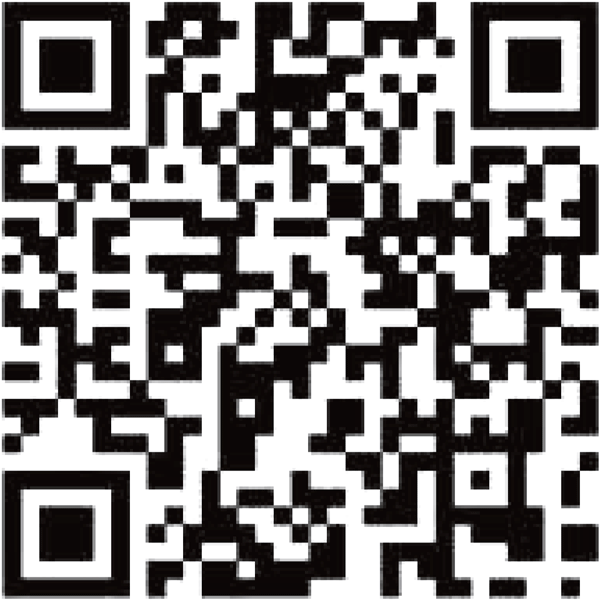
我が国では、人工林1,009万haのうち、私有林人工林が650万haと64%を占めています(*1)。私有林では、平成24(2012)年度から導入された森林経営計画制度の下、施業の集約化を行いながら適切な経営管理が進められてきました。しかしながら、私有林人工林の約3分の2では経営管理が不十分となっているおそれがあり、森林所有者の高齢化や相続による世代交代・不在村化、未登記等により、所有者の特定や境界の明確化に多大な労力がかかることから、民間が主体の取組だけでは森林整備が進みにくい状況にありました。
このため、平成31(2019)年4月、森林経営管理法が施行され、市町村が主体となって森林の経営管理を行う森林経営管理制度が導入されました。本制度では、手入れの行き届いていない森林について、市町村が所有者に対する意向調査を行い、それに基づき所有者から委託(経営管理権の設定)を受けた場合は、所有者と林業経営者の仲介役となり、林道から近く収益が見込めるなどの林業経営に適した森林は林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が自ら管理を行うこととしています。所有者不明森林等についても、一定の手続を経れば経営管理権の設定ができる特例措置(*2)が設けられています。
本制度の導入から5年が経過する中で、市町村においては、これまでに実施体制の整備、意向調査の実施、現地調査と境界明確化の実施、経営管理権集積計画・経営管理実施権配分計画の策定等について、地域の実情に応じた方法を検討の上、様々な取組が行われてきました。この結果、制度の活用が必要な市町村のほぼ全て(1,132市町村)において本制度に基づく取組が実施されています。令和5(2023)年度末までに、意向調査については、約103万ha実施されています。回答があったもののうち約4割について市町村への委託希望があり、所有者から経営管理を受託する際に策定する経営管理権集積計画については、40道府県394市町村の23,290haで策定され、うち294市町村で8,370haの森林整備(市町村森林経営管理事業)が実施されています。林業経営者に再委託する経営管理実施権配分計画については、24道府県78市町村の3,177haで策定され、48市町村で598haの森林整備が実施されています。このほか、林業経営体へのあっせん、市町村と所有者との協定の締結、市町村独自の補助の活用等の手法も含めると、市町村への委託希望の森林のうち約5割で森林整備につながる動きがみられます。また、所有者不明森林等への対応については、156市町村において所有者の探索が実施され、令和6(2024)年度末までに12市町において特例措置が活用されています。
本制度の運用については、積極的な取組がみられる一方、林業経営体など地域の関係者と市町村との連携が不十分で集約化につながっていない、林務担当職員を始め市町村職員の不足等により市町村の体制が十分でないなどの課題もあります。
これらの課題を踏まえ、令和7(2025)年2月に、現行の仕組みに加えて、受け手となる林業経営体など地域の関係者が森林の経営管理の将来像を共有し、経営管理の集約化を通じた森林資源の循環利用を進める新たな仕組みの創設や、委託を受けて市町村事務を支援する法人を制度的に位置付けることなどを内容とする「森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。
(*1)林野庁「森林資源の現況(令和4年3月31日現在)」
(*2)所有者不明森林等の特例措置については、第1章第2節(5)65-66ページを参照。
2.「林業職種」の技能検定がスタート ~「林業技能士」の誕生~


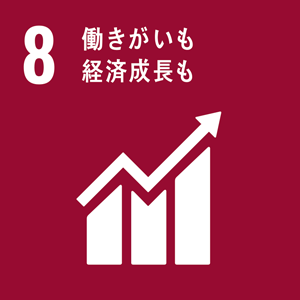


林業は、多様な自然条件下での作業が多いことから、林業従事者は気象や地形など現地の状況に応じた適切な作業を行うとともに、チェーンソー等の機械類や刃物を使用するに当たっては正確かつ安全に作業を行う必要があり、高度な技能や専門的知識が求められます。また、林業従事者を守り、林業労働力を確保するためには、林業が⾧く働き続けられる魅力ある産業となることが重要です。
このため、林業従事者の技能向上とともに、就業環境の整備及び社会的・経済的地位の向上、さらには安全性の向上による労働災害の減少に寄与することを目的として、令和6(2024)年8月、「職業能力開発促進法施行規則」等の一部が改正され、国家検定制度である技能検定の職種に「林業職種」が新設されました。本検定の合格者は「林業技能士」と名乗ることができます。
林業職種は、育林作業、素材生産作業における必要な技能や知識が対象で、複数等級(1級、2級、3級及び基礎級)により試験が実施されます。各級は学科試験及び実技試験から構成されており、実技試験にはチェーンソーを実際に使用して行われる科目も含まれます。
本検定は、試験業務を行う指定試験機関として指定された一般社団法人林業技能向上センターにより行われます。第1回試験(1~3級)として、令和7(2025)年1月から2月にかけて、学科試験及び実技試験が愛媛県、熊本県の2か所で行われました。
また、本検定は、令和6(2024)年9月に林業職種(育林・素材生産作業)が追加された外国人技能実習制度(*3)における評価試験としても活用されます。これにより、技能実習2号及び3号へ移行でき、1号から通算して最大5年の技能実習が可能となります。同センターは、令和7(2025)年3月に愛媛県で技能実習生向けの試験(基礎級)を実施しました。
林野庁では、関係省庁や関係団体と連携を図りつつ、本検定における林業職種の受検勧奨等も含め、林業従事者の技能の向上、さらには能力評価を通じた雇用環境の改善に取り組んでいくこととしています。
(*3)人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とした制度。
3.木材自給率が近年で最も高い43%まで回復


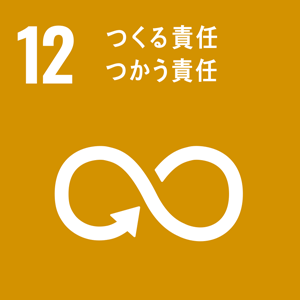

世界有数の森林国である我が国において、森林資源の循環利用を進めることは、森林の有する多面的機能の持続的な発揮や地域経済の活性化に貢献します。
我が国の木材自給率は、国産材供給の減少と木材輸入の増加により低下が続いていましたが、平成14(2002)年の18.8%を底に近年は上昇傾向で推移してきました。令和5(2023)年の木材自給率は43.0%まで回復し、直近で最も高い水準となりました。特に建築用材等においては、製材用材で56.3%、合板用材で52.3%となるなど5割を超えています。
自給率が上昇してきた背景には、人工林資源の充実のほか、合板原料としての国産材利用の増加等が挙げられます。技術革新により間伐材等の小径木から合板の生産が可能になった(*4)ことなどから、平成14(2002)年頃から国産材利用が急速に進みました。
また、平成24(2012)年に再生可能エネルギーの固定価格買取(FIT)制度が導入されたことなどにより、木質バイオマス発電施設の整備が各地で進んだことに伴い、燃料用チップ等の燃料材の利用量も年々増加しており、国産材供給量増加の要因となっています。
建築用の製材用材では、木造軸組工法においてスギ集成材など国産材利用が進みつつあるほか、枠組壁工法構造用製材の国産材率が上昇傾向にあります。一方、梁(はり)や桁等の横架材では輸入材が高いシェアを有しており、林野庁では、更なる自給率向上に向けて、スギ大径材を効率的に製材する技術の開発や、国産材による高強度の異樹種LVL梁(はり)の開発等、国産材率の低い部材への国産材利用に向けた技術開発・普及等を推進しています。
また、今後は人口減少等により⾧期的に新設住宅着工が減少する可能性を踏まえると、住宅分野以外にも、中高層建築物等における木材利用を進めることが重要となっています。
(*4)合板の製造に必要な単板はロータリーレースという機械を使用して原木を大根の桂剥きのように切削して作られるが、かつては切削時に太い「剥き芯」が残ることから大径の輸入材が利用されていた。
4.中高層建築物等における木造化の広がり



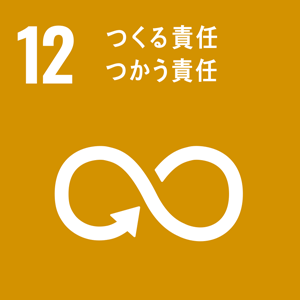

建築用木材の需要の大部分は1~3階建ての低層住宅が占めていますが、近年、木材があまり使われてこなかった都市部の4階建て以上の中高層建築物においても、国産材を活用した木造ビルが多くみられるようになっています。
建築物に利用される木材は炭素を⾧期的に貯蔵すること、製造・加工時のエネルギー消費が比較的少ないため二酸化炭素排出量の削減につながること、再生産可能であることなどから、建築物への木材利用は2050年ネット・ゼロの実現に貢献することが期待されます。このことから、大手建設会社等では中高層ビル等を建設する際に国産材を積極的に利用する動きが広がっています。
これらの大手建設会社等の中には、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化推進法)において創設された建築物木材利用促進協定を締結している企業もあります。協定に基づく木造建築物は全国で増加しており、令和6(2024)年に木造化・木質化された建築物は2,817件、木材使用量は計124,852m3となっています。また、令和6(2024)年12月時点で、国との協定締結は25件、地方公共団体との協定締結は146件となっています(*5)。
さらに、中高層ビルだけでなく、木造率が低い状況にある店舗やオフィスなどの民間の低層の建築物においても木造化の動きがみられ、コンビニエンスストアを展開する企業が協定を締結し、新店舗を木造で建設するなどの例もあります。
林野庁では、中高層木造建築物等が今後更に広がるよう、優良事例の普及・展開や協定制度の周知などに取り組んでまいります。
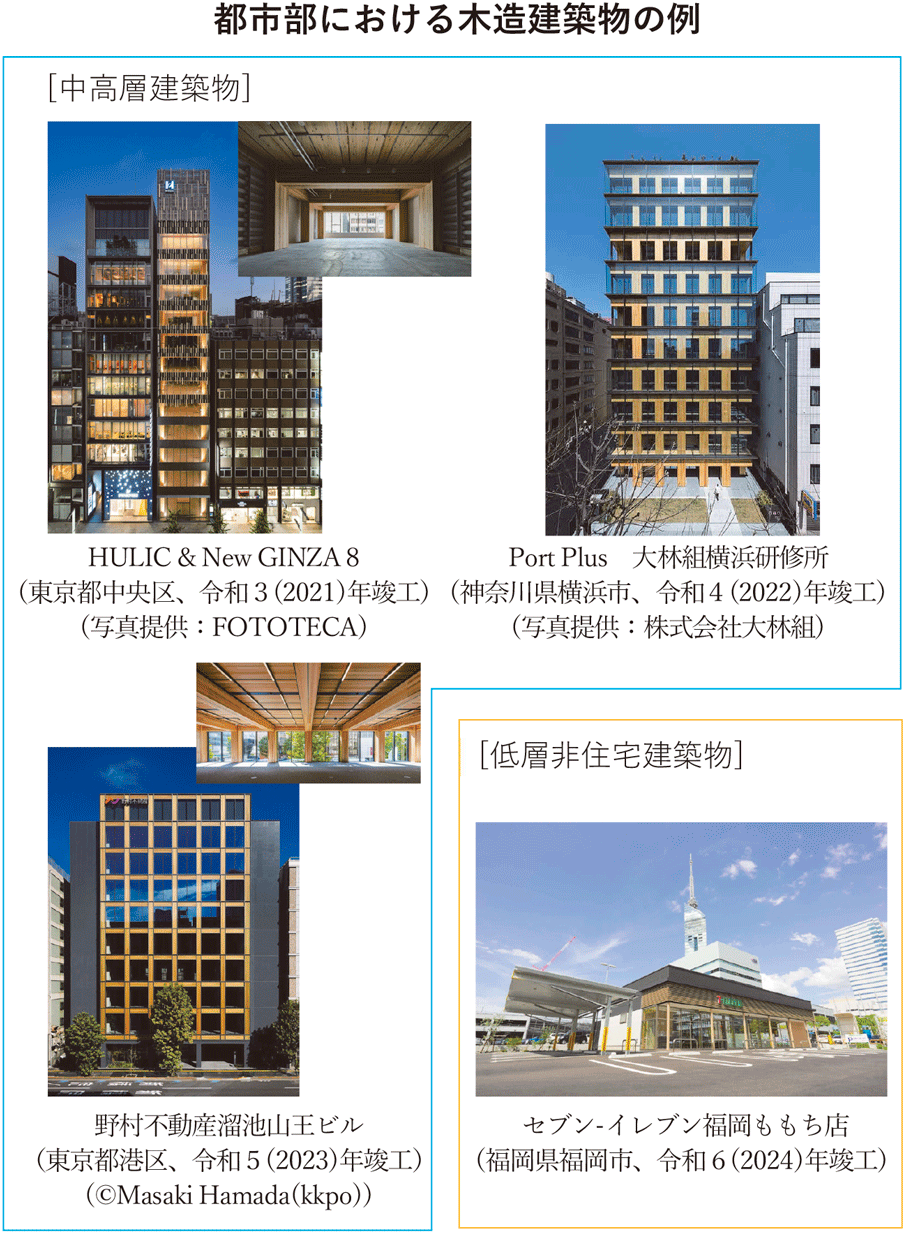
(*5)農林水産省プレスリリース「「令和6年度 建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ」等について」(令和7(2025)年3月26 日付け)
5.プラスチックを代替するバイオマス由来素材「改質リグニン」の今後の展開


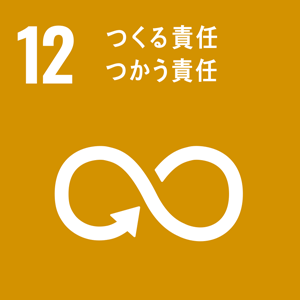

2050年ネット・ゼロの実現に向け、温室効果ガス排出削減の取組が世界的に進められる中、国内外の産業界から、従来の化石資源由来プラスチックを代替するバイオマス由来の素材が強く求められています。林地残材や製材端材等の木質バイオマスを原料とする木質系新素材は、このような社会ニーズに応えることが可能であるほか、地域経済の活性化やサーキュラーエコノミー(循環経済)の観点からも、その社会実装が急務となっています。
木材の主要成分の一つであるリグニンは、化学構造が多様であるため、安定した品質が求められる工業材料としての利用は困難とされてきましたが、国立研究開発法人森林研究・整備機構は、我が国固有の樹種であるスギのリグニンが比較的均質であることに着目し、スギ材を原料とした木質系新素材「改質リグニン」を開発しました。加工性が高く耐熱性・強度に優れ、高機能プラスチックを始め幅広い用途に利用できることから、産学官の連携を推進する「地域リグニン資源開発ネットワーク」(リグニンネットワーク)の会員企業等(*6)と国立研究開発法人森林研究・整備機構の共同により、様々な用途開発が行われてきました。
このような中、改質リグニンの社会実装の早期実現に向けて、林野庁では、学識経験者を交えて「改質リグニンの今後の展開に向けた勉強会」を開催し、課題を整理した上で、令和6(2024)年4月に、改質リグニンの大規模製造技術の確立や環境適合性の評価などの今後の展開方向を取りまとめました。
これを踏まえ、林野庁では、令和6(2024)年度から、愛媛県⿁北町(きほくちょう)でスタートアップ企業が行う大規模製造技術の実証を支援しています。この実証の成果を基に、1工場で年間16,000m3のスギ材(*7)から2,000トンの改質リグニン(*8)を製造することが計画されています。また、ライフサイクルアセスメント(LCA)の観点から改質リグニンの環境適合性の定量的評価を実施しています。
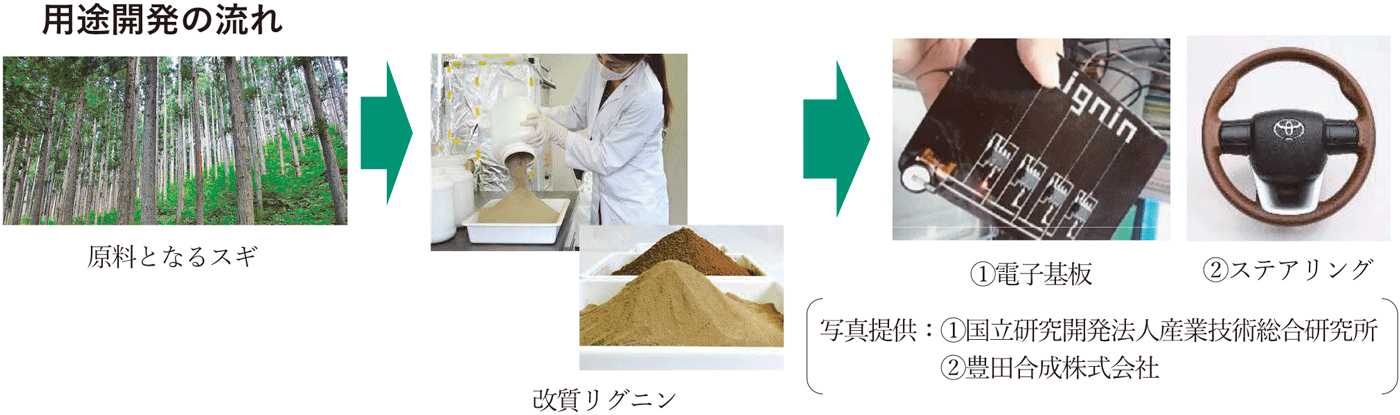
(*6)林業や木材加工業、化学品製造業、電機・電子部品製造業、自動車部品製造業、卸売業(商社など幅広い分野の約130の企業等が参画(令和6(2024)年12月時点)。
(*7)年間の原木消費量4万m3の製材工場(工場の規模としては中程度)において生ずる製材端材に相当する量。
(*8)これまでの研究成果では、製品に含まれるプラスチックの2割を改質リグニンに置き換えることが可能。2,000トンの改質リグニンは、自動車10万台(国内新車販売台数の約2%)のプラスチックを置換え可能な量。
6.令和6年能登半島地震と大雨による山地災害等への対応



令和6(2024)年1月1日に発生した令和6年能登半島地震における林野関係の被害箇所数は、令和7(2025)年3月時点で、林地荒廃278か所、治山施設68か所、林道施設等2,283か所、木材加工流通施設・特用林産施設等140か所、被害総額は約901億円となっています。
林野庁では、地震発生翌日に、ヘリコプターによる被害の全容把握調査を行ったほか、農林水産省サポート・アドバイスチーム(MAFF-SAT)を派遣し、山地の被害状況把握や復旧計画の策定に向けた技術支援を実施しました。くわえて、国土地理院と連携して航空レーザ計測を行い、地形状況を把握し、令和6(2024)年7月からその速報成果について石川県や関係市町村への提供を開始しました。
被災地域の早期復旧に向けては、輪島(わじま)市及び珠洲(すず)市の民有林に生じた大規模な山腹崩壊箇所等について、国直轄による災害復旧等事業を実施しています。令和6(2024)年9月には災害復旧等事業に引き続き、継続的な復旧を進めるため、両市の民有林6区域において10年間を復旧期間とする民有林直轄治山事業に着手しました。
被害箇所数の多い林道施設については、他の地方公共団体の職員及び県外のコンサルタントの応援を得ながら、林道の被害調査・測量、林道施設災害復旧事業の災害査定申請書類作成等が進められてきました。林野庁では、簡素化・効率化を図りながら災害査定を実施し、令和6(2024)年12月末に完了しました。
また、被災者の生活と生業(なりわい)の再建に向け、木材加工流通施設、特用林産振興施設等の復旧・整備等を支援するとともに、被災林業者を一時的に雇用する事業体を支援しています。
応急仮設住宅については、鉄骨プレハブに加え、⾧屋型の木造や被災前の居住環境に近い戸建風の木造での建設が行われています。令和6(2024)年12月時点で、石川県では、応急仮設住宅のうち23.3%が木造で建設されています。
このような中、石川県能登地域においては、令和6(2024)年9月20日からの大雨によっても山腹崩壊等の被害が発生しており、令和7(2025)年3月時点で、林地荒廃17か所、治山施設25か所、林道施設等539か所、木材加工流通施設等5か所で被害が確認され、被害総額は約220億円となっています。林野庁では、地震被害の際に取得した航空レーザ計測データも活用しながら、石川県や関係市町に対して、被害把握や復旧計画の策定に向けた技術支援を行っています。
これまでの支援等を通じて、石川県内の地震及び大雨により被災した木材加工流通施設・特用林産施設等は、令和7(2025)年3月時点で、61か所のうち49か所で営業が再開されています。
林野庁では、引き続き被災地の早期復旧に向けた取組を全力で進めるとともに、林業・木材産業等の復旧・復興への支援を行ってまいります。
→応急仮設住宅における木材の活用については第3章第2節(2)を参照
「農林水産祭」における天皇杯等三賞の授与
林業・木材産業の活性化に向けて、全国で様々な先進的な取組がみられます。このうち、特に内容が優れていて、広く社会の賞賛に値するものについては、毎年、秋に開催される「農林水産祭」において、天皇杯等三賞が授与されています。ここでは、令和6(2024)年度の受賞者(林産部門)を紹介します。
天皇杯 出品財:経営(林業経営) 株式会社T-FORESTRY 神奈川県小田原(おだわら)市
株式会社T-FORESTRYは、スギ、ヒノキ人工林等の森林資源と、都市近郊で観光地に隣接した立地を活かし、森林をレクリエーションのための活動空間とするサービスを展開しています。「フォレストアドベンチャー」では、木々の間に張られたワイヤーを使い、ジップスライド(空中滑空)や樹間歩行で約1haの森林内を巡ることができます。また、森林作業道を活用した2.5kmのコースでマウンテンバイクを楽しむ「フォレストバイク」事業も展開しており、年間約2万人が訪れる人気スポットになっています。森林空間の活用によって収入を確保し、林業経営の持続性を高める先進事例として注目されています。
内閣総理大臣賞 出品財:技術・ほ場(苗ほ) 惣田 政宏 氏 北海道広尾町(ひろおちょう)
惣田氏は、平成8(1996)年に有限会社惣田種苗園に入社し、森林管理局、北海道、民間から技術者を招いて苗木生産の技術を研鑽(さん)しました。令和3(2021)年に同社代表取締役に就き、「北海道内で一番優良な苗木の安定供給」を自身の理念に掲げ、現在は70haのほ場で主にトドマツ、カラマツの苗木を年間約160万本生産しています。また、同社創業の地であるえりも町(ちょう)では、かつて森林が失われ流出した土砂で漁場が荒れたため、先人たちが森林づくりに取り組み漁場を復活させたという経緯を強く受け止め、漁業関係者を積極的に雇用し、苗木生産を通じて森林の重要性の理解の共有につなげています。
日本農林漁業振興会会長賞 出品財:経営(林業経営) 山田 芳朗 氏 静岡県静岡市
山田氏は、所有する157haの森林において、115m/haの高密度な路網と高性能林業機械を活用して間伐等の森林整備を行っており、柱材を主とした良質な木材生産により、林業収支がプラスとなる経営を続けています。また、指導林家(注)として若手の林業家や林業従事者の技術力の向上に取り組むほか、地元の小学生を対象とした森林教室の講師を引き受けるなど、幅広い活動に取り組んでいます。さらに、山田氏が所属する林業研究グループでは、平成17(2005)年に山田氏の所有林を含むグループの所有林で森林認証を取得し、地元のイベントにおいても認証制度の普及に取り組んでいます。
注:模範的な施業技術等を有しているとして都道府県知事が認定した林家。
森林×ACT(アクト)チャレンジ
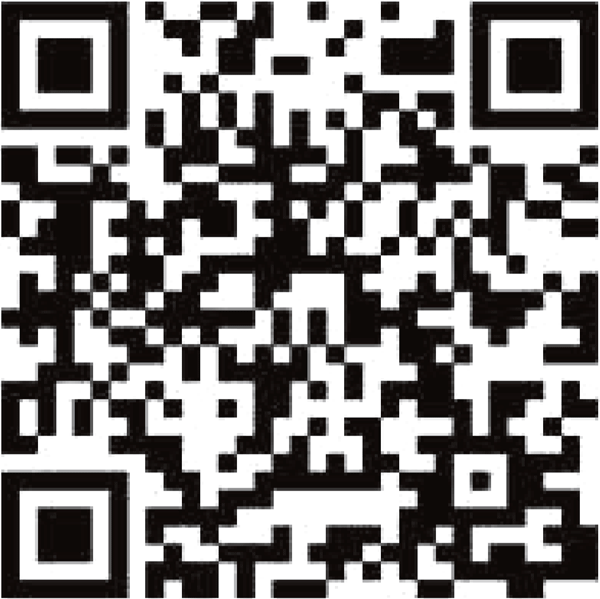

林野庁では、企業等による森林(もり)づくり活動をカーボンニュートラルへの貢献や生物多様性保全等の観点から顕彰する「森林×ACTチャレンジ(注)」を実施しています。ここでは令和6(2024)年の受賞者と取組内容を紹介します。

(注)令和6(2024)年に「森林×脱炭素チャレンジ」から「森林×ACTチャレンジ」に名称を変更。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219