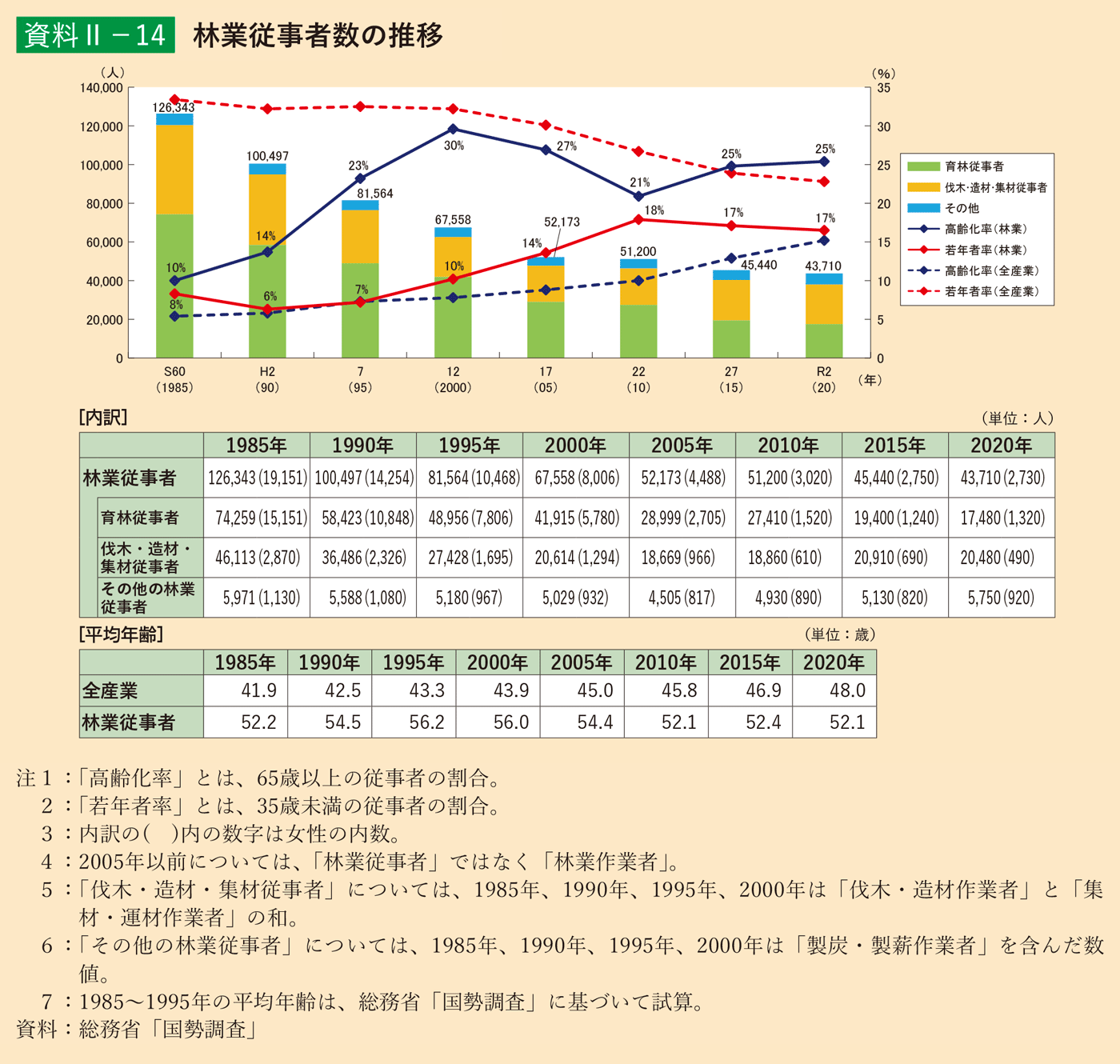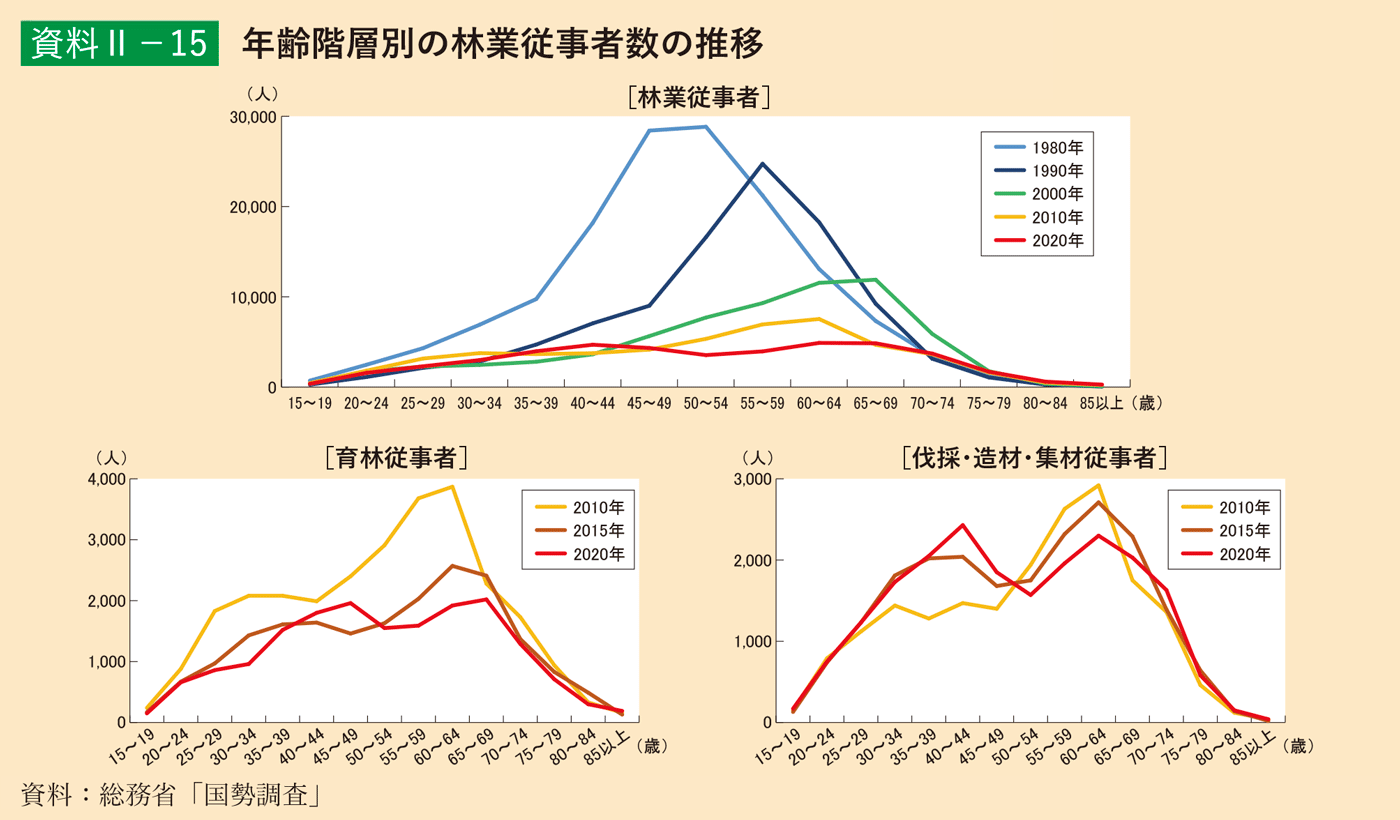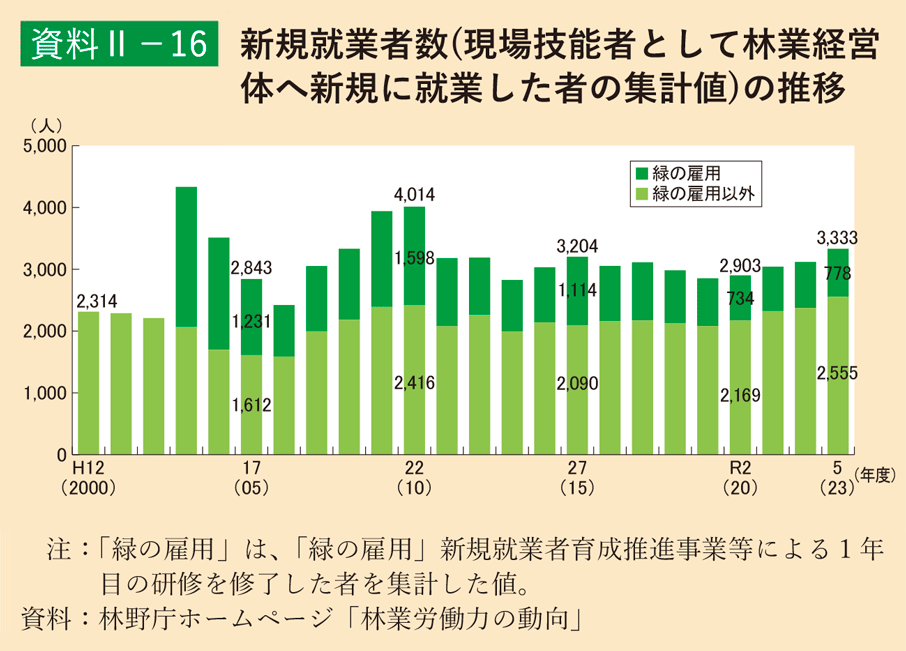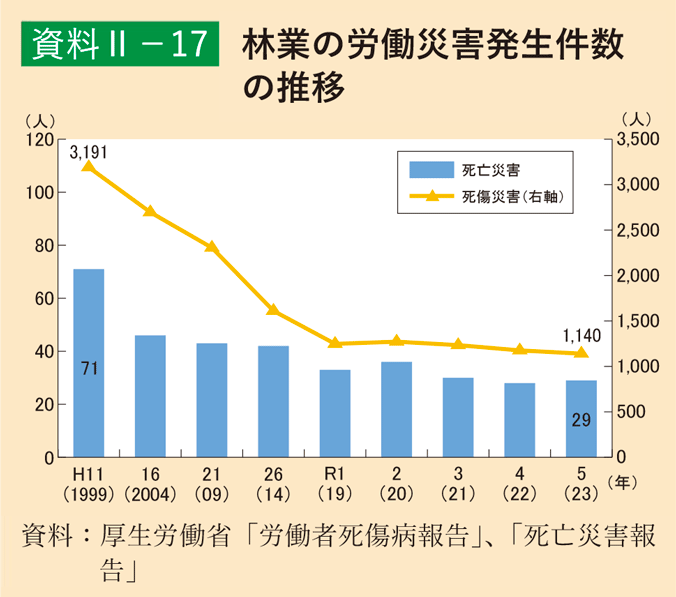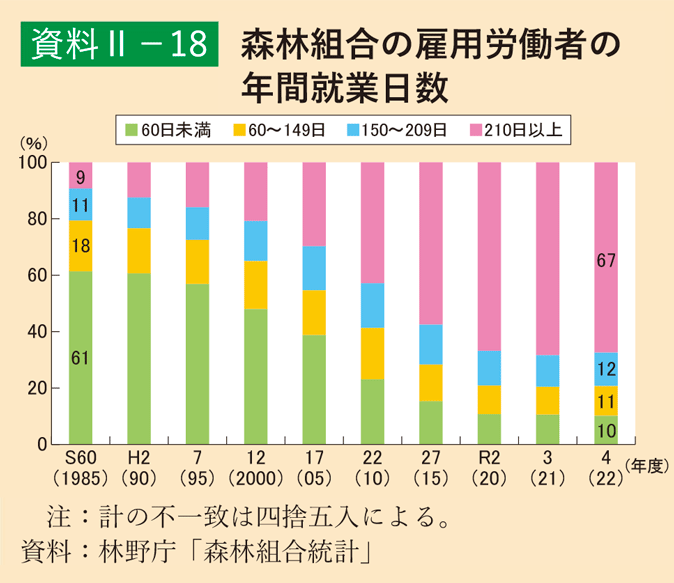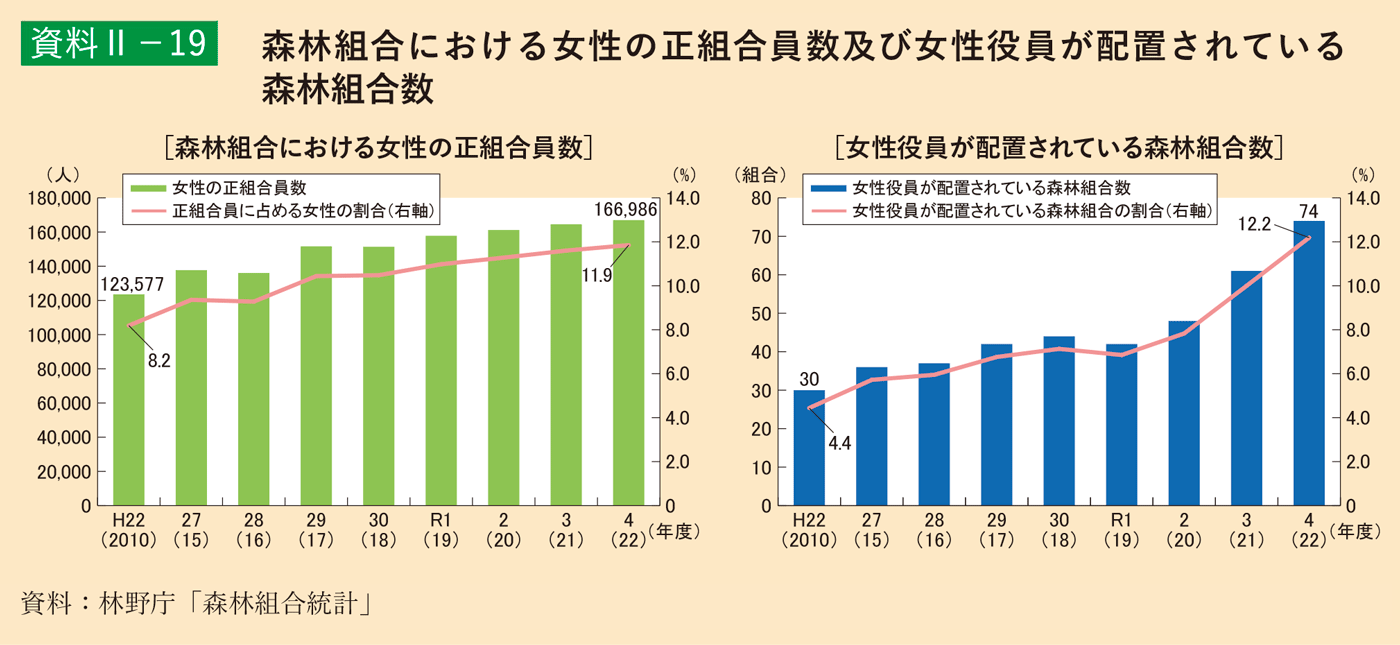第1部 第2章 第1節 林業の動向(3)
(3)林業労働力の動向
(林業労働力の現状)
林業従事者数は⾧期的に減少傾向であったが、平成27(2015)年から令和2(2020)年にかけて横ばいに転じ、4.4万人となっている(資料2-14)。
林業従事者数を年齢階層別にみると、昭和55(1980)年には45~54歳の林業従事者数が突出して多く、特徴的な山型の分布であったが、年齢階層ごとの人数差は縮小し、山は徐々に低くなり平準化が進展している。特に高齢層が辞めていく中で、若年層が恒常的に就業し続けたことがこの傾向に寄与したものと考えられる(資料2-15)。林業従事者の若年者率は、全産業の若年者率が低下する中、平成2(1990)年から平成22(2010)年にかけて上昇した後に横ばいで推移するとともに、平均年齢は、平成7(1995)年の56.2歳をピークに令和2(2020)年には52.1歳まで下がっており、若返り傾向にある(資料2-14)。
林業従事者数を従事する作業別にみると、育林従事者については、平成22(2010)年から平成27(2015)年にかけての減少率が29%であったのに対して、平成27(2015)年から令和2(2020)年にかけての減少率は10%となり、減少幅が縮小している。育林従事者数を年齢階層別にみると、45~49歳の年齢層が増加している。他方、素材生産量の増加が続く中で、伐木・造材・集材従事者数については、平成27(2015)年から令和2(2020)年にかけて横ばいで推移している。伐木・造材・集材従事者数を年齢階層別にみると、40~44歳が最も多くなっており、若返りが進んでいる(資料2-14、15)。
(林業労働力の確保)
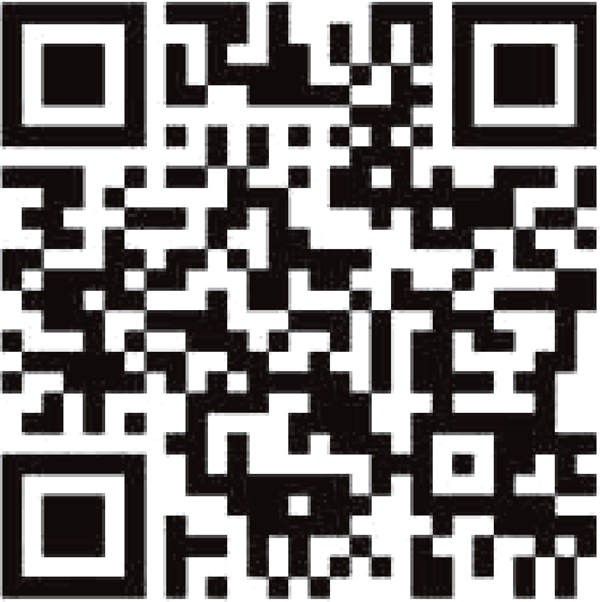
林業生産活動を継続させていくためには、施業を担う林業従事者の育成・確保が必要である。また、林業労働力の確保は、山村の活性化の観点からも重要である。林業労働力の確保のためには、継続して新規就業者を確保するとともに、人材育成や労働環境の改善などを通じて定着率を高めていくことが重要である。
林野庁では、森林・林業基本計画(令和3(2021)年6月閣議決定)を踏まえ、「グリーン成⾧」の実現に向けた木材生産や再造林・保育を担う林業労働力の確保を促進するため、「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」を令和4(2022)年に変更し、林業従事者が生きがいを持って働ける魅力ある林業の実現に向けた取組を推進していくこととしている。
林業労働力の確保に向けては、林業に関心のある都市部の若者等が就業相談等を行うイベントの開催や、就業希望者の現地訪問の実施及び林業への適性を見極めるためのトライアル雇用の実施への支援のほか、林業経営体に就業した幅広い世代に対して、林業に必要な基本的な知識や技術・技能の習得等の支援を行う「緑の雇用」事業により新規就業者の確保・育成を図っている。
令和5(2023)年度は同事業を活用し778人が新規に就業しており(資料2-16)、同事業を活用した令和3(2021)年度の新規就業者の3年後(令和5(2023)年度末)の定着率は69.9%となっている。林野庁は、「緑の雇用」事業による新規就業者を毎年度1,200人、就業3年後の定着率を令和7(2025)年度までに80%とすることを目標としている。
また、林野庁では、季節ごとに作業量が変動する農業や、機械の操作などで共通点の多い建設業等の他産業との連携、施業適期の異なる他地域との連携による労働力確保の取組を支援している(事例2-2)。
その他、林業分野における障害者雇用の促進を図るため、造林作業や山林種苗生産などの分野で、地方公共団体による林福連携の動きがみられる。
林業を営む事業所に雇用されている外国人労働者は、令和6(2024)年10月末時点で234人となっている(*21)。このような中、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる特定技能制度について、令和6(2024)年3月に林業分野の追加が決定され、同年9月に運用が開始された(*22)。また、同月、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的としている技能実習制度に、林業職種(育林・素材生産作業)が追加されたことにより、技能実習2号及び3号へ移行できるようになり、1号から通算して最大5年の技能実習が可能となった。なお、技能実習で修得した技能等を評価する試験として、技能検定が活用されている。
事例2-2 通年雇用や林業労働力確保を可能とする地域間連携
茨城県石岡(いしおか)市のつくばね森林組合は、冬期の積雪によって作業ができない富山県富山市の立山山麓森林組合との地域間連携に取り組んでいる。
作業員不足等の課題を抱えていたつくばね森林組合は、冬期間における雇用先を求める問合せをきっかけとして、立山山麓森林組合からの作業員の受入れを開始した。受入れに当たっては、10月につくばね森林組合が調査した山を案内し、期間や人数を決定した上で、冬期の3~4か月間程度、搬出間伐等を主な業務として請負契約を締結している。
これにより作業員不足の解消だけでなく、連携先の立山山麓森林組合から搬出間伐のノウハウを取り入れることが可能となり、事業の拡大、施業の効率化にもつながっている。令和6(2024)年度は、作業員2名を受け入れ、約20haの搬出間伐を行った。
このような地域間連携は、冬の積雪によって作業ができない林業経営体の通年雇用を可能とするだけでなく、受入れ側の労働力の確保や技術の向上にも貢献している。
(*21)厚生労働省プレスリリース「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」(令和7(2025)年1月31日付け)
(*22)「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」に位置付けられたことによる。
(高度な知識と技術・技能を有する従事者の育成)
林業従事者にとって、林業が⾧く働き続けられる魅力ある産業となるためには、林業作業における生産性と安全性の向上や、能力評価等を活用した他産業並みの所得、安定した雇用環境の確保が必要である。
林野庁では、林業従事者の技術力向上やキャリア形成につながる取組を後押しするため、キャリアアップのモデルを提示し、林業経営体の経営者による教育訓練の計画的な実施を支援するとともに、現場管理責任者等のキャリアに合わせた研修を用意している。現場管理責任者等の育成目標は、令和7(2025)年度までに7,200人としている。
また、チェーンソー作業の正確性や安全性を競う日本伐木チャンピオンシップが開催されている。林業技術や安全作業意識の向上、林業の社会的地位の向上、新規就業者数の拡大等を目的としており、優秀な成績を収めた選手は世界伐木チャンピオンシップ(WLC)の代表として選出されている。令和6(2024)年9月にオーストリアで開催された第35回WLCにおいても、日本人選手が活躍した。
(林業大学校等での人材育成)
林業従事者の技術の向上を図り、安全で効率的な作業を行うためには、就業前の教育・研修も重要である。近年、道府県等により、各地で就業前の教育・研修機関として林業大学校を開校するなどの動きが広がっている。令和6(2024)年度に新たに栃木県林業大学校、三好林業アカデミー、香川県立農業大学校の3校を加え、令和6(2024)年度末時点において、林業大学校は全国で27校となっている(*23)。
林野庁では、緑の青年就業準備給付金事業により、林業大学校等において林業への就業を目指して学ぶ学生等を対象に給付金を給付し、就業希望者の裾野の拡大を図るとともに、将来的な林業経営の担い手の育成を支援している。令和6(2024)年4月時点で、令和5(2023)年度に給付金を受けた卒業生のうち214人が林業に就業している。
また、森林・林業に関する学科・コース・科目を設置している高等学校は令和6(2024)年度末時点において全国で72校となっている(*24)。林野庁では、次代を担う人材を確保・育成するため、令和4(2022)年度より、森林技術総合研修所において教職員向け研修を実施しているほか、授業や自習用の教材として活用できるスマート林業オンライン学習コンテンツの作成・配信、モデル校による地域協働型スマート林業教育の実証を行うとともに、教職員サミットを開催している。また、森林や林業の魅力を肌で感じることができる貴重な機会として、林業研究グループが高校生を対象に実施する高性能林業機械の体験学習等を支援している。
さらに、森林・林業に関する学部・学科・コースを設置している4年制大学は令和6(2024)年度末時点において全国で32校、専門職大学は令和6(2024)年4月に開学した東北農林専門職大学を含めて全国で2校となっている(*25)。
(*23)林野庁研究指導課調べ。
(*24)林野庁研究指導課調べ。
(*25)林野庁研究指導課調べ。
(安全な労働環境の整備の必要性)
安全な労働環境の整備は、林業従事者を守り、継続的に確保し定着させ、林業を持続可能な産業とするために必要不可欠である。
林業労働における死傷者数は⾧期的に減少傾向にあるものの、ここ数年の死傷者数は横ばい傾向にある(資料2-17)。林業における労働災害発生率は、令和5(2023)年の死傷年千人率(*26)でみると22.8で全産業平均(2.4)の約10倍となっており(*27)、安全確保に向けた対応が急務である。林野庁は、令和3(2021)年以後10年を目途に林業における死傷年千人率を半減させることを目標としている。
林業経営体の経営者や林業従事者には、引き続き、労働安全衛生関係法令等の遵守の徹底が求められる。
(*26)労働者1,000人当たり1年間で発生する労働災害による死傷者数(休業4日以上)を示すもの。
(*27)厚生労働省「労働災害統計(令和5年)」
(林業労働災害の特徴に応じた対策)

林業労働災害は、1)伐木作業中の死亡災害が全体の7割を占めており、特にかかり木に関係する事故が多い、2)経験年数の少ない林業従事者の死亡災害が多い、3)高齢者や小規模事業体の事故が多い、4)被災状況が目撃されずに発見に時間を要するなどの特徴がある(*28)。
このような状況を踏まえ、農林水産省は令和3(2021)年2月に「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定し、林業経営体の経営者や林業従事者自身の安全意識の向上を図るとともに、林野庁では、同年11月に都道府県や林業関係団体に対し、林業労働災害の特徴に対応した安全対策の強化を図るための留意事項(*29)を取りまとめ、その周知活動を実施するなど、林業経営体等の労働安全確保に向けた取組を進めている。
また、林野庁では、林業従事者のチェーンソーによる切創事故を防止するための安全靴や、緊急連絡体制を構築するための無線機や衛星携帯電話を含む安全衛生装備・装置の導入、林業経営体の安全管理体制の確保のための診断、ベテラン作業員向けの伐木技術の学び直し研修への支援を行っているほか、「緑の雇用」事業の研修生に対して行う法令遵守や安全確保のための研修を支援している。くわえて、安全性向上のための自動運転や遠隔操作の機能を有する林業機械の開発・実証に対しても支援を行っており、令和6(2024)年度末時点で、油圧式集材機とロージンググラップルを組み合わせた架線集材システム及び下刈り機械について、遠隔操作の機能を有する機種が販売されている。
さらに、都道府県等が地域の実情に応じて、厚生労働省、関係団体等と連携して行う林業経営体への安全巡回指導や、林業従事者に対する各種の研修等の実施を支援している。
(*28)林野庁経営課において平成29(2017)~令和元(2019)年の労働災害の分析を行った結果による。
(*29)「林業労働安全対策の強化について」(令和3(2021)年11月24日付け3林政経第322号林野庁⾧官通知)
(雇用環境の改善)

令和4年度森林組合統計によると、林業に従事する雇用労働者の賃金の支払形態については、月給制が徐々に増加しているものの32%と低い状況にある。一方、年間就業日数210日以上の雇用労働者の割合は上昇しており、令和4(2022)年度では67%と通年雇用化が進展している(資料2-18)。それに伴い、社会保険等への加入割合も上昇している。林野庁は、森林組合の雇用労働者の年間就業日数210日以上の者の割合を令和7(2025)年度までに77%まで引き上げることを目標としている。
「緑の雇用」事業に取り組む事業体等への調査結果によると、林業従事者の年間平均給与は、平成29(2017)年の343万円から令和4(2022)年の361万円と5%増加しているが(*30)、全産業平均の458万円(*31)と比べると100万円程度低い状況にあり、他産業並みの所得を実現することが重要である。このため、林野庁では、販売力やマーケティング力の強化、施業の集約化や路網の整備及び高性能林業機械の導入による林業経営体の収益力向上、林業従事者の多能工化(*32)、キャリアアップや能力評価による処遇の改善等を推進している。また、令和6(2024)年8月、林業従事者の技能向上、就業環境の整備及び社会的・経済的地位の向上等への寄与を目的として、技能検定の職種に「林業職種」が新設された。これにより本検定の合格者は「林業技能士」と名乗ることができる。試験業務を行う指定試験機関として一般社団法人林業技能向上センターが指定され、令和7(2025)年1月から3月にかけて最初の技能検定試験が行われた。林野庁としても、技能検定の目的が達成されるよう引き続き支援していくこととしている。
(*30)林野庁経営課調べ。
(*31)国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」
(*32)1人の林業従事者が、素材生産から造林・保育までの複数の林業作業や業務に対応できるようにすること。
(林業活性化に向けた女性の活躍促進)
かつて、多くの女性林業従事者が造林や保育作業を担ってきた。これらの作業の減少に伴い、女性従事者数は減少してきたが、平成22(2010)年以降は約3,000人で推移しており、令和2(2020)年には2,730人となった(資料2-14)。
女性の活躍促進は、現場従事者不足の改善、業務の質の向上、職場内コミュニケーションの円滑化等、様々な効果をもたらす。女性が働きやすい職場となるために働き方を考えることや、車載の移動式更衣室・トイレ、従業員用シャワー室等の環境を整えること、産前産後休業や育児休業・休暇、介護休業・休暇を取得しやすい環境を整備することは、男性も含めた「働き方改革」にもつながる。
森林組合においては、正組合員に占める女性の割合や、女性役員が配置されている森林組合の割合が低いなど、女性が森林組合の意思決定に関わる機会は少ない状況となっていることから、令和2(2020)年に改正された森林組合法において、森林組合の理事の年齢や性別に偏りが生じないよう配慮する旨の規定が設けられた(*33)。これにより、女性役員を配置する森林組合の割合は徐々に上昇し、令和4(2022)年度には12.2%となっている(資料2-19)。
また、女性の森林所有者や林業従事者等による女性林業研究グループが全国各地にあり、特産品開発等の林業振興や地域の活性化に向けた様々な研究活動を行っている。その女性林業研究グループ等からなる「全国林業研究グループ連絡協議会女性会議」が各地域での取組を取材し全国に発信するとともに、全国規模の交流会等を実施している。
令和2(2020)年には、森林や林業に関心を持つ様々な職業や学生等の女性が気軽に集い、学び、意見を交わし合うことを目的としたオンラインネットワーク「森女(もりじょ)ミーティング(*34)」が発足し、メンバー間の交流が行われている。
林野庁では、森林資源を活用した起業や既存事業の拡張の意思がある女性を対象に、地域で事業を創出するための対話型の講座を実施する取組等を支援しており、「Forest Creative Women's School」等のオンラインスクールやセミナーが開催されている。
(*33)森林組合の動向については、(2)106-107ページを参照。
(*34)全国林業研究グループ連絡協議会が、林野庁補助事業を活用して創設。一般社団法人全国林業改良普及協会が企画運営を実施。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219