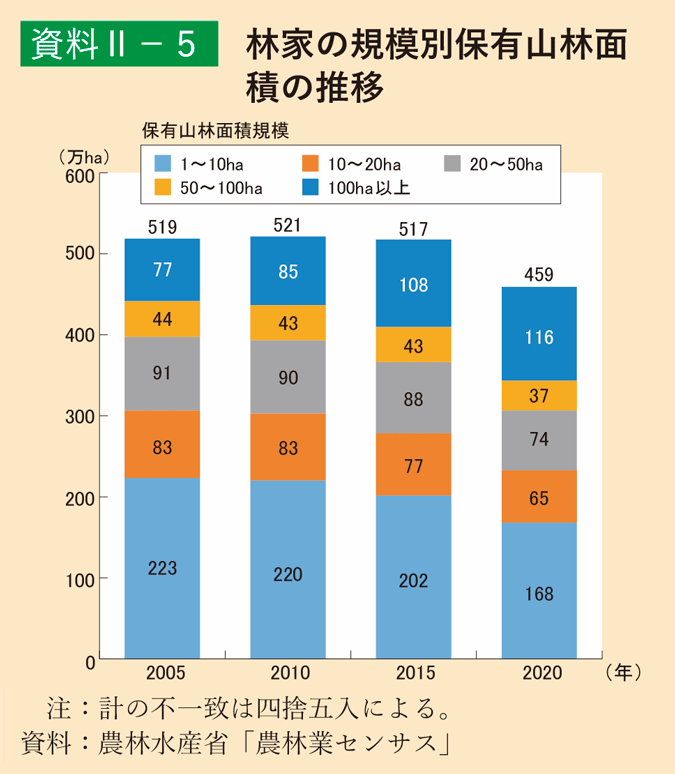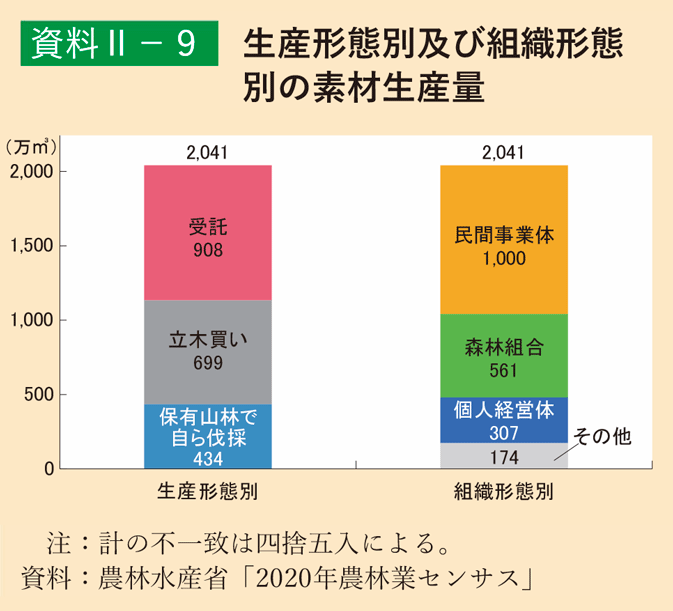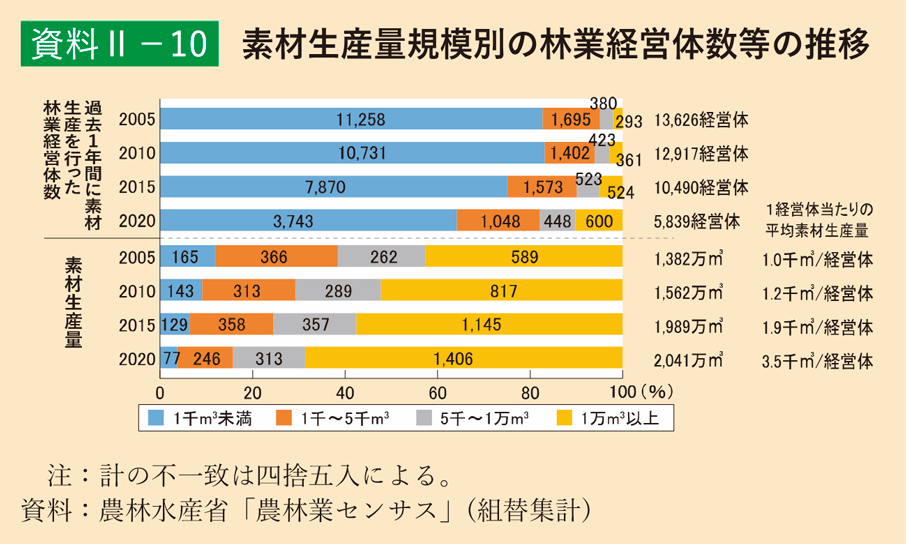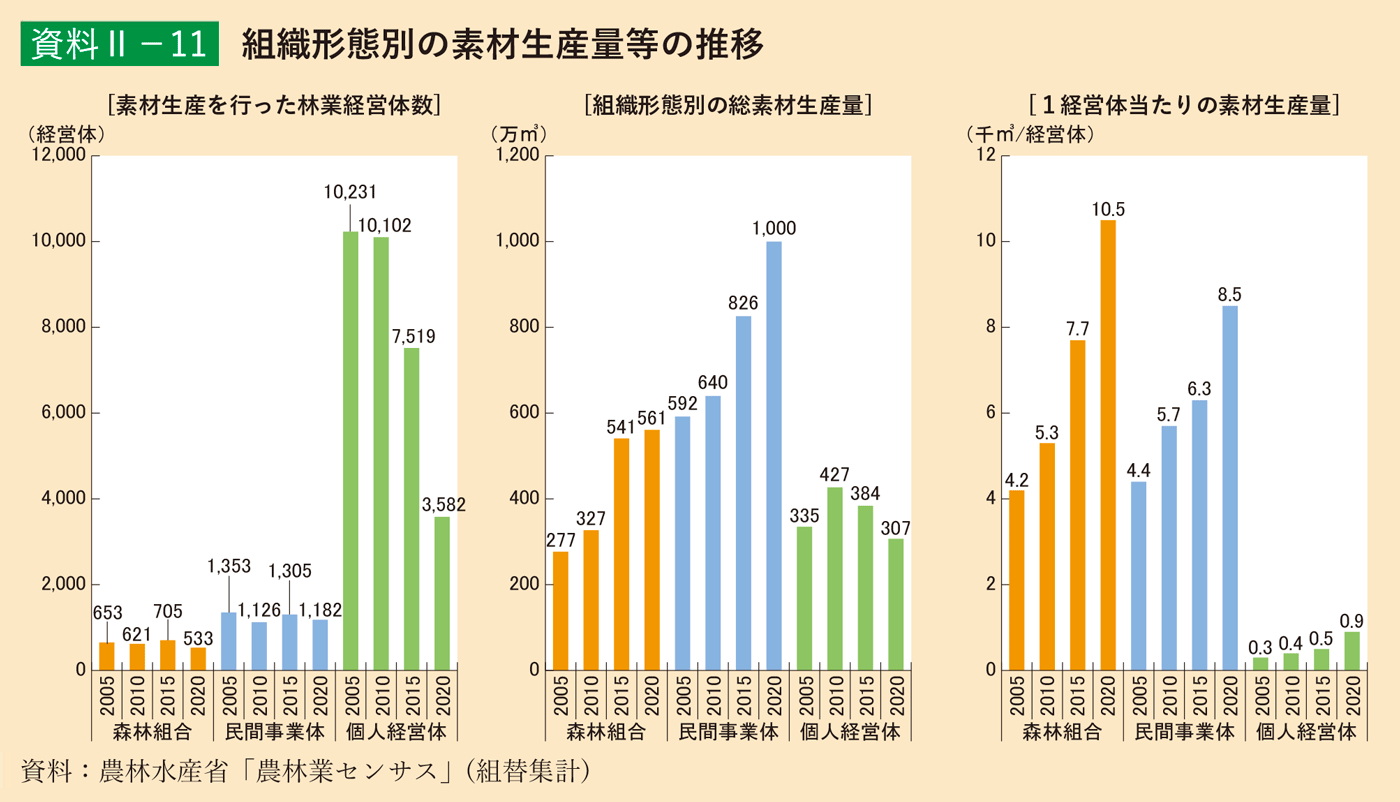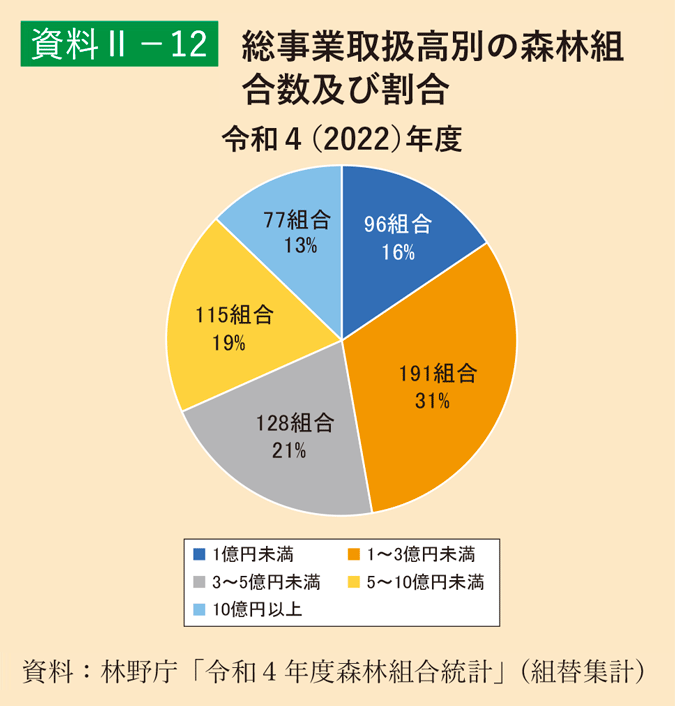第1部 第2章 第1節 林業の動向(2)
(2)林業経営の動向
(林家)
2020年農林業センサスによると、林家(*5)の数は69万戸となっている。保有山林(*6)面積が10ha未満の林家の数が全体の88%と小規模・零細な所有構造となっており、その5年前の前回調査(2015年農林業センサス)と比べ、この層の林家の割合は大きく変化していない。なお、平均保有山林面積は6.65ha/戸と増加している(資料2-4)。
保有山林面積の合計は459万haであり、前回調査から減少しているが、100ha以上の規模の林家の面積は116万haと、前回調査から増加し、保有山林面積の合計に占める割合も上昇している(資料2-5)。
(*5)保有山林面積が1ha以上の世帯。
(*6)自らが林業経営に利用できる(している)山林のこと。
保有山林=所有山林-貸付山林+借入山林
(林業経営体)
令和2(2020)年の林業経営体(*7)数は3.4万経営体で、前回調査の8.7万経営体と比べて大幅に減少している(資料2-6)。
林業経営体数を組織形態別にみると、個人経営体(*8)は82%(2.8万経営体)と大半を占める(資料2-7)。自伐林家については、明確な定義はないが、保有山林において素材生産を行う家族経営体(*9)に近い概念と考えると、2,954経営体存在する(*10)。
林業経営体の保有山林面積の合計は332万haで、前回調査の437万haから減少しているが、平均保有山林面積は100.77ha/経営体と、前回調査から約2倍に増加している(資料2-6)。
林業経営体数・保有山林面積の減少要因としては、山林の高齢級化の進行等により直近5年間に間伐等の施業を行わなかったため調査対象外となった者が増加したことが一因と推察される。
(*7)1)保有山林面積が3ha以上かつ過去5年間に林業作業を行うか森林経営計画を作成している、2)委託を受けて育林を行っている、3)受託や立木の購入により過去1年間に200m3以上の素材生産を行っている、のいずれかに該当する者。なお、森林経営計画については(4)117ページを参照。
(*8)個人(世帯)で事業を行っており、法人化していない林業経営体。
(*9)1世帯(雇用者の有無は問わない。)で事業を行う者をいう。なお、法人化した形態である一戸一法人を含む(2005年農林業センサスから2015年農林業センサスまでの区分。個人経営体を含む。)。
(*10)農林水産省「2020年農林業センサス」(組替集計)
(林業経営体の作業面積)
保有山林について、作業面積の推移をみると、間伐、下刈り等の育林作業の減少が顕著である。作業面積を組織形態別にみると、個人経営体の占める割合が低下しており、特に間伐では大きく低下している。
作業受託については、森林組合や民間事業体(*11)の占める割合が大きく、作業の中心的な担い手となっている。このうち、植林、下刈り、間伐は森林組合が、主伐は民間事業体が中心的な担い手となっている(資料2-8)。主伐を行う林業経営体には、主伐後の再造林を実施することが期待されており、森林所有者に適切に働き掛けることが重要である。主伐のみを行う民間事業体においても森林組合等の造林事業者と連携した再造林の取組がみられる。
また、作業ごとの受託とは異なり林業経営体が保有山林以外で期間を定めて一連の作業・管理を一括して任されている山林の面積は98万haであり、その約9割を森林組合又は民間事業体が担っている(*12)。
(*11)民間事業体とは、株式会社(有限会社も含む。)、合名・合資会社、合同会社、相互会社。
(*12)農林水産省「2020年農林業センサス」。森林組合が53万ha、民間事業体が35万ha。
(林業経営体による素材生産量は増加)
素材生産量の約8割は森林所有者からの受託や立木買いにより生産されており、民間事業体や森林組合が素材生産全体の約8割を担う状況となっている(資料2-9)。
また、素材生産を行った林業経営体数は、令和2(2020)年で5,839経営体であり、前回調査の10,490経営体から減少する一方で、素材生産量の合計は増加し、1経営体当たりの平均素材生産量は3.5千m3と、前回調査の1.9千m3から増加している。年間素材生産量が1万m3以上の林業経営体による生産量は、生産量全体の約7割を占めるまで伸展しており、規模拡大が進んでいる(資料2-10)。
素材生産を行った林業経営体数を組織形態別にみると、特に個人経営体は、前回調査の7,519経営体から大幅に減少し、3,582経営体となっている(資料2-11)。
また、令和5年林業経営統計調査結果に基づき、会社経営体(*13)の素材生産量を就業日数(通年雇用・素材生産従事者)で除した1人・日当たり素材生産量(労働生産性)を算出すると平均で8.1m3/人・日である。林野庁は、令和12(2030)年度までに、林業経営体における主伐の労働生産性を11m3/人・日、間伐の労働生産性を8m3/人・日とする目標を設定している。
(*13)会社経営体の調査の対象は、農林水産省「2020年農林業センサス」に基づく林業経営体のうち、株式会社、合名・合資会社等で、1)過去1年間の素材生産量が1,000m3以上、2)過去1年間の受託収入が3,000万円以上のいずれかに該当するもの。
(林業所得に係る状況)
令和5年林業経営統計調査結果によると、個人経営体(*14)の1経営体当たりの年間林業粗収益は467万円で、林業粗収益から林業経営費を差し引いた林業所得は145万円となっている。
会社経営体の経営状況をみると、1経営体当たり林業事業売上高は1億2,820万円、林業事業営業費は1億2,541万円であり、林業事業営業利益は279万円となっている(*15)。
(*14)個人経営体の調査の対象は、農林水産省「2020年農林業センサス」に基づく林業経営体のうち、保有山林面積が20ha以上で、一定程度以上の施業を行っている林業経営体。
(*15)会社経営体における林業事業外営業利益を含む営業利益は1,218万円。
(森林組合の動向)

森林組合は、森林組合法に基づく森林所有者の協同組織で、組合員である森林所有者に対する経営指導、森林施業の受託、林産物の生産・販売・加工等を行っている。また、森林経営管理制度の主要な担い手として森林の経営管理の集積・集約化を推進し労働生産性を高めることや、木材の販売を強化し収益力を高めることが求められている。これらの取組を通じて組合員や林業従事者の収益を確保することで、組合員の再造林への意欲を高め、地域において持続的な林業経営の推進に寄与することが、より一層期待されている。
令和4年度森林組合統計によると、令和4(2022)年度の組合数は607で、全国の組合員数は147万人となっている。組合員が所有する森林面積は、私有林面積全体の約3分の2を占め、また令和2(2020)年の全国における植林、下刈り等の受託面積に占める森林組合の割合は約5割となっており(*16)、我が国の森林整備の中心的な担い手となっている。また、令和4(2022)年度の素材生産量は670万m3であり、平成24(2012)年度の411万m3と比べると、10年間で大幅に増加している。
森林組合の総事業取扱高は、令和4(2022)年度には3,007億円、1森林組合当たりでは4億9,537万円となっており、事業規模も拡大傾向にある(事例2-1)。
一方、総事業取扱高が1億円未満の森林組合も16%存在するなど、経営基盤の強化が必要な森林組合も存在する(資料2-12)。また個々の森林組合の得意とする分野も異なる。
令和2(2020)年に森林組合法が改正され、事業、組織の再編等による経営基盤の強化を図るため、事業譲渡、吸収分割及び新設分割が連携手法として導入され、合併に限らずそれぞれの状況に応じた連携手法の選択が可能となった。また、販売事業等に関し実践的な能力を有する理事の配置が義務付けられ、各組合においては販売担当の役職員等に加え、地域の林業・木材産業関係者や民間企業などからも当該理事として配置されている。さらに、理事の年齢や性別に偏りが生じないよう配慮する旨の規定が設けられ、現役職員等の若年層や女性の理事が就任している組合もみられる。
また、森林組合等が生産する原木(*17)を森林組合連合会が取りまとめ、さらに、複数の森林組合連合会が連携し、大口需要者に販売する協定を結ぶ取組等、森林組合系統内での連携による経営基盤の強化の取組が進展している。森林組合系統では、おおむね5年に一度、森林組合系統全体の運動方針を策定しており、令和3(2021)年に策定された運動方針では、国産材供給量の5割以上を森林組合系統で担うことなどを掲げている。
事例2-1 6つの森林組合が合併し「滋賀県森林組合」を設立
滋賀県内には、8つの森林組合があったが、各森林組合は生産規模が小さく経営の安定化が困難なため、財政基盤や執行体制が脆弱であった。そのため、令和元(2019)年に滋賀県森林組合連合会の協力を得ながら「県内森林組合広域合併検討会」を立ち上げ、県内の森林組合の在り方について議論を重ねた結果、令和6(2024)年6月に、滋賀県内の6つの森林組合が合併し、新たに「滋賀県森林組合」を設立した。この新たな組合は、組合員の保有する森林面積が約10万7,500ha(全国第1位)、組合員数が約1万9,000人(全国第2位)の規模となる。なお、合併に伴い総務・管理部門等の一元化・効率化を進める一方で、合併前の森林組合を事業所として残しており、組合員へのサービスの維持・向上に努めている。
今回の合併により財政基盤や執行体制を強化し、ICT等の新技術導入による効率的な施業の実施や新たな事業展開に取り組むとともに、搬出間伐を中心とした施業体系だけではなく、皆伐・再造林により森林の資源循環と木材生産量の増加を促進していく。これにより、組合員への収益還元を通じて、琵琶湖の水源林である豊かな森林資源を次世代に引き継ぐため取り組んでいく。また、県内外の製材工場や県外の集成材・合板等の大規模工場からの需要に応え、広域化による供給力の強化と併せて、近畿・中部地方の近隣地域との連携により、県域を越えた原木の安定供給にも取り組み、「森林よし」「組合員よし」「組織よし」の三方よしの実現を目指していく。
(*16)農林水産省「2020年農林業センサス」
(*17)製材・合板等の原材料に供される丸太等。
(2025年は「国際協同組合年」)
2025年は、国際連合が定めた国際協同組合年(International Year of Cooperatives:IYC2025)であり、2012年に続き2回目となる。国際連合は今回のIYC2025を通じて、協同組合の持続可能な開発目標(SDGs)の実現への貢献に対する認知度の向上や、協同組合の振興の取組を講ずることを、各国政府や関係機関に対して求めている。
IYC2025は、「協同組合はよりよい世界を築きます」をテーマとしており、ロゴマークでは、より良い世界を築くために世界中の人々が互いに結びつく様子を表している。
我が国では、平成24(2012)年の1回目の国際協同組合年を契機に、異なる協同組合同士が連携して社会課題の解決に取り組む機運が高まり、平成30(2018)年に、一般社団法人全国農業協同組合中央会や全国森林組合連合会を始めとする協同組合全国組織等により日本協同組合連携機構(JCA)が設立された。
令和6(2024)年7月には、JCAが事務局となり、全国森林組合連合会等の各種協同組合が参加する形で「2025国際協同組合年全国実行委員会」が発足し、記念イベントの開催や広報活動などに取り組むこととしている。令和7(2025)年2月には、2025国際協同組合年キックオフイベントが開催され、茨城県と島根県の協同組合連携組織等が取組について講演するとともに、森林組合を始め各種協同組合からのビデオメッセージが流された。
また、全国森林組合連合会は、間伐材を使用したIYC2025のロゴマーク入り木製バッジ等を作製し、関係者が着用することでIYC2025を盛り上げる活動に取り組んでいる(資料2-13)。
(民間事業体の動向)
素材生産、森林整備等の施業を請け負う民間事業体(*18)は、令和2(2020)年には1,211経営体となっている(資料2-7)。このうち植林を行ったものは35%(426経営体)、下刈り等を行ったものは47%(565経営体)、間伐を行ったものは68%(826経営体)となっている。また、受託又は立木買いにより素材生産を行った民間事業体は980経営体となっており、うち52%(505経営体)が年間の素材生産量5,000m3未満と小規模な林業経営体が多い(*19)。安定的な事業量の確保のために、民間事業体においても、施業の集約化(*20)や経営の受託などを行う取組が進められている。
林野庁では、民間事業体等の経営基盤の強化を図るため、低利な資金貸付けや利子助成、林業信用保証等の様々な措置を実施している。令和5(2023)年度には、森林経営管理法に基づき、経営管理実施権の設定を受けられるものとして都道府県が公表した者が行う素材生産に必要な機械の取得等に対する資金、樹苗養成に必要な資金の拡充を行った。また、独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証においては、創業間もない民間事業体等に対して、将来性を評価した保証引受等により資金調達の円滑化を支援している。
(*18)調査期間の1年間に林業作業の受託を行った林業経営体のうち、株式会社(有限会社も含む。)、合名・合資会社、合同会社、相互会社の合計。
(*19)農林水産省「2020年農林業センサス」
(*20)隣接する複数の森林所有者が所有する森林を取りまとめて路網整備や間伐などの森林施業を一体的に実施すること。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219