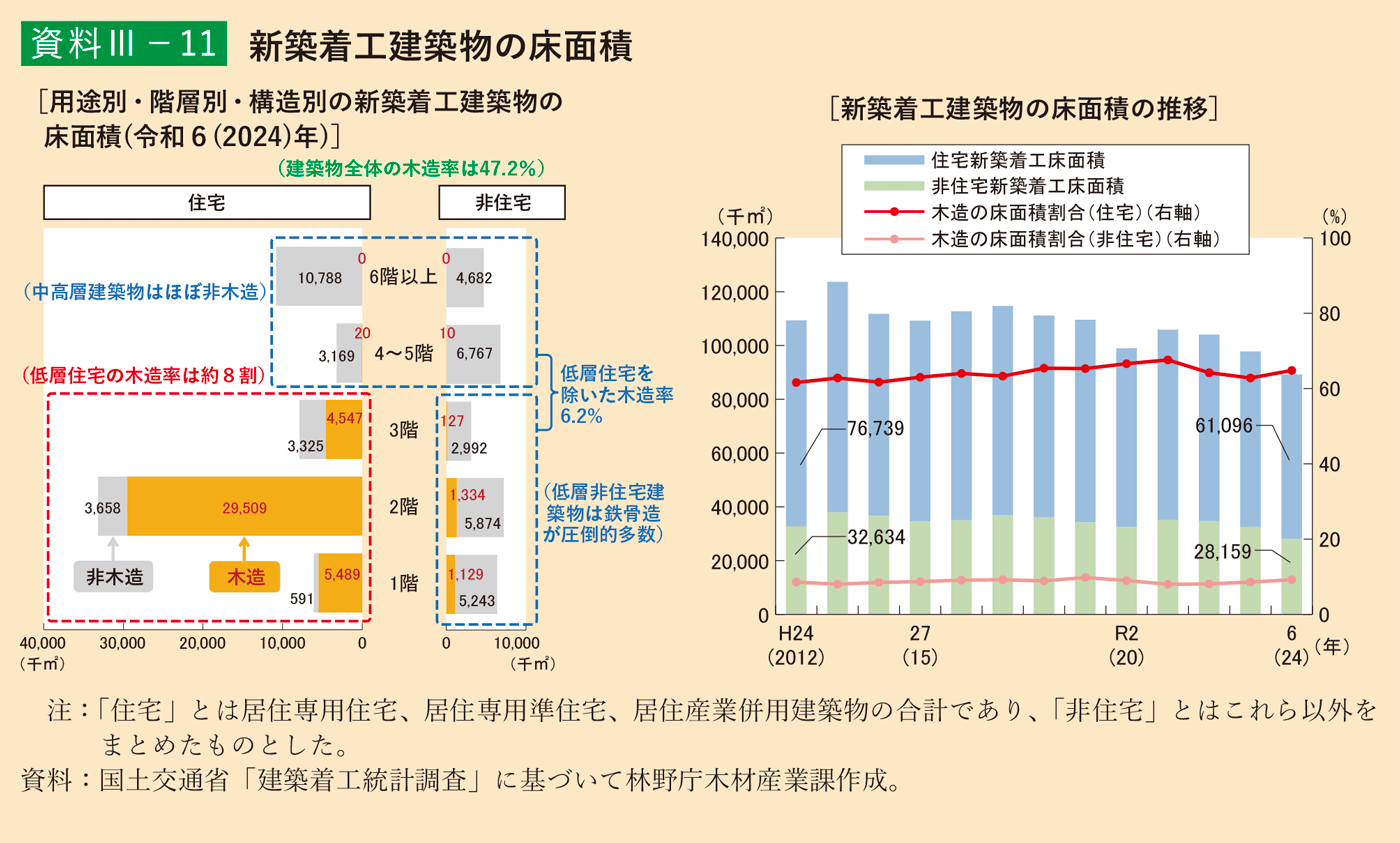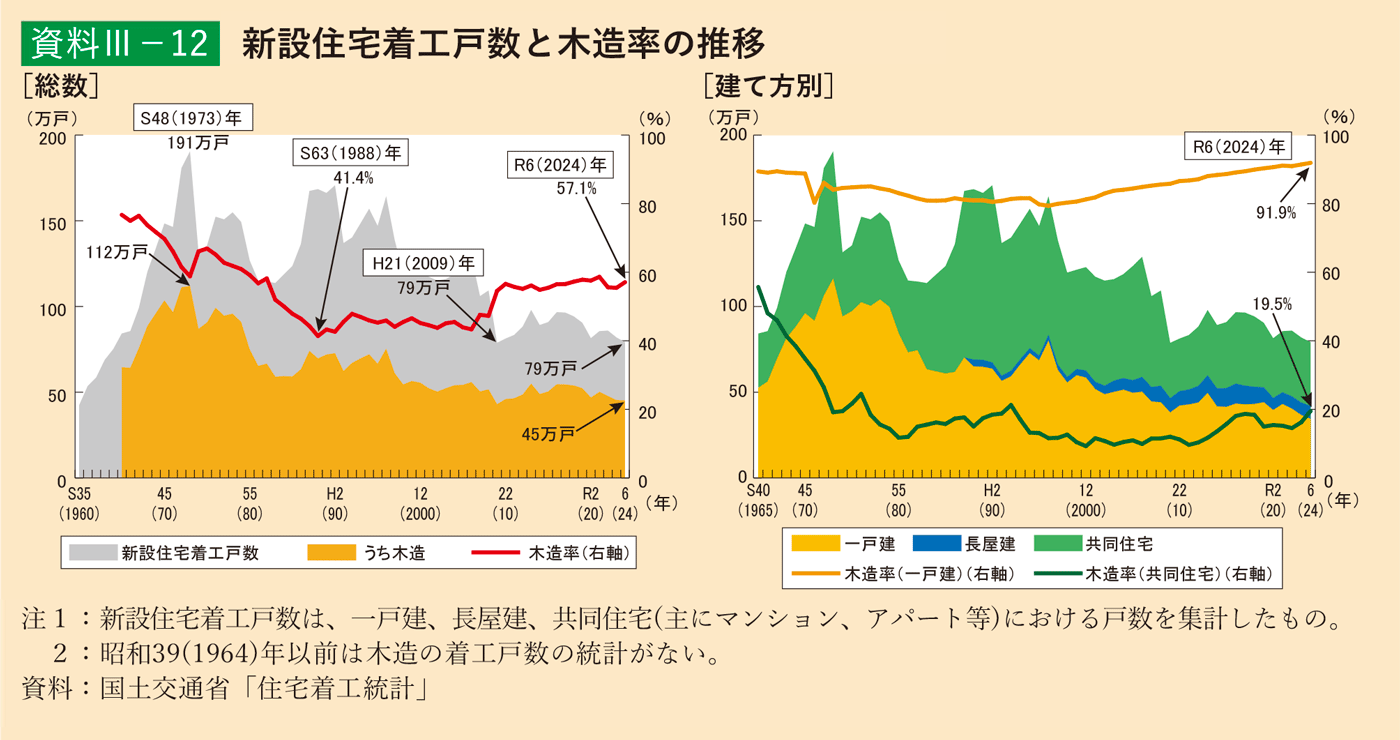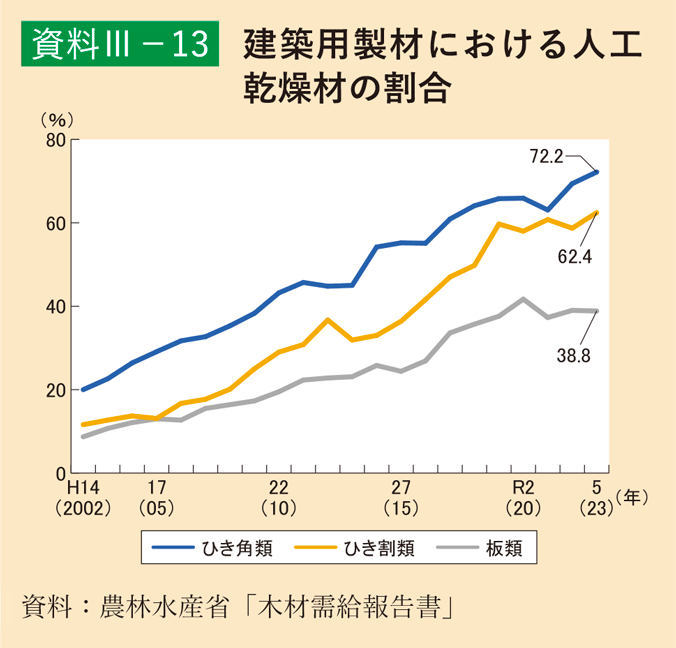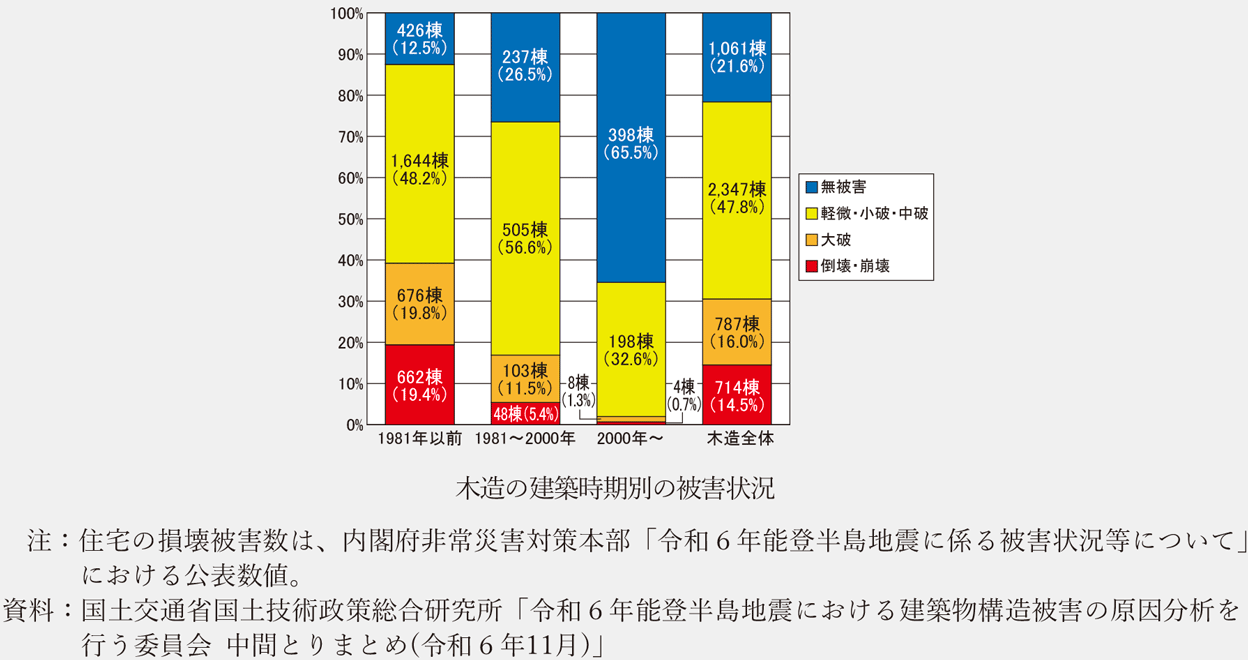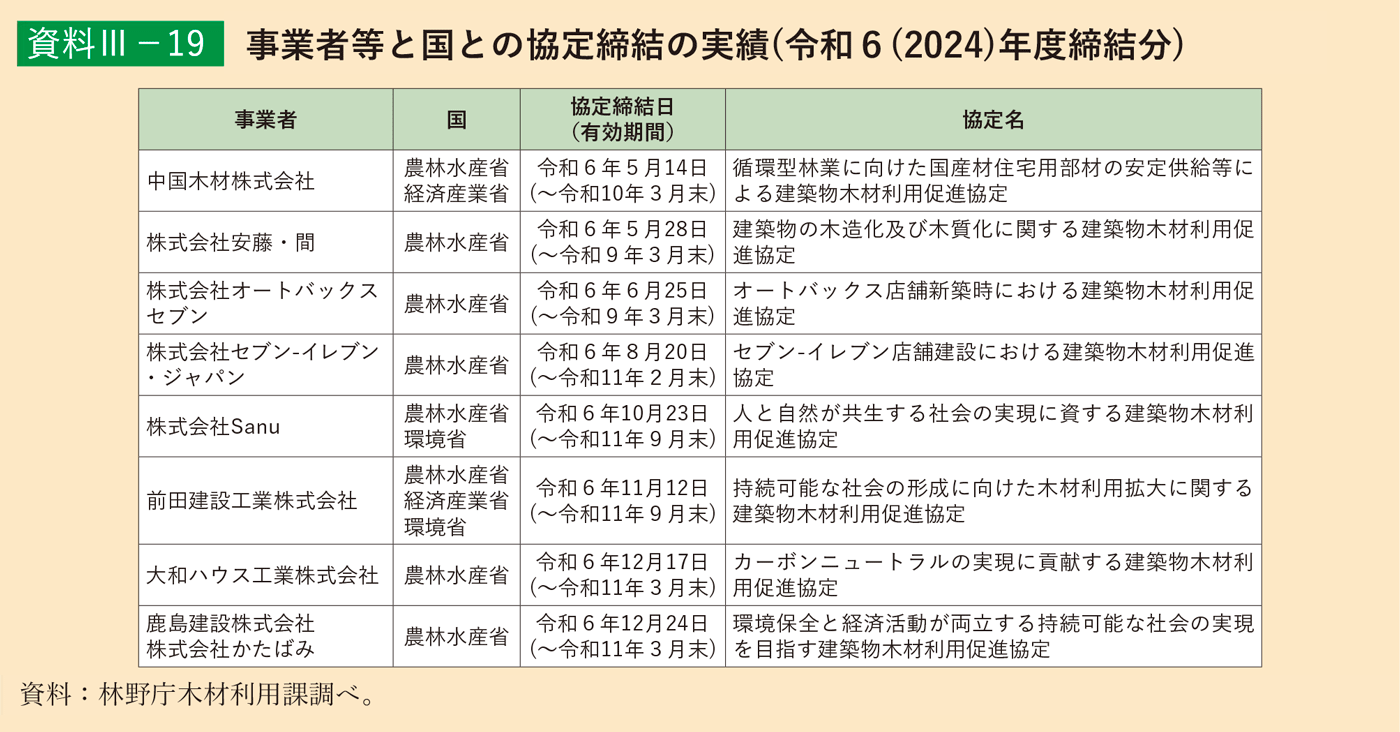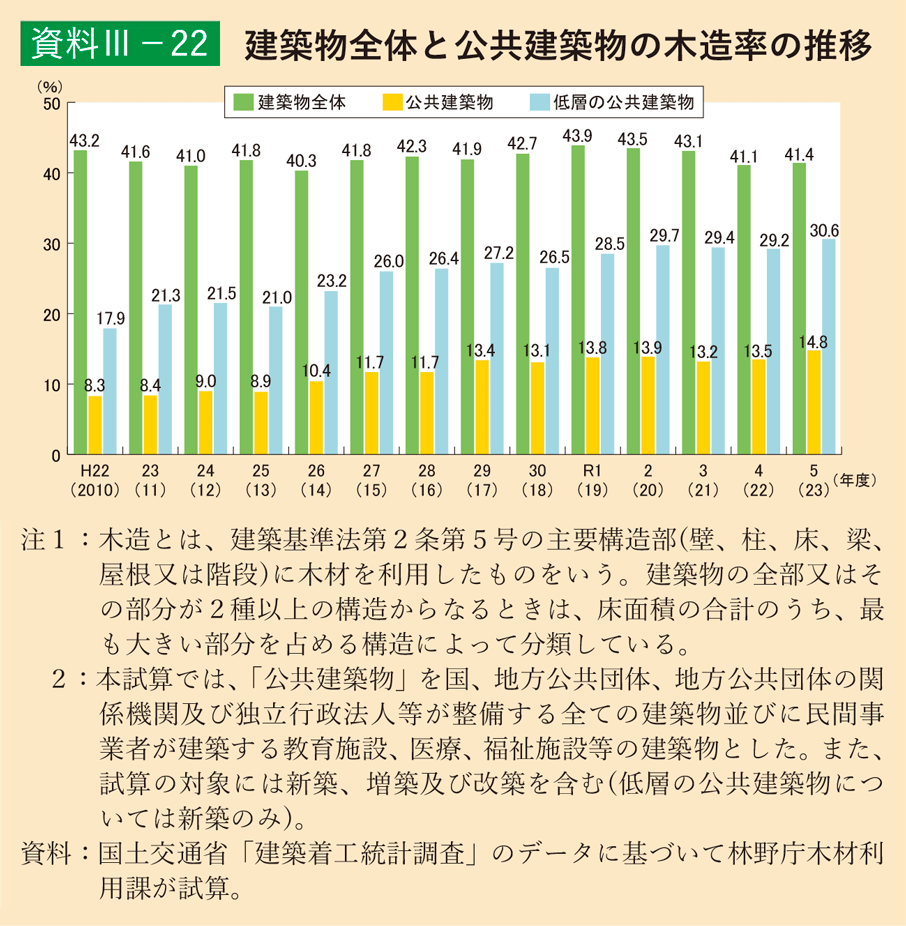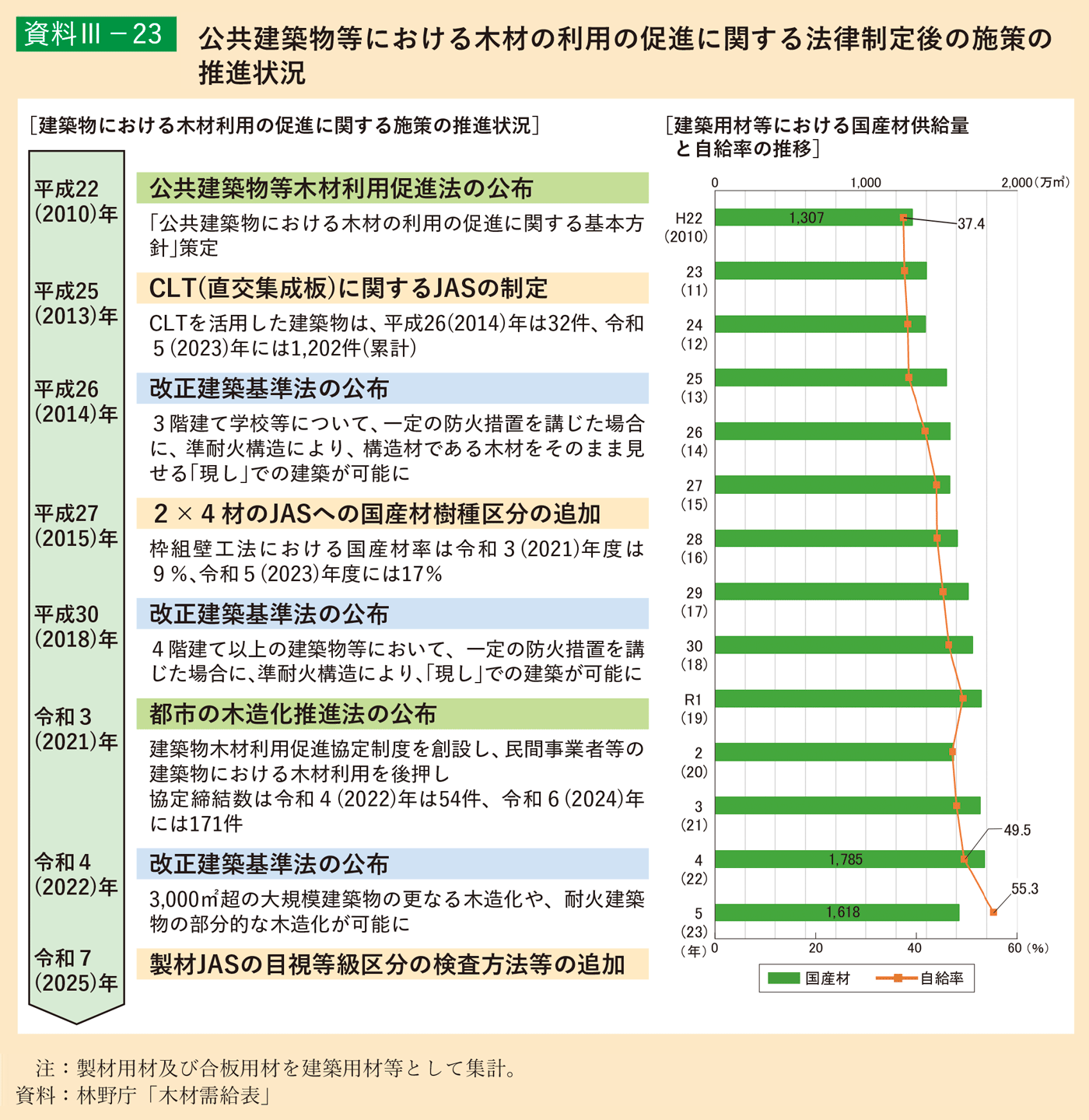第1部 第3章 第2節 木材利用の動向(2)
(2)建築分野における木材利用
(ア)建築分野における木材利用の概況
(建築物の木造率)
木材は、軽くて扱いやすい割に強度があることから、建築資材等として多く用いられている。
令和6(2024)年の着工建築物(*21)の木造率(*22)(床面積ベース)は47.2%であり、用途別・階層別にみると、1~3階建ての低層住宅は80%を超えるが、低層非住宅建築物は15%程度、4階建て以上の中高層建築物は1%以下と低い状況にある(資料3-11)。
低層住宅分野は建築用木材の需要の大部分を占めているが、最も普及している木造軸組工法(*23)の住宅でも、国産材の使用割合は5割程度にとどまっているため、低層住宅分野で国産材の利用を拡大していくことが重要である。
同時に、新設住宅着工戸数が人口減少等により⾧期的に減少していく可能性を踏まえると、非住宅・中高層建築物での木造化・木質化を進め、新たな木材需要を創出することが重要となっている。
(*21)本節における国土交通省「建築着工統計調査」に関する数値は、令和7(2025)年1月31日に公表された統計情報に基づくもの。
(*22)木造とは、国土交通省「建築着工統計調査」においては、建築基準法第2条第5号の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)に木材を利用したものをいう。
(*23)単純梁形式の梁・桁で床組や小屋梁組を構成し、それを柱で支える柱梁形式による建築工法。
(建築物全般における木材利用の促進)
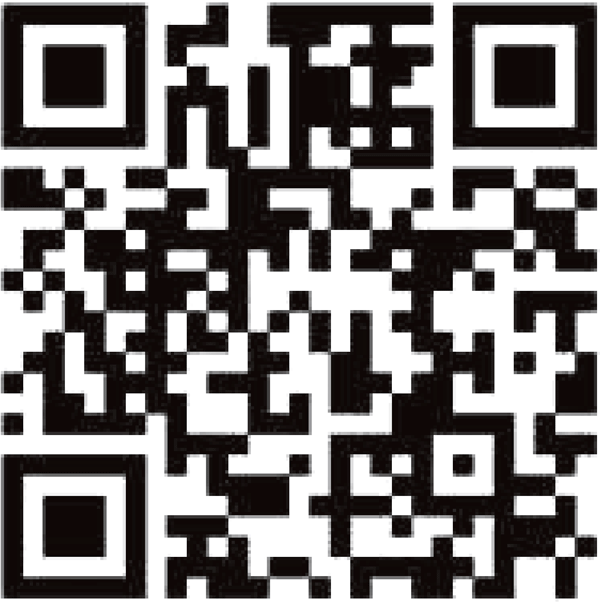
建築物での木材利用の促進に向けて、都市(まち)の木造化推進法に基づき、木材利用促進本部(*24)は、令和3(2021)年10月に建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(以下「建築物木材利用促進基本方針」という。)を決定した。基本方針では、建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、建築物木材利用促進協定制度の活用、国が整備する公共建築物における木材の利用の目標等を定めている。
地方公共団体においては、令和7(2025)年2月末時点で、全ての都道府県と1,652市町村(95%)が都市(まち)の木造化推進法に基づく木材の利用の促進に関する方針を策定しており、建築物木材利用促進基本方針に沿って改定が進められている。
(*24)都市の木造化推進法に基づき設置された組織であり、農林水産大臣を本部⾧、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣を本部員としている。
(イ)住宅分野における木材利用の動向
(住宅分野における木材利用の概況)
令和6(2024)年の新設住宅着工戸数は、前年比3.4%減の79万戸で、このうち木造住宅が前年比0.5%減の45万戸であった。一方、新設住宅着工戸数に占める木造住宅の割合(木造率)は、一戸建て住宅では91.9%と特に高く、全体では57.1%となっている(資料3-12)。
令和6(2024)年の木造の新設住宅着工戸数における工法別のシェアは、木造軸組工法(在来工法)が76.6%、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)が21.0%、木質プレハブ工法(*25)が2.4%となっている(*26)。
(*25)木材を使用した枠組の片面又は両面に構造用合板等をあらかじめ工場で接着した木質接着複合パネルにより、壁、床、屋根を構成する建築工法。
(*26)国土交通省「住宅着工統計」(令和6(2024)年)。木造軸組工法については、木造住宅全体からツーバイフォー工法及び木質プレハブ工法を差し引いて算出。
(住宅向けの木材製品への品質・性能に対する要求)
耐震性や省エネルギー性能の向上などの住宅におけるニーズの変化(*27)を背景に、住宅に用いられる木材製品には、寸法安定性や強度等の品質・性能が一層求められている。
この結果、建築用製材では、寸法安定性の高い人工乾燥材(KD材(*28))の割合が上昇している(資料3-13)。また、木造軸組工法の住宅を建築する大手住宅メーカーでは、寸法安定性の高い集成材を多く使用する傾向にあるが、柱材等において輸入集成材からスギ集成材等への転換の動きがみられ、それにより住宅一戸当たりの国産材使用割合が上昇している。一方、横架材については、高い曲げヤング率(*29)や多様な寸法への対応が求められるため、輸入集成材の減少を米(べい)マツ製材等により代替する動きがみられ、引き続き輸入材が高いシェアを持つ状況にある(資料3-14)。また、一部の住宅メーカーや工務店では、横架材を含めて国産材を積極的に利用する取組がみられる。特に、工務店では、大手住宅メーカーに比べて、部材によらず国産材製材の使用割合が比較的高い傾向にある(資料3-15)。
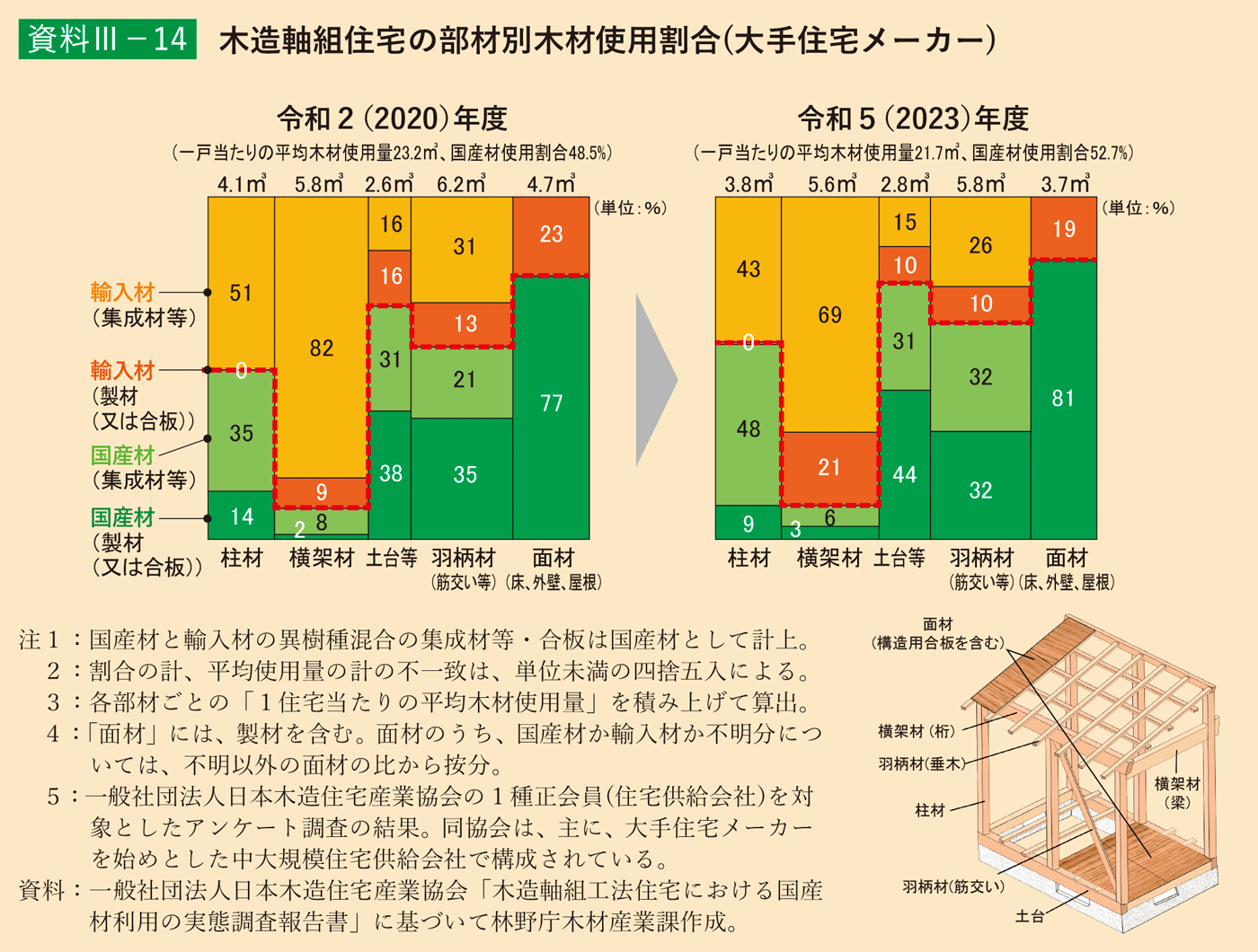
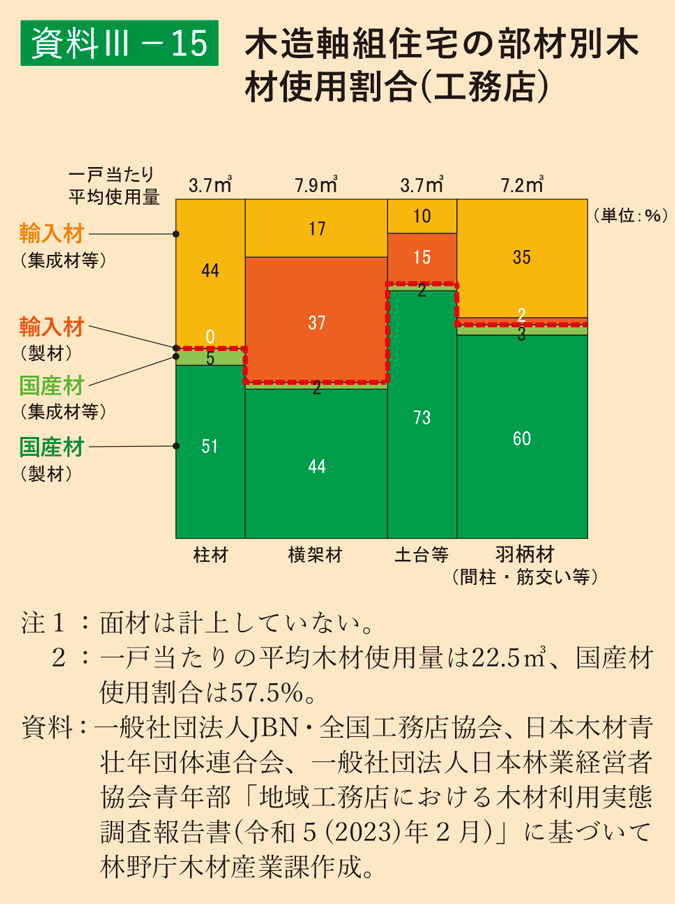
(*27)住宅におけるニーズの変化については「令和3年度森林及び林業の動向」特集2第2節(1)23-25ページを参照。
(*28)KDはKiln Dryの略。
(*29)ヤング率は材料に作用する応力とその方向に生ずるひずみとの比。このうち、曲げヤング率は、曲げ応力に対する木材の変形(たわみ)のしにくさを表す指標。
(地域で流通する木材を利用した住宅の普及)
素材生産者や製材業者、木材販売業者、大工・工務店、建築士等の関係者の間では、木造住宅の建設に当たりネットワークを構築し、地域で生産された木材を多用するなど、健康的に⾧く住み続けられる家づくりを行う取組がみられる。林野庁では、平成13(2001)年度から、関係者が一体となって消費者の納得する家づくりに取り組む「顔の見える木材での家づくり」を推進している。令和5(2023)年度には、関係者の連携による家づくりに取り組む団体数は501、供給戸数は17,957戸となった(*30)。
(*30)林野庁木材産業課調べ。
(ウ)非住宅・中高層建築物における木材利用の動向
(非住宅・中高層建築物における木材利用の概況)
令和6(2024)年の着工建築物を用途別・階層別にみると、低層住宅以外の非住宅・中高層建築物の木造率(床面積ベース)は、6.2%と低い状況にある(資料3-11)。一方、低層で床面積が500m2未満であれば、既存の住宅における技術を使える場合があることなどから、木造率は比較的高い傾向にある(資料3-16)。
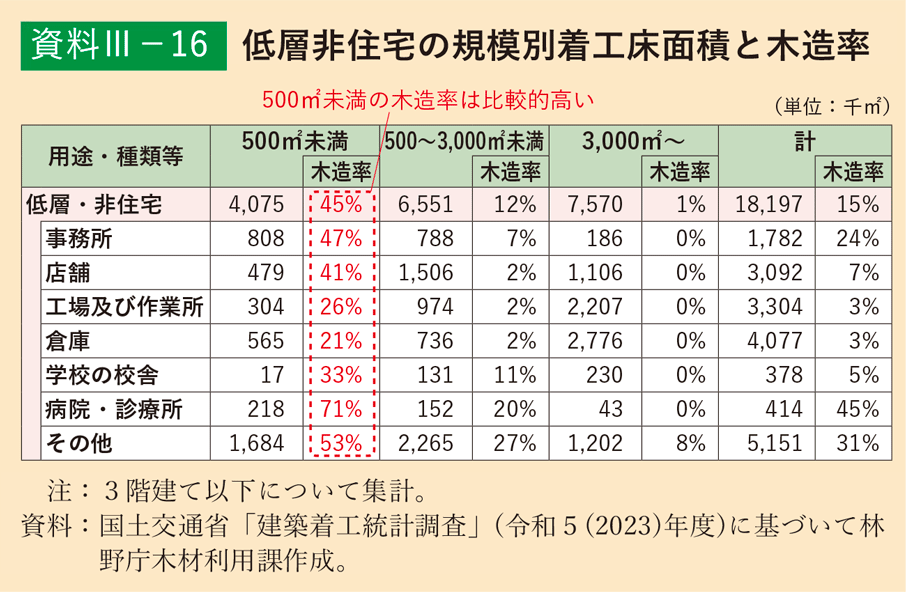
(非住宅・中高層建築物での木材利用拡大の取組)
近年、住宅市場の縮小見込みや、持続可能な資源としての木材への注目の高まりなどを背景に、建設・設計事業者や建築物の施主となる企業等が、非住宅・中高層建築物の木造化や木質化に取り組む例が増えつつある(資料3-17)。
非住宅・中高層建築物に関しては、建築基準の合理化が図られるとともに、製材や直交集成板(CLT(*31))、木質耐火部材等の技術開発が進んできた。近年では、令和5(2023)年4月の改正建築基準法施行令の施行により、新たに1.5時間及び2.5時間の耐火性能の基準が設定されるとともに、令和6(2024)年4月の改正建築基準法等の施行により、3,000m2超の大規模木造建築物においても燃えしろ設計が可能となった。これにより、木材を構造部材等に使用した10階建てを超える先導的な高層建築や、構造部材の木材を現(あらわ)しで用いた大規模な中層建築物の例も出てきている(事例3-2)。林野庁では、非住宅・中高層建築物における一層の木材利用を進めるため、国土交通省と連携して、非住宅・中高層建築物の木造化に必要な知見を有する設計者や施工者等の育成を支援している。また、設計・施工コストの低減に向けて、標準的な設計や工法等の普及、部材の標準化等を進めている。
コラム 令和6年能登半島地震における木造住宅の耐震性
建築基準法に基づく現行の耐震基準(新耐震基準)は、昭和53(1978)年の宮城県沖地震等を踏まえて昭和56(1981)年6月に導入された。平成12(2000)年には、平成7(1995)年の阪神・淡路大震災を受けて、木造住宅の基礎の仕様や接合部の仕様、壁配置のバランスのチェック等の規定の明確化等が行われた。
令和6(2024)年1月1日に発生した能登半島地震では、最大震度7を観測するなど能登半島を中心に強い揺れを観測し、163,724棟の住宅が損壊被害を受けた(令和7(2025)年3月11日時点)。国土交通省国土技術政策総合研究所に設置された「令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会」が、輪島(わじま)市、珠洲(すず)市、穴水町(あなみずまち)のうち、被害の大きかった地区内の約5,000棟の木造建築物を対象に実施した分析によると、新耐震基準導入以前に建築された木造住宅の倒壊・崩壊率が19.4%であったのに対して、接合部の仕様等が明確化された平成12(2000)年以降建築されたものの倒壊・崩壊率は0.7%にとどまった。
これは、平成28(2016)年の熊本地震の際に益城町(ましきまち)において実施した調査・分析結果と同様の傾向を示している。
この結果から、現行の耐震基準が地震に対する倒壊・崩壊の防止に有効であることが認められたことから、新耐震基準導入以前に建築された建築物で耐震化の一層の促進を図ることが課題となっている。このため、国土交通省では、耐震診断・耐震改修の推進等により住宅・建築物の耐震化の促進に取り組んでいる。また、林野庁では、木造住宅の耐震性に関する情報の発信に取り組んでいる。
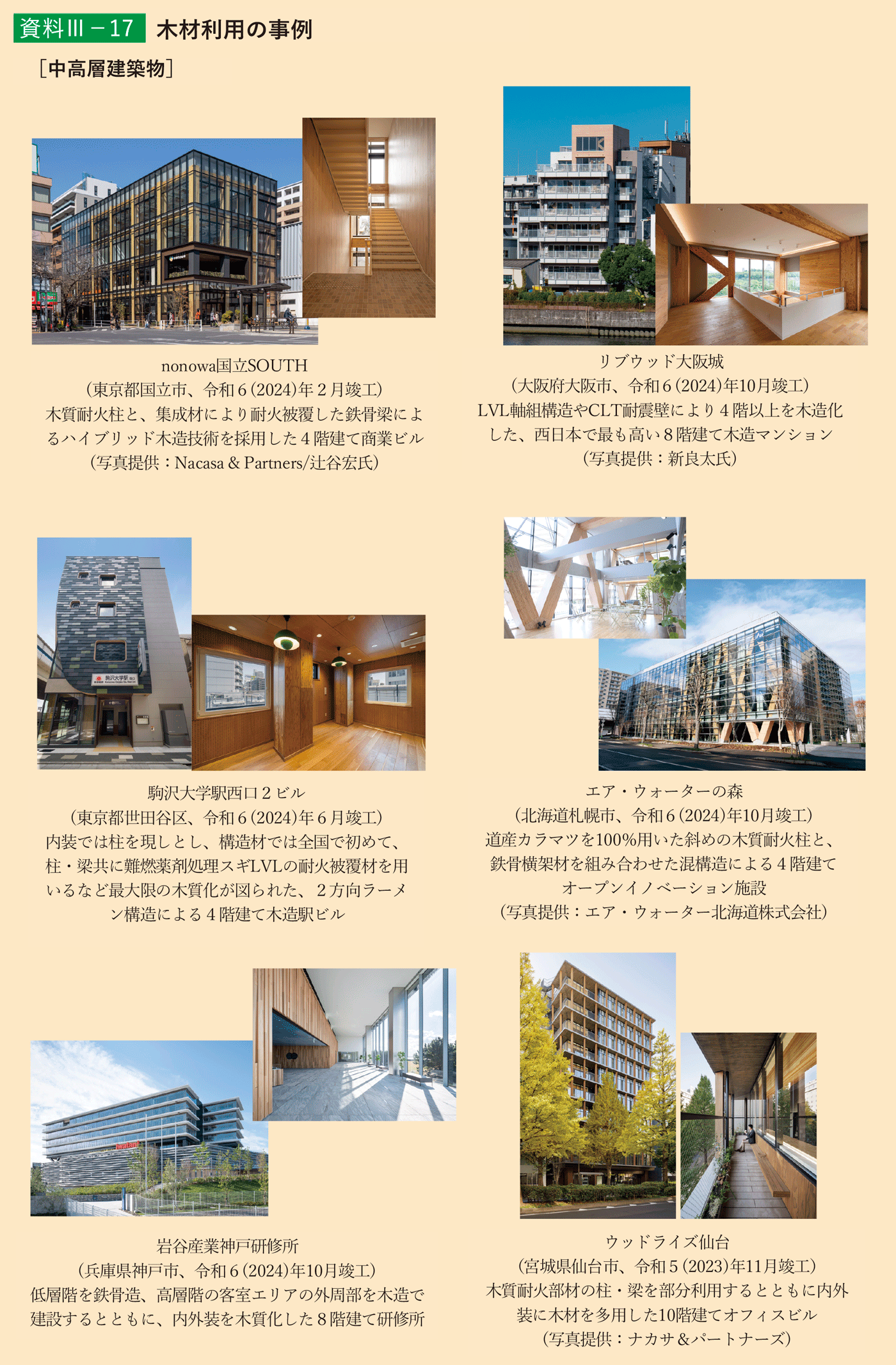
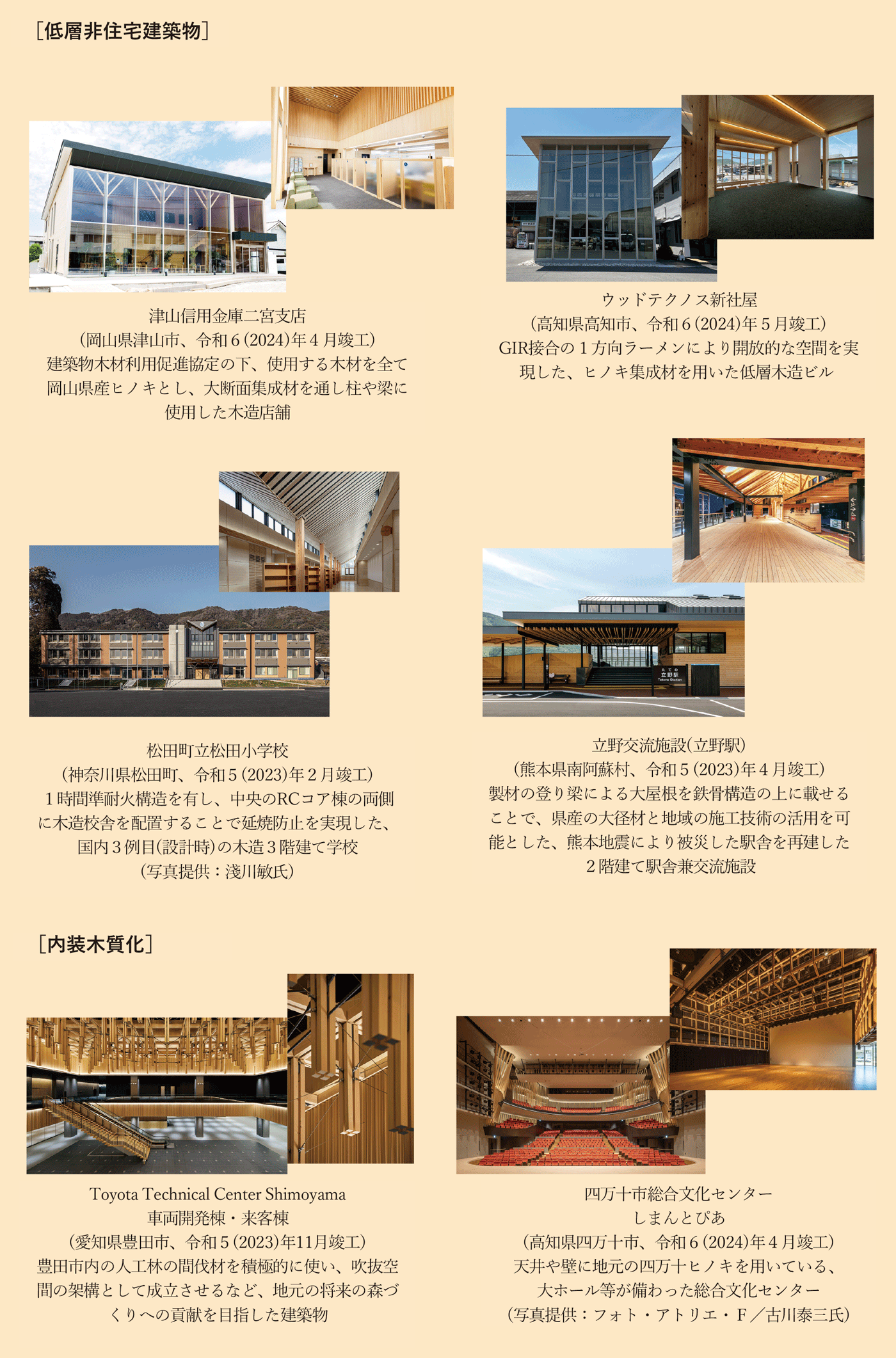
事例3-2 燃えしろ設計による全国初の木造4階建て県営住宅
従来、4階建て以上の建築物や共同住宅等の特殊建築物(注)は、構造部材を耐火構造とする必要があったが、平成30(2018)年の建築基準法改正により新たに⾧時間準耐火構造による燃えしろ設計が可能となった。
令和4(2022)年、徳島県徳島市において、この燃えしろ設計による全国初の4階建て県営住宅となる徳島県新浜町団地県営住宅2号棟が建設された。この建築物では、在来軸組工法の柱・梁(はり)に国産カラマツの大断面集成材を採用し、75分間準耐火構造の燃えしろ設計とすることで、構造部材の木材を現(あらわ)しで用いている。また、法令上耐火性能が要求されない斜材には、国産ヒノキ製材を現しで用い、外装やフローリングには県産スギ材を活用している。
建築に当たっては、火災時の避難安全性の検証、木造遮音床の開発、高耐力壁を実現する接合金物の開発、県産材調達に向けた木材関連団体との協議等が行われており、同様の建築物を設計する上で必要となる知見が蓄積されている。令和6(2024)年4月に施行された改正建築基準法等において建築基準が合理化されたことにより、今後、このような木材を現しで用いた大規模な建築物が一層普及することが期待できる。
(注)不特定又は多数の人が利用する建築物や就寝に利用する建築物など、火災時における利用者の避難安全性確保に特に配慮を要する建築物。
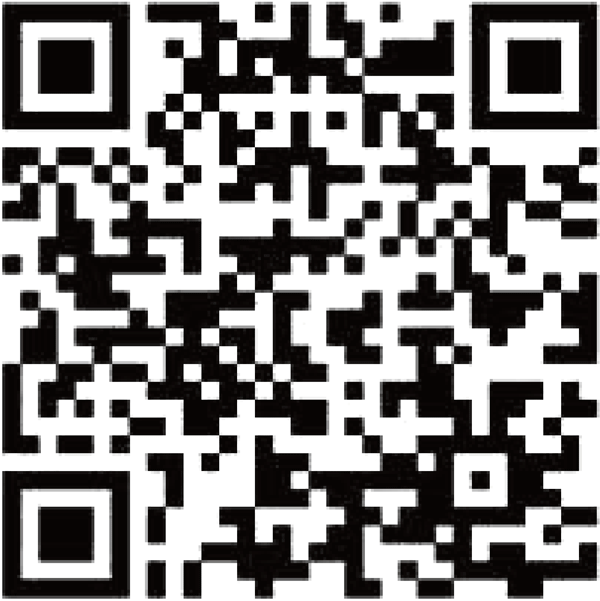
また、川上から川下までの関係者が広く参画する官民協議会「民間建築物等における木材利用促進に向けた協議会」(ウッド・チェンジ協議会)は、民間建築物等における木材利用に当たっての課題や解決方法の検討、木材利用の先進的な取組等の発信など、木材を利用しやすい環境づくりに取り組んでいる。
さらに、民間建築物等での木材利用を後押ししていくため、都市(まち)の木造化推進法により、建築物木材利用促進協定制度が創設された(資料3-18)。国若しくは地方公共団体と建築主等との2者、又は、林業・木材産業事業者や建築事業者も加えた3者等で協定を結ぶ仕組みであり、令和6(2024)年12月末時点で、国において25件(資料3-19、事例3-3)、地方公共団体において146件の協定が締結されており、各地でこれに基づく建設が進んでいる(資料3-20)。協定に基づき令和6(2024)年に木造化・木質化した建築物の木材利用量は約124,852m3となっている。
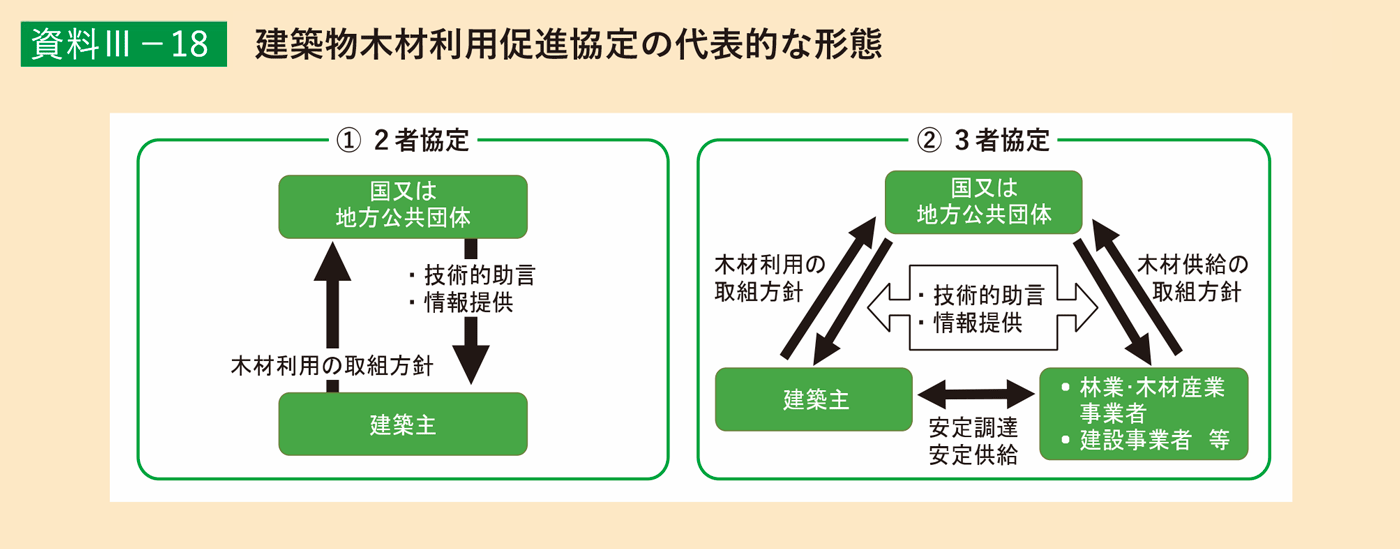
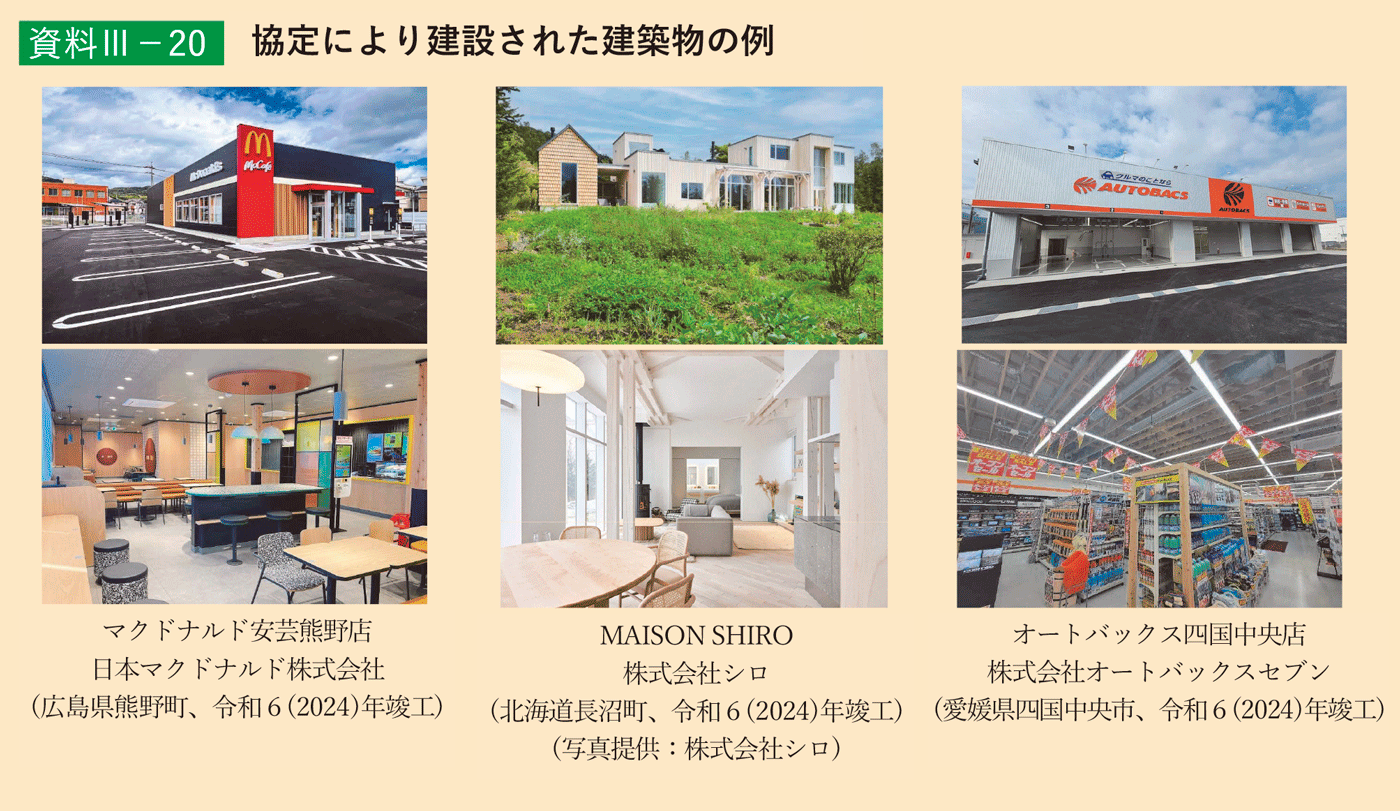
事例3-3 建築物木材利用促進協定に基づく営業拠点の木造化の取組
日本生命保険相互会社(大阪府大阪市)は、令和5(2023)年10月に農林水産省及び環境省と建築物木材利用促進協定を締結した。営業職員が勤務する営業拠点の整備に当たり、全国で100物件、約4,800m3の木材利用を目指すなど、建築物の木造化・木質化及び脱炭素化を推進することとしている。
令和6(2024)年5月、同社は協定締結後第1号となる木造の営業拠点を群馬県富岡(とみおか)市にオープンした。構造やアクセントウォール(注)等の内外装において木材を積極的に利用し、意匠性の高い建物とすることで、地域社会や営業職員に訴求し、木材利用の普及・促進を目指している。この拠点では全体で約50m3の木材を利用し、その8割強が群馬県産材となっている。
協定期間は令和12(2030)年度末までを予定しており、同社は今後、木造営業拠点の整備を始めとする様々な取組を通じて、サステナビリティ経営の一層の高度化を進めることとしている。
(注)壁の一部を異なる素材や色に変えるなどしてアクセントを作ること。
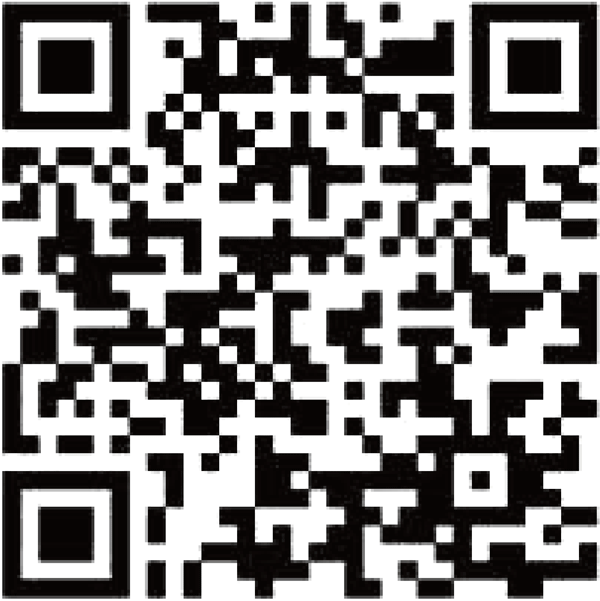
このほか、建築物に木材を利用しやすい環境づくりの一環として、建築物の木造化・木質化に関する国の支援事業・制度等に関する一元的な案内窓口である「建築物の木造化・木質化支援事業コンシェルジュ」が木材利用促進本部事務局に設置されている。
(*31)Cross Laminated Timberの略。一定の寸法に加工されたひき板(ラミナ)を繊維方向が直交するように積層接着したもの。
(木材や木造建築物の耐久性)
非住宅・中高層建築物の木造化・木質化の取組が増える中で、木材や木造建築物の耐久性への関心も高まっている。木材は利用する環境によっては腐朽菌や虫などにより影響を受けるため、耐久性を付与する保存処理技術が開発されてきた。保存処理が行われた木材は、屋外で使用された場合でも20年以上の耐久性を有するという試験結果もある(*32)。日本農林規格(JAS)又は優良木質建材等認証(AQ)制度に基づき薬剤の注入等による保存処理が行われた製品については、使用した薬品やその浸潤度(*33)に応じた性能区分が表示されており、建築物の土台等に利用されている。
国土交通省では、令和6(2024)年10月に、木材・木質材料の経年劣化や維持管理方法、コスト面などの情報を分析・整理した資料(*34)を公表するとともに、同年12月に新築の木造の非住宅建築物の耐久性に係る第三者評価の基準や枠組みを定めたガイドライン(*35)を公表した。
(*32)酒井温子ほか「銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤(ACQ)を加圧注入した杭の25年間の被害経過」(奈良県森林技術センター研究報告 No.48(2019))
(*33)保存処理に使用した薬剤がどの程度木材の内部まで浸潤しているかを示すもの。
(*34)国土交通省「中大規模建築物に木材を使用する際に知っておきたい維持保全・維持管理の考え方と設計等の工夫」
(*35)国土交通省「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」
(持続可能な木材利用に関する評価)
持続可能な開発目標(SDGs)やESG投資(*36)への関心の高まりを背景に、建築事業者、不動産事業者や建築主(企業)が、投資家や金融機関に木材利用をアピールすることで評価を獲得し、企業価値を向上しようとする動きがある。建築物への木材利用は、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、地域経済の活性化、快適な空間の提供等に寄与することから、これらの木材利用の環境価値を見える化することが重要となっている。
林野庁は、令和3(2021)年10月に、建築事業者等が建築物への木材利用によるカーボンニュートラル等への貢献を対外的に発信する手段として、「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」を策定した。また、令和6(2024)年3月には、「建築物への木材利用に係る評価ガイダンス」を作成・公表して、建築事業者が建築物への木材利用による効果を対外的に訴求する際に参考となる評価項目・評価方法を整理した。評価分野は、1)カーボンニュートラルへの貢献、2)持続可能な資源の利用、3)快適空間の実現の3つを提示した。林野庁では、同ガイダンスを普及するための資料を作成して、建築事業者、不動産事業者、建築主等に対して活用を呼び掛けている(資料3-21)。
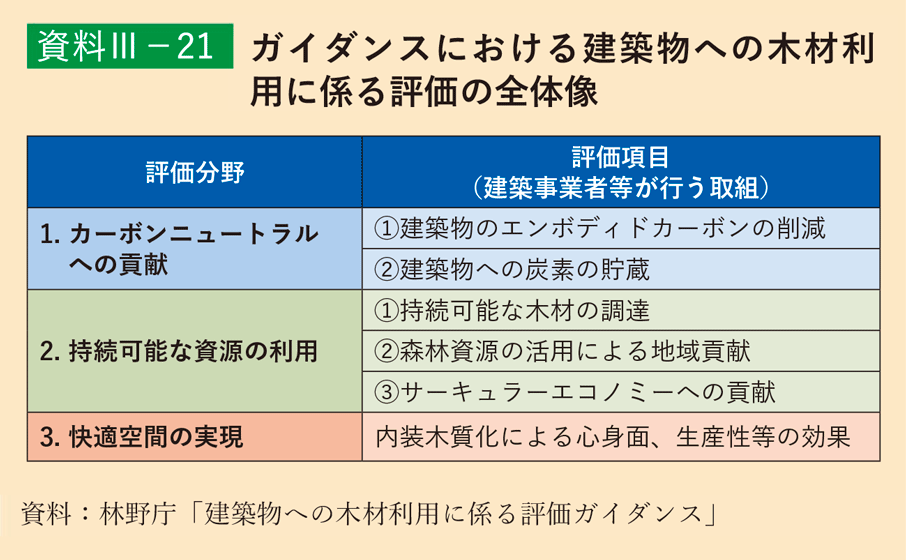
(*36)従来の財務情報に加え、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を判断材料とする投資手法。
(エ)公共建築物等における木材利用
(公共建築物の木造化・木質化の実施状況)
公共建築物は、広く国民一般の利用に供するものであることから、木材を用いることにより、国民に対して、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供することができる。このため、建築物木材利用促進基本方針では、公共建築物について、積極的に木造化を促進することとしている。
令和5(2023)年度に着工された公共建築物の木造率(床面積ベース)は、14.8%となった。そのうち、低層(3階建て以下)の公共建築物の木造率は30.6%であり、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が制定された平成22(2010)年の17.9%から10ポイント以上上昇している(資料3-22)。都道府県ごとの低層の公共建築物の木造率については、1~2割と低位な都府県がある一方、5割を超える県もみられるなど、ばらつきがある状況となっている。
国の公共建築物については、令和4(2022)年度以降に設計に着手するもの(*37)について、建築物木材利用促進基本方針に基づき、計画時点においてコストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、原則として全て木造化を図ることとしている。国が整備し令和5(2023)年度に完成した、積極的に木造化を促進するとされている公共建築物のうち、木造化された建築物は79棟であった。各省各庁において木造化になじまないなどと判断し木造化されなかった公共建築物6棟について、林野庁・国土交通省の合同検証チームが検証した結果、いずれも施設が必要とする機能等の観点から木造化が困難であったと評価され、木造化が可能であったものの木造化率は100%となった(*38)。
(*37)令和3(2021)年度末までに公表された設計着手前の基本計画等に基づき設計を行うものを除く。
(*38)農林水産省プレスリリース「「令和6年度 建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ」等について」(令和7(2025)年3月26日付け)
(学校施設の木造化・木質化を推進)
学校施設は、児童・生徒の学習及び生活の場であり、学校施設に木材を利用することは、木材の持つ高い調湿性、温かさや柔らかさ等の特性により、健康や知的生産性等の面において良好な学習・生活環境を実現する効果が期待できる(*39)。
このため、文部科学省では、学校施設の木造化や内装の木質化を進めており、令和5(2023)年度に新しく建設された公立学校施設の70.3%で木材が利用された(木造で整備されたものが15.6%、非木造で内装が木質化されたものが54.7%)(*40)。また、文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省が連携して認定している「エコスクール・プラス(*41)」において、特に農林水産省は、内装の木質化等を行う場合に積極的に支援している。
(*39)林野庁「平成28年度都市の木質化等に向けた新たな製品・技術の開発・普及委託事業」のうち「木材の健康効果・環境貢献等に係るデータ整理」による「科学的データによる木材・木造建築物のQ&A」(平成29(2017)年3月)
(*40)文部科学省プレスリリース「公立学校施設における木材利用状況(令和5年度)」(令和7(2025)年1月14日付け)
(*41)学校設置者である市町村等が、環境負荷の低減に貢献するだけでなく、児童生徒の環境教育の教材としても活用できるエコスクールとして整備する学校を、関係省庁が連携協力して「エコスクール・プラス」として認定するもの。
(応急仮設住宅における木材の活用)
東日本大震災以前、応急仮設住宅のほとんどは鉄骨プレハブにより供給されていたが、東日本大震災においては木造化の取組が進み、25%以上の仮設住宅が木造で建設された(*42)。
東日本大震災における木造応急仮設住宅の供給実績と評価を踏まえて設立された一般社団法人全国木造建設事業協会では、大規模災害発生後に木造の応急仮設住宅を速やかに供給する体制を構築するため、地方公共団体と災害時の協力に係る必要な事項等を定めた災害協定の締結を進めており、令和7(2025)年3月までに、45都道府県及び11市と災害協定を締結している。
令和6(2024)年1月1日に発生した令和6年能登半島地震では、これまでの災害時に建てられてきた⾧屋型の木造のほか、被災前の居住環境に近い戸建風の木造での応急仮設住宅が建設された。令和6(2024)年12月時点で、石川県では全体の23.3%(*43)が木造で建設されている。また、民間企業から木造の復興支援施設等を被災地へ提供する取組もみられる(事例3-4)。
事例3-4 令和6年能登半島地震の被災地における移動式の木造宿舎の活用
令和6(2024)年1月に発生した令和6年能登半島地震では、被災によって宿泊施設が激減したことから、被災者の仮設住宅だけでなく復興支援者の宿泊所の確保も課題となった。
東急建設株式会社(東京都渋谷区)は、復興支援者用仮設宿舎として自社で開発する可搬型木造建物「モクタスキューブ」20棟を輪島(わじま)市の能登空港多目的広場に設置した。このモクタスキューブは、建築基準法に適合可能な木造建築物であり、復興支援が⾧期間にわたっても木の温もりを感じながら生活を送ることができるほか、あらかじめ屋根、内外装まで全て工場で製作し、大型トラック(10トン積)1台で1棟を搬送・設置するため、現地での作業時間や工程を大幅に短縮できる。能登半島の被災地においても、現地での実働作業期間は約2週間、要請から僅か3か月で完成した。このほか、同社は輪島塗の仮設工房としてモクタスキューブを7棟設置するなど、被災地の復興に向け協力を続けている。
また、SAI GROUP HOLDINGS株式会社、株式会社采建築社、株式会社GATE(いずれも福岡県福岡市)の3者は、石川県志賀町(しかまち)にCLTセルユニットを活用した仮設宿泊施設を設置した。本被災地支援事業には、一部クラウドファンディングを活用した。CLTセルユニットとは、国産CLTを国内の伝統技術「蝶蟻(ちょうあり)」により接合した木製の箱型ユニットであり、災害時の避難施設や医療施設として有用である。工場で生産(プレファブ)されたユニットを現地で基礎の上に設置して連結・連層する工法により、超短工期での完成を可能としており、志賀町での現地工事は僅か2日で完了した。緊急を要する被災地において、その有用性が示されている。


(*42)国土交通省調べ。
(*43)石川県「応急仮設住宅の進捗状況(2024年12月24日時点)」に基づいて林野庁木材産業課が算出。
(オ)建築分野における木材利用の進捗状況
平成22(2010)年の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の制定後、令和3(2021)年に同法が改正され、建築物木材利用促進協定制度の創設等を内容とする都市まちの木造化推進法が施行されたほか、建築基準の合理化や国産材を活用した新たな製品・技術の開発・普及(*44)に向けた取組が進められてきたことなどを背景に、建築用材等における国産材の割合は上昇傾向にある(資料3-23)。
(*44)国産材活用に向けた製品・技術の開発・普及については、第3節(3)182-185ページを参照。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219