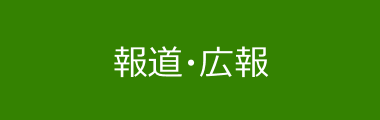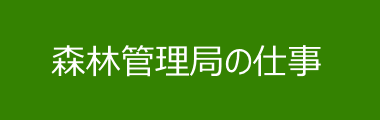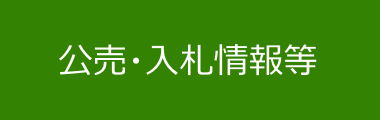保護林制度
保護林制度の概要
保護林とは
国有林野内の原生的な天然林等を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資するため保護林を設定しています。
保護林には、その設定目的や規模等に応じて、「森林生態系保護地域」「生物群集保護林」「希少個体群保護林」の3区分があります。
| 区分 | 目的 | 設定基準 |
| 森林生態系保護地域 | 我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資する。 | 我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を主体とした、森林生態系としてまとまりを持つ区域で、原則2,000ha以上(島嶼、半島等特殊な環境にあっては、原則500ha以上)。 |
| 生物群集保護林 | 地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資する。 | 自然状態が十分保存された天然林を主体とした、地域固有の生物群集がまとまりを持って存在する区域で、原則300ha以上。 自然状態が十分保存された天然林を中心に、地域固有の生物群集が存在し、今後、復元の取組が見込まれる森林を周辺部に包含する区域で原則1,000ha以上。 |
| 希少個体群保護林 | 希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術研究等に資する。 | 次のアからキのいずれかに該当する個体群を有し、原則として当該個体群がその存続に必要な条件を含む5ha以上(設定に際しては野生生物の生育・生息地の他に個体群の存続に必要となる更新適地等に配慮) ア 希少化している個体群 イ 分布限界域等に位置する個体群 ウ 他の個体群から隔離された同種個体群 エ 遺伝資源の保護を目的とする個体群 オ 草地、湿地、高山帯、岩石地等、特殊な立地条件の下に成立 している個体群 カ 温暖化等の影響により将来的に消失が懸念される個体群 キ その他保護が必要と認められる個体群 (注)目的とする個体群の消失が懸念される危機的な森林等で、遺伝的に関連のある個体群の生育・生息地、更新適地等が周辺に飛び地として存在する場合には、野生生物の存続に必要な個体群の集合体(メタ個体群)を保護することを目的に、核となる森林等の周辺の当該飛び地を同一の保護林として設定可能。 |
制度の経過
学術の参考、風致の維持、高山植物保存等に資する国有林を保護することを目的として、大正4年(1915年)に保護林制度が発足し、先駆的な自然環境の保全制度として機能してきました。その後、保護林制度が改正され、平成元年には、保護林内を保存地区と保全利用地区に区分して保護・管理するゾーニングの考え方を取り入れた「森林生態系保護地域」が新設されるなど、保護林は7種類に再編・区分され、それぞれの設定目的に応じた管理が行われてきました。
平成元年の保護林制度改正から、四半世紀が経過し、この間、生物多様性保全に関する科学的知見や保護地域の管理手法が大きく進歩するなど保護林制度をめぐる状況は大きく変化しました。このため、平成27年に保護林制度の見直しを行い、森林生態系や個体群の持続性に着目したわかりやすく効果的な保護林区分の導入、簡素で効率的な管理体制の再構築、森林生態系を復元する考え方の導入などを行いました。
これにより従来の7種類(九州森林管理局管内では、6種類)の保護林区分は、上記の表に記した森林生態系保護地域、生物群集保護林、希少個体群保護林の3区分に再編されることとなりました。
再編の基本的考え方としては、森林生態系保護地域はそのまま、森林生物遺伝資源保存林及び比較的規模の大きな(300ha以上)林木遺伝資源保存林、植物群落保護林は生物群集保護林へ、それ以外の林木遺伝資源保存林、植物群落保護林、特定動物生息地保護林は、保護林に生息・生育する動植物や生態的特性、地域名等を表す名称に変更しつつ希少個体群保護林へ移行させることとしました。
なお、全国の森林生態系保護地域のうち、白神山地、屋久島、知床、小笠原諸島の4地域については、世界自然遺産の価値を有するものとされ、将来にわたり守るべき地域として国際的に認められたことから、世界自然遺産に登録されました。最近は、これに加え、令和3年7月、新たに「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」が、5番目の世界自然遺産地域として登録されることとなり、現在、5地域が世界自然遺産に登録されています。また、旧区分の「郷土の森」は、地元の意向を踏まえて、「協定の森」に移行するなど柔軟に対応することとしています。
生物多様性保全への貢献
九州森林管理局管内の保護林は、上記の目的のため設定されています。近年は森林の持つ生物多様性保全機能への国民の期待が高まっており、国有林野は主に奥地脊梁山地に存し、また比較的大きな面積がまとまっていることから、貴重な野生動植物の生息・生育地としての期待は大きなものがあります。
一方、保護林では、近年、シカによる食害や、大気汚染、森林病害虫の発生等深刻な問題も発生しており、設定時から大きな状況の変化が見られるものもあります。このため、すべての保護林を対象にモニタリング調査を実施しており、得られた結果をもとに、森林生態系の的確な保全・管理や区域の見直し等を行うこととしています。
また、最近の管理区域の見直し再編事例としては、隣接する複数の保護林で類似している林相を有する保護林がある場合で、生物多様性の保全、保護対象種の保全の観点から、一体的に取り扱うことで効果的な保全対策(メタ個体群の生存地の常備性の向上、遺伝子交流、野生生物の移動・拡散のコアエリアの充実、各種試験的評価・分析への活用など)が考えられる場合には、再編統合することとしており、これまで、英彦山モミ等遺伝資源希少個体群保護林、行者スギ遺伝資源希少個体群保護林、城山タブノキ等遺伝資源希少個体群保護林、対馬スダジイ等遺伝資源希少個体群保護林、種子島ヤクタネゴヨウ等希少個体群保護林 (令和3年4月現在)などの保護林を統合・再編しています。
令和3年度には、新村照葉樹林生物群集保護林を新設(令和4年度施行)しています。
管内の保護林
管内の保護林の種類、箇所数、面積
(令和7年4月1日現在)
| 保護林区分 | 名称 | 箇所数 | 面積〔ha〕 |
| 森林生態系保護地域 | 祖母山・傾山・大崩山周辺、 綾、奄美群島、稲尾岳周辺、屋久島、やんばる、西表島 |
7 | 53,887.18 |
| 生物群集保護林 | 普賢岳、男女群島、九州中央山地、白鬚岳、鬼の目山、掃部岳、大森岳、 猪八重照葉樹林、新村照葉樹林、霧島山、高隈山 |
11 | 17,262.08 |
| 希少個体群保護林 | 英彦山スギ等遺伝資源 ほか68箇所 | 69 | 4,083.25 |
| 計 | 87 | 75,232.51 | |
保護林管理委員会
保護林モニタリング調査
保護林の状況を把握し、現状に応じた保全・管理を推進するため、10年・5年・5年未満でモニタリング調査を実施しています。
調査結果については、保護林管理委員会において、評価・検討し今後の保護林の保護・管理に反映させます。
希少野生生物種保護管理対策
入林者のみなさまへお願い
森林生態系からなる自然環境の維持、貴重な動植物の保護、遺伝資源の保存のため、保護林ごとに取り扱いの方針が定められておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。詳細は保護林一覧及び位置図を御覧ください。
なお、調査研究活動等を目的として入林される場合には、事前に入林届けを提出していただいています。
お問合せ先
計画保全部計画課
担当者:生態系保全係
ダイヤルイン:096-328-3612