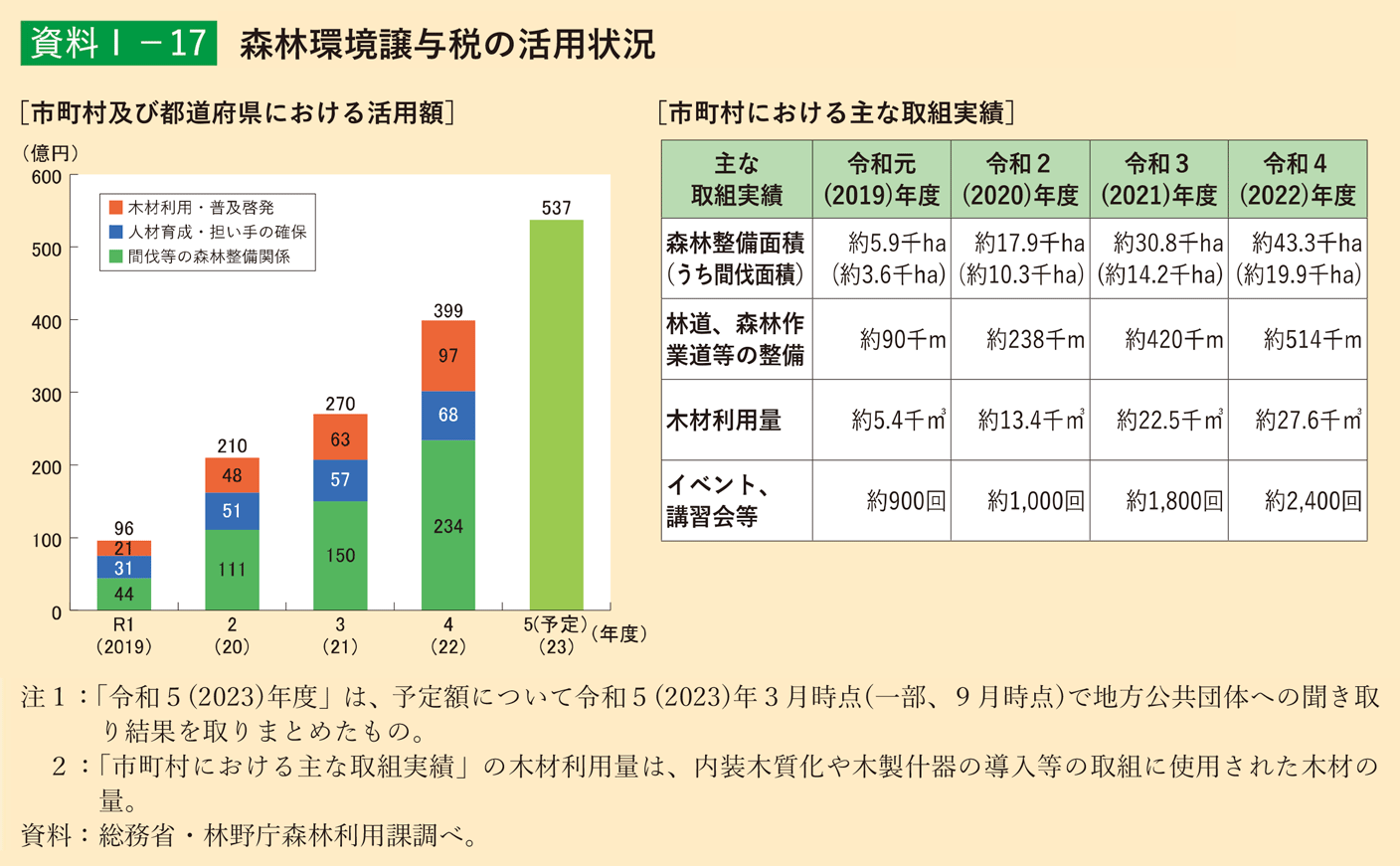第1部 第1章 第2節 森林整備の動向(4)
(4)森林経営管理制度及び森林環境税・森林環境譲与税
(ア)森林経営管理制度
(制度の概要)

これまで、私有林では、森林経営計画の作成を通じて施業の集約化を推進してきたが、所有者不明や境界不明確などにより、民間の取組だけでは事業地を確保することが困難になりつつあり、森林整備が進みにくい状況となっている。このような中、平成31(2019)年4月に、森林経営管理法が施行され、市町村が主体となって森林の経営管理を行う森林経営管理制度が導入された。
同制度では、市町村が、森林所有者に対して、経営管理の現況や今後の見通しを確認する調査(以下「意向調査」という。)を実施した上で、市町村への委託希望の回答があった場合には、市町村が森林の経営管理を受託することが可能となる。市町村が受託した森林のうち、林業経営に適した森林は一定の要件を満たす民間事業者(*19)に再委託する一方、林業経営に適さない森林は市町村が自ら管理する。
また、所有者の一部又は全部が不明な場合に、所有者の探索や公告など一定の手続を経て、市町村に経営管理権を設定することを可能とする特例も措置されている。
(*19)民間事業者については、(ア)森林所有者及び林業従事者の所得向上につながる高い生産性や収益性を有するなど効率的かつ安定的な林業経営の実現を目指す、(イ)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められるといった条件を満たす者を都道府県が公表している。
(制度の進捗状況)
令和4(2022)年度末までに、1,070の市町村において、81万haの意向調査が実施された。また、回答があったもののうち約4割について委託の希望があった。
市町村が受託する際に策定する経営管理権集積計画(*20)は、累計で337市町村の1万5,658ha(前年度比約1.7倍)で策定され、うち232市町村の4,865haで同計画に基づく市町村による森林整備が実施された。また、林業経営者(*21)への再委託を行う際に策定する経営管理実施権配分計画(*22)は70市町村の2,150ha(前年度比約2倍)で策定され、うち34市町村で林業経営者による森林整備が334ha実施された。このうち、13市町では主伐が行われ、8市町では再造林まで行われるとともに、残る5市町についても再造林が予定されている(事例1-3)。
さらに、経営管理権集積計画の策定のほか、民間事業者へのあっせん、市町村と森林所有者との協定の締結、市町村独自の補助の活用等の手法も含め、市町村への委託希望の森林のうち約6割で森林整備につながる動きがみられた(*23)。
事例1-3 地域に応じた森林経営管理制度の取組
最上町では、令和2(2020)年度に意向調査を実施し、委託希望のあった森林のうち46haで経営管理権集積計画・経営管理実施権配分計画を策定した。計画に基づき、林業経営者により令和4(2022)年10月に主伐3.88ha、搬出間伐0.76haが行われ、木材の販売収益の一部が森林所有者に支払われた。主伐跡地には令和5(2023)年に再造林が行われた。森林所有者からは「森林整備が進められて良かった」という声があった。
綾部市では、市内の人工林の約6割で過去10年間に手入れが行われていないことから、森林経営管理制度を活用した森林整備を推進している。
集落や幹線道に接しており手入れの優先度が高い森林をモデル地区に設定し、意向調査を実施した。経営管理権集積計画の同意取得の際、共有林(0.33ha)の所有者(25名の共有名義。確知した相続権利者147名。)の一部について宛先が不明等(8名)の状況であったため、共有者不明森林等の特例措置を活用し、令和5(2023)年4月に経営管理権集積計画を策定し、5月に間伐を実施した。
本山町では、令和4(2022)年に、町内の森林管理や整備に関する⾧期的な基本方向と目標、必要な施策を明らかにする「本山町森林・林業ビジョン」を策定した。構想の策定に当たって、高校生を含む町内の関係者14名からなる委員会による議論を行い、50年先を見据え、森林の基盤整備、人材育成や木材利用など7つのテーマと25の取組項目を整理した。この構想に基づき、地域関係者が森林管理の課題や方向性を共有しつつ、計画的に森林経営管理制度に係る取組を進めていくこととしている。
(*20)市町村が森林所有者から森林の経営管理を受託する(市町村に経営管理権を設定する)際に策定する計画。
(*21)経営管理実施権の設定を受けた民間事業者。
(*22)市町村が経営管理権を有する森林について、林業経営者への再委託を行う(経営管理実施権の設定をする)際に策定する計画。
(*23)林野庁ホームページ「森林経営管理制度の取組状況について(令和5年10月)」
(イ)森林環境税・森林環境譲与税
(税制の概要)

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設された。
森林環境税は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が賦課徴収される。森林環境譲与税は、市町村による森林整備等の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按(あん)分して譲与されている。
(森林環境譲与税の使途と活用状況)
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充て、都道府県においては、森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てるものとされている。譲与額は令和元(2019)年度の総額200億円から段階的に引き上げられ、令和5(2023)年度は市町村に440億円、都道府県に60億円の総額500億円が譲与された。
市町村及び都道府県における活用額は、令和3(2021)年度の270億円から令和4(2022)年度は399億円に増加しており、令和5(2023)年度の予定では537億円となっている。市町村における活用状況を使途別にみると、令和4(2022)年度は、全体の79%の市町村が間伐等の森林整備関係、35%の市町村が人材育成・担い手の確保、52%の市町村が木材利用・普及啓発に取り組んだ。取組実績としては、令和4(2022)年度の間伐等の森林整備面積は約4万3,300haで、令和元(2019)年度の約7倍になるなど、取組が着実に進展している。また、流域の上流と下流などの関係にある地方公共団体が連携した取組も広がりをみせており、令和4(2022)年度は44件の取組が実施された(*24)(資料1-17、事例1-4)。
森林環境譲与税の活用を促進するため、林野庁と総務省は、令和4(2022)年度から、市町村が森林環境譲与税を活用して実施可能な具体的な取組項目を整理した「森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例」を公表している。
また、森林環境譲与税については、地方公共団体等から、森林整備を一層推進するため、譲与基準の見直しを求める要望が上がっていたところであり、令和6年度税制改正において、これまでの活用実績等を踏まえ、私有林人工林面積及び人口の譲与割合の見直しを行うこととされた。具体的には、令和6年度税制改正の大綱(令和5(2023)年12月閣議決定)において、森林環境譲与税の譲与基準について、「私有林人工林面積の譲与割合を100分の55(現行:10分の5)とし、人口の譲与割合を100分の25(現行:10分の3)とする」こととされた。
令和6(2024)年度から、森林環境譲与税の財源となる森林環境税の課税が開始されることも踏まえ、今後とも、森林環境譲与税に対する国民の理解が深まるよう、市町村等における森林環境譲与税の一層の有効活用を促すとともに、森林環境譲与税を活用した取組成果の一層の情報発信に取り組むこととしている。
事例1-4 森林環境譲与税を活用した取組(注)
八頭町では、戦後造成されたスギ・ヒノキの人工林が利用期を迎えているが、木材価格の低迷やシカによる食害のため主伐・再造林が進んでいない。
このため、再造林に係る経費への上乗せ補助により主伐・再造林を推進しており、植栽対象をクヌギとコナラとすることで、花粉発生源対策の推進とともに、しいたけ原木の不足解消も図っている。
令和4(2022)年度は、0.94haのコナラ植栽及び651mのシカ防護ネット設置を支援した。
【事業費:24万円】
成田市は、令和元(2019)年の台風による多数の倒木が道路や電線等のインフラ施設に多大な被害をもたらしたことから、被害を未然に防止するための森林整備を進めている。
令和4(2022)年度は、現況調査や市民要望等を踏まえ、市道沿いの森林1.22haの伐採、搬出を実施した。
伐採跡地には、倒木による災害リスク低減と良好な景観の形成に配慮して、イロハモミジ等の中低木の広葉樹を植栽した。
【事業費:921万円】
佐賀県では、県内の林業の担い手が年々減少しており、今後、県内の森林を持続的に守り育てていくために、林業の担い手の育成・確保が急務となっている。
このため、令和4(2022)年度に「さが林業アカデミー」を開講し、就業セミナー、体験会、林業講習会の3ステップで、知識や技術力を備えた人材を育成している。令和4(2022)年度は、林業講習会を受講した6名全員が県内の林業事業体等へ就職した。
【事業費:475万円】
小田原市は、地域産木材の利用拡大を図るため、市内小学校の内装木質化を実施している。
令和4(2022)年度は、地域産のスギ・ヒノキの間伐材を34m3活用して、小学校の腰壁や天井、室名札等の木質化を実施した。山元への利益還元を目指し、低質材も積極的に活用した。
さらに、木質化の意義を伝える学習や端材を使ったワークショップにより、児童に対し普及啓発を行った。
【事業費:1,833万円】
注:事業費は森林環境譲与税を財源とした額を記載。
(ウ)市町村に対する支援
森林経営管理制度を円滑に進めるためには、市町村の役割が重要であるが、林務担当職員が不足している市町村もある。このため、林野庁では、人材育成、情報提供及び体制整備を通じて、市町村の支援に取り組んでいる。
人材育成については、市町村への技術的助言・指導を行う者(通称:森林経営管理リーダー)を養成するため、都道府県の地方機関やサポートセンター等の職員を対象とする「森林経営管理リーダー育成研修」を開催しており、5年間に37か所で開催し、計788名が参加した。令和5(2023)年度からは、内容の見直しを行い、所有者探索の机上演習、地域課題解決に向けたグループワーク、市町村講師による先進事例の紹介等を通じて、実践的人材の育成を図っている。また、都道府県・市町村等が開催する説明会・研修会に、講師として林野庁職員を派遣しており、令和5(2023)年度は30回派遣した。
情報提供については、毎年度、森林経営管理制度の取組事例集を作成するとともに、令和4(2022)年度から、毎月、森林経営管理制度と森林環境譲与税の最新情報を紹介する情報誌「シューセキ!」を各都道府県及び市町村等に配布している。
体制整備については、市町村が森林・林業の技術者を雇用する「地域林政アドバイザー制度(*25)」の活用を促している。林野庁は、アドバイザー活用希望のある市町村の情報を技術者団体に提供するとともに、当該市町村の一覧を林野庁ホームページで公表している。令和4(2022)年度には、204の地方公共団体で307名のアドバイザーが活用された。
このほか、都道府県でも、森林環境譲与税の活用により、市町村に提供する森林情報等の精度向上・高度化、都道府県レベルの事業支援団体の運営支援、市町村職員の研修など、地域の実情に応じた市町村支援の取組が展開されている。
(*25)平成29(2017)年度に創設され、市町村が雇用(法人委託)する際に要する経費については、特別交付税の算定の対象となっている。なお、平成30(2018)年度から都道府県が雇用(法人委託)する場合も対象となった。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219