第1部 第1章 第2節 森林整備の動向(3)
(3)路網の整備
(路網整備の現状と課題)
路網は、間伐や再造林等の施業を効率的に行うとともに、木材を安定的に供給するために重要な生産基盤であり、林野庁では、役割に応じて林道(林道及び林業専用道)と森林作業道に区分している(資料1-15)。我が国においては、地形が急峻(しゅん)で、多種多様な地質が分布しているなど厳しい条件の下、路網の整備を進めてきたところであり、令和4(2022)年度末の総延⾧は41.0万km、路網密度は24.1m/haとなっている(*18)。
しかし、相対的に開設コストの低い森林作業道に比べ、10トン積以上のトラックが通行できる林道の整備が遅れている。木材流通コストの低減を図るためには、大型車両により効率的に木材を運搬することが重要であり、大型の高性能林業機械の運搬等のためにも幹線となる林道の整備を進めていくことが不可欠である。
また、山地災害が激甚化する中で、災害に強い路網の整備が求められており、開設から維持管理までのトータルコストも考慮して、強靱(じん)な路網の開設に加え、排水施設の設置等の路網の改良を行うなど、新設・既設の双方について必要な整備を進めることが重要である(事例1-2)。
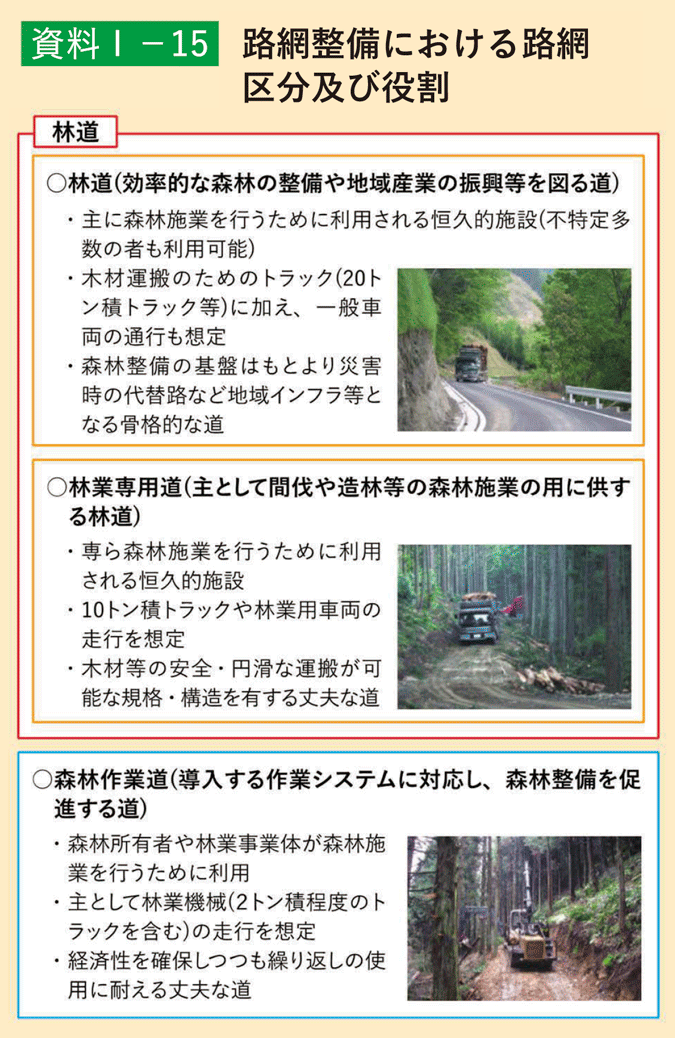
事例1-2 災害リスクに備えた林道の整備
福井県福井市の国山町(くにやまちょう)集落は豊富な森林が存在する丹生(にゅう)山地に位置しており、木材の効率的な生産が求められていた。一方で、集落周辺には山地災害危険地区が複数設定されていたことから、森林の公益的機能発揮のために上流部において森林整備を実施する必要があった。また、集落外に通じる県市道が限られていたことから、土砂崩れや河川氾濫により県市道が被災した際に孤立するリスクにさらされていた。こうした状況を踏まえ、福井市は昭和60(1985)年度から令和4(2022)年度にかけて総延⾧約10kmの林道「越前西部四号線」を整備した。その結果、沿道の森林819haにおいて、効率的な木材生産や公益的機能発揮のための森林整備が可能となったほか、災害時には代替路として機能することで地域の防災力の強化に貢献している。
また、この林道は大雨などの災害に強い林道となるよう十分に配慮して側溝や横断溝などの排水施設が配置されている。
(*18)林野庁整備課調べ。
(望ましい路網整備の考え方)
森林・林業基本計画では、傾斜や作業システムに応じ、林道と森林作業道を適切に組み合わせた路網の整備を引き続き推進するとともに、災害の激甚化や走行車両の大型化等への対応を踏まえた路網の強靱(じん)化・⾧寿命化を図ることとしている。
また、同計画では、林道等の望ましい総延⾧の目安を25万km程度とした上で、令和17(2035)年までに21万kmを目安に整備するとともに、改築・改良により質的向上を図ることで、大型車両が安全に通行できる林道の延⾧を7,000kmまで増やしていくこととしている(資料1-16)。
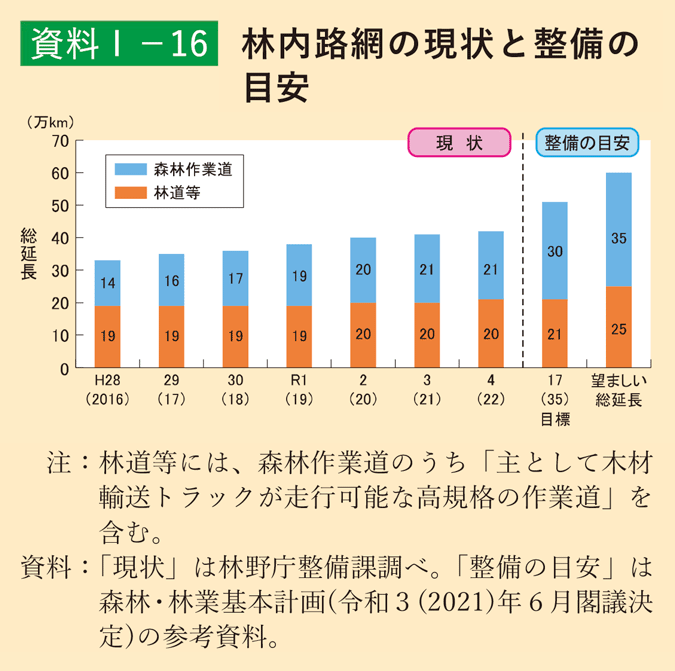
(路網整備を担う人材育成)
路網整備には、路網ルートの設定や設計・施工に高度な知識・技能が必要であり、林野庁や都道府県等では、ICT等の先端技術を活用した路網設計等ができる技術者や、路網整備の現場で指導的な役割を果たす人材の育成を目的とした研修を実施している。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219






