第1部 特集 第1節 生物多様性の重要性と関心の高まり(2)
(2)生物多様性をめぐる近年の動き
(生物多様性に関する国際的な動き)
生物多様性の確保は、気候変動の問題と並ぶ地球規模の課題として認識されており、一体的に取り組むことが必要となっている。生物多様性と気候変動への国際的な取組は、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット)に合わせて採択された生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)と気候変動に関する国際連合枠組条約(国連気候変動枠組条約)の下で進められてきた。
2022年12月には、カナダのモントリオールで開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)第二部において、COP10で定められた「愛知目標(*7)」に代わる新たな目標として「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択された。この中で、2030年までに、生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せるための緊急の行動をとるとの目標が掲げられており、この考え方は、2021年のG7の合意文書において「ネイチャーポジティブ(自然再興)」と呼ばれている。また、その具体的な目標として、陸と海のそれぞれ少なくとも30%を保護地域(*8)及びOECM(*9)(保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域)により保全する「30by30目標」(目標3)や農林水産業が営まれる地域の持続可能な経営管理(目標10)など、23の目標が掲げられている(資料 特-3)。このように、保護地域以外も含めて生物多様性確保の取組が求められている。
(*7)2020年までの短期目標「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」を達成するために定められた20の個別目標。
(*8)陸域については自然公園、自然海浜保全地区、自然環境保全地域、鳥獣保護区、生息地等保護区、近郊緑地特別保全地区、特別緑地保全地区、保護林、緑の回廊、天然記念物、都道府県が条例で定めるその他保護地域。
(*9)Other Effective area-based Conservation Measuresの略。
(生物多様性に関する国内の動き)
我が国においては、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択を受けて、令和5(2023)年3月に、2030年のネイチャーポジティブの実現を目指す「生物多様性国家戦略2023-2030」を閣議決定した。農林水産省においても、同月に「農林水産省生物多様性戦略」を改定し、生物多様性保全を重視した農林水産業を推進することとしている。同戦略における森林・林業分野の取組としては森林の整備・保全を通じた生物多様性の保全や、生物多様性に配慮した林業と国内森林資源の活用による貢献が位置付けられている。
また、30by30目標を契機として、令和5(2023)年4月から国が「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定し、保護地域との重複を除いた箇所をOECMとして国際データベースに登録する仕組みが開始されている。令和7(2025)年3月時点で、企業の社有林や水源林など328か所が認定されており、その多くは対象区域に森林が含まれている(資料 特-4)。
このOECMの設定を更に促進するため、令和6(2024)年4月には、事業者等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制度を創設するなどの措置を講ずる「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(以下「地域生物多様性増進法」という。)が成立し、令和7(2025)年4月に施行されることとなった。これに伴い、自然共生サイトの申請・認定については、令和7(2025)年度から地域生物多様性増進法に基づく認定制度に一本化される。
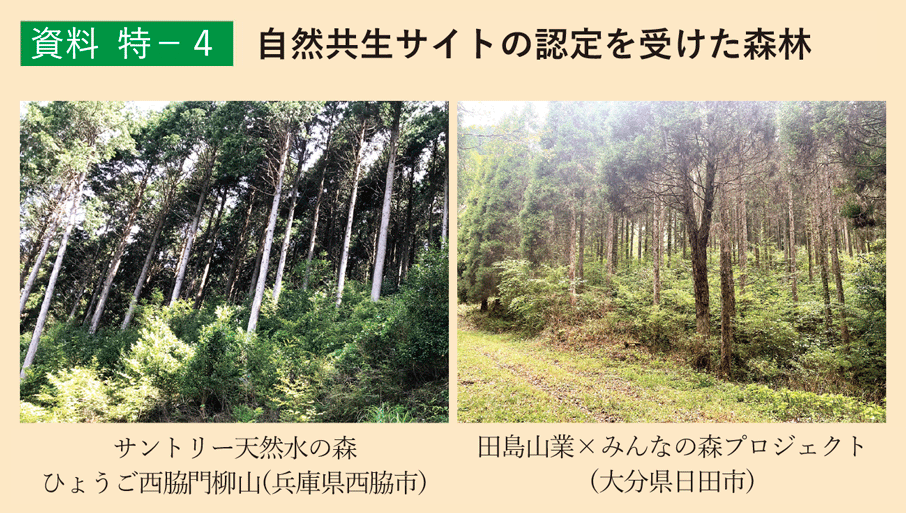
(民間企業が主体となった動き)
民間企業においても、生物多様性の損失や自然資本の劣化が事業の継続性を損なうリスクとして認識されつつあり、気候変動対策に加えて、生物多様性・自然資本への対応をビジネス課題と位置付けて、企業経営に組み込んでいく動きが加速している。
既に気候変動の分野では、企業の事業の持続性確保の点から、気候変動対策を企業経営に組み込んでいくため、2017年6月に公表された「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD(*10))」の提言等に基づく情報開示が進んでいるが、自然資本の分野においても、2023年9月に公表された「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD(*11))」の提言等により、民間企業が自然資本への依存度等の評価を行いつつ、サプライチェーンを含む事業活動全体が自然資本と生態系サービスに及ぼす影響や、その損失による事業活動への影響等について情報開示を行うことが求められるようになっている。これにより、民間企業においても、生物多様性保全を含む森林の有する多面的機能の発揮に向けた取組を行うことが重要な課題と認識されるようになってきている。
なお、令和6(2024)年10月時点で、TNFD提言に基づく開示に取り組む意向を表明した企業「TNFD Adopters」は世界で502社、そのうち133社が我が国の企業であり、国別では最多となっている。
(*10)Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。TCFD提言では、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4本柱の下、計11の項目について開示を推奨している。
(*11)Taskforce on Nature-related Financial Disclosuresの略。TNFD提言では、TCFD提言と共通の「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4本柱の下、計14の項目について開示を推奨している。
コラム 国際的な議論における持続可能な森林経営と生物多様性

森林に関する国際的な議論は、特に熱帯林を中心として急速な減少・劣化の進行等が指摘されていたことに端を発し、国際連合等において進められてきた。1992年の地球サミットでは、森林に関する初めての世界的合意である「森林原則声明」が採択されるとともに、持続可能な開発に向けた実施計画であるアジェンダ21では第11章に森林減少対策が位置付けられ、全ての森林の経営、保全及び持続可能な開発のために、科学的に信頼できる基準とガイドラインを作成することが盛り込まれた。
これを受けて、森林経営の持続可能性を客観的に把握するものさしとして、国際的な基準・指標の作成及び評価に関する取組が国際的に進展してきた。我が国を含む12か国(注1)が参加する「モントリオール・プロセス」は、面積で世界の温帯林と亜寒帯林の90%、世界の森林の49%、世界の人工林の59%を占めており、人工林の割合が高く、多くの国で木材生産量の継続的な増加が見込まれている。同プロセスでは、1994年から基準・指標の作成等を進め、現在は7基準54指標に基づき、各国がデータを収集し、国別報告書等を作成している。我が国においても、平成15(2003)年に第1回国別報告書を作成して以降、森林・林業の現状を取りまとめて報告しており、令和7(2025)年3月には第4回国別報告書を公表した。国別報告書作成に当たっては、平成11(1999)年度から継続的に実施している全国レベルの森林調査である森林生態系多様性基礎調査(注2)の結果等を活用している。
2024年にモントリオール・プロセスが30周年を迎えたことから、同年12月には林野庁主催により国際シンポジウム「温帯林・亜寒帯林における生物多様性の保全と調和した林業経営とそのモニタリング」を開催した。シンポジウムでは、モントリオール・プロセス参加国や関連国際機関等から森林政策の専門家などが集まり、同プロセスの基準1「生物多様性の保全」に関して、各国の生物多様性と調和した林業経営の優良事例とそのモニタリング、国際機関及びヨーロッパにおける生物多様性の保全に関する視点等を共有するとともに、これらの取組における必要な要素と課題について議論が行われた。また、シンポジウムに併せて、東京都内で木材生産と生物多様性の両立の取組が行われている森林や木材を利用した中高層建築物の視察、国立研究開発法人森林研究・整備機構の研究者を交えた意見交換も実施することで、参加国間での生物多様性等に関する知見の共有を図った。これらを契機として、生物多様性を含む持続可能な森林経営に関する国際的な議論のより一層の発展が期待される。
注1:アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、チリ、中国、日本、メキシコ、ニュージーランド、韓国、ロシア、米国、ウルグアイ
2:国土全域に4km間隔の格子点を想定し、その格子点を調査地点とする標本調査であり、5年間で全国を一巡するサイクルで実施されている。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219






