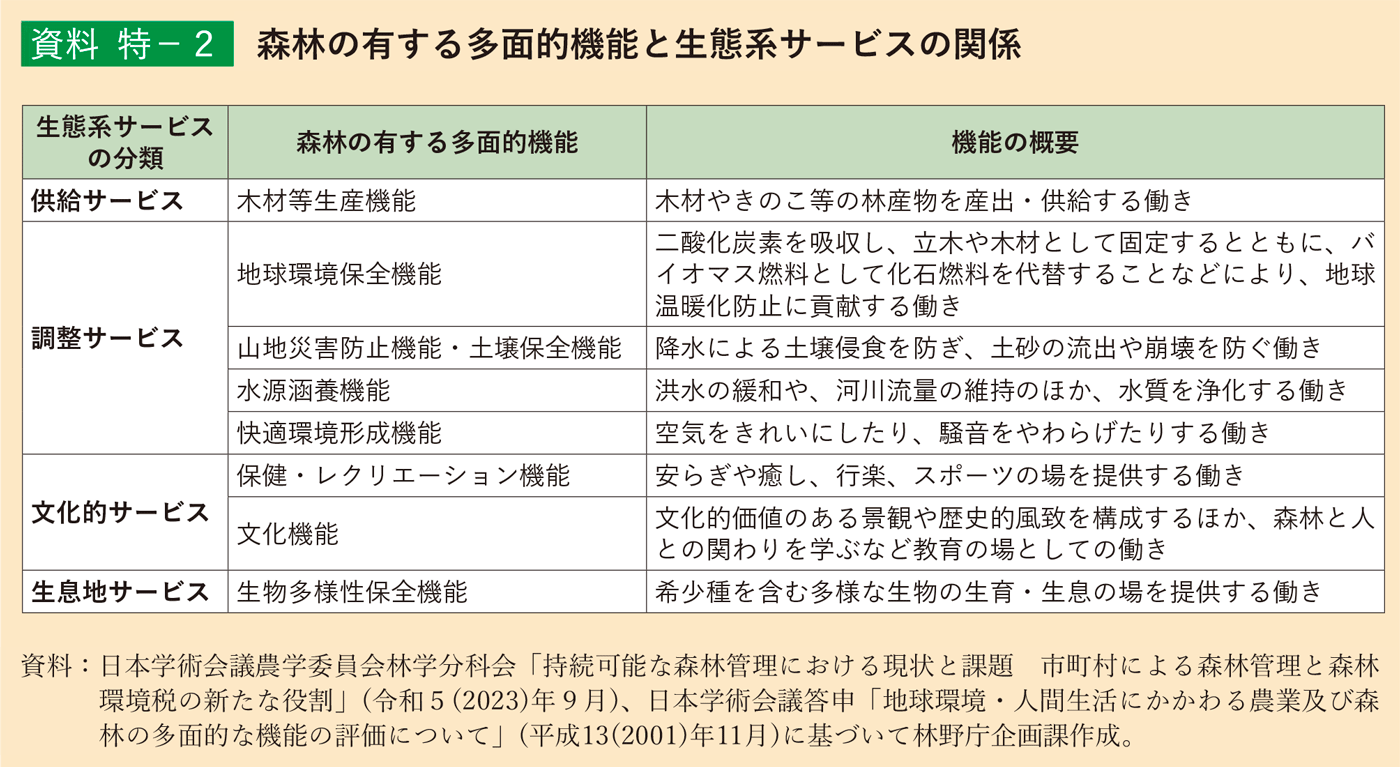第1部 特集 第1節 生物多様性の重要性と関心の高まり(1)
(1)生物多様性とその意義
(生物多様性とは)
世界では既知の生物だけで約175万種、まだ知られていないものも含めると地球上には3,000万種とも言われる生物が存在すると推定されている(*1)。中でも、森林は、面積でみれば世界の陸地の約3割を占めるにすぎないが、陸上の多くの生物種が生育・生息するとされている(*2)。これら多様な生物が相互につながりを持ちながら構成する生態系は、食料や水、木材、大気中の酸素の供給、気候の安定等をもたらしており、人々の暮らしはそれによって支えられている。
生物多様性とは、全ての生物の間に違いがあることであり、「生物多様性基本法(*3)」において、「様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在すること」と定義されている。これは、生態系、種(種間)、遺伝子(種内)の3つのレベルにおける様々な多様性を指しており、生態系の多様性とは、森林、河川、湿原、干潟など、環境によって様々なタイプの生態系が形成されていること、種の多様性とは、多様な動物・植物や菌類等が生育・生息していること、遺伝子の多様性とは、同じ種であっても、個体や個体群の間に遺伝子レベルで違いがあることである(資料 特-1)。
生物多様性には階層があり、これらが相互に関連し、生態系の多様性が確保されていることで、異なる生物の種や集団に生育・生息場所を提供し、種や遺伝子の多様性に貢献している。生物多様性を考える上では、生態系レベルでみた場合の面的な広がりにおける多様性から、種や遺伝子レベルでみた場合の個別の多様性まで複数の視点が必要である。
これらの階層内における違いが生物の⾧い進化の歴史の中で受け継がれてきた結果、現在の生物多様性が形成されている。生物多様性は、損なわれると回復するまでに極めて⾧い期間が必要であるほか、一度絶滅した種は基本的に再生しないという不可逆性がある。
生物多様性の損失の例として、世界自然遺産に登録されている「小笠原諸島(おがさわらしょとう)」では、20世紀初頭に生活に必要な木炭等の原料として南西諸島からの外来種であるアカギが持ち込まれたが、成⾧が早く急速に分布域を広げたため、固有の植物相を脅かしている。現在、アカギの駆除活動が行われているが、繁殖力が非常に強く、在来植生への回復に多大な労力と時間が必要となっている(*4)。このように一度崩れた生態系のバランスを回復することは容易でなく、ある生物種の影響が地域の生態系を大きく変えてしまうことがある。
(*1)「生物多様性国家戦略2023-2030」(令和5(2023)年3月閣議決定)附属書
(*2)FAO and UNEP(2020)The State of the World’s Forests 2020: Forests, biodiversity and people: xvi.
(*3)平成20(2008)年に議員立法により成立。
(*4)小笠原諸島での外来種対策については、「平成28年度森林及び林業の動向」第2章第3節(3)の事例2-8(65ページ)を参照。
(森林の有する多面的機能と生態系サービス)
森林・林業基本法においては、国土の保全、水源の涵(かん)養、地球温暖化の防止、林産物の供給等の森林の有する多面的機能の持続的な発揮が国民生活及び国民経済の安定に欠くことができないものと位置付けられている。こうした多面的機能は、自然資本(*5)が提供する恵みであり国際的には生態系サービス(Ecosystem services)とも呼ばれている。
生態系サービスは、1)食料や水、木材、繊維、医薬品資源等を提供する「供給サービス」、2)気候調整や自然災害の防止・被害の軽減、水源涵(かん)養、土壌保全、花粉の媒介、天敵の存在による病害虫の抑制等の「調整サービス」、3)自然景観の保全やレクリエーションの場の提供等の「文化的サービス」、4)生育・生息環境の提供、遺伝的多様性の保全等の「生息地サービス」の4つに分類されている(*6)。
森林の有する多面的機能と生態系サービスの関係を整理すると、供給サービスとしては、林産物の産出・供給といった木材等生産機能、調整サービスとしては、国土保全や水源涵(かん)養、地球温暖化防止等の機能、文化的サービスとしては、保健・レクリエーション機能、文化機能、生息地サービスとしては、生物多様性保全機能がある(資料 特-2)。
森林の生物多様性の確保は、自然資本の基盤を維持することであり、生態系サービスを支えるものであることから、木材等生産機能や水源涵(かん)養機能など、多くの機能の維持・向上に関わっている。生物多様性が損なわれると、我々が享受できる生態系サービスのレベルの低下や将来にわたる暮らしの基盤の喪失につながる。このため、将来にわたって様々な生態系サービスを享受することを可能としていくためには、その源となる生物多様性を確保していくことが極めて重要である。
(*5)森林、土壌、水、大気等の自然由来の資源。
(*6)公益財団法人地球環境戦略研究機関「TEEB報告書第0部:生態学と経済学の基礎(IGES仮訳)」(平成23(2011)年9月)
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219