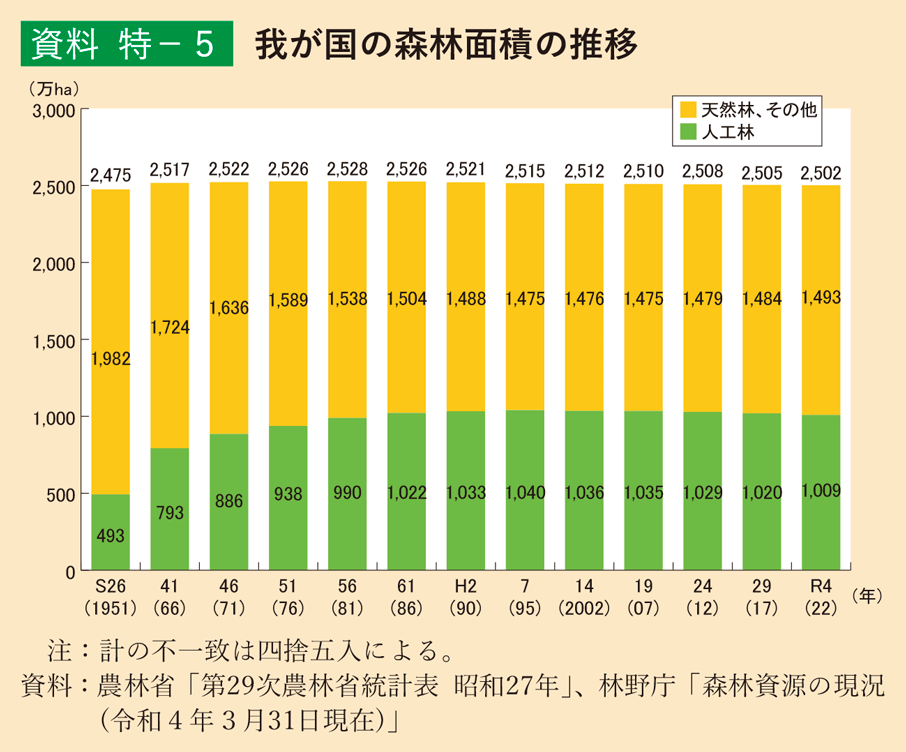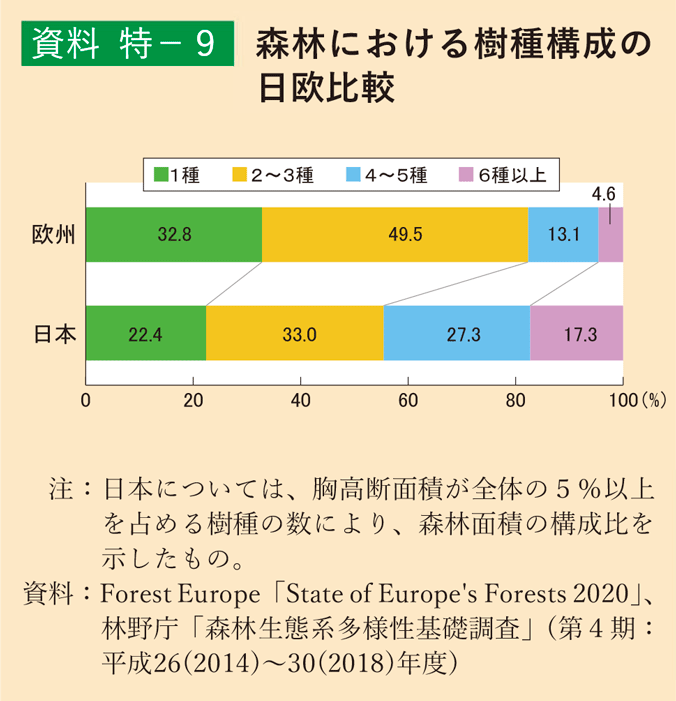第1部 特集 第2節 我が国の森林における生物多様性とこれまでの保全の取組(1)
(1)高い生物多様性を誇る我が国の森林
(我が国の森林の概況)
我が国は、南北に⾧い国土を有し、海岸から山岳までの標高差があって多様な気候帯に属するとともに、独特の地史を有する琉球列島、小笠原諸島があることなどを背景に、多様な生物の生育・生息環境が広がっている。温暖な気温と豊富な降水量等の恵まれた気候条件の下、我が国は、国土面積3,780万ha(*12)のうち森林面積が2,502万haと、森林が国土の約3分の2を占める森林大国である。世界全体では森林減少が続いている中、70年以上にわたってその面積・割合は維持されてきており(資料 特-5)、経済協力開発機構(OECD)加盟国の中でも、フィンランド、スウェーデンに次いで、3番目に高い森林率を誇る(*13)。生物相が豊かな我が国にあって、森林は陸域で最大の生物種の宝庫である。森林では、生産者である植物以外の生物相も豊富であり、消費者である昆虫類、鳥類、哺乳類等のほか、分解者である土壌動物や土壌微生物など多様な生物群が生育・生息している。
(*12)国土交通省「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」
(*13)林野庁ホームページ「森林・林業分野の国際的取組(世界森林資源評価2020 Main report 概要(仮訳))」
(森林における生態系レベルの多様性)
我が国の森林は、北部から南部にかけて、年平均気温の差等によって、北海道のトドマツ、エゾマツ等に代表される亜寒帯林、ブナ、ミズナラ等に代表される冷温帯林、クリ、コナラ等に代表される暖温帯落葉広葉樹林、シイ類、カシ類に代表される暖温帯常緑広葉樹林(照葉樹林)、ガジュマル、アコウ等に代表される亜熱帯林が分布する。このような植生帯の水平分布に加えて、同じ地域でも気温は標高差に応じて変化することから、例えば、高い山では、麓は落葉広葉樹林となっているが、山頂付近では亜寒帯性の針葉樹林や高山植生となるといった変化のように、植生帯の垂直分布がある(資料 特-6)。
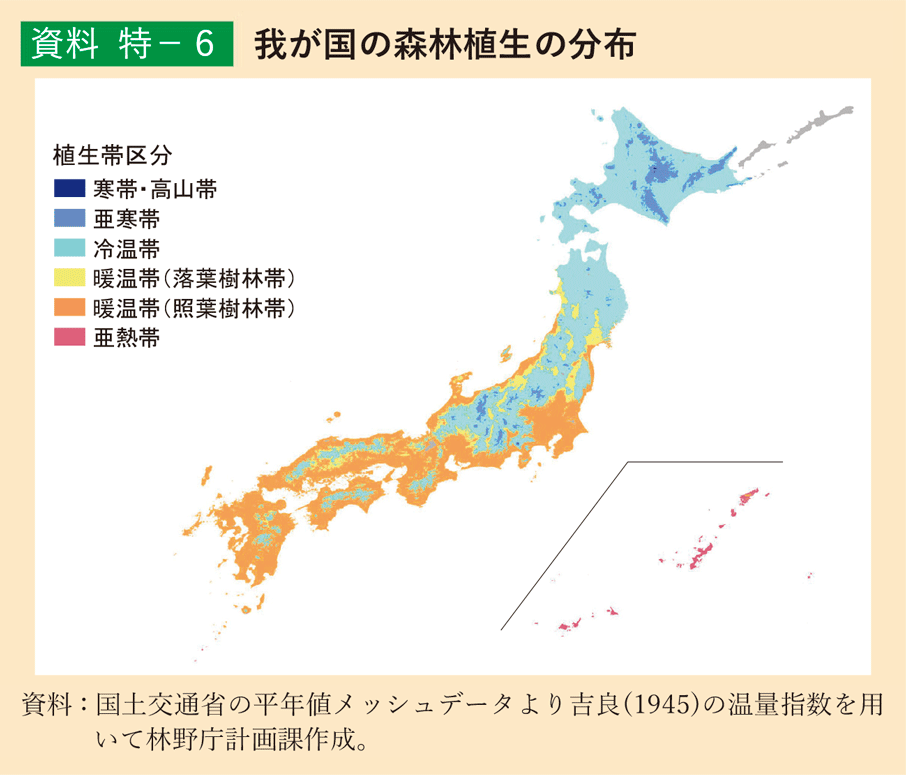
また、我が国の森林は、季節風等の気候条件や地形・地質等の立地条件、自然災害、天然更新、人為による伐採や植栽等によって変化しており、様々なタイプの森林が存在する(資料 特-7)。⾧期間にわたって人手が加わっていない原生的な天然林に対して、人手が加わることによって成立してきた森林は、二次的な自然とも呼ばれ、生活資材等の供給源として継続的に利用され、維持管理されることで成立してきた里山林(*14)や、林業を通じて木材を生産する場である人工林が含まれる。これらの森林はそれぞれ異なる生物相を形成し、生物多様性に貢献する。我が国においては、原生的な天然林の厳格な保護・管理に加えて林業等による持続的な利用を通じて、空間的にも時間的にも多様な森林が形成され、多様な生物の生育・生息環境が創出されている(資料 特-8、事例 特-1)。
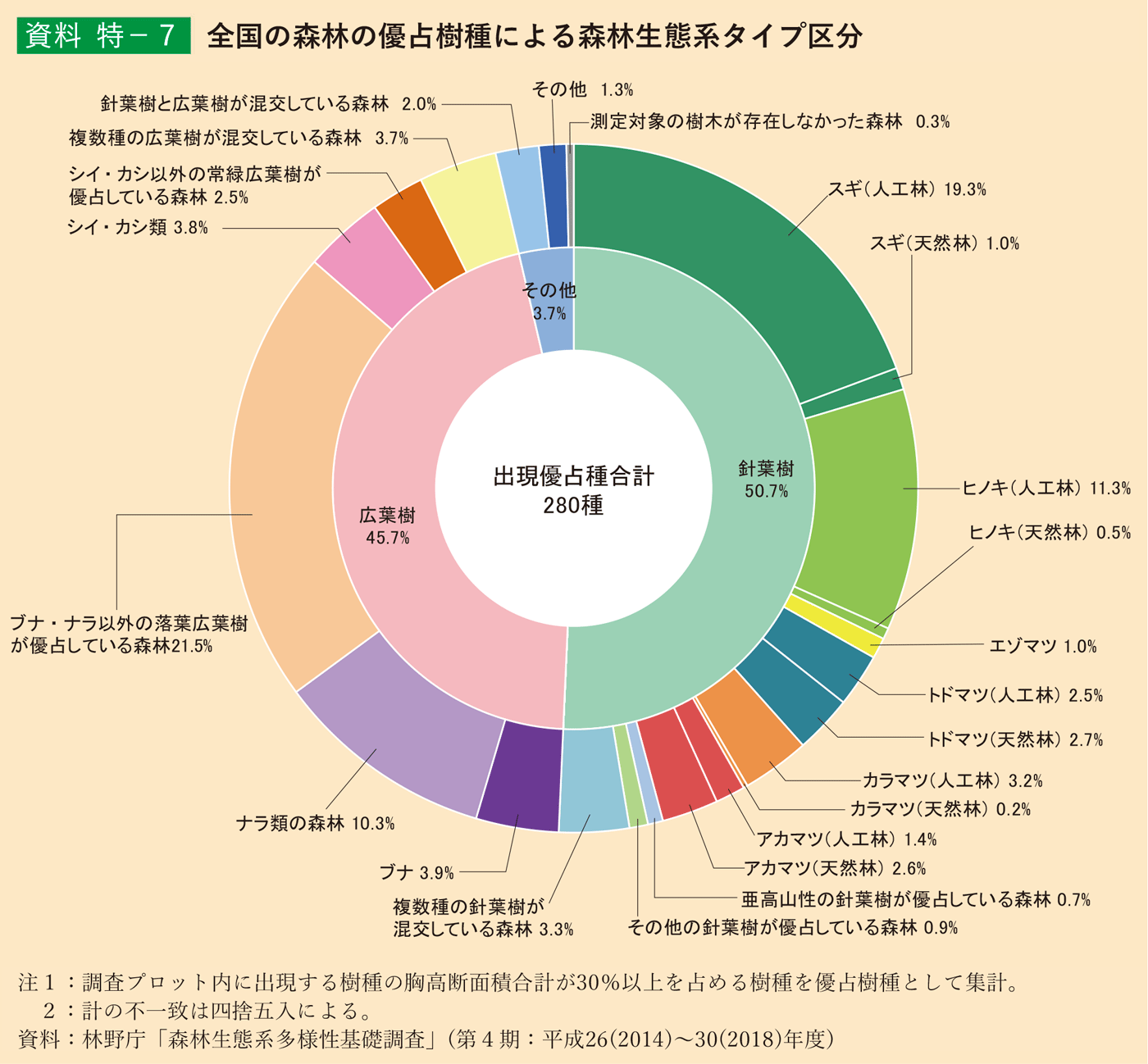
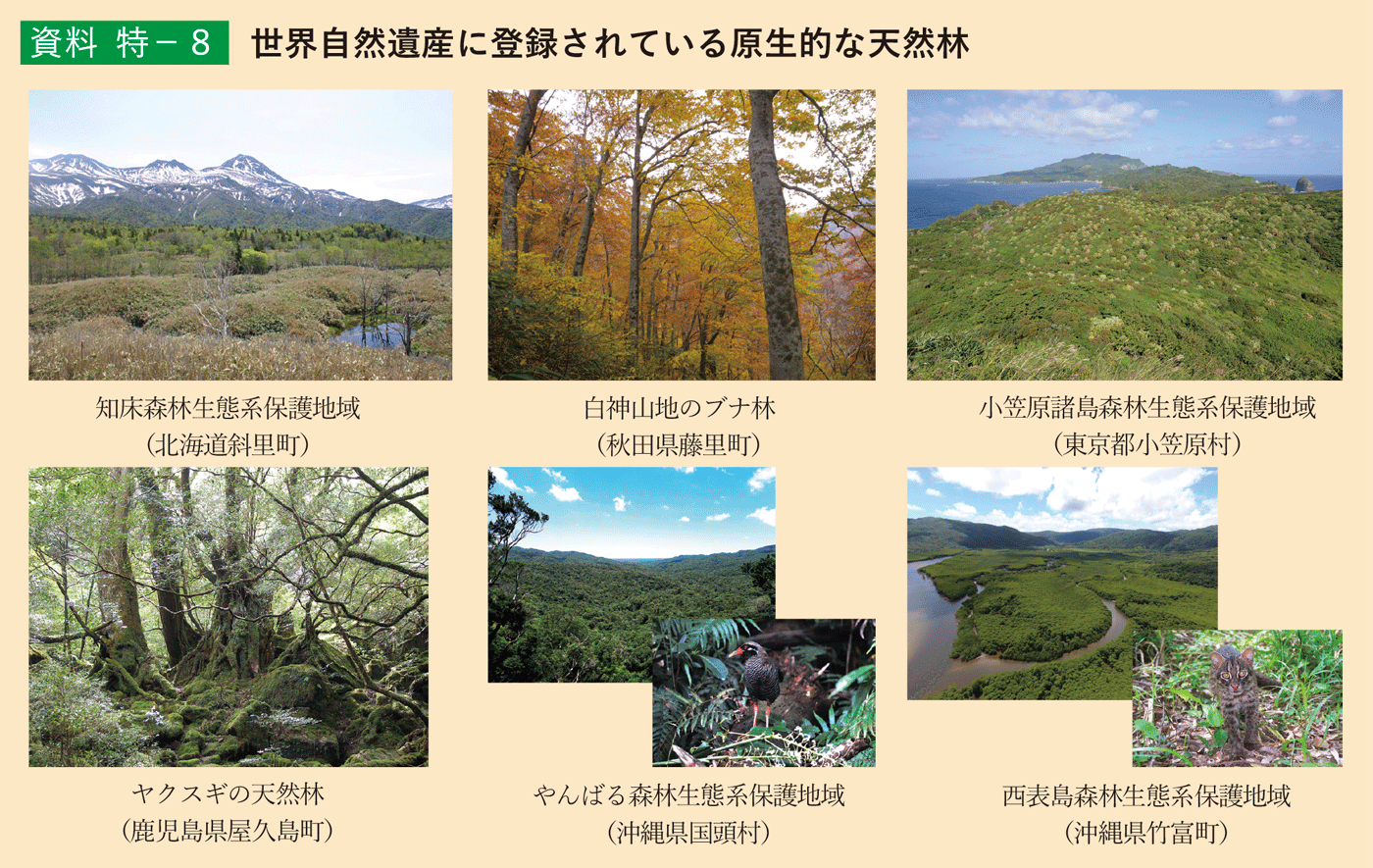
事例 特-1 「林業立村」100年の村がつくる多様なモザイク林相
宮崎県諸塚村(もろつかそん)は、山間部に位置し平地が少なく、森林率が9割を超える土地柄から、「林業立村」をスローガンに、林業やしいたけ栽培、畜産等を組み合わせる複合経営を行いながら、森林と共生してきた。このような山間地の農林業複合の取組等が評価され、平成27(2015)年には、周辺の4町村(高千穂町(たかちほちょう)、日之影町(ひのかげちょう)、五ヶ瀬町(ごかせちょう)、椎葉村(しいばそん))と共に、世界農業遺産にも認定されている
戦後の拡大造林期には、全国的にスギ、ヒノキの一斉林(注1)が造成される中で、針葉樹一斉林ではなく、適地適木を旨として、針葉樹と広葉樹を混植する施策をとり、用材生産のための針葉樹林、しいたけ栽培用原木の生産のための落葉広葉樹林、天然生林として保全管理される常緑の照葉樹林がモザイク状に配置されている。
林業やしいたけ栽培等が⾧きにわたり営まれてきた結果として生み出されたモザイク林相は、四季折々の美しい景観を形成するとともに、大面積の画一的な人工林と比べ、植物種の多様度は高く(注2)、生物多様性にも優れた森林となっている。
注1:同一樹種かつ同一年齢の林木で構成される森林。同齢単純林も同義。
2:柿澤宏昭ら編「保持林業-木を伐りながら生き物を守る」(2018)
(*14)里山二次林とも呼ばれる。伐採等の人手が加わることなどにより攪乱が起きた後に成立し、遷移している状態の森林。
(森林における種レベルの多様性)
様々な動植物等の種が存在するためには、それらの種の生育・生息が可能となる多様な森林環境が必要である。数十年以上という⾧期間にわたる森林の発達段階は、林分成立段階、若齢段階、成熟段階、老齢段階に分けられる。このような森林の発達の過程で草本、中低木から高木までの複雑な階層構造ができることで、多様な環境が形成され、時間の経過と共に変化することにより、環境に応じた様々な動植物等が生育・生息する。この階層構造は農地や草地の生態系にはない特徴である。
多様な森林のタイプが成立している我が国においては、種レベルの多様性も高く、例えば、我が国の林業を概観する際に比較することの多い欧州と比べると、我が国の森林を構成する樹種は多様である(資料 特-9)。また、森林に限った比較ではないが、我が国の植物種数は5,565種とされ、同程度の面積で同じ島国であるイギリスの1,623種やニュージーランドの2,382種よりも多くなっている(*15)。なお、東京都八王子(はちおうじ)市にある高尾山(たかおさん)の森林において発見されている植物種数は約1,500種に及ぶ(*16)など、我が国では都市近郊の森林であっても多様な植物種が生育している。
(*15)World Resources Institute(2000)World Resources 2000-2001: People and Ecosystems: The Fraying Web of Life: 248-249.
(*16)山田隆彦「新版 高尾山全植物」(2024)
(森林における遺伝子レベルの多様性)
森林には多様な生物種が生育・生息していることに加え、同じ種であっても個体ごとに異なる遺伝子を持ち、その性質には個体差がある。我が国では気候条件等に応じて多様な遺伝的特性が存在しており、森林についてはスギやヒノキを中心に、古くから地域ごとに品種を選抜し育成することで林業用に利用してきた。
中でもスギは、幅広い立地で生育していることが確認されており、その天然分布は青森県鯵ヶ沢町(あじがさわまち)から鹿児島県屋久島町(やくしまちょう)まで広範囲にわたっている(*17)が、同じスギの中でも遺伝的多様性があることにより、成⾧や形質の優れている品種、雪害に強い品種など多様な品種が存在する。特徴的な遺伝的特性は雪に対する耐性であり、太平洋側に分布し雪に弱い「表スギ」、日本海側に分布し雪に強い「裏スギ」が知られているが、表スギを日本海側など寒冷地域に植栽した場合には、裏スギに比べて成⾧が劣るほか、雪害を受けやすいといった調査結果もある(*18)。
このため、同じスギ人工林を造成する場合であっても、気候条件等に適した品種を選択する必要があるなどの留意点があるが、遺伝子レベルの多様性が確保されていることは、気象害や病虫害等に対して集団としての抵抗性が増し、森林全体として安定して存続することに寄与する。
(*17)森林遺伝育種学会「日本における森林樹木の遺伝的多様性と地理的遺伝構造」(2022)
(*18)糸屋吉彦「産地によるスギの成⾧と形態の違い-碇ヶ関の試験地での55年生時の結果から-」(森林・林業技術交流発表集【秋田営林局】(1998))、八重樫良暉・草葉敏郎「冠雪による産地別スギ造林木の被害」(林木の育種 77(1973))
(総体としての森林の生物多様性)
このように、我が国には、様々なタイプの異なる森林が分布しており(生態系レベルの多様性)、個々の森林をみても、その発達段階等に応じた生物種が生育・生息し(種レベルの多様性)、同じ種の中でも多様な遺伝的特性が保持されている(遺伝子レベルの多様性)ことで、総体として豊かな生物多様性が形成されている。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219