第1部 特集 第2節 我が国の森林における生物多様性とこれまでの保全の取組(2)
(2)我が国の森林における生物多様性保全の取組の経過
(森林の荒廃と伐採等の規制)
我が国の森林は、江戸時代には、過剰な利用により荒廃し、災害の発生が深刻となったことから、幕府や各藩によって森林の伐採を禁ずる「留山(とめやま)」など森林を保護するための規制が講じられた。また、公益的機能の回復や資源の造成を目的として、スギやヒノキ等の造林も行われた。
明治時代に入ると、近代産業の発展に伴って建築資材や産業用燃料等の様々な用途に木材が使われるようになり、国内各地で森林伐採が盛んに行われたため、森林の荒廃は再び深刻化し、災害が頻発した。このような中、明治30(1897)年に森林法が制定され、保安林制度の創設等によって森林の伐採を本格的に規制する措置等が講じられた。
昭和10年代には戦争の拡大に伴い、軍需物資等として大量の木材が必要となり、森林の伐採が進んだことから、我が国の森林は大きく荒廃した。戦後も復興や経済成⾧のための旺盛な木材需要を背景に、天然林の伐採が進むとともに、薪炭利用から化石燃料利用へと転換する燃料革命とあいまって、その跡地では針葉樹の人工林を造成する拡大造林が進んだ。このような中、昭和26(1951)年には森林法が改正され、森林計画制度が創設されるとともに、民有林の適正伐期齢未満の伐採を許可制にするなど伐採規制が強化された。なお、昭和37(1962)年の森林法改正によって伐採許可制は改められ、保安林以外の伐採については、事前届出制となっている。また、昭和40年代後半には、国民の自然環境保全への意識が高まる中、昭和49(1974)年の森林法改正により、一定規模を超える森林の開発を規制する林地開発許可制度が創設された。
(国有林野における保護等の施策)
このような森林における規制等の措置は、国土の保全や森林資源の造成を目的とする側面が強かったが、奥地脊梁(せきりょう)山地等に広く分布する国有林野においては、国民の自然環境保全への意識が高まりをみせる以前の大正4(1915)年に、学術研究等を目的として原生的な森林等を保護する「保護林」制度が設けられ、我が国の自然保護に先駆的な役割を果たしてきた(資料 特-10)。この保護林制度は、⾧期間にわたり、我が国の気候帯を代表する森林生態系や希少な野生生物、遺伝資源の保護等に重要な役割を担っており、大正時代から昭和時代にかけて設定された保護林の多くは、後に創設された自然公園や天然記念物にも指定されている。保護林制度については、平成元(1989)年に、国民からの森林保護の要請の高まりを受けて、新たに「森林生態系保護地域」を設ける(*19)などの制度改正を行ってきた。我が国の世界自然遺産の登録に当たっては、原生的な森林が保護林として厳格に保護・管理され、その価値の完全性が確保されてきたことが評価されており、保護林の一つである「森林生態系保護地域」が、世界自然遺産の保護を措置するための国内制度の一つに位置付けられている。さらに、平成12(2000)年には、国有林野において、野生生物の移動経路を確保することにより個体群の交流を促進し、種の保全や遺伝的多様性を確保することを目的として、保護林を中心にネットワークを形成する「緑の回廊」の設定を開始した(資料 特-11)。

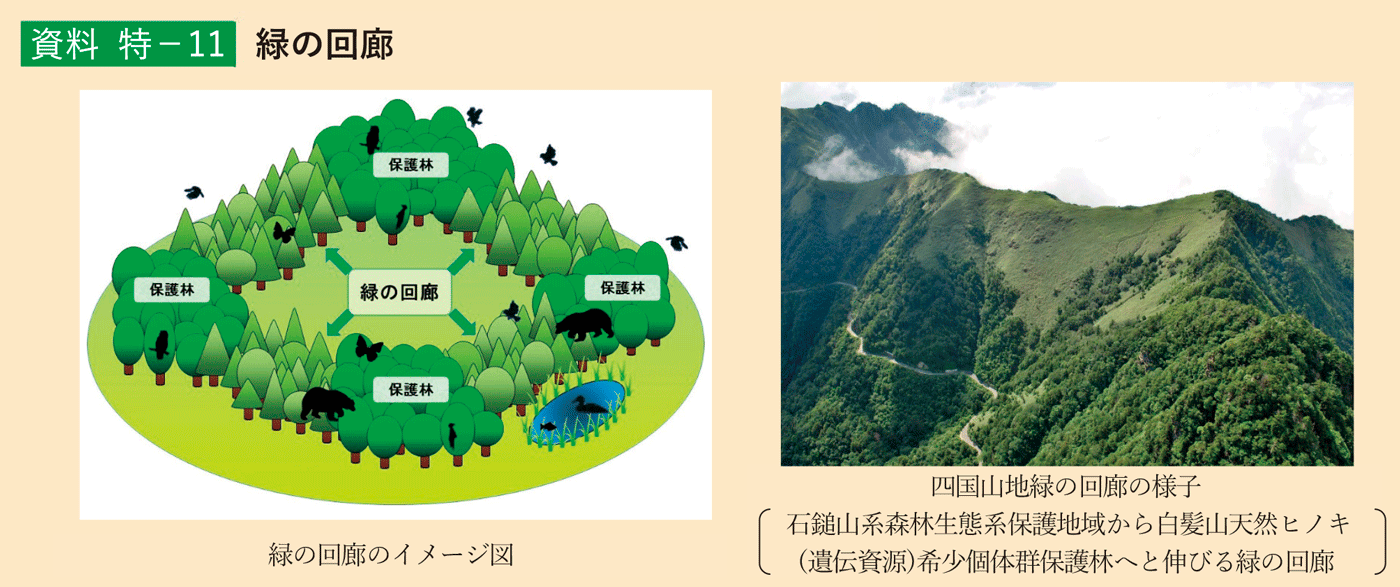
(*19)森林生態系の厳正な保護を図る「保存地区」と保存地区に外部の影響が直接及ばないよう、緩衝の役割を果たす「保全利用地区」に区分する「地帯区分」の考え方を取り入れた。現在の保護林は、森林生態系保護地域のほか、地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理する「生物群集保護林」、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理する「希少個体群保護林」の3つに区分されている。
(保全管理・利用までを含む施策)
平成13(2001)年に施行された森林・林業基本法に基づき新たに策定された森林・林業基本計画においては、従来の木材の生産を主体とした政策から、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るための政策へ転換することを旨とし、貴重な野生動植物の生育・生息の場として重要な森林の保護のみならず、居住地周辺の里山林等の森林の保全及び整備に対する要請が一層高まっていること、全ての森林は、多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与していることなどが明記された。
平成21(2009)年には、愛知県名古屋市における生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の開催を前に、林野庁において「森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用の推進方策」を取りまとめた。同方策では、生物多様性を保全するには、単に原生的な自然環境を保護することだけではなく、一定の面的広がりにおいて、その土地固有の自然条件、立地条件下に適した様々な植生タイプが存在し、地域の生物相の維持に必要な様々な遷移段階の森林が、種及び遺伝子の保管庫としてバランスよく配置されることが重要であるとした。その上で、森林生態系のモニタリング等を活用しながら森林の変化等を的確に把握して、課題や重点的に取り組むべき施策を明らかにし、森林計画に反映させていくという、森林計画策定プロセスのより一層の透明化を図っていくことが重要であるなどとした。こうした考え方については、その後に策定された全国森林計画等に反映されている。
現在、我が国においては、戦後造成された人工林の森林面積に占める割合が約4割となっており、原生的な天然林について引き続き厳格な保護・管理を行うとともに、人手を加えることによって継続的に利用しながら管理していく人工林等において、森林資源の循環利用を図ることが重要となっている。
このように、行為規制から始まった我が国の森林の保護に関する施策は、生物多様性の概念も取り込みながら、単純な保護にとどまらず、保全管理・利用までを含む施策へと深化しているといえる。
コラム 生物多様性の4つの危機
我が国の生物多様性は、全体としては⾧期的に損失の傾向が継続しているとされており、「生物多様性国家戦略2023-2030」においては、生物多様性の直接的な損失要因について、4つの危機に整理している。
第1の危機は、開発を含む土地利用の変化や、乱獲といった生物の直接採取など、人が引き起こす生物多様性への負の影響である(オーバーユース)。森林については、かつての拡大造林に伴い、天然林の減少・劣化といった質的変化を経験したものの、森林法に基づく保安林への指定や林地開発許可制度の運用等により森林の保全等を図っており、森林面積も維持されている。
第2の危機は、第1の危機とは逆に、自然に対する働き掛けが縮小・撤退することによる生物多様性への負の影響である(アンダーユース)。里山の薪炭林や農用林、採草地等の二次草原は、かつては燃料や農業用資材の供給源であり、人の生活に不可欠なものとして維持され、同時に明るい環境に依存する種等の生育・生息環境となっていたが、近年では、人の働き掛けが縮小することにより、特有の多様性の消失が懸念されている。
第3の危機は、外来種の侵入や化学物質による汚染など、人が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれたものによる生物多様性への負の影響である。外来種は、本来の移動能力を超えて国外や国内の他地域から導入された生物を指し、地域固有の生物相や生態系にとって大きな脅威となり得る。例えば、全国的に甚大な影響を与えた外来種の一つに、北米から持ち込まれたマツノザイセンチュウがある。これを在来種のマツノマダラカミキリが媒介することで松くい虫被害が全国に急速に広がった。北米に自然分布するマツ属と異なり、我が国のアカマツやクロマツは外来種であるマツノザイセンチュウに対する抵抗性が弱かったことが要因である。
第4の危機は、地球温暖化や降水量の変化等の気候変動を始めとする地球環境の変化による生物多様性への負の影響である。地球温暖化による影響については、我が国においても既に、温暖な気候に生育するタケ類(モウソウチク、マダケ)の分布の北上等が確認されている。地球環境の変化は、生物の絶滅リスクを高め、森林の植生や動物相にも影響を与える。また、気候変動に伴う自然災害や森林病虫害の発生リスクの増大は、森林生態系の損失の要因にもなり得る。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219




