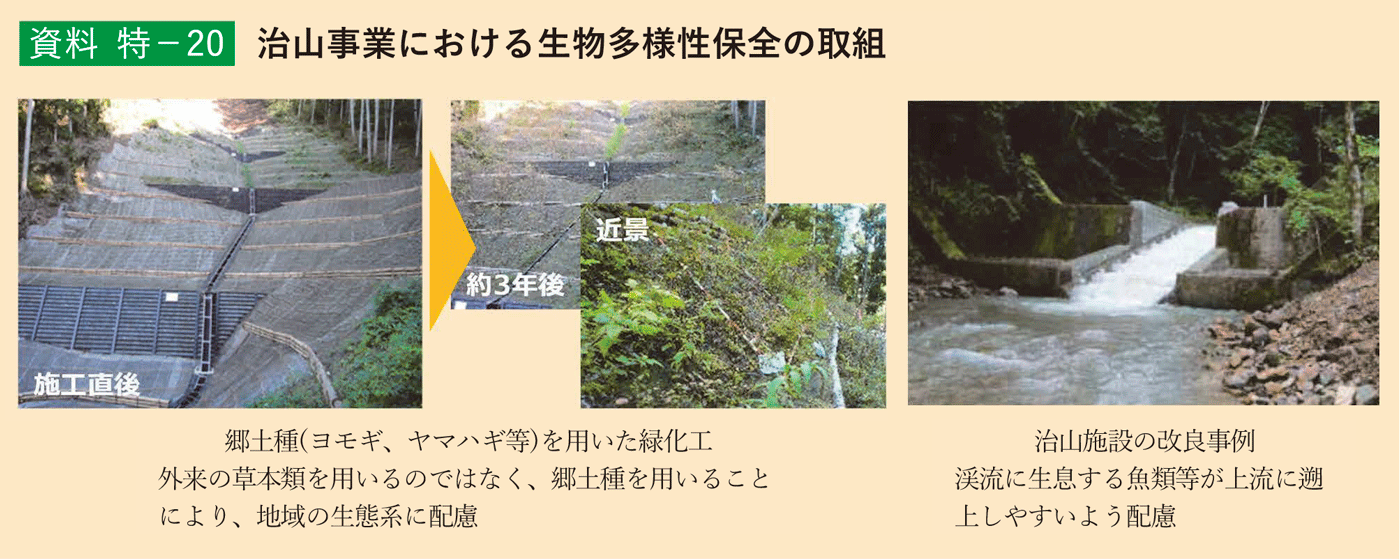第1部 特集 第2節 我が国の森林における生物多様性とこれまでの保全の取組(3)
(3)生物多様性保全に関する具体的な施策
(ア)流域レベルの視点での生物多様性
(面的な広がりにおける生物多様性保全)
全ての森林は多種多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与していることも踏まえ、令和3(2021)年6月に閣議決定された森林・林業基本計画においては、一定の広がりにおいて、様々な生育段階や樹種から構成される森林が、モザイク状に配置されている状態を目指して、針広混交林化や広葉樹林化(*20)、⾧伐期化(*21)等を含め多様な森林整備を推進することとしている。また、原生的な天然林については、自然の推移に委ねることを基本として、必要に応じて植生の復元を図ることとしている。これらを通じて、面的な広がりにおいて多様な森林がバランスよく配置されることが重要である(資料 特-12)。
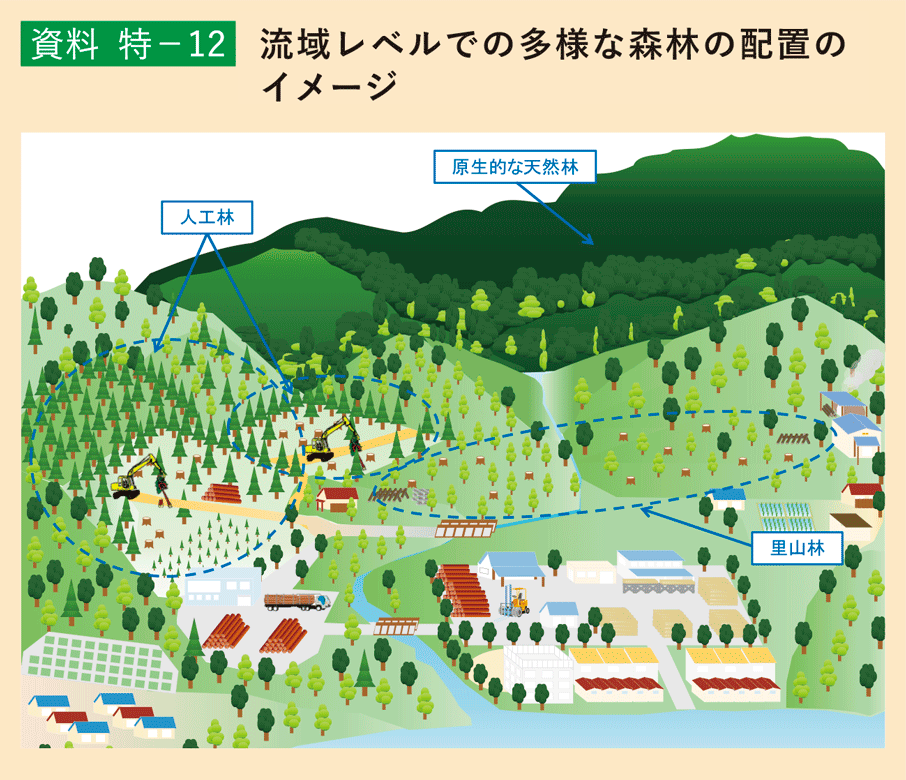
多様な森林への誘導を図るためには、⾧期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いが必要であり、森林法に基づき、全国森林計画、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画、市町村森林整備計画、森林経営計画からなる森林計画制度が運用されている。森林の状況や森林の機能に対する要請は流域ごとに異なることから、森林計画制度においては、一定の地理的まとまりである流域を単位として、国、都道府県、市町村の各段階における施策の方向や、森林整備等の目標、森林所有者が行う森林施業の規範等を定めており、森林所有者等による自発的な森林の施業及び保護を通じて、森林の有する多面的機能の発揮を図っている。
市町村森林整備計画や国有林の地域別の森林計画等においては、水源涵(かん)養や山地災害防止・土壌保全、生物多様性保全など個々の森林において発揮が期待される機能に応じた区分を行う「ゾーニング」を定めており、それぞれの機能の維持増進を図るための施業方法として、伐期の延⾧や伐区の縮小等の施業方法を記載している。
このような制度的な枠組みと併せて、平成11(1999)年度から25年間にわたり継続的に実施している全国レベルの森林調査である森林生態系多様性基礎調査により、森林の状態と変化を継続的にモニタリングしながら、森林法に基づく「鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域」の設定といった順応的管理(*22)を推進している。これらの施策を通じて、生態系・種レベルを中心として森林の生物多様性の保全に貢献している。
(*20)針葉樹一斉人工林を帯状、群状等に択伐し、その跡地に広葉樹を天然更新等により生育させることにより、針葉樹と広葉樹が混在する針広混交林や広葉樹林にすること。
(*21)従来の単層林施業が40~50年程度以上で主伐(皆伐等)することを目的としていることが多いのに対し、これのおおむね2倍に相当する林齢以上まで森林を育成し主伐を行うこと。
(*22)自然を扱う政策・技術の実現性や未来予測の不確実性を認め、モニタリングによる評価と検証を繰り返し、政策を順次見直し、計画や技術に改良を加えながら管理すること。
(森林生態系ネットワークの保護・管理)
国土の約3分の2を占める森林は、生態系ネットワークの根幹として重要な役割を果たしており、農地、河川、海等の他の生態系とも結び付くほか、渓流など水辺と一体となって良好な環境を形成していることも多く、このような生態系の連続性を確保し、森林生態系ネットワークを保護・管理していくことも重要である。
このため、点在する天然林等も含めた森林生態系の保護・管理のほか、渓流等水辺の森林等については、野生生物の移動経路や種子の供給源等として保全を図っている。
コラム 貴重な生態系を形成する渓畔林
渓流沿いに成立している渓畔林は、水域から陸域へ推移する移行帯に成立する植生で構成され、一般的にその構造は複雑であり、地形や水流による攪(かく)乱にさらされながら、特有の生態系を形成している。
渓流は降雨等の影響により増水して渓岸の侵食、土砂の移動や堆積等の攪(かく)乱をもたらすが、その後には樹木の更新しやすい裸地が生ずるなど、森林の新陳代謝を促し、樹木の多様性を高める。渓畔林からの落葉や倒木は渓流沿いに多様な生物の生息環境を提供し、また、森林土壌は渓流に流れる水の栄養塩類を吸着するなど水質を整える機能がある。この結果、適切に保全された渓畔林は生物多様性が高い貴重な生態系を形成する。
(イ)森林施業のまとまりである林分レベルの視点での生物多様性
(原生的な天然林)
奥地脊梁(せきりょう)山地等に分布する原生的な天然林は、⾧期間にわたって人手が加わっておらず、一般に階層構造が発達し、老齢木から幼齢木まで様々な樹齢、大きさの樹木により構成される。また、枯死木や倒木等が存在することも特徴の一つであり、これらの樹木は鳥類等の生物の採餌や営巣の場として重要である。このように複雑な構造を有する原生的な天然林は、希少種を含む多様な野生生物の生育・生息の場となるなど、生物多様性に富んでおり、世界自然遺産に登録されている「知床(しれとこ)」、「白神山地(しらかみさんち) 」、「小笠原諸島(おがさわらしょとう)」、「屋久島(やくしま)」や「奄美大島(あまみおおしま)、徳之島(とくのしま)、沖縄島北部(おきなわじまほくぶ)及び西表島(いりおもてじま)」の主要な構成要素にもなっている。
原生的な天然林や、希少な野生生物が生育・生息する森林は、国有林野に広く分布しており、林野庁では、これらを保護林に設定するなど自然の推移に委ねることを基本として、森林生態系の保存及び復元、点在する希少な森林生態系の保護・管理等を実施している。
また、国有林野に生育・生息する希少な野生生物の保護に向けては、研究機関、地方公共団体等と連携を図りながら、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく保護増殖事業等を実施しており、生育・生息状況の把握、生育・生息環境の維持・改善等を図っている(資料特-13)。
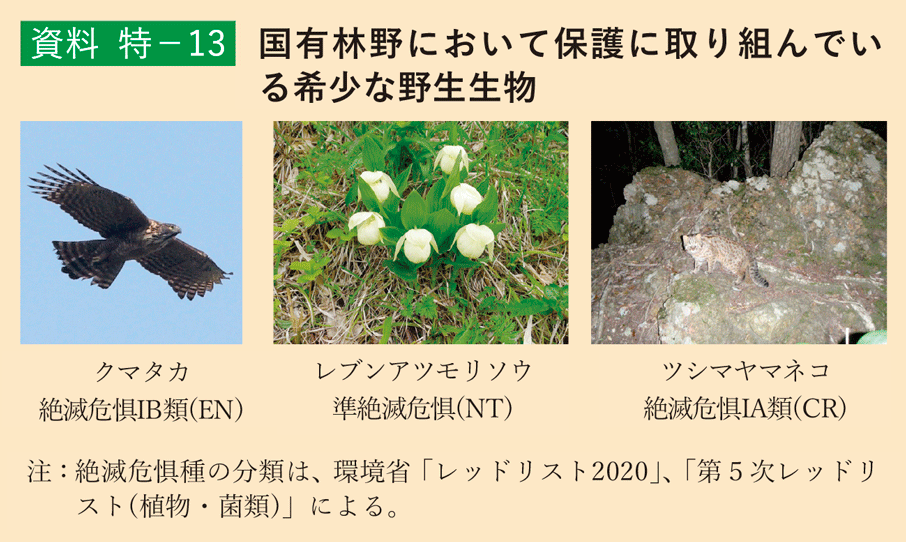
(里山林)
集落の周辺に広がり、薪炭材や落葉等の生活資材・農業用資材を供給してきた里山林は、コナラやクヌギ等の落葉広葉樹林、アカマツ林等からなり、地域住民に継続的に利用されることにより、維持管理されてきた。20~30年程度の間隔での継続的な伐採・更新や落葉の採取等により、明るい環境が維持されることで、カタクリ、スミレ等の背丈の低い植物が生育するなどの特徴があり、これらの植物は昆虫類への蜜供給源としての役割を果たす。このように里山林は、適度に利用されることで特有の生態系が形成されており、これは生物多様性の保全と森林資源の持続可能な利用の調和が図られた一つの形である(資料 特-14)。
一方で、昭和30年代以降、燃料革命や農業における化学肥料の使用など産業構造や生活様式の変化によって薪炭利用等が縮小することに伴い、里山林の遷移が進行し、現在は、林内が明るい環境から暗い環境へと変化している。これは、里山林が利用価値を失って伐採・更新が行われなくなったことにより、大径木化が進むとともに、林内には耐陰性(*23)の高い常緑の樹種やササ類が繁茂することによりもたらされる変化である。このような状態が、明るい環境に依存してきた里山林の生物の生育・生息環境の質の低下や喪失を引き起こすほか、管理放棄された里山林はシカ等の大型野生動物の格好の生息地となっているとされている(*24)。
くわえて、里山林においては、森林病害虫による被害もみられる。特にナラ枯れ被害(*25)については、ナラ菌を媒介するカシノナガキクイムシが繁殖しやすいナラ類等の大径木が増加することにより、被害の拡大に影響を及ぼすとの指摘がある(資料 特-15)。また、管理放棄された竹林の増加や、近隣の里山林への竹の侵入等の問題が生じている地域もみられる。
このような里山林の利用・管理の縮小(アンダーユース)は、生物多様性の第2の危機である自然に対する働き掛けの縮小による危機の代表例であり、生態系による負の影響が顕在化している。
特に、山村地域においては、産業構造や生活様式の変化に加えて、過疎化・高齢化等に伴って、人と里山林との関わりが薄れている。
林野庁では、多様な主体による里山林への働き掛けを促していくため、森林・山村多面的機能発揮対策交付金等により、地域住民、NPO、企業等の連携による森林づくり活動への支援を実施するとともに、里山林の活用方策の検討等を通じて、里山林の多面的・継続的な利用を促進している(資料 特-16)。また、里山の広葉樹林の適切な更新を促すため、抜き伐りや群状伐採など部分的な伐採に対して森林整備事業による支援を実施している。
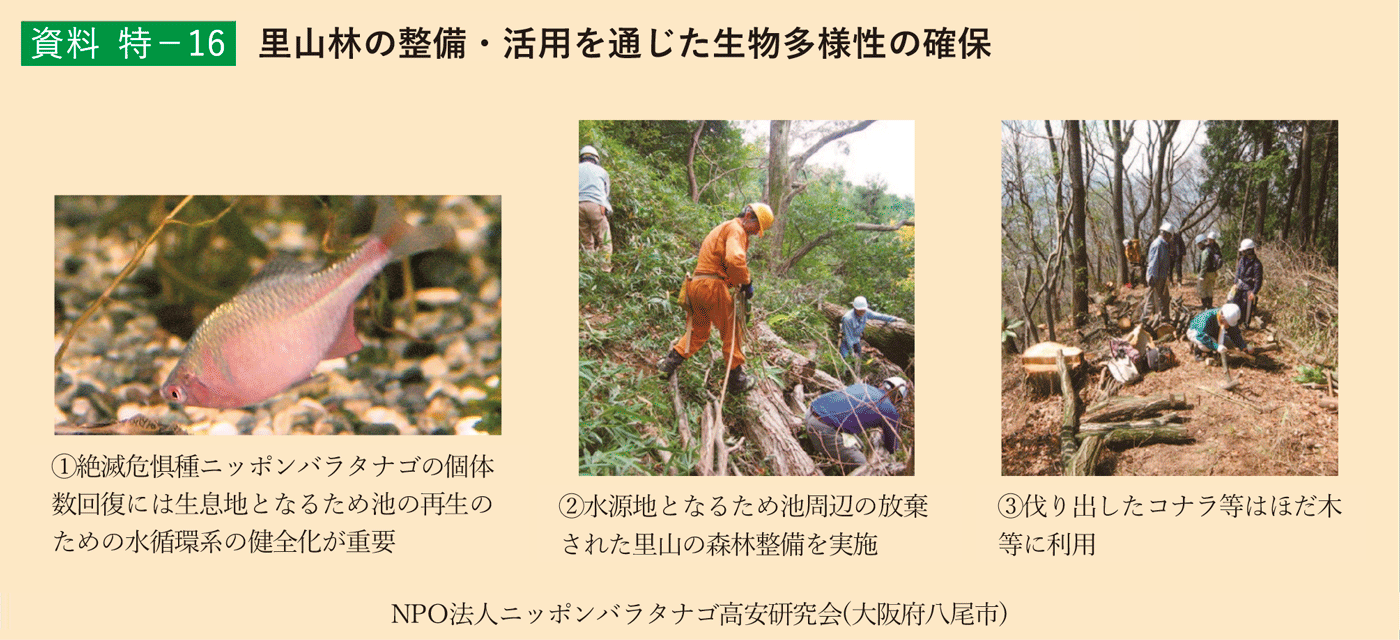
(*23)光の不足に耐えて生存できる性質。
(*24)鈴木牧ほか「人と生態系のダイナミクス2 森林の歴史と未来」(2019)
(*25)ナラ枯れ被害の発生するメカニズム等については、第1章第3節(3)86ページを参照。
コラム 統計からみる里山林の利用・管理の縮小(アンダーユース)
昭和30年代以降、燃料革命により薪炭林としての里山林の利用は縮小し、薪炭材の国内生産量は⾧期的に減少している。昭和30(1955)年の国内生産量は当時の木材需要量の約3割に当たる約2,000万m3であり、里山林の伐採・更新が広く行われていたことが伺えるが、昭和30年代後半頃から薪炭材の国内生産量は急激に減少し、平成25(2013)年には23万m3と約100分の1まで減少している(図表1)。
また、昭和36(1961)年の天然林(里山林を含む)の齢級構成をみると、30年生までの天然林が全体の約半数を占めており、里山林においては、伐採・更新が繰り返されていたことで、若齢級の天然林が維持されていたものと推測される。一方、現在の天然林の齢級構成をみると、大部分が60年生を超えており、薪炭林としての里山林の利用の縮小の結果、高齢級化が進んでいることがみて取れる(図表2)。


(人工林)
木材生産を主たる目的として造成される人工林は、スギ、ヒノキ、カラマツ等の単一の樹種を植栽することで、針葉樹の一斉林(*26)を造成することが多い。一般に人工林は、1)樹種や構造が単純である、2)老齢段階に達する前に伐採されることが多く、老齢林にみられる枯死木や倒木等がみられない、3)主伐、植栽、下刈り、間伐等の人為的な攪(かく)乱がある、といった特徴がある。
人工林も多様な動植物等の生育・生息の場として、森林生態系の重要な構成要素となっている。例えば、成⾧段階に応じた間伐等の適切な森林整備により、光環境が改善され下層植生が発達するほか、伐採・更新により生じた伐採跡地や幼齢林が、国内で大幅に縮小し失われつつある草原性の生物の生育・生息地としての機能やイヌワシ等の猛禽類の狩場としての機能を果たすといった一面もある。群馬県みなかみ町(まち)に広がる国有林野約1万haを対象とした「赤谷プロジェクト」では、関東森林管理局、地域住民で組織する「赤谷プロジェクト地域協議会」及び公益財団法人日本自然保護協会の3者の協働により、スギ人工林に試験地を設定し、小面積の皆伐によるイヌワシの狩場創出の取組を実施するとともに、これにより生産される木材の利用に取り組んできた。この結果、イヌワシが試験地周辺に出現する頻度は試験伐採後に高まり、獲物を探す行動の増加もみられるなどの成果が上がっている(資料 特-17)。
また、⾧短多様な伐期による伐採と植栽等による更新を通じ、生育段階の異なる林分をモザイク状に配置することや、伐採時に侵入広葉樹を残すことなどにより生物多様性の確保に貢献している(*27)。
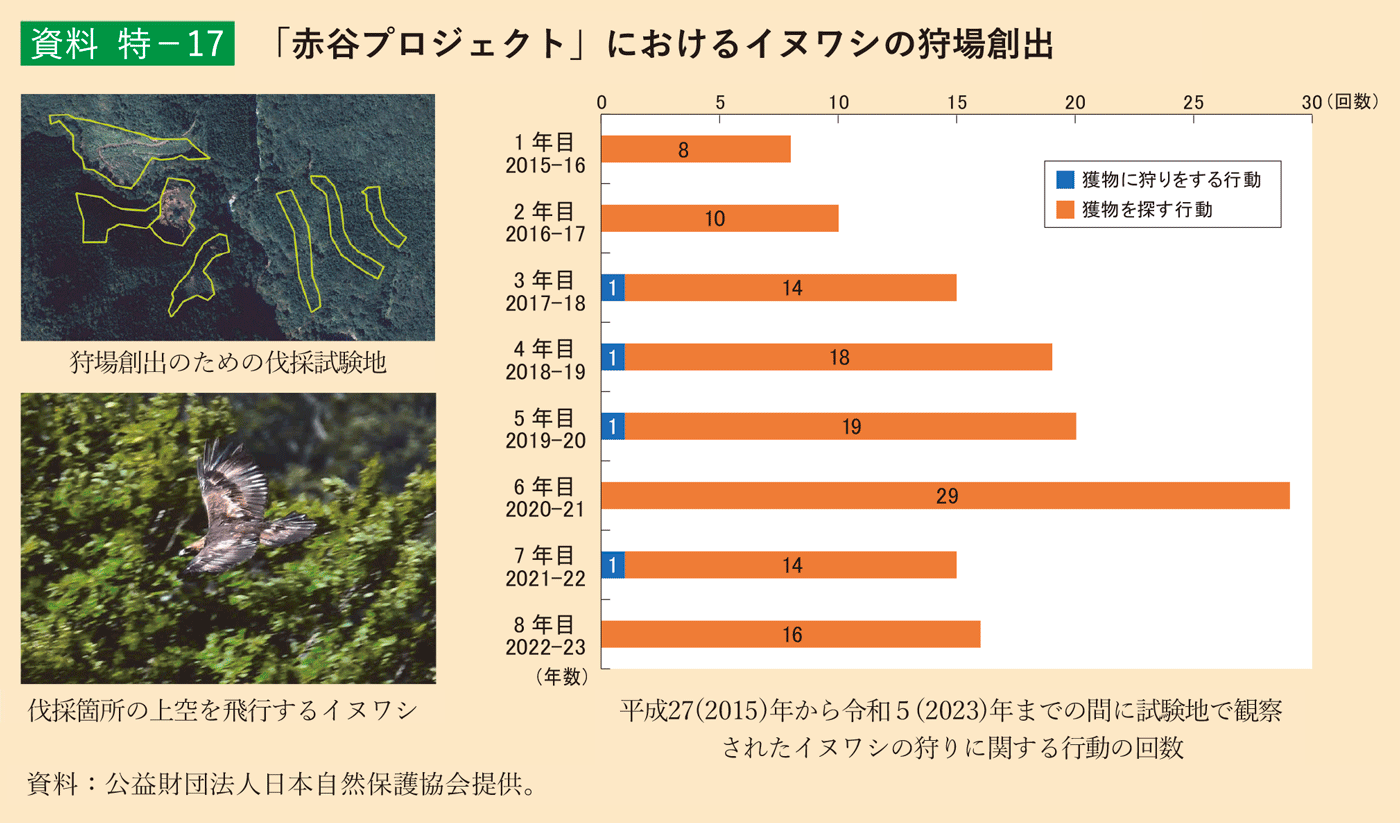
林野庁では、民有林において成⾧段階に応じた適切な森林整備が実施されるよう、地域森林計画や市町村森林整備計画で、地域ごとの森林施業の指針を示すとともに、伐採造林届出制度の運用、森林整備事業等による支援を通じて、森林所有者等による造林、間伐等の森林施業の推進に取り組んでいる。国有林野においても、国有林野の管理経営に関する基本計画等に基づき、適切な間伐の実施、⾧伐期化や複層林化など、多様で健全な森林の整備・保全を推進している。
(*26)同一樹種かつ同一年齢の林木で構成される森林。同齢単純林も同義。
(*27)国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所・地方独立行政法人北海道立総合研究機構プレスリリース「わずかな広葉樹の大きな役割-人工林内の広葉樹の保持は効率的に鳥類を保全する-」(令和5(2023)年2月13日付け)
(ウ)野生鳥獣等による森林被害と生物多様性
野生鳥獣による森林被害は、森林生態系に大きな影響を及ぼす。特にシカは、植栽木を食害するだけでなく、採食や踏付けによる下層植生の衰退や希少な植物の消失を引き起こすなど、生物多様性を始めとする森林の多面的機能への影響が大きい。
シカは古くから狩猟の対象等として、人の生活と深く関わってきたが、昭和50年代後半頃から個体数が増加し、農林業被害や植生への影響が深刻化していった。平成4(1992)年には、環境庁、林野庁等で構成される「野生鳥獣の保護及び管理に関する関係省庁連絡会議」において、森林における被害対策の方向等について検討が行われ、防護柵の設置等の被害防止対策を講ずることが必要とされた。その後、関係省庁の連携により対策が続けられてきているものの、⾧期にわたるシカの生息頭数の増加及び生息域の拡大(*28)により、森林被害は深刻化している(資料 特-18)。
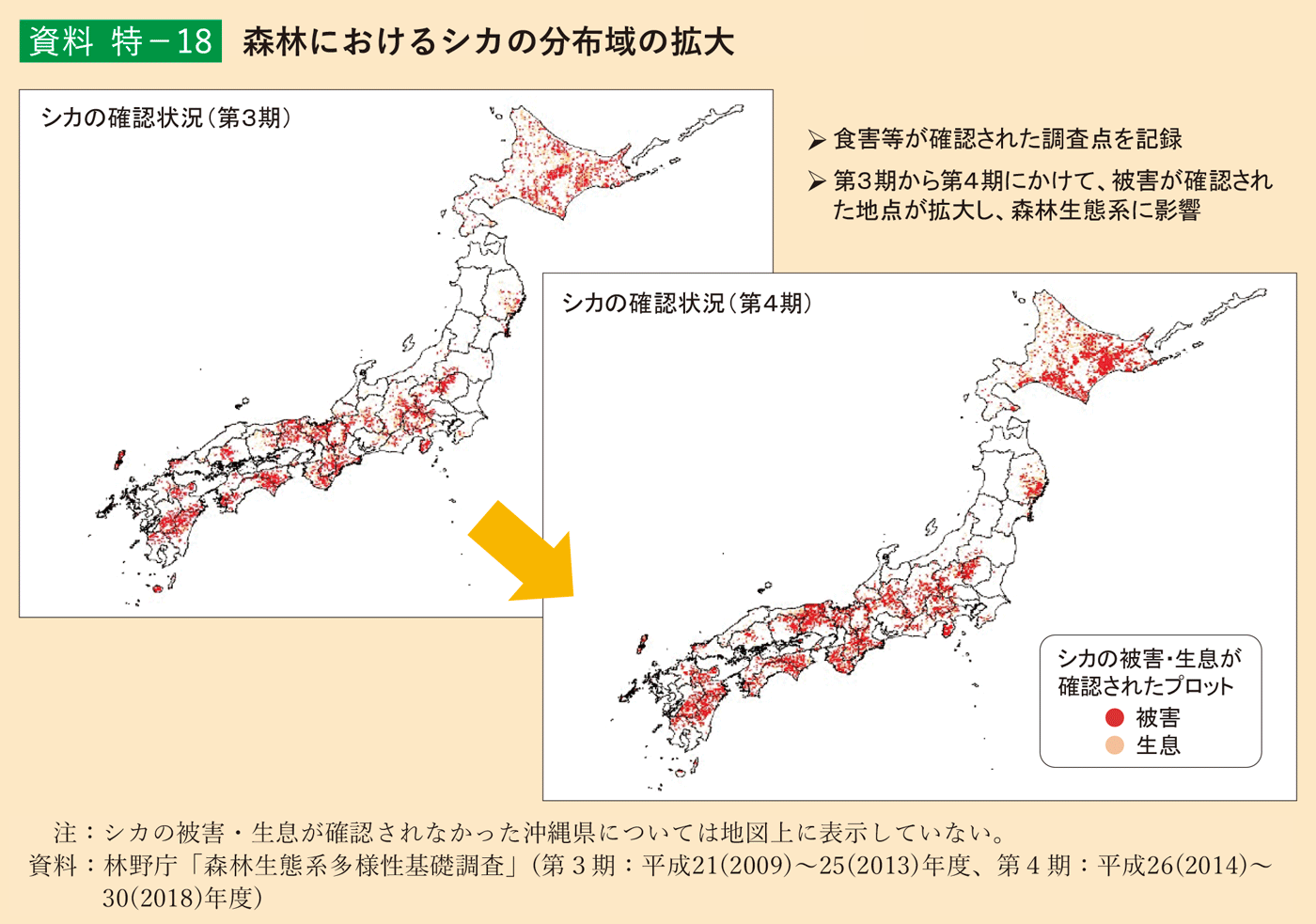
このため、林野庁では、コストや労力を削減する情報通信技術(ICT)の導入等により捕獲を推進するほか、防護柵による植栽木の保護等の被害対策を推進している(*29)。また、国有林野における希少な植物への被害対策として植生保護柵の設置を実施している。
また、松くい虫被害やナラ枯れ被害等の森林病害虫による被害は、適時適切に制御しなければ、これまで被害が確認されていなかった地域にまで拡大し、森林生態系に多大な影響を及ぼすおそれがある。
このため、林野庁では、松くい虫被害対策については、公益的機能が高い保全すべき松林において、薬剤による予防対策や被害木の伐倒くん蒸処理等の駆除対策を支援するとともに、保全すべき松林の周辺では広葉樹等への樹種転換を推進している。ナラ枯れ被害対策については、被害が発生しやすい大径木の伐採・更新や、被害を受けない樹種への転換を図ることが効果的であり、特に守るべき樹木及びその周辺においては、健全木への粘着剤の塗布やビニールシート被覆による侵入予防、被害木のくん蒸による駆除等を推進している(*30)。
(*28)ニホンジカの個体数増加及び分布拡大の要因については、地域によって異なるものの、明治期の乱獲による個体数激減に対応した捕獲規制等により減少に歯止めがかかった後、元々繁殖力が高い動物であることに加え、死亡率が低下したことがある。具体的には、積雪量が減少したこと、造林や草地造成などによりニホンジカの餌となる植生量が増加したこと、中山間地域の過疎化等により耕作放棄地や利用されないまま放置された里地里山が生息に適した環境となったこと、狩猟者が減少し、捕獲圧が減少したことなどが要因として考えられている。
(*29)野生鳥獣被害対策の具体的な取組については、第1章第3節(3)84-85ページを参照。
(*30)松くい虫被害対策、ナラ枯れ被害対策の具体的な取組については、第1章第3節(3)85-86ページを参照。
(エ)気候変動と生物多様性
国際的な議論において、気候変動と生物多様性は特に深い関連があるとされており、気候変動による生物多様性の劣化は生態系サービスの損失につながるリスクがある。両者は互いに影響し合っていることから、一体的に取り組むことが重要であるが、それぞれの対策間においてはトレードオフや相乗効果があるとされている。
2021年に、「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)」と「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の専門家が共同で発表した「生物多様性と気候変動 IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書」においては、気候変動対策として行う歴史的に森林でなかった生態系への植林、特に外来樹種を用いた単一樹種の再植林は、生物多様性に悪影響を及ぼすなどトレードオフの関係にある一方で、持続的な林業の実践は、生物多様性と気候変動に対して有益な対策であると指摘されており、相乗効果がある。
我が国においては、固有種であるスギ、ヒノキ等を中心に人工林を造成してきており、持続的な林業に向けた主伐後の再造林や間伐等の適切な森林整備により、中⾧期的な森林吸収量確保や生物多様性保全に貢献している。
(オ)防災・減災対策と生物多様性
「生物多様性国家戦略2023-2030」では、「自然を活用した社会課題の解決」(NbS)における推進施策として、生態系を基盤として災害リスクを低減する「Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災)」や、自然環境が有する機能を課題解決に活用する「グリーンインフラ」の考え方が位置付けられている。
これらの考え方に符合して、我が国では、森林の維持・造成を通じて山地災害から国民の生命・財産を守ることに寄与する治山事業を実施することで、森林の持つ山地災害防止機能・土壌保全機能の維持・向上に取り組んできた(資料 特-19)。
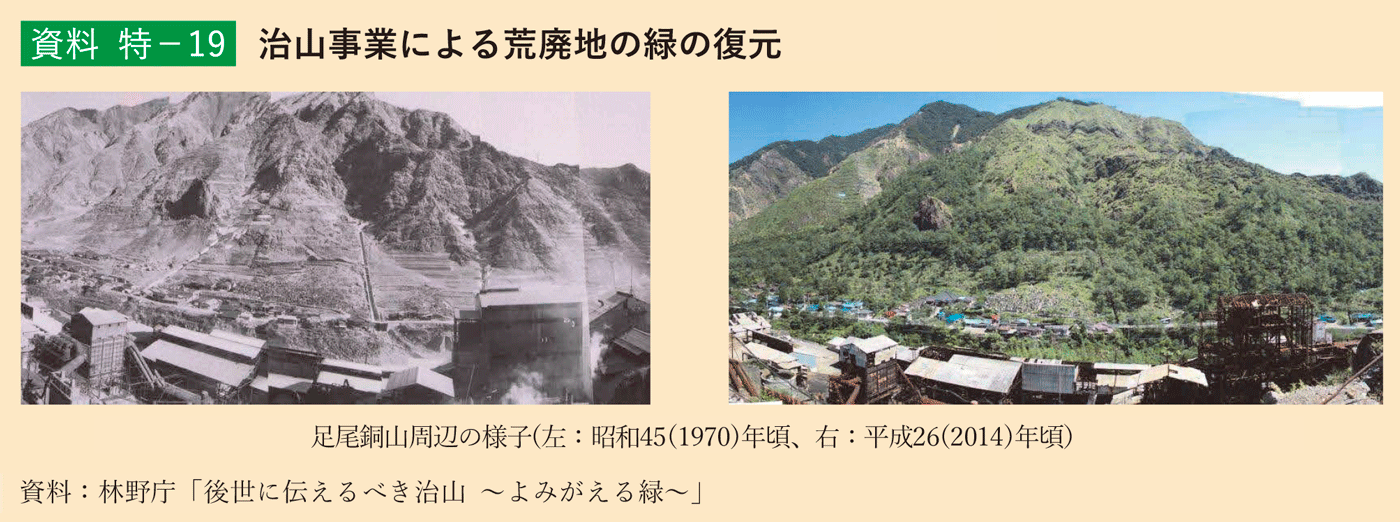
治山事業の工法には、構造物の設置と植栽等により山の斜面を安定させ、森林の復旧・再生を図る山腹工、治山ダム等の設置により渓岸・渓床の侵食を防止し両岸の山脚を安定化させ(山脚固定)、森林の生育基盤の確保を図るほか、渓流の勾配が緩和されることから、土石流等の流下速度を低減させ、下流への土砂流出の防止・軽減が図られる渓間工がある。その実施に当たっては、生態系に対する影響が生じ得ることも考慮し、現地の実情に応じて、郷土種による緑化や治山施設の改良等により、生物多様性保全の取組を行っている(資料 特-20)。
このように、森林は防災・減災を含めて国民生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」であり、適切に整備・保全していくことが、森林の生態系を維持し、災害リスクを低減していくことにつながる。
コラム 豊かな森と海をよみがえらせた、えりも岬の海岸防災林造成
北海道えりも町(ちょう)のえりも岬は、かつて落葉広葉樹の天然林に覆われていたが、明治時代から開拓が行われ、薪炭材の採取等のため森林の伐採が行われ荒廃が進んだ。昭和初期には「えりも砂漠」とも呼ばれるような状況であり、飛砂により住民の生活環境は悪化し、沿岸の土砂流出も発生したことで、赤土による海の汚濁も生じていた。
このような中、地域住民からの要望を受け、昭和28(1953)年から開始された海岸防災林造成事業では、海岸に打ち上げられた海藻により種子を覆う「えりも式緑化工法」等により草本緑化が進められ、つづいて、完了した箇所から、最も生育の良かったクロマツを主体に木本緑化が実施された。多種多様な森林へ誘導するため、クロマツを主としつつ、郷土種であるカシワ、ミズナラ等の広葉樹植栽も行われ、延⾧約10km、面積約195haに及ぶ海岸防災林が造成されるに至った。
この結果、森林生態系の持つ防災機能により飛砂発生が防止されるなど被害が低減されるとともに、魚介類の成⾧に必要な養分が供給され、沿岸海域の生態系は大きく改善し、水産資源も回復した。

お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219