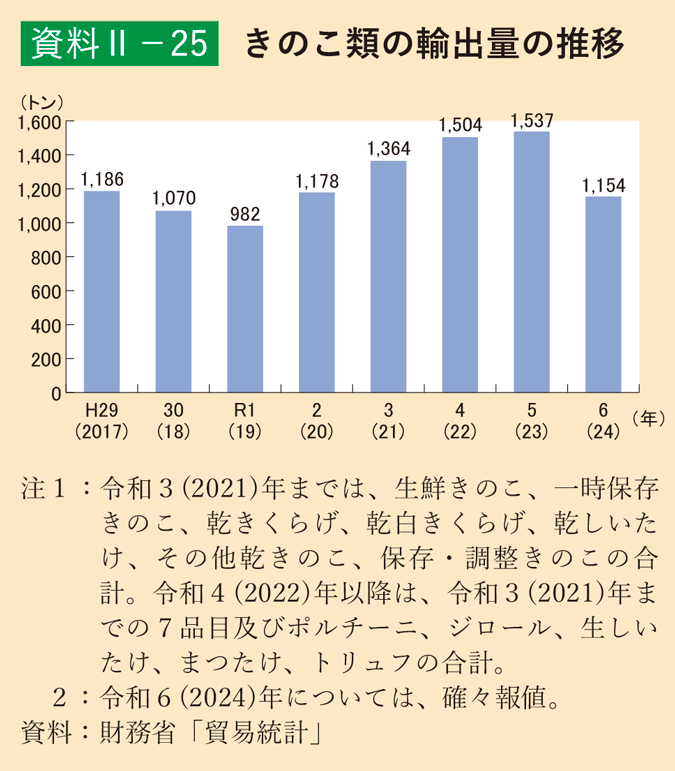第1部 第2章 第2節 特用林産物の動向(1)
(1)きのこ類等の動向
(特用林産物の産出額)
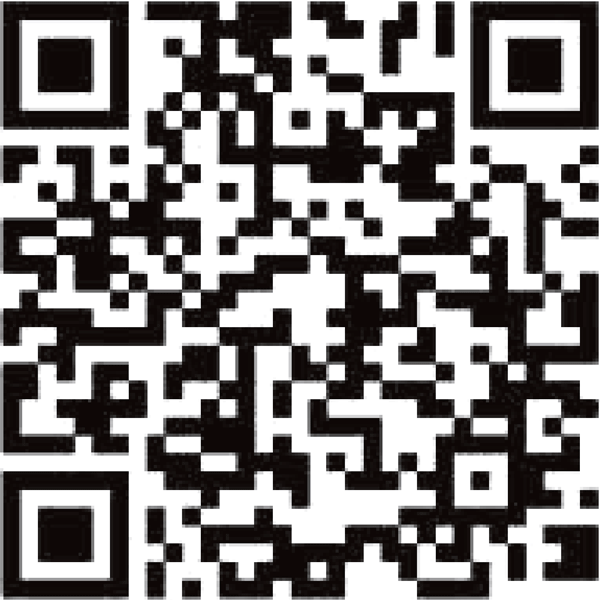
「特用林産物」とは、一般に用いられる木材を除いた森林原野を起源とする生産物の総称であり、食用きのこ類、樹実類や山菜類、漆や木ろうなどの工芸品の原材料、竹材、桐材、木炭、森林由来の精油や薬草・薬樹など多彩な品目で構成されている。その産出額は林業産出額の約4割を占めるなど、地域経済の活性化や山村地域における所得の向上などに大きな役割を果たしている。
令和5(2023)年の特用林産物の産出額は2,306億円で、このうち「栽培きのこ類生産」が全体の9割以上を占める2,199億円、樹実類、山菜類、漆等の「林野副産物採取」が35億円、薪、木炭等の「薪炭生産」が72億円となっている(*54)。
(*54)農林水産省「林業産出額」。「令和5年度森林及び林業の動向」までは東京都中央卸売市場等の卸売価格等をベースにした農林水産省「特用林産基礎資料」に基づき生産額を算出。
(きのこ類の産出額等)
栽培きのこ類生産の産出額の内訳をみると、生しいたけが562億円で最も多く、次いでぶなしめじが534億円、まいたけが347億円の順となっている。
きのこ類の生産量について、令和5(2023)年は、天候不順や需要減を見込んだ生産調整、生産者の減少等で乾しいたけが前年比10.7%減、えのきたけが前年比6.9%減となったことなどにより、全体として5.1%減の43.6万トンとなった(資料2-24)。食料・農業・農村基本計画(令和7(2025)年4月閣議決定)では、令和12(2030)年度の生産量を47万トンと設定している。
令和5(2023)年のきのこ類の生産者戸数は前年比8.0%減の約2.1万戸となっている。そのうち約1.1万戸を占める原木しいたけ生産者については、高齢化の進行により減少傾向にあり、10年間で半減している。
(きのこ類の安定供給に向けた取組)
きのこ類は、健康増進効果(*55)が広く認められていることなどから、日常の食卓に欠かせない食材であり、国内需要の89%が国内で生産されている。林野庁では、きのこ類の安定供給に向けて、効率的な生産を図るための施設整備等に対して支援しているほか、消費拡大や生産効率化などに先進的に取り組む生産者のモデル的な取組を支援している。また、近年、燃油・電気代に加え、きのこ生産に用いる原木やおが粉の価格高騰等により生産資材の安定的・効率的な調達が困難な状況となっており、経営に影響が生じたことから、林野庁では、省エネ化やコスト低減に向けた施設整備、次期生産に必要な生産資材の導入費の一部に対して支援している。くわえて、令和6(2024)年度については、きのこ生産者の経営安定化に向け、おが粉製造業者等とのおが粉の需給マッチングの推進や、栽培後に発生する廃菌床のより有効な活用に向けた取組も支援している。
(*55)低カロリーで食物繊維が多い、カルシウム等の代謝調節に役立つビタミンDが含まれているなど。
(きのこ類の消費拡大に向けた取組)
令和5(2023)年におけるきのこ類の一人当たりの年間消費量は前年比5.6%減の3.2kgとなった(*56)。きのこ類生産者団体や関係団体はきのこ類の消費拡大に向け、おいしさや機能を消費者に伝えるPR活動を展開している。また、一般社団法人日本きのこマイスター協会では、きのこマイスター認定講座を開設し、きのこの知識、機能、調理方法等について普及を図ることのできる人材を育成している。
さらに、消費者が国産原木又は菌床由来のしいたけと輸入菌床由来のものとを区別できるようにするため、消費者庁は、令和4(2022)年に原産地表示のルールを見直しており、これに基づき原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示することとしている。
そのほか、生産者等において菌床やほだ木(*57)に国産材が使用されていることを表示するマーク等の取組も進められている。
(*56)農林水産省「令和5年度食料需給表(概算)」
(*57)原木にきのこの種菌を植え込んだもの。
(きのこ類の輸出拡大に向けた取組)
きのこ類の輸出量については、海外における和食の普及や健康的な食生活への関心の高まりに伴い、令和元(2019)年以降、香港等の近隣国・地域向け、北米向け等が増加していた。一方で令和6(2024)年については、鮮度保持の課題等から生鮮きのこ類の輸出量が減少し、前年比24.9%減の1,154トンとなった(資料2-25)。また、これに伴い、令和6(2024)年のきのこ類の輸出額についても、前年比7.3%減の10億円となっている(*58)。
林野庁では、きのこ類の輸出を促進するため、輸出に取り組む民間事業者に対して、輸出先国・地域の市場調査や情報発信などの販売促進活動を支援している。令和6(2024)年は、台湾、ベトナム等において、乾しいたけの流通調査を行うとともに、展示即売会・試食会を開催し、その品質の良さや魅力のPRを行った。また、生鮮きのこ類については、アジア以外の北米等への輸出に対応するため、鮮度保持に係る調査を行い、温度管理体制(コールドチェーン)の確認及び改善に取り組んでいる。
きのこ類は栄養繁殖が可能であり増殖が容易であることから、生鮮きのこ類の輸出に当たっては、輸出先で無断培養されることにより、潜在的な輸出機会の喪失や、国内に逆輸入されることによる国内産地への影響が懸念される。このため、農林水産省では、主要なきのこ類のDNAデータベースの構築を支援するなど、育成者権の保護に関する体制の整備に取り組んでいる。
なお、令和6(2024)年のきのこ類の輸入額は、前年比7.8%増の156億円(10,176トン)となっており、その多くは中国産の乾しいたけと乾きくらげが占めている(*59)。
(*58)財務省「貿易統計」。令和3(2021)年から、乾きくらげ類、調整きのこ、保存処理をしたきのこ及びしいたけ以外の乾燥きのこを集計項目に追加した。
(*59)財務省「貿易統計」。令和6(2024)年については、確々報値。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219