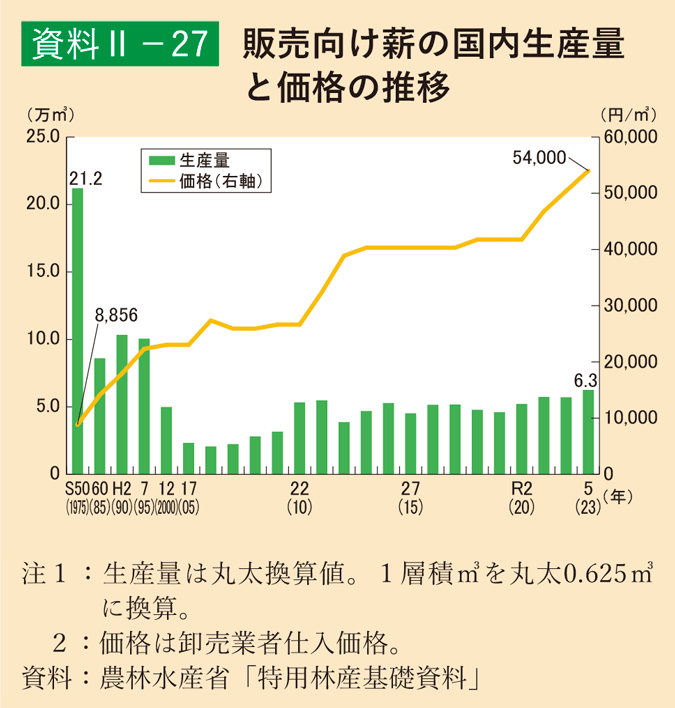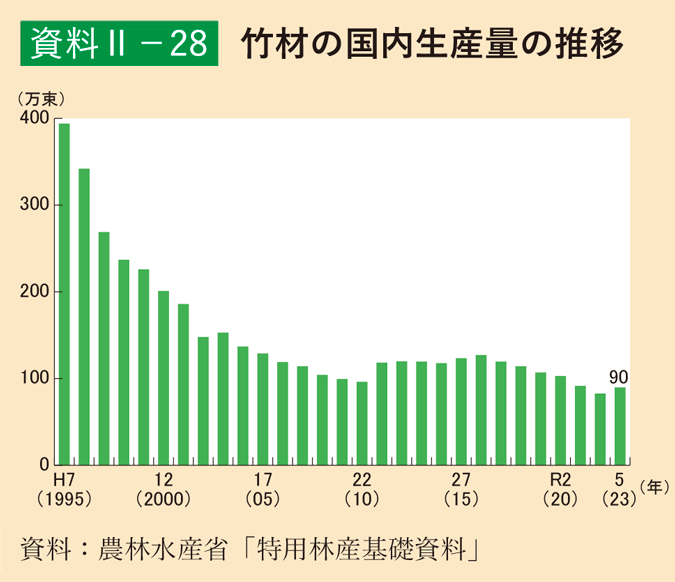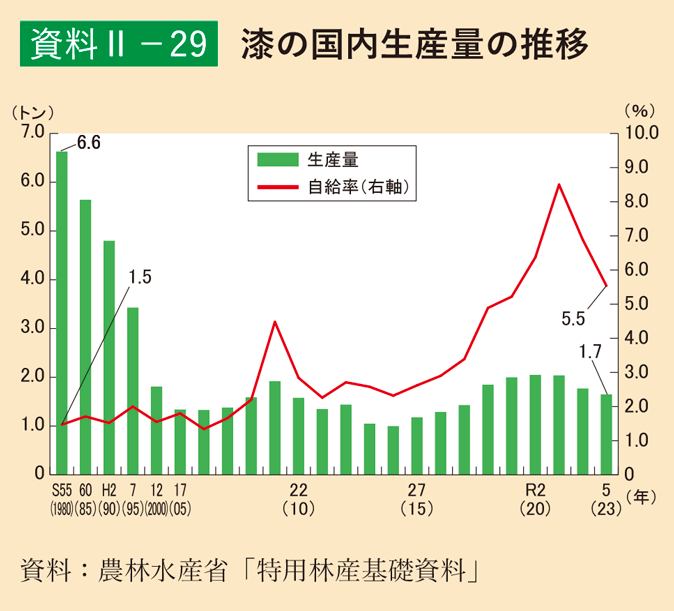第1部 第2章 第2節 特用林産物の動向(2)
(2)薪炭・竹材・漆の動向
(薪炭の動向)
木炭は、家庭用の燃料としては使用する機会が少なくなっているが、飲食店、茶道等では根強い需要があるほか、電力なしで使用できるなどの利点から災害時の燃料としても活用されている。木炭(黒炭、白炭、粉炭、竹炭及びオガ炭)の国内生産量は、⾧期的に減少傾向にあるが、飲食店需要の回復等により、令和5(2023)年は前年比19.9%増の2.0万トンとなった(資料2-26)。
多孔質(*60)である木炭は、燃料としての利用以外にも浄水施設のろ過材や消臭剤としての利用のほか、近年では、土壌改良材として農地に施用する「バイオ炭(*61)」が注目されている。バイオ炭の農地施用は、難分解性の炭素を土壌に貯留する効果があり、気候変動緩和効果も期待できることから、J-クレジット制度(*62)において、温室効果ガスの排出削減活動としてクレジット化が可能となっている。また、国産木炭は、和食文化の拡がりに加え、その品質の高さによる海外の需要も期待されることから、海外市場への参入を目指す動きもみられる。
これらの取組が木炭の需要の拡大につながり、伝統的な製炭技術の継承や大径化が進む薪炭林の若返りにもつながることが期待される。
販売向け薪の生産量についても、石油やガスへの燃料転換等により減少傾向が続いていたが、平成19(2007)年以降は、ピザ窯やパン窯用などとしての利用、薪ストーブの販売台数の増加(*63)等を背景に増加傾向で推移している。令和5(2023)年の生産量は、アウトドア需要が継続したことなどから、前年比9.5%増の6.3万m3となっている(資料2-27)。
(*60)木炭は表面に無数の微細な孔を持つ。孔のサイズ分布や化学構造によって、水分子やにおい物質などの吸着機能や、孔内に棲息する微生物による分解機能を有し、湿度調整や消臭、水の浄化などの効果を発揮する。これらの効果は、木炭の原材料や炭化温度により異なる。
(*61)燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物。
(*62)J-クレジット制度については、第1章第2節(6)72-74ページを参照。
(*63)一般社団法人日本暖炉ストーブ協会ホームページ「公表販売台数」
(竹材の動向)
竹材は従来、身近な資源として、日用雑貨、建築・造園用資材、工芸品等様々な用途に利用されてきた。このような利用を通じて整備された竹林は、里山の景観を形作ってきたのみならず、食材としてのたけのこを供給する役割を果たしてきた。しかし、プラスチック等の代替材の普及や住宅様式の変化、安価な輸入たけのこの増加等により、国内における竹材やたけのこの生産は減退してきた。このため、管理が行き届かない竹林の増加や、周辺森林への竹の侵入などの問題も生じている。
竹材の生産量は、製紙原料としての利用の本格化等を背景に、平成22(2010)年から増加に転じた。平成29(2017)年以降再び減少傾向にあったが、令和5(2023)年は前年比8.5%増の90万束(*64)となった(資料2-28)。
近年では、竹資源の有効利用に向けた取組として、家畜飼料や土壌改良材などの農業用資材、竹材の抽出成分を原料にした洗剤等の日用品、舗装材等の土木資材等への活用が進められている。また、たけのことしての収穫適期を過ぎて成⾧した若い竹をメンマに加工・販売することで竹林整備につなげる取組も全国各地で行われている。さらに、竹資源の需要と供給のミスマッチ等の解決に向けた産学官連携の取組も行われている(事例2-4)。
事例2-4 山口県における竹林整備や竹資源の有効活用を促進する取組
山口県は、竹林面積が全国4位の約1万2,000haであるが、放置竹林の増加により、人工林への竹の侵入や山地災害の発生が懸念されている。このような中、令和5(2023)年に立ち上げた竹利活用プラットフォーム「YAMAGUCHI Bamboo Mission」(以下「YBM」という。)を通じて、竹の伐採・供給関係者、加工・製品製造・販売事業者等が連携しながら、竹資源の有効活用を促進し、同県の里山の再生、森林環境の保全及び産業の振興に向けた取組を進めている。
YBM設立1年目は、竹搬出・搬送勉強会や竹利活用のための竹林整備講習会の開催、竹材の無償提供が可能な竹林の伐採地情報の公開、会員同士の交流会の実施、YBMや会員企業の商品紹介等に取り組んだ。
令和6(2024)年8月に開催されたYBM設立1周年を記念したイベントでは、竹を活用した多様な新製品等を展示し、ビジネス機会の拡大に向けた商談等を行う展示・交流会を実施するとともに、効率的な竹林整備に向けた伐採竹の運搬方法の実演等を行い、山口県の竹の認知度向上や新規参入者の拡大に取り組んだ。
YBM立ち上げ当初、山口県、宇部(うべ)市、美祢(みね)市、地方独立行政法人山口県産業技術センターと企業5社の計9者だった会員数は、県外の企業も含め50者(令和7(2025)年3月時点)まで増加しており、産学官が連携した竹の利活用の取組が一層進んでいる。
(*64)2.7万トン(1束当たり30㎏として換算)。
(漆の動向)
漆は、樹木であるウルシから採取された樹液と樹脂の混合物を精製した塗料で、食器、工芸品、建造物等の塗装や接着に用いられてきた。化学塗料の発達や生活様式の変化などを背景に、漆の消費量は⾧期的に減少しており、令和5(2023)年の国内消費量は29.8トンと、昭和55(1980)年と比較し6.6%となっている(*65)。令和5(2023)年の国内生産量は消費量の5.5%に相当する1.7トンとなっており、高温多雨により漆掻(か)きが進まなかったことなどから前年比6.5%減となった(資料2-29)。
平成26(2014)年度に文化庁が国宝・重要文化財建造物の保存修理に原則として国産漆を使用する方針としたことを背景に、各産地では漆の生産振興に力を入れるとともに、生産者からの生漆の買取価格の引上げを図ったことから、国産漆の生産量は平成27(2015)年以降増加に転じた。しかし、国産漆の生産量は、国宝・重要文化財建造物の理想的な修理周期での保存修理における漆の年平均使用量である約2.2トン(*66)に満たない上、工芸品等向けの国産漆の需要もあることから、国産漆の生産量を増やしていくことが重要となっている。このような中、近年は岩手県等の主要産地を中心にウルシ林の造成・整備等が進められている(*67)。
(*65)農林水産省「特用林産基礎資料」
(*66)文化庁プレスリリース「文化財保存修理用資材の⾧期需要予測調査の結果について」(平成29(2017)年4月28日付け)
(*67)例えば、「令和3年度森林及び林業の動向」第2章第2節(2)の事例2-4(120ページ)を参照。

お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219