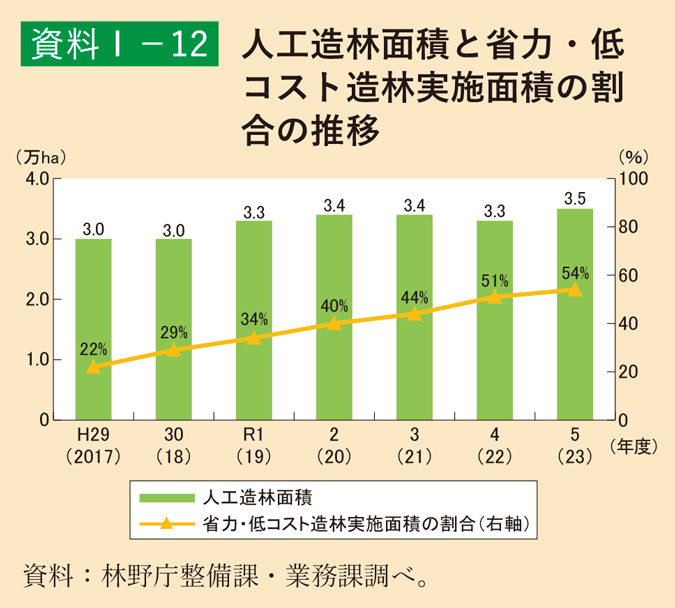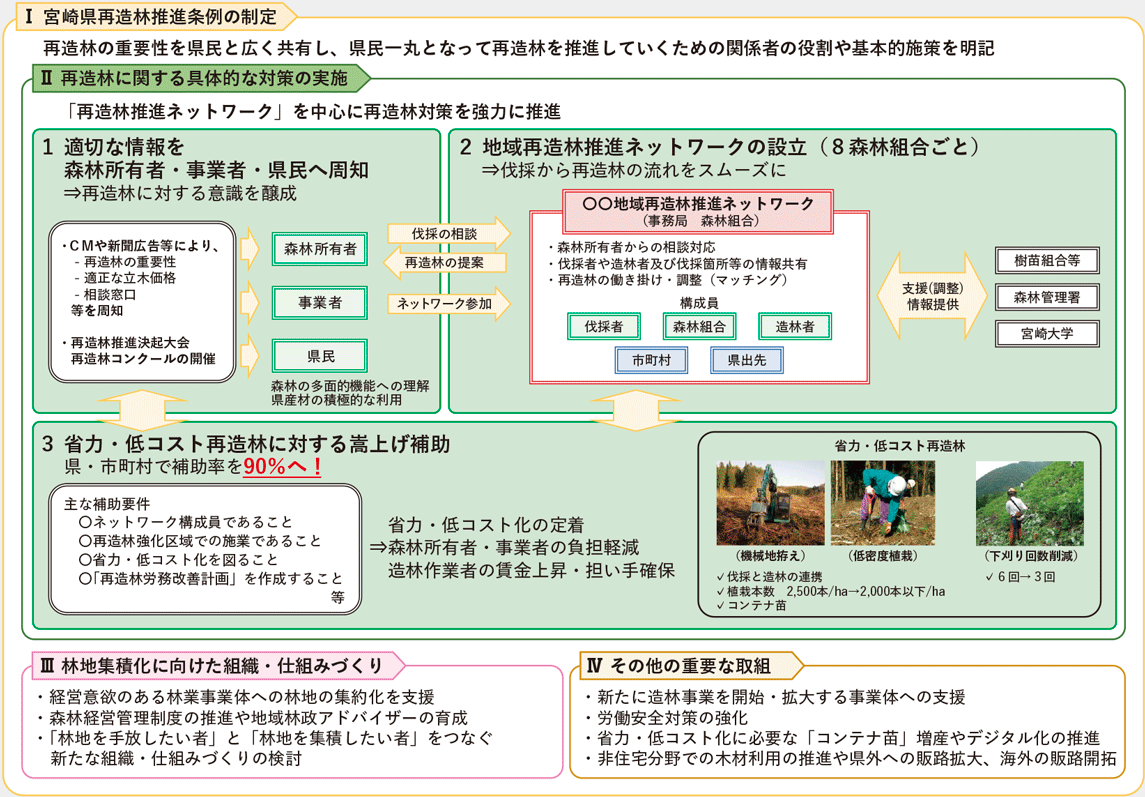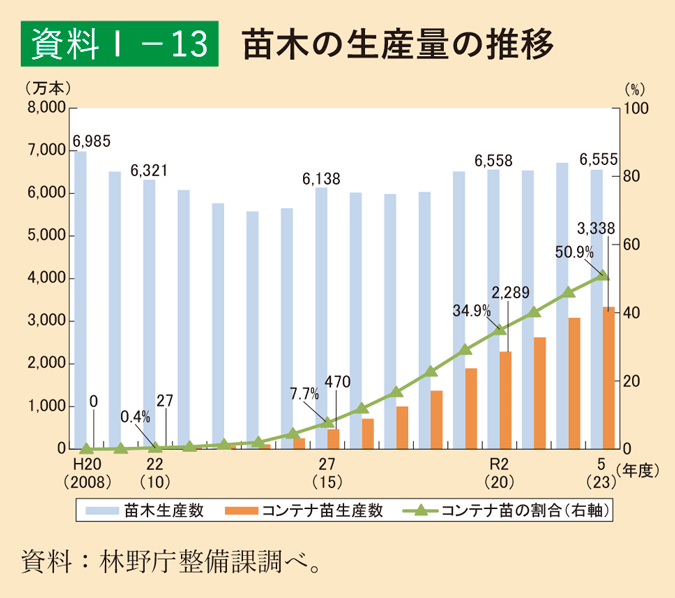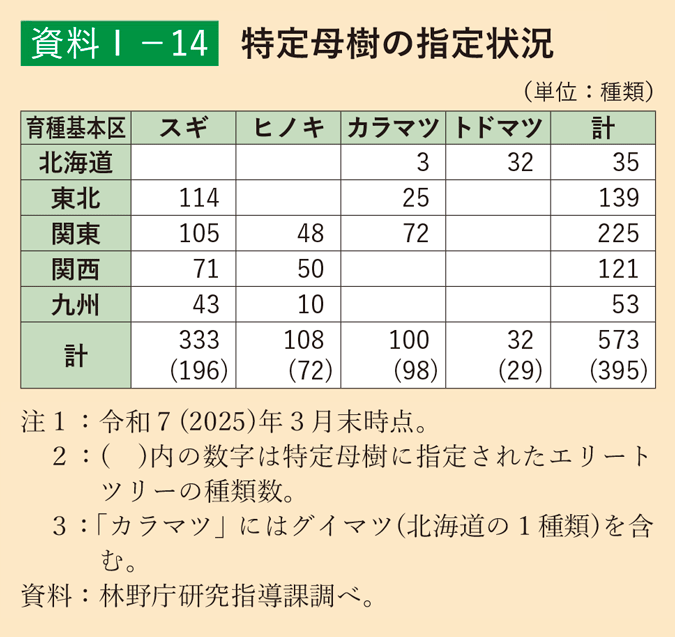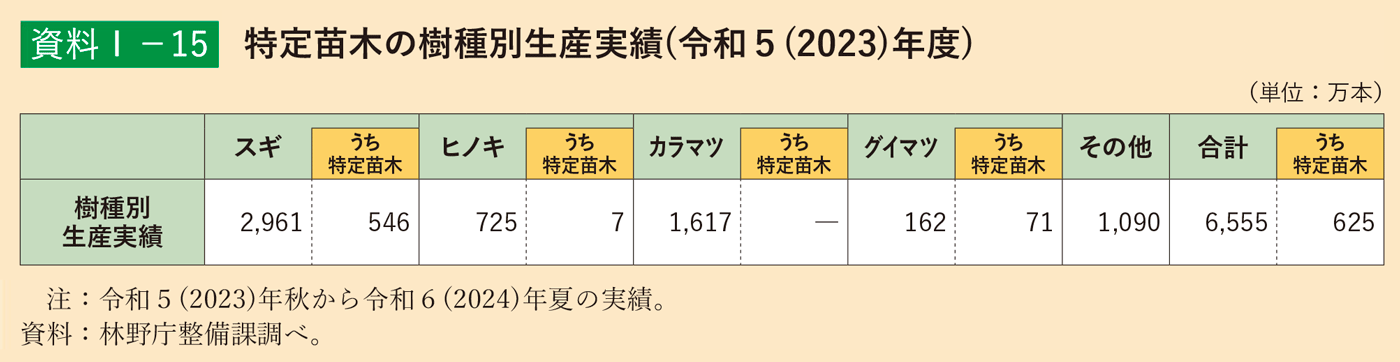第1部 第1章 第2節 森林整備の動向(2)
(2)再造林の着実な実施
(再造林の必要性)
我が国の人工林が本格的な利用期を迎えている中、森林の有する公益的機能の発揮や森林資源の持続的な利用を確保していくためには、適正な伐採と再造林を着実に進めていくことが必要である。また、2050年ネット・ゼロに向けて、中⾧期的な森林吸収量の確保・強化が必要となっている一方で、我が国の人工林は、高齢級の割合が増え、二酸化炭素吸収量が減少傾向にあることから、成⾧の旺盛な若い森林を造成するためにも、主伐後の再造林を進めていくことは重要である。
しかし、主伐収入で造林費用を賄えないことや再投資の意欲が湧かないこと、育林従事者の減少などの理由により、再造林が進んでいないことが課題となっていることから、林野庁では造林適地の選定や、造林の省力化と低コスト化に向けた取組等を進めている。
(造林適地の選定)
林野庁では、全国森林計画に基づく伐採及び伐採後の再造林を着実に進めていくこととしており、自然的・社会的条件等を勘案し再造林を行うべき森林を明らかにするため、市町村森林整備計画における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」の設定を進めている。また、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(以下「間伐等特措法」という。)により、成⾧に優れた種苗の母樹(特定母樹)の増殖を促進するとともに、特定母樹から採取された種穂から育成された苗木(特定苗木)を活用した再造林を推進するため、特定苗木を積極的に用いた再造林を計画的かつ効率的に推進する「特定植栽促進区域」の設定を進めている。令和5(2023)年度末時点の設定面積は、「特に効率的な施業が可能な森林の区域」が106万ha(*14)、「特定植栽促進区域」が56万ha(*15)となった。
さらに、都道府県や市町村が造林適地を適切に判定し、これらの区域設定や路網計画の効率的な策定につなげられるよう、GISを活用した補助ツールの普及に取り組んでいる。なお、令和7(2025)年度までに補助ツール等を活用した造林適地の判別が全都道府県で行われることを目標としている。
(*14)林野庁計画課調べ。
(*15)林野庁整備課調べ。
(造林の省力化と低コスト化に向けた取組)
再造林については、地拵(ごしら)え、植栽、下刈りといったそれぞれの作業における労働負荷やコストを低減する技術の開発・実証が進められている。
林野庁では、再造林の省力化と低コスト化に向けて、伐採と並行又は連続して地拵(ごしら)えや植栽を行う「伐採と造林の一貫作業システム」(以下「一貫作業システム」という。)や、低密度植栽(*16)、下刈りの省略等を推進している。
一貫作業システムでは伐採と再造林のタイミングを合わせる必要があることから、春や秋の植栽適期以外でも高い活着率が見込めるコンテナ苗の活用が有効である。
また、主要樹種における低密度植栽の有効性については、令和4(2022)年に改訂した「スギ・ヒノキ・カラマツにおける低密度植栽のための技術指針」と「低密度植栽技術導入のための事例集」で、これまでの実証実験の成果等を取りまとめており、引き続き低密度植栽の普及を行っていくこととしている。
下刈りについては、通常、植栽してから5~6年間は毎年実施されているが、雑草木との競合状態に応じた下刈り回数の低減や、従来の全刈りから筋刈り(*17)、坪刈り(*18)への変更などによる省力化に加え、下刈り回数の低減が期待される大苗や特定苗木の導入を進めていく必要がある。また、特定苗木の導入により、伐期の短縮による育林費用回収期間の短縮も期待される。
林野庁では、造林の省力化や低コスト化を推進するための取組を森林整備事業等により支援しているほか、全国の先進的な造林技術等の事例や技術資料のリンクを取りまとめた「革新的造林モデル事例集 令和4年度版」及び最新の取組事例により下刈りの省力化へのアプローチを解説した「下刈り作業省力化の手引き」を令和5(2023)年に公表した。また、省力・低コスト造林技術の林業現場での定着に向け、令和6(2024)年7月から令和7(2025)年1月にかけて全国5か所で「省力・低コスト造林技術の普及に向けたシンポジウム」を開催し、現地検討会と併せて省力・低コスト造林技術に関する指針の説明、周知を行った。同指針については、シンポジウムを通じて林業経営体等から出された意見や要請等を踏まえ、令和7(2025)年3月に「造林に係る省力化・低コスト化技術指針」として公表している。
このほか、短期間で成⾧して早期の収穫が期待されている早生樹についても、実証の取組が各地で進められている。林野庁では、センダンとコウヨウザンについて植栽の実証を行い、用途や育成についての留意事項を取りまとめた「早生樹利用による森林整備手法ガイドライン」を令和4(2022)年に改訂した。
林野庁は、人工造林面積に占める造林の省力化や低コスト化を行った面積の割合を令和10(2028)年度までに85%とする目標を設定しており、令和5(2023)年度の省力・低コスト造林実施面積の割合は54%となっている(資料1-12)。
(*16)一般的に普及している3,000本/ha程度よりも低密度で植栽する方法。
(*17)植栽木の列に沿って一定幅で雑草木を刈り払うこと。国有林野における筋刈りの取組については、第4章第2節(2)の事例4-3(201ページ)を参照。
(*18)植栽木の周辺のみの雑草木を刈り払うこと。
(地域における再造林の推進に向けた取組)
各地域では、再造林の推進に向けて、再造林に係る協定締結や基金の創設等の様々な取組が行われている。例えば、森林組合と建築資材メーカー等の企業、行政機関による再造林コスト等を織り込んだ水準で木材の取引価格を明記した協定の締結や、素材生産業者や木材加工事業者などが協力金を積み立て、再造林の支援に充てる基金の創設といった地域独自の取組も広がりをみせている。
令和6(2024)年7月には、宮崎県が都道府県においては全国初となる再造林に関する条例を制定するとともに、更なる再造林の推進に向けた取組を進めることとしており、他の都道府県への取組の広がりが期待される(事例1-3)。
事例1-3 宮崎県における再造林推進に向けた取組
宮崎県は、主伐後の再造林率が約70%と高い水準にあるが、主伐の大部分が林道から近い箇所など林業適地で行われていると考えられている中でも、近年は再造林されていない林地等が増加していることから、森林資源の循環利用や森林が持つ公益的機能の発揮等の観点から再造林の推進が課題となっている。
このため、再造林率日本一を目標に掲げた「グリーン成⾧プロジェクト」を立ち上げ、令和6(2024)年度からの3年間の集中的な取組として、産学官と県民が一丸となって再造林に取り組む「宮崎モデル」を構築した。同モデルでは、「宮崎県再造林推進条例」の制定を掲げるとともに、具体的な対策として「適切な情報を森林所有者・事業者・県民へ周知」「地域再造林推進ネットワークの設立」「省力・低コスト再造林に対する嵩上げ補助」を中核とした再造林対策に取り組むこととしている。
令和6(2024)年7月に施行された宮崎県再造林推進条例は、都道府県初となる再造林に関する条例であり、再造林を推進するための基本理念を共有し、行政、森林所有者、森林・林業関係者、県民の役割を明らかにし、基本的施策の方向性を定めることにより、森林の多面的機能を発揮させ、県民の安全・安心で豊かな暮らしを実現することを目的としている。
また、具体的な対策のうち、「宮崎モデル」推進の核となるのが地域再造林推進ネットワークの設立である。県内の森林組合を単位とする8地域において、再造林や立木取引に関する森林所有者からの相談対応や、伐採者と造林者、市町村間の伐採情報の共有、再造林のマッチングを行うネットワークを創設し、運営を開始している。
宮崎県では、本プロジェクトにより再造林対策を強化し、持続可能な木材供給はもとより多面的機能を発揮する森林・林業・木材産業の確立を目指していくこととしている。
(優良種苗の安定供給)
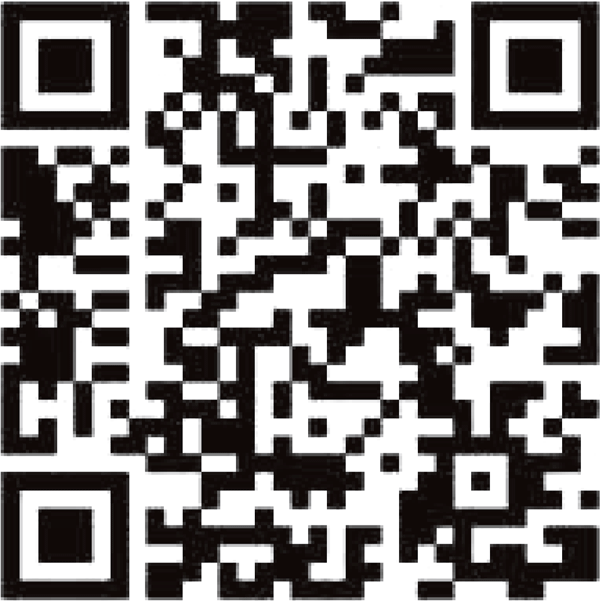
再造林の推進には苗木の安定供給が重要である。令和5(2023)年度の苗木の生産量は、約6,600万本と近年横ばい傾向にあり、このうち約5割をコンテナ苗が占めている(資料1-13)。また、苗木生産事業者数は、全国で850者となっており、同様に近年横ばい傾向にある(*19)。
(*19)林野庁整備課調べ。
(成⾧等に優れた苗木の供給に向けた取組)
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センターでは、収量の増大と造林・保育の効率化に向けて、林木育種によりエリートツリーの選抜が行われてきており、更に改良を進めるため、エリートツリー同士を交配した次世代の精英樹の開発も進められている。
農林水産省では間伐等特措法に基づき、エリートツリー等のうち、成⾧や雄花着生性等に関する基準(*20)を満たすものを特定母樹に指定しており、令和7(2025)年3月末時点で、573種類(うちエリートツリー395種類)となっている(資料1-14)。林野庁では、特定母樹を増殖する事業者の認定や採種園・採穂園(*21)の整備を推進している。
特定苗木は、従来の苗木と比べ成⾧に優れており、下刈り期間の短縮による育林費用の削減及び伐期の短縮による育林費用回収期間の短縮とともに、二酸化炭素吸収量の向上も期待されることから、これらの苗木を積極的に用いた再造林を推進している。令和5(2023)年度の特定苗木の生産本数は、スギが九州を中心とした16県で546万本、グイマツ(クリーンラーチ(*22))が北海道で71万本、ヒノキが三重県など5県で7万本、合計625万本となっており、苗木生産量の約1割となっている(資料1-15)。
農林水産省は、「みどりの食料システム戦略」において、特定苗木の活用を、令和12(2030)年までに苗木生産量の3割(*23)、令和32(2050)年までに9割とする目標を設定している。
(*20)成⾧量が同様の環境下の対照個体と比較しておおむね1.5倍以上、材の剛性や幹の通直性に著しい欠点がなく、雄花着生性が一般的なスギ・ヒノキのおおむね半分以下等。
(*21)苗木を生産するための種子やさし穂を採取する目的で、精英樹等を用いて造成した圃場。
(*22)強度があるグイマツ特定母樹「中標津5号」と成⾧の早いカラマツ精英樹の掛け合わせにより得られた、強度があり成⾧の早い特性を併せ持つグイマツF1世代の総称。
(*23)林野庁では、3,000万本程度を想定。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219