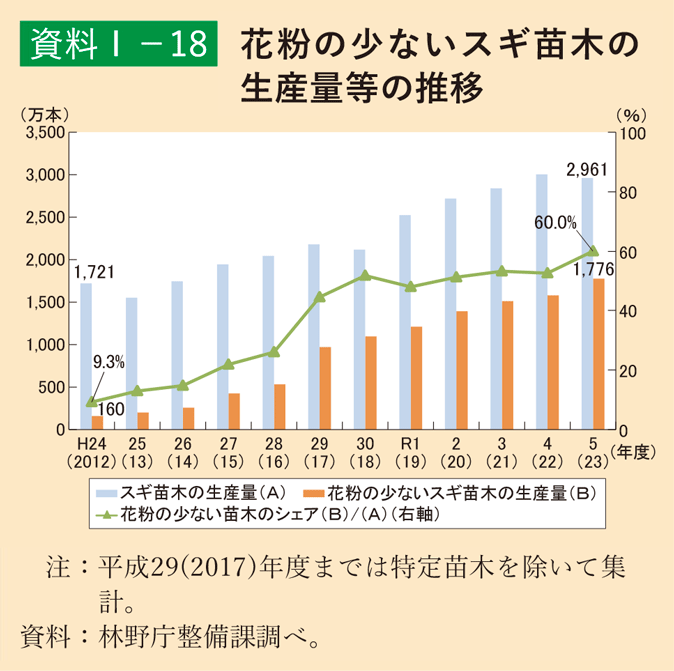第1部 第1章 第2節 森林整備の動向(3)
(3)花粉発生源対策
(「花粉症対策の全体像」に基づき花粉症対策を推進)
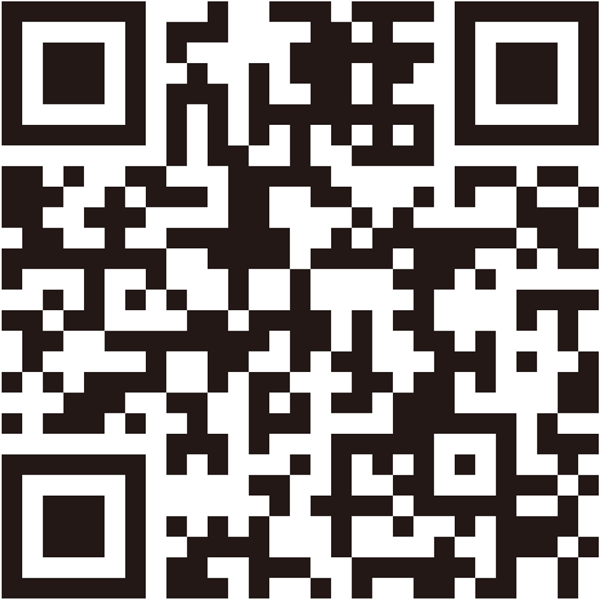
スギ花粉症患者の数については、耳鼻咽喉科医及びその家族約2万人を対象とした全国的な疫学調査によると、有病率は平成10(1998)年の16%から令和元(2019)年には39%に達していると推定されている(*24)。
令和5(2023)年5月、政府は「花粉症対策の全体像」を決定し、その中では、花粉の発生源であるスギ人工林の伐採・植替え等の「発生源対策」や、花粉飛散量の予測精度向上や飛散防止剤の開発等の「飛散対策」、治療薬の増産等の「発症・曝(ばく)露対策」を3本柱として総合的に取り組み、花粉症という社会問題を解決するための道筋を示している。
同年10月には、「花粉症対策の全体像」が想定している期間の初期の段階から集中的に実施すべき対応を「花粉症対策 初期集中対応パッケージ」として取りまとめた。
(*24)松原篤ほか「鼻アレルギーの全国疫学調査2019(1998年、2008年との比較):速報-耳鼻咽喉科医およびその家族を対象として-」(日本耳鼻咽喉科学会会報 123巻6号(2020))
(花粉発生源対策の目標)
「花粉症対策の全体像」においては、令和15(2033)年度に花粉発生源となるスギ人工林を約2割減少させることを目指している(資料1-16)。また、将来的(令和5(2023)年度から約30年後)には花粉発生量の半減を目指すこととしている。
これを実現するため、スギ人工林の伐採量を増加させるとともに、花粉の少ない苗木(*25)や他樹種による植替えを推進することとしている。
花粉を発生させるスギ人工林の減少を図っていくためには、伐採・植替え等の加速化、スギ材の需要拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、生産性向上と労働力の確保等の対策を総合的に推進する必要がある(*26)(資料1-17)。
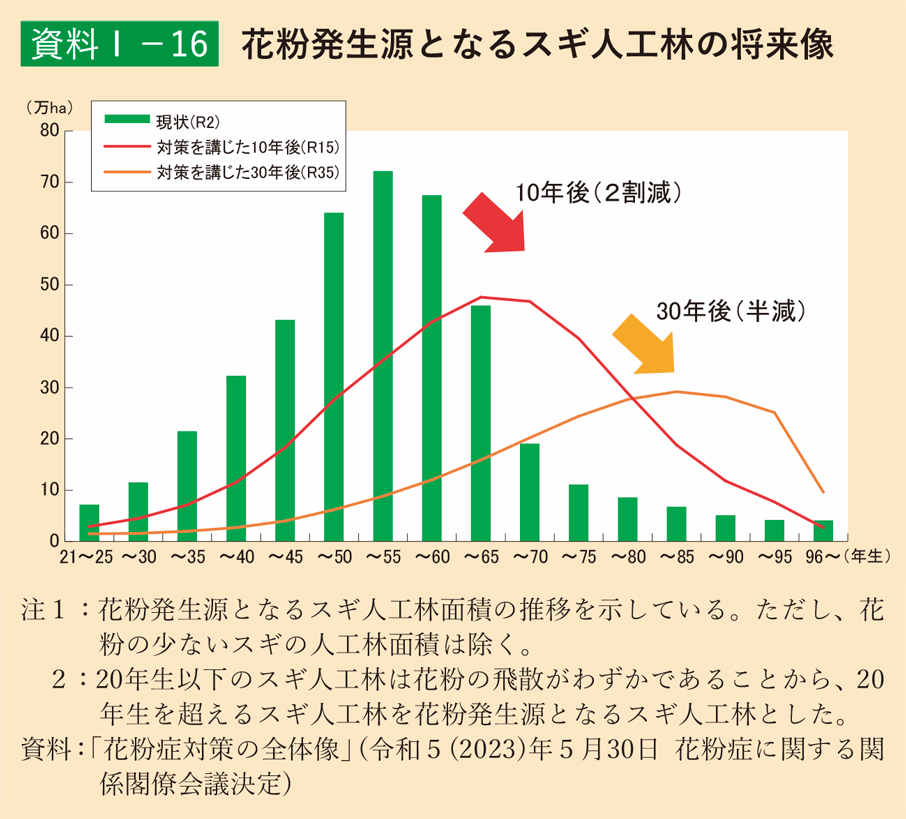
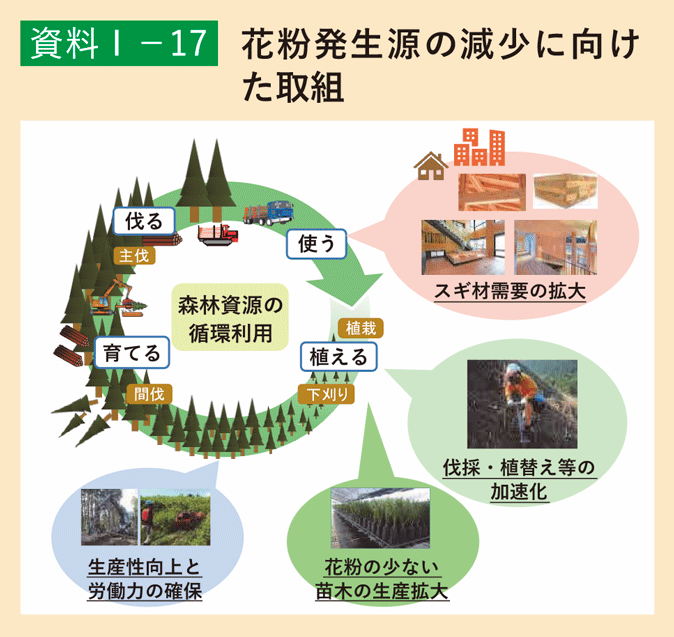
(*25)無花粉品種、少花粉品種、低花粉品種及び特定苗木。
(*26)花粉発生源対策については、「令和5年度森林及び林業の動向」特集第3節16-23ページを参照。
(スギ人工林の伐採・植替え等の加速化)
「花粉症対策 初期集中対応パッケージ」では、人口の多い都市部周辺など(*27)において重点的に伐採・植替え等を実施する区域(スギ人工林伐採重点区域)を令和5(2023)年度内に設定することとされ、約98万haのスギ人工林が設定されている。スギ人工林伐採重点区域においては、森林の集約化を進めるとともに、伐採・植替えの一貫作業の実施やそのために必要な路網整備を推進している。
伐採・植替え等の加速化のためには、現状で林業経営体による集約化が進んでいない森林においても伐採・植替えの実施を促していく必要がある。そのため、スギ人工林伐採重点区域内で、林業経営体による森林所有者への伐採・植替えの働き掛け等を支援し、森林の集約化を推進している。
花粉発生源となるスギ人工林を減少させていくに当たっては、森林の有する公益的機能が持続的に発揮されるよう、伐採後の適切な更新が必要であり、再造林を確実に確保する観点からも、伐採・植替えの一貫作業を推進している。
また、路網は、間伐や再造林等の施業を効率的に行うとともに、木材を安定的に供給するために重要な生産基盤であり、これまでも傾斜や作業システムに応じて林道と森林作業道を適切に組み合わせた路網の整備を推進してきた。スギ人工林伐採重点区域においても、スギ人工林の伐採・植替えに寄与する路網の開設・改良を推進している。
さらに、森林環境譲与税等を活用することにより、林業生産に適さないスギ人工林の広葉樹林化等の地方公共団体による森林整備を促進することとしている。
(*27)1)県庁所在地、政令指定都市、中核市、施行時特例市及び東京都区部から50km圏内にあるまとまったスギ人工林のある森林の区域、又は、2)スギ人工林の分布状況や気象条件等から、スギ花粉を大量に飛散させるおそれがあると都道府県が特に認める森林の区域。
(花粉の少ない苗木の生産拡大)
令和5(2023)年度の花粉の少ないスギ苗木の生産量(*28)は約1,800万本で、平成24(2012)年度の約160万本から大幅に増加し、スギ苗木の生産量の約6割に達している(資料1-18)。
「花粉症対策の全体像」では、令和15(2033)年度には花粉の少ないスギ苗木の生産割合をスギ苗木の生産量の9割以上に引き上げることを目指している。
花粉の少ない苗木の生産拡大に向けては、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センターにおける原種苗木増産施設、都道府県等における採種園・採穂園、苗木生産事業者におけるコンテナ苗生産施設の整備を進めるなど、官民を挙げて花粉の少ない苗木の生産体制の強化を進めている。
(*28)令和5(2023)年秋から令和6(2024)年夏の実績。
(その他の花粉症対策)
スギ花粉の発生を抑える技術の実用化に向けては、スギの雄花だけを枯死させる日本固有の菌類(Sydowia japonica)や食品添加物(トリオレイン酸ソルビタン)を活用したスギ花粉飛散防止剤の開発が進展している。林野庁では、スギ林への効果的な散布方法の確立や散布による生態系への影響調査、花粉飛散防止剤の製品化などの技術開発等を支援している。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219