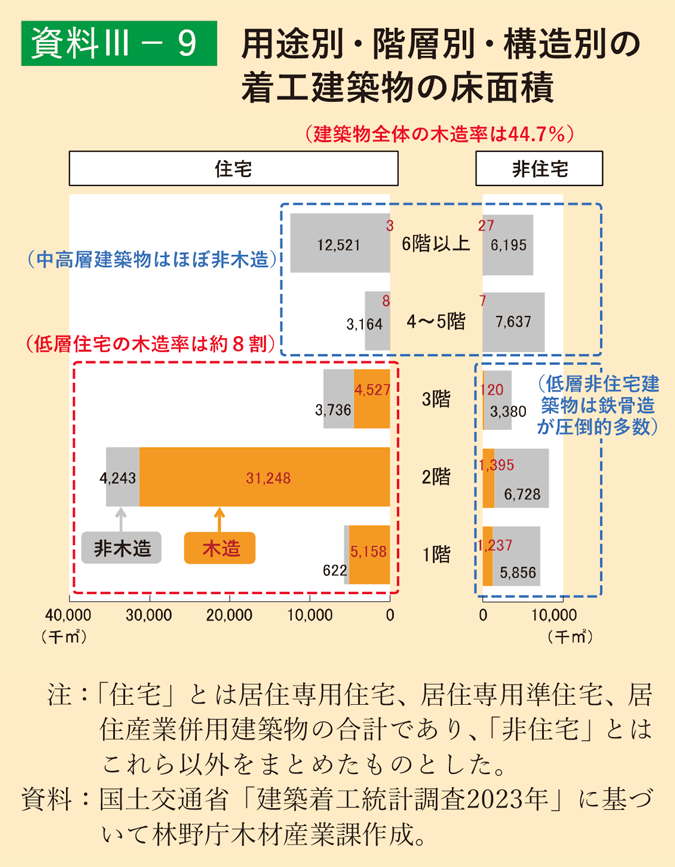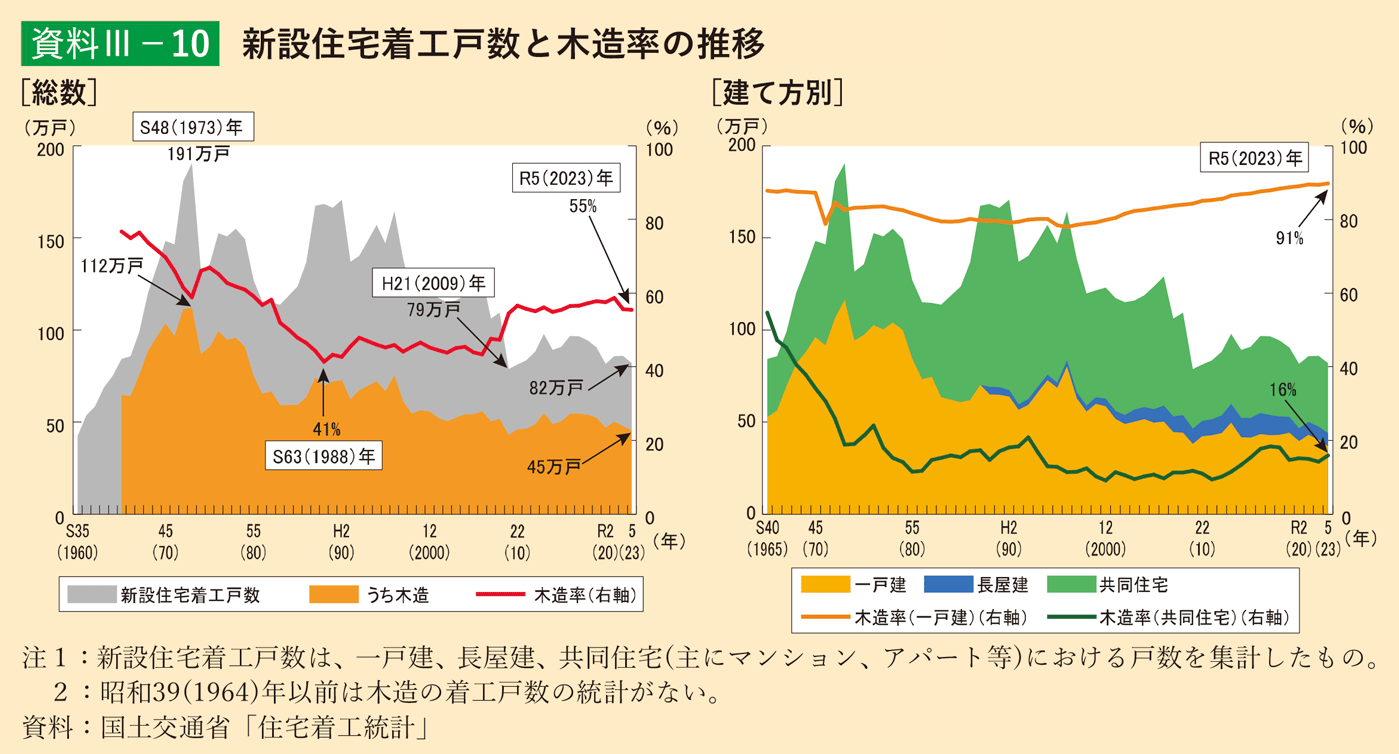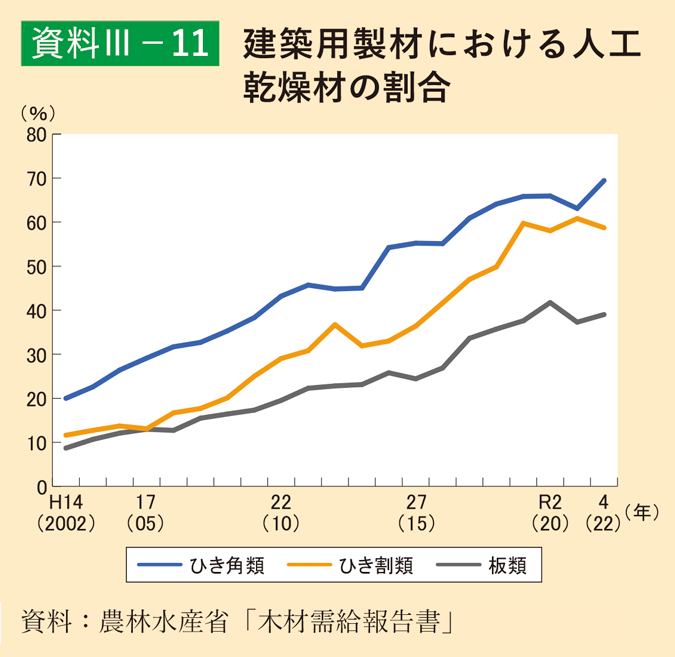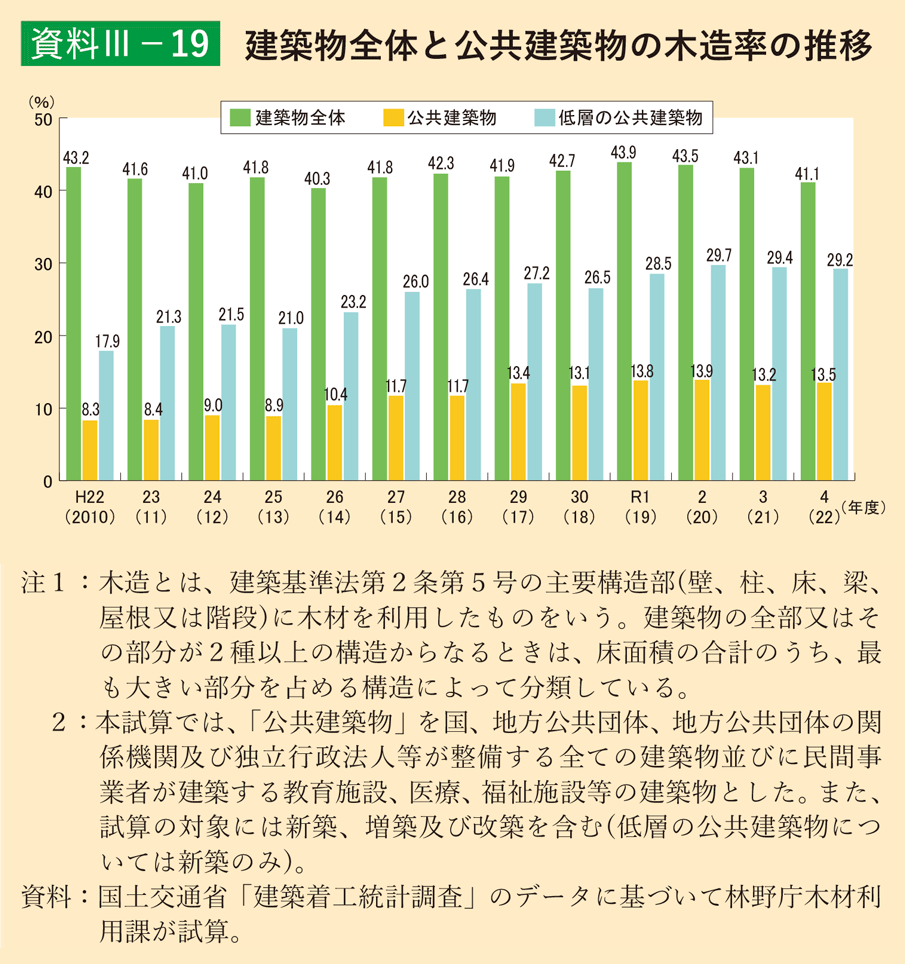第1部 第3章 第2節 木材利用の動向(2)
(2)建築分野における木材利用
(ア)建築分野における木材利用の概況
(建築物の木造率)

木材は軽くて扱いやすい割に強度があることから我が国では建築資材等として多く用いられてきた。
我が国の令和5(2023)年の建築着工床面積の木造率は44.7%であり、これを用途別・階層別にみると、1~3階建ての低層住宅は80%を超えるが、低層非住宅建築物は15%程度、4階建て以上の中高層建築物は1%以下と低い状況にある(資料3-9)。
このように、建築用木材の需要の大部分を低層住宅分野が占めているが、最も普及している木造軸組工法(*23)の住宅における国産材の使用割合は全体として5割程度にとどまっており、低層住宅分野において国産材の利用を拡大していくことが重要である。
一方、新設住宅着工戸数が人口減少等により⾧期的には減少していく可能性を踏まえると、非住宅・中高層建築物での木造化・木質化を進め、新たな木材需要を創出することも重要となっている。
(*23)単純梁形式の梁・桁で床組や小屋梁組を構成し、それを柱で支える柱梁形式による建築工法。
(建築物全般における木材利用の促進)
都市(まち)の木造化推進法に基づき、木材利用促進本部(*24)は、令和3(2021)年10月に建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(以下「建築物木材利用促進基本方針」という。)を策定し、建築物での木材の利用の促進を図っている。
地方公共団体においては、令和6(2024)年2月末時点で、全ての都道府県と1,640市町村(94%)が都市(まち)の木造化推進法に基づく木材の利用の促進に関する方針を策定しており、建築物木材利用促進基本方針に沿って改定が進められている。
(*24)都市の木造化推進法に基づき設置された組織であり、農林水産大臣を本部⾧、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣を本部員としている。
(イ)住宅分野における木材利用の動向
(住宅分野における木材利用の概況)
新設住宅着工戸数は、令和5(2023)年は前年比4.6%減の82万戸、このうち木造住宅が前年比4.9%減の45万戸となった。一方、新設住宅着工戸数に占める木造住宅の割合(木造率)は、前年から大きな変化はなく、一戸建て住宅では91.4%と特に高く、全体では55.4%となっている(資料3-10)。
令和5(2023)年の木造の新設住宅着工戸数における工法別のシェアは、木造軸組工法(在来工法)が77.7%、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)が20.0%、木質プレハブ工法(*25)が2.3%となっている(*26)。
(*25)木材を使用した枠組の片面又は両面に構造用合板等をあらかじめ工場で接着した木質接着複合パネルにより、壁、床、屋根を構成する建築工法。
(*26)国土交通省「住宅着工統計」(令和5(2023)年)。木造軸組工法については、木造住宅全体からツーバイフォー工法及び木質プレハブ工法を差し引いて算出。
(住宅向けの木材製品への品質・性能に対する要求)
耐震性や省エネルギー性能の向上などの住宅におけるニーズの変化(*27)を背景に、住宅に用いられる木材製品について、より一層の寸法安定性や強度等の品質・性能を求めるニーズが高まっている。
この結果、建築用製材において、寸法安定性の高い人工乾燥材(KD材(*28))割合が増加している(資料3-11)。また、木造軸組工法の住宅を建築する大手住宅メーカーでは、柱材と横架材で寸法安定性の高い集成材の割合が増加している。このうち、横架材については、高い曲げヤング率(*29)や多様な寸法への対応が求められるため、米(べい)マツ製材やヨーロッパアカマツ(レッドウッド)集成材等の輸入材が高いシェアを持つ状況にあるが、柱材ではスギ集成柱が普及するなど国産材の利用も進みつつある(資料3-12)。
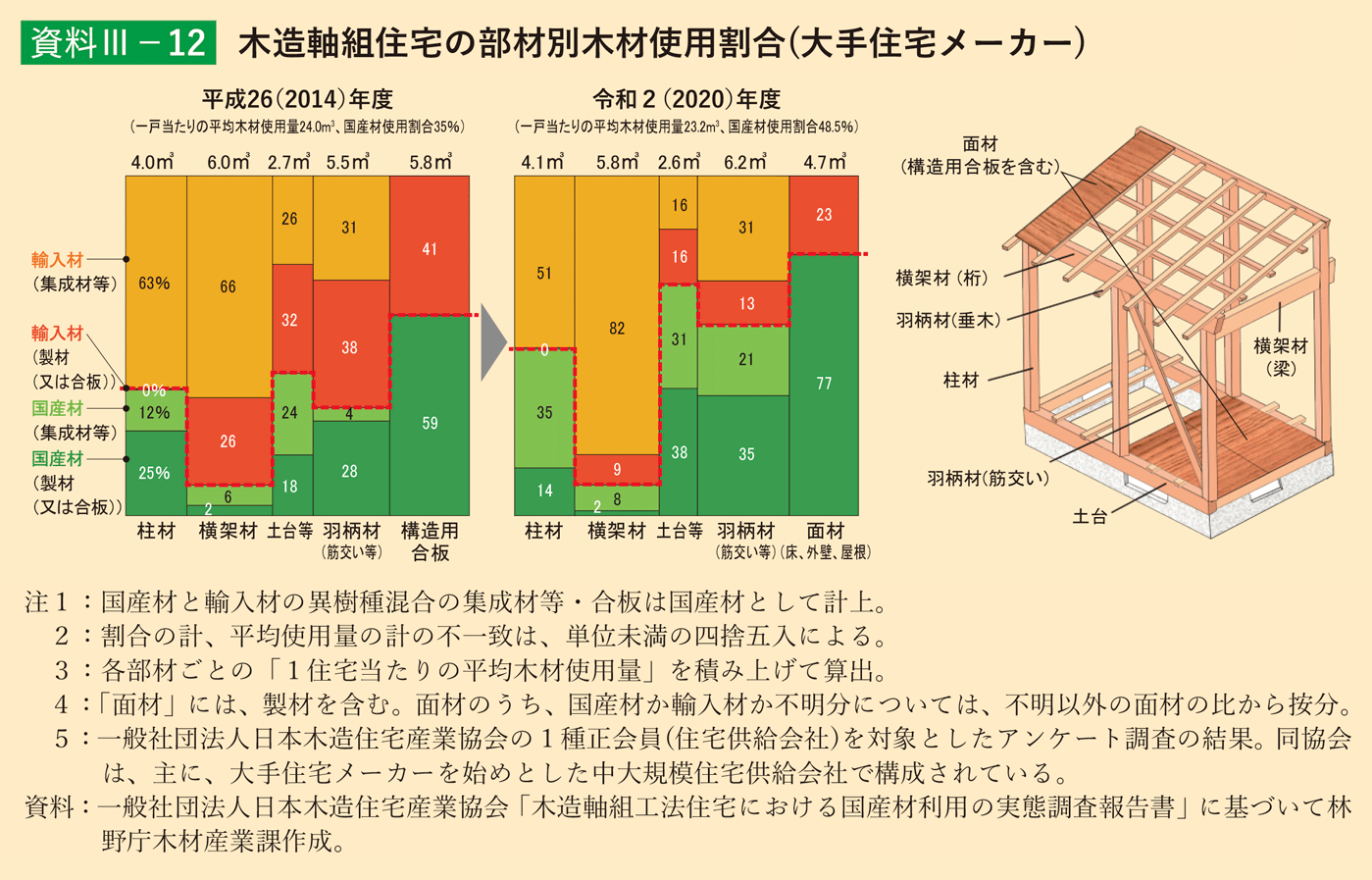
(*27)住宅におけるニーズの変化については「令和3年度森林及び林業の動向」特集2第2節(1)23-25ページを参照。
(*28)KDは「Kiln Dry」の略。
(*29)ヤング率は材料に作用する応力とその方向に生じるひずみとの比。このうち、曲げヤング率は、曲げ応力に対する木材の変形(たわみ)のしにくさを表す指標。
(地域で流通する木材を利用した住宅の普及)
素材生産者や製材業者、木材販売業者、大工・工務店、建築士等の関係者がネットワークを構築し、地域で生産された木材を多用して、健康的に⾧く住み続けられる家づくりを行う取組がみられることから、林野庁では、これらの関係者が一体となって消費者の納得する家づくりに取り組む「顔の見える木材での家づくり」を推進している。令和4(2022)年度には、関係者の連携による家づくりに取り組む団体数は584、供給戸数は26,109戸となった(*30)。
また、一部の工務店や住宅メーカーでは、横架材を含めて国産材を積極的に利用する取組もみられ、特に工務店では製材の使用率が高く、部材によらず国産材の使用率が比較的高い傾向にある(資料3-13)。
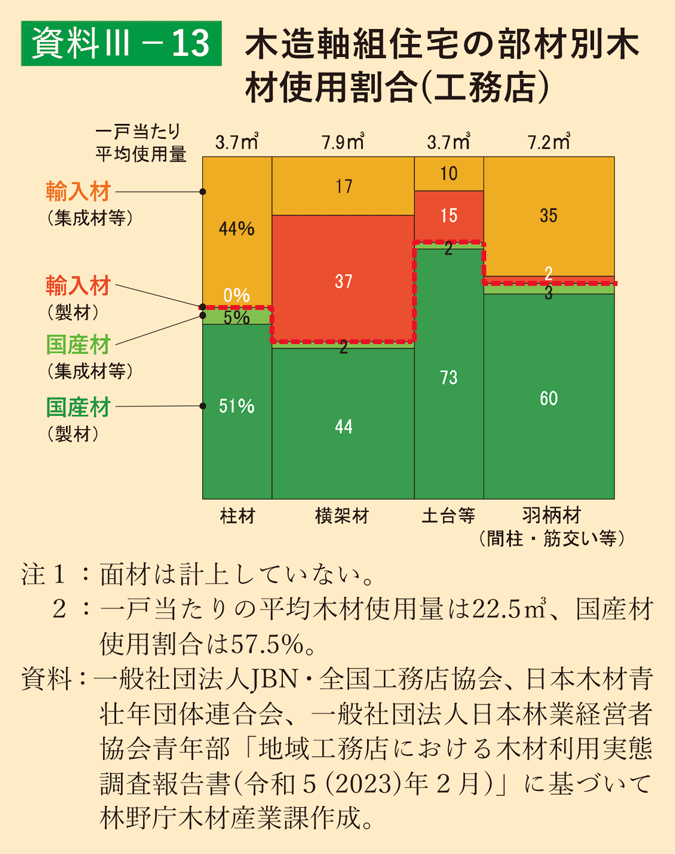
(*30)林野庁木材産業課調べ。
(ウ)非住宅・中高層建築物における木材利用の動向
(非住宅・中高層建築物における木材利用の概況)
令和5(2023)年の我が国の建築着工床面積の現状を用途別・階層別にみると、低層住宅以外の非住宅・中高層建築物の木造率は、5.8%と低い状況にある(資料3-9)。一方、低層で床面積の小さい非住宅については、既存の住宅建築における技術をそのまま使える場合があることなどから木造率が比較的高い傾向にある(資料3-14)。
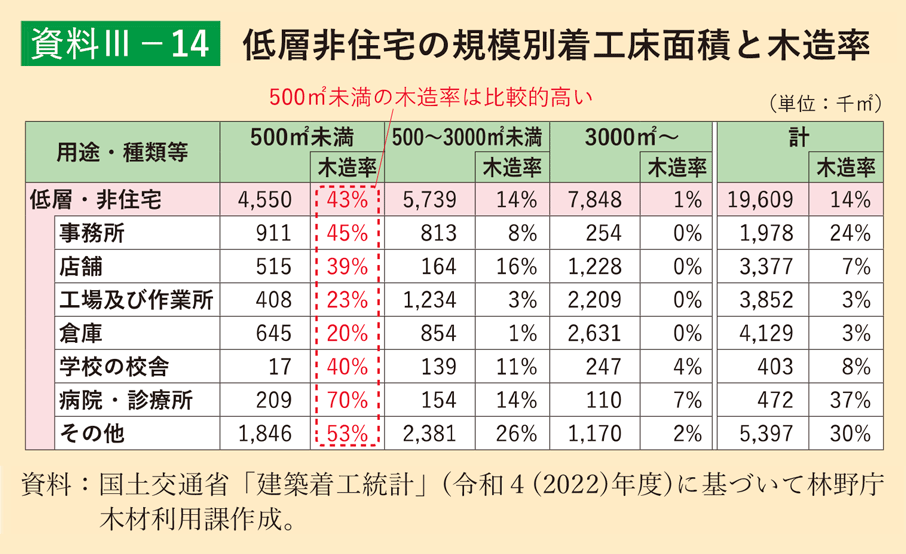
(非住宅・中高層建築物での木材利用拡大の取組)
近年、住宅市場の減少見込みや、持続可能な資源としての木材への注目の高まりなどを背景に、建設・設計事業者や建築物の施主となる企業等が非住宅・中高層建築物の木造化や木質化に取り組む例が増えつつある(資料3-15)。
非住宅・中高層建築物に関しては、製材やCLT(*31)(直交集成板)、木質耐火部材等に係る技術開発とともに、建築基準の合理化が図られ、技術的・制度的に木材利用の環境整備が一定程度進んできた。その中で、木材を構造部材等に使用した10階建てを超える先導的な高層建築の例も出てきている。
林野庁では、非住宅・中高層建築物における一層の木材利用を進めるため、国土交通省と連携して、非住宅・中高層建築物の木造化に必要な知見を有する設計者や施工者等の育成を支援している。また、設計・施工コストの低減に向けて、普及性の高い標準的な設計や工法等の普及を図っている(資料3-16)。くわえて、一般流通材以外の木質耐火部材やCLT等の低コスト化を図るため、それらの部材の標準化等を進めている。
さらに、令和4(2022)年6月に公布された建築基準法等の改正(*32)により、簡易な構造計算に基づき建築できる木造建築物の範囲が拡大されるとともに、令和5(2023)年4月に施行された建築基準法施行令の改正により、新たに1.5時間及び2.5時間の耐火性能の基準が設定されるなど、建築物における木材利用の更なる促進に向けた建築基準の合理化が進んでいる。
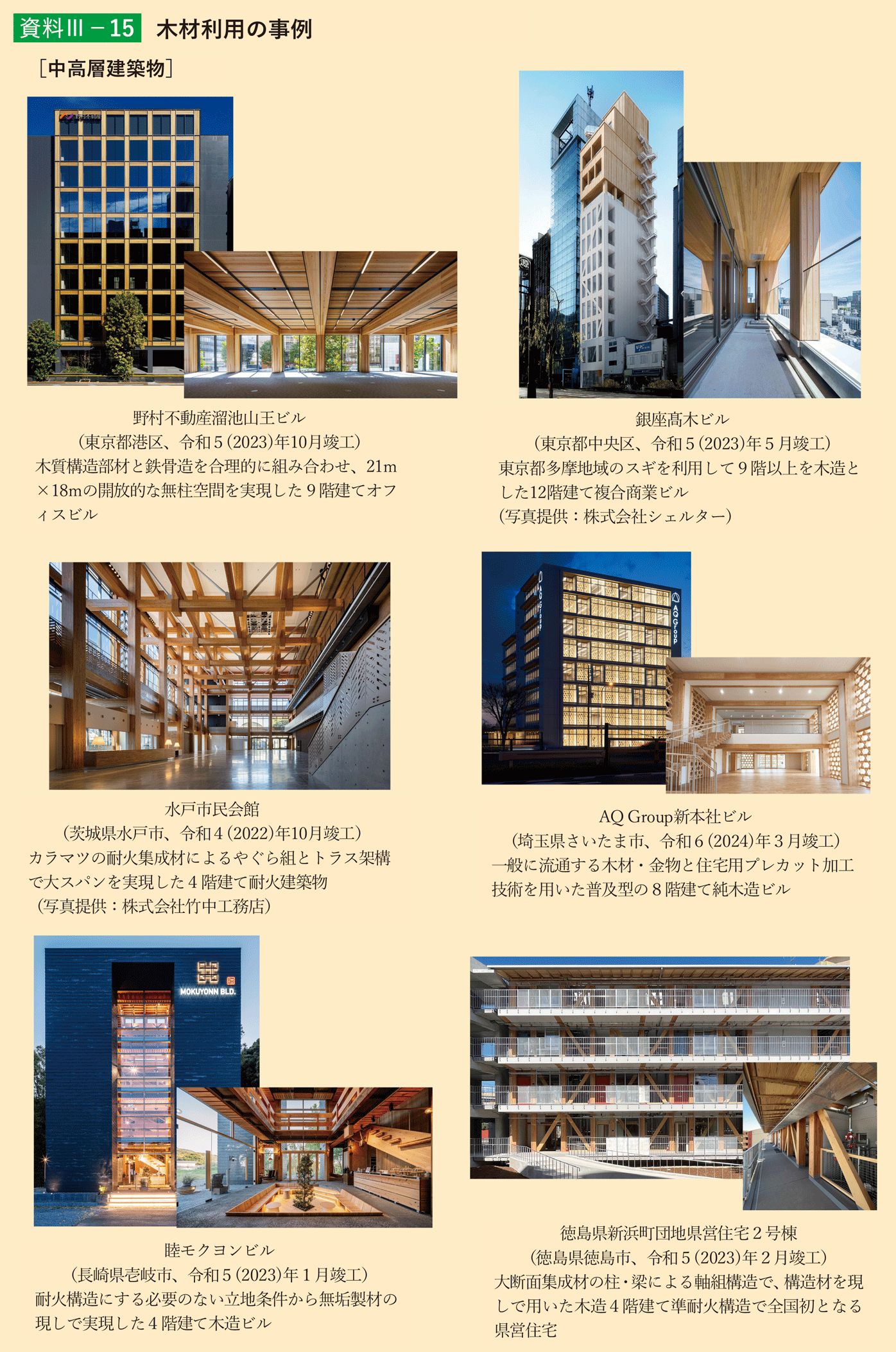
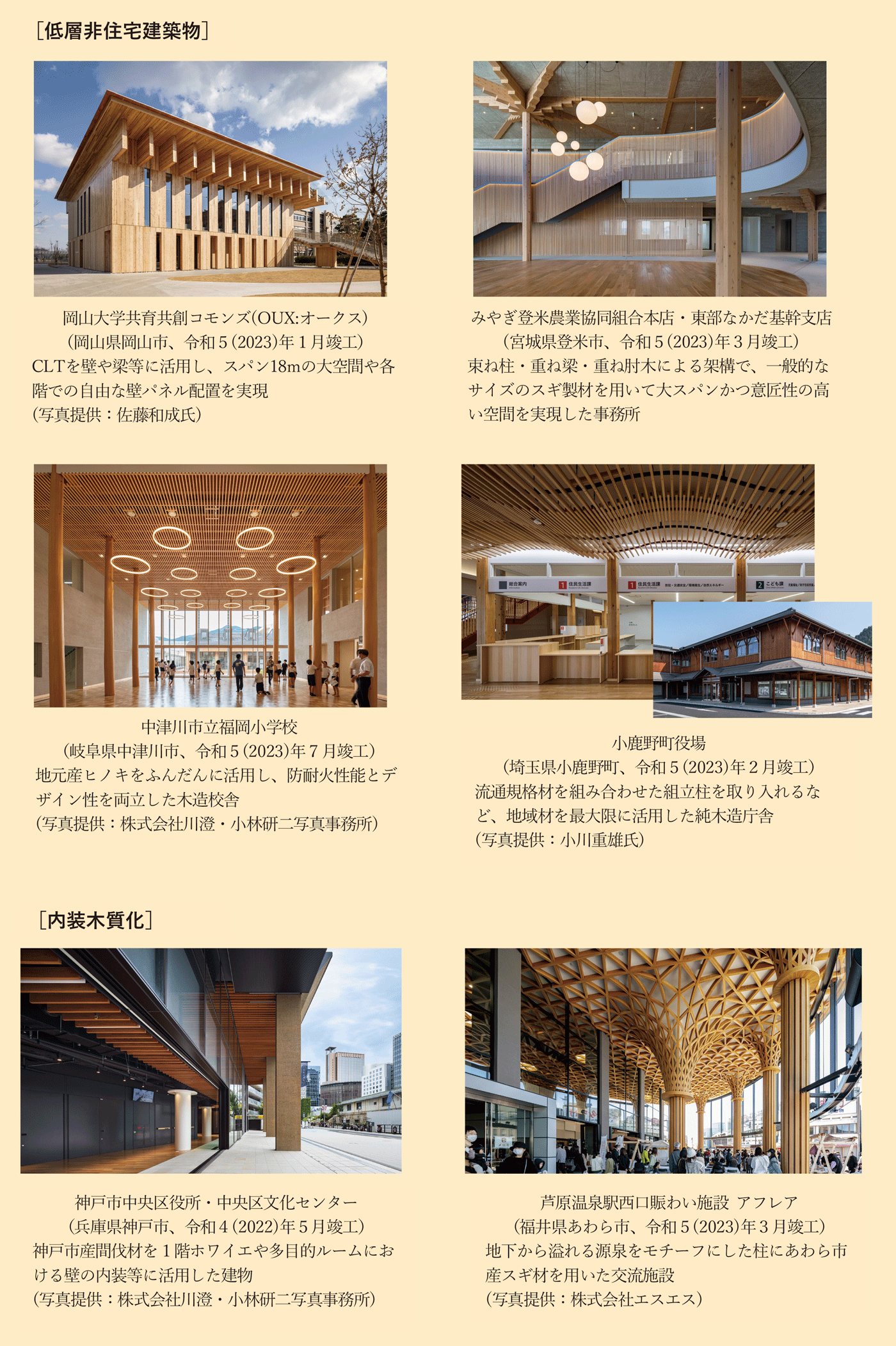



また、川上から川下までの関係者が広く参画する官民協議会「民間建築物等における木材利用促進に向けた協議会(ウッド・チェンジ協議会)」において、民間建築物等における木材利用に当たっての課題や解決方法の検討、木材利用の先進的な取組等の発信など、木材を利用しやすい環境づくりに取り組んでいる。
さらに、民間建築物等での木材利用を後押ししていくため、都市(まち)の木造化推進法により、建築物木材利用促進協定制度が創設された(資料3-17)。国若しくは地方公共団体と建築主等との2者、又は、木材産業事業者や建築事業者も加えた3者等で協定を結ぶ仕組みであり、令和6(2024)年3月末時点で、国において17件(資料3-18)、地方公共団体において113件の協定が締結されている(事例3-2、事例3-3)。協定に基づき令和5(2023)年に木造化・木質化した建築物の木材利用量は65,884m3となっている(*33)。
このほか、建築物に木材を利用しやすい環境づくりの一環として、建築物の木造化・木質化に関する国の支援事業・制度等に関する一元的な案内窓口である「建築物の木造化・木質化支援事業コンシェルジュ」が木材利用促進本部事務局に設置されている。
また、SDGsやESG投資への関心の高まりを背景に、木材利用の環境価値を「見える化」することが重要となっている。林野庁は、令和3(2021)年10月に、建築事業者等が建築物への木材利用によるカーボンニュートラルへの貢献を対外的に発信する手段として、「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」を策定し、普及を図っている。
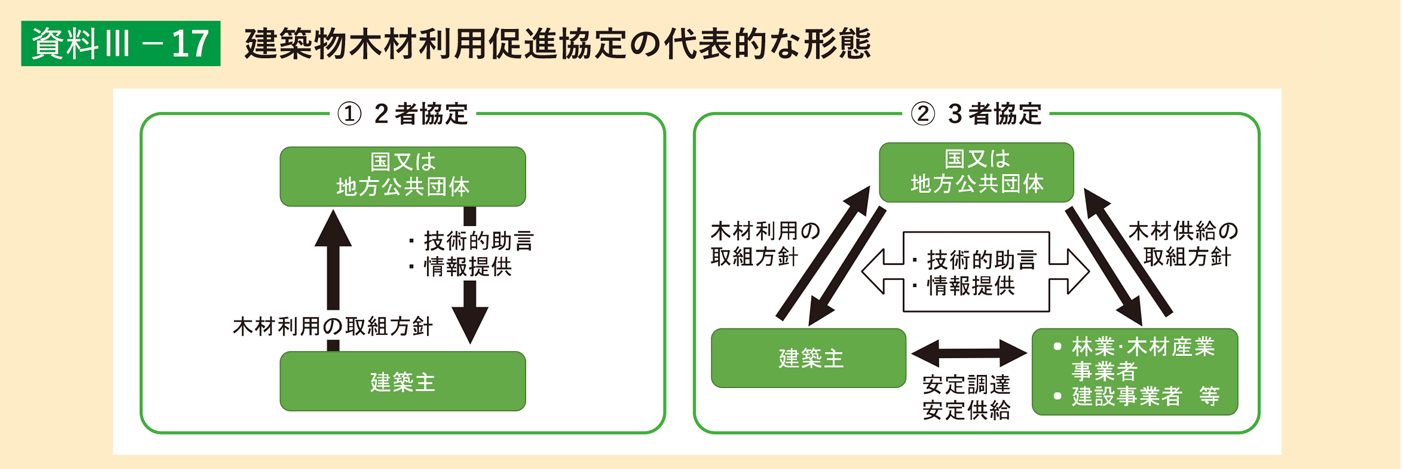
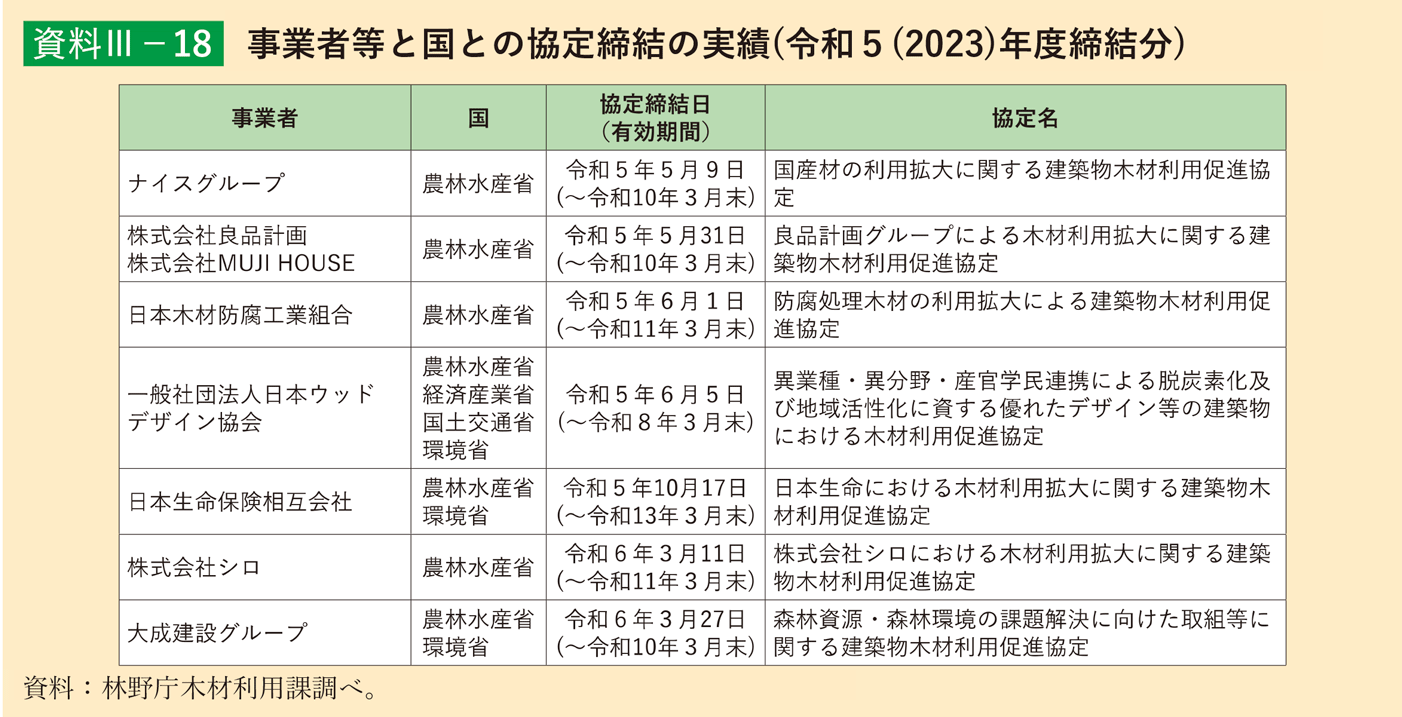
事例3-2 森林経営の持続性を担保しつつ行う木材利用促進の取組
ウイング株式会社、佐伯広域森林組合、ウッドステーション株式会社、佐伯(さいき)市の4者が令和5(2023)年6月、都市(まち)の木造化推進法に基づく建築物木材利用促進協定を締結した。
本協定は、佐伯市産材の利用拡大及び森林資源の循環利用のため、年間1万m3以上の市産材の利用を目標とするとともに、伐採、再造林、育林コストを織り込んだ水準で木材の取引価格を設定した。これにより、再造林に関わる費用や負担を透明化し、その応分の責任を取引関係者で相互負担する仕組みとなっている。取引価格を明記した建築物木材利用促進協定は全国で初となる。
4者は、再造林可能な価格での木材利用の促進を通じて植林事業を活性化させるとともに、施主や建設事業者に対しても炭素固定や再造林費用の創出の重要性を周知し、連携を広げていきたいと考えている。
事例3-3 建築物木材利用促進協定に基づく店舗の木造化の取組
株式会社良品計画及び株式会社MUJI HOUSEは、令和5(2023)年5月に農林水産省と建築物木材利用促進協定を締結した。本協定では、構造材や内外装に国産材を積極的に活用した木造店舗等の整備(今後5年間で計1万m3を目安)等に努めることとしている。
協定に基づき、佐賀県唐津(からつ)市において、良品計画では初となる木造店舗の建設が進められており、令和6(2024)年8月以降の完成を予定している。木造でも大空間・大開口の実現が可能な工法を採用し、内装材には主に国産材を、外壁には佐賀県産材を現(あらわ)しで利用する計画であり、非住宅分野の建築物における木材利用のモデルになると期待されている。さらに、大分県日田(ひた)市でも木造店舗の建設が予定されており、今後も各地で協定に基づく木造店舗の整備が見込まれる。
(*31)「Cross Laminated Timber」の略。一定の寸法に加工されたひき板(ラミナ)を繊維方向が直交するように積層接着したもの。
(*32)公布から3年以内に施行することとしている。
(*33)農林水産省プレスリリース「「令和5年度 建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ」等について」(令和6(2024)年3月26日付け)
(エ)公共建築物等における木材利用
(公共建築物の木造化・木質化の実施状況)
公共建築物は、広く国民一般の利用に供するものであることから、木材を用いることにより、国民に対して、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供することができる。このため、建築物木材利用促進基本方針では、公共建築物について、積極的に木造化を促進することとしている。
令和4(2022)年度に着工された公共建築物の木造率(床面積ベース)は、13.5%となった。そのうち、低層(3階建て以下)の公共建築物の木造率は29.2%であり、平成22(2010)年の17.9%から10ポイント以上増加している(資料3-19)。都道府県ごとの低層の公共建築物の木造率については、4割を超える県がある一方、都市部では1~2割と低位な都府県がみられるなど、ばらつきがある状況となっている。
国が整備し令和4(2022)年度に完成した、積極的に木造化を促進するとされている公共建築物のうち、木造化された建築物は91棟であった。各省各庁において木造化になじまない等と判断し木造化されなかった公共建築物12棟について、林野庁と国土交通省が検証した結果、いずれも施設が必要とする機能等の観点から木造化が困難であったと評価され、木造化が可能であったものの木造化率は100%となった(*34)。
なお、令和4(2022)年度以降に設計に着手する国の公共建築物(*35)については、建築物木材利用促進基本方針に基づき、計画時点においてコストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、原則として全て木造化を図ることとしている。
(*34)農林水産省プレスリリース「「令和5年度 建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ」等について」(令和6(2024)年3月26日付け)
(*35)令和3(2021)年度末までに公表された設計着手前の基本計画等に基づき設計を行うものを除く。
(学校等の木造化・木質化を推進)
学校施設は、児童・生徒の学習及び生活の場であり、学校施設に木材を利用することは、木材の持つ高い調湿性、温かさや柔らかさ等の特性により、健康や知的生産性等の面において良好な学習・生活環境を実現する効果が期待できる(*36)。
このため、文部科学省では、学校施設の木造化や内装の木質化を進めており、令和4(2022)年度に新しく建設された公立学校施設のうち14.8%が木造で整備され、55.8%が非木造で内装の木質化が行われたことから、公立学校施設の70.6%で木材が利用された(*37)。また、文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省が連携して認定している「エコスクール・プラス(*38)」において、特に農林水産省は、内装の木質化等を行う場合に積極的に支援している。
(*36)林野庁「平成28年度都市の木質化等に向けた新たな製品・技術の開発・普及委託事業」のうち「木材の健康効果・環境貢献等に係るデータ整理」による「科学的データによる木材・木造建築物のQ&A」(平成29(2017)年3月)
(*37)文部科学省プレスリリース「公立学校施設における木材利用状況(令和4年度)」(令和6(2024)年1月16日付け)
(*38)学校設置者である市町村等が、環境負荷の低減に貢献するだけでなく、児童生徒の環境教育の教材としても活用できるエコスクールとして整備する学校を、関係省庁が連携協力して「エコスクール・プラス」として認定するもの。
(応急仮設住宅における木材の活用)
東日本大震災以前、応急仮設住宅のほとんどは鉄骨プレハブにより供給されていたが、東日本大震災においては木造化の取組が進み、25%以上の仮設住宅が木造で建設された(*39)。
東日本大震災における木造の応急仮設住宅の供給実績と評価を踏まえて、平成23(2011)年9月に、一般社団法人全国木造建設事業協会が設立された。同協会では、大規模災害後、木造の応急仮設住宅を速やかに供給する体制を構築するため、地方公共団体と災害時の協力に係る必要な事項等を定めた災害協定の締結を進め、令和6(2024)年2月までに、43都道府県及び11市と災害協定を締結している。
(*39)国土交通省調べ。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219