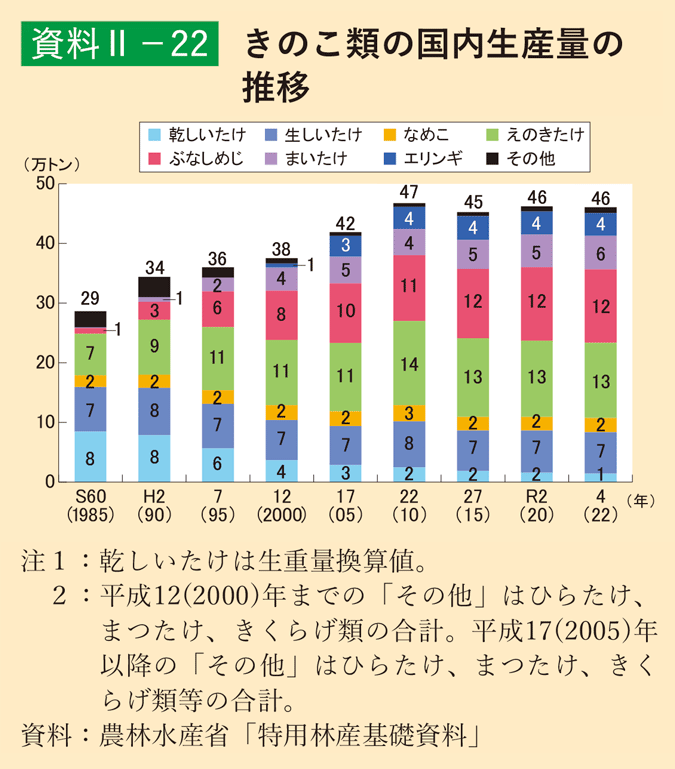第1部 第2章 第2節 特用林産物の動向(1)

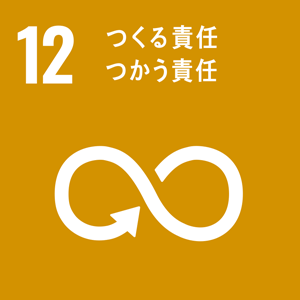

(1)きのこ類等の動向
(特用林産物の生産額)

「特用林産物」とは、一般に用いられる木材を除いた森林原野を起源とする生産物の総称であり、食用きのこ類、樹実類や山菜類、漆や木ろう等の工芸品の原材料、竹材、桐材、木炭、森林由来の精油や薬草・薬樹等多彩な品目で構成されている。その産出額は林業産出額の約4割を占めるなど地域経済の活性化や山村地域における所得の向上等に大きな役割を果たし、和食や伝統工芸品、日本建築に欠かせない素材であるとともに、近年は加工技術の発展により、新たな用途が開発されつつある。
令和4(2022)年の特用林産物の生産額は前年比1.9%増の2,658億円であった(*53)。このうち「きのこ類」は全体の8割以上(2,270億円)を占めている。このほか、樹実類、たけのこ、山菜類等の「その他食用」が288億円、木炭、漆等の「非食用」が101億円となっている。
(*53)林業産出額における栽培きのこ類等の産出額(庭先販売価格ベース)については、第1節(1)82ページを参照。なお、以下では、東京都中央卸売市場等の卸売価格等をベースにした農林水産省「令和4年特用林産基礎資料」に基づく生産額を取り扱う。
(きのこ類の生産額等)
きのこ類の生産額の内訳をみると、生しいたけが684億円で最も多く、次いでぶなしめじが477億円、まいたけが351億円の順となっている。
きのこ類の生産量については、近年46万トン前後で推移している。令和4(2022)年の生産量は、天候不順や生産者の減少により乾しいたけが前年比8.2%減となる一方、ぶなしめじが前年比2.8%増、まいたけが4.1%増となったこと等により、全体として横ばいの46.1万トンとなった(資料2-22)。食料・農業・農村基本計画(令和2(2020)年3月閣議決定)では、令和12(2030)年度までに49万トンとする生産努力目標を設定している。
令和4(2022)年の生産者戸数は約2.3万戸であり、そのうち約1.2万戸を占める原木しいたけ生産者については、高齢化の進行により減少傾向にあり、過去10年間で半減している。一方できくらげについては、近年の国産志向の高まりや技術開発の進展等により、生産者戸数が増加しており、約1千戸となっている(*54)。
(*54)農林水産省「特用林産基礎資料」
(きのこ類の安定供給に向けた取組)
きのこ類は、年間を通じて安定した価格で生産が可能であることや健康増進効果(*55)が広く認められていることなどから、日常の食卓に欠かせない食材であり、国内需要の89%が国内で生産されている。しかしながら、近年、生産コストの上昇がきのこ生産者の経営を圧迫している。このため、林野庁では、きのこ類の安定供給に向けて、効率的な生産を図るための施設整備等に対して支援しているほか、消費拡大や生産効率化などに先進的に取り組む生産者のモデル的な取組を支援している。また、令和5(2023)年度は、燃油・電気代や生産資材価格が高騰し、経営に影響が生じたことから、林野庁では、令和4(2022)年度に引き続き、省エネ化やコスト低減に向けた施設整備、次期生産に必要な生産資材の導入費の一部に対して支援した。特に、きのこ生産では夏場の冷房などに電気代がかかることから、電気代高騰の影響を大きく受けた生産者に対しては補助率を引き上げて支援した。
(*55)低カロリーで食物繊維が多い、カルシウム等の代謝調節に役立つビタミンDが含まれているなど。
(きのこ類の消費拡大に向けた取組)
令和4(2022)年におけるきのこ類の一人当たりの年間消費量は3.4kgであり、平成15(2003)年以降横ばいで推移している(*56)。一方、きのこ類の単価はほぼ横ばい若しくは低下傾向にある。きのこ類生産者団体や関係団体はきのこ類の消費拡大に向け、おいしさや機能性を消費者に伝えるPR活動を展開している(事例2-5)。また、一般社団法人日本きのこマイスター協会では、きのこマイスター認定講座を開設し、きのこの知識、機能、調理方法等について普及を図ることのできる人材を育成している。
近年、輸入菌床由来のしいたけの流通量が増加してきたことを受け、消費者が国産原木又は菌床由来のしいたけと輸入菌床由来のものとを区別できるようにするため、消費者庁は、令和4(2022)年3月に、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地として表示するよう原産地表示のルールを見直した。
また、生産者等において菌床やほだ木(*57)に国産材が使用されていることを表示するマーク等の取組も進められている。
事例2-5 きのこの消費拡大・食育に向けた取組
きのこに関する正しい知識の普及と消費拡大を目的に、日本特用林産振興会は、昭和63(1988)年から、きのこ料理コンクールを開催している。令和5(2023)年3月の全国大会では、応募総数1,277点の中から、群馬県みなかみ町(まち)の高校生が考案したレシピ「旨味たっぷりきのこ餃子の香味ソース」が、最高賞となる林野庁⾧官賞の一つに選出された。
みなかみ町では、地域の自然の恵みや郷土の食文化を学ぶ給食会を定期的に実施しており、同年9月には、この受賞レシピを、まいたけ等地元産きのこを用いて給食用にアレンジし、同町全ての小中学校やこども園等に提供した。給食会を通じてきのこに興味を持った児童たちがきのこの菌床栽培に取り組むなど、総合的な食育につながっている。
(*56)農林水産省「令和4年度食料需給表(概算)」
(*57)原木にきのこの種菌を植え込んだもの。
(きのこ類の輸出拡大に向けた取組)
近年、アジア各国における和食の普及や健康的な食生活への関心の高まりに伴い、香港等の近隣国向けに日本産の生鮮きのこ類の輸出量が拡大し、更に北米向け等が増加したことから、令和5(2023)年のきのこ類の輸出量は前年比2.1%増の1,537トンとなり、令和元(2019)年以降5年連続で増加している。一方、令和5(2023)年のきのこ類の輸出額については、輸出品目の中で高価格帯を占める原木乾しいたけが天候不順により不作だったこと等が影響して、前年比1.7%減の11億円となっている(*58)。
日本産の原木乾しいたけについては、古くから中国において高級品として人気があったが、為替の変動や中国における生産技術の向上等により、昭和59(1984)年をピークに大幅に輸出量が減少していた。しかし、近年の欧米におけるヴィーガンブームや、香港、台湾等の購買力の高まりに伴い、改めて日本産に注目が集まっている(事例2-6)。
林野庁では、きのこ類の輸出を促進するため、輸出に取り組む民間事業者に対して、輸出先国の市場調査や情報発信等の販売促進活動を支援している。令和5(2023)年は、台湾と米国において、乾しいたけの流通調査を行うとともに、展示即売会・試食会の開催を通して、その品質の良さや魅力のPRを行った。
また、きのこ類は栄養繁殖が可能であり増殖が容易であることから、生鮮きのこ類の輸出に当たっては、輸出先で無断培養されることにより、潜在的な輸出機会の喪失や、国内に逆輸入されることによる国内産地への影響が懸念される。このため、農林水産省では、主要なきのこ類のDNAデータベースを構築するなど、育成者権の保護に関する体制の整備に取り組んでいる。
なお、令和5(2023)年のきのこ類の輸入額は、前年比0.4%増の144億円(9,436トン)となっている。その多くが中国産の乾しいたけと乾燥きくらげで占められている(*59)。
事例2-6 乾しいたけの輸出に向けた取組
株式会社杉本商店(宮崎県高千穂町(たかちほちょう))は、乾しいたけの国内市場が縮小しても地元で生産される原木栽培による乾しいたけを安定的に販売できるよう輸出に力を入れている。海外での販売に当たっては、原木栽培がクヌギのぼう芽力を活かした循環型のビジネスモデルであること、原木乾しいたけは旨味・食感・食品安全性に優れていること等をSNSにより情報発信し、他国産より高価でも好調な売れ行きを示している。海外ではオーガニック食品の需要が高いことから、有機栽培にも力を入れており、令和元(2019)年には有機JAS認証を取得している。
また、近隣の福祉事業所と連携し、規格外の乾しいたけを使ったパウダーの生産販売にも取り組んでおり、幅広い料理に活用できることから、海外でも人気となっている。
これらの取組により、現在は、欧米を中心に累計23か国に販路を広げており、輸出で得られた利益を地元に還元することで産地と生産者を守り続けることにも貢献している。
(*58)財務省「貿易統計」。令和3(2021)年から、乾燥きくらげ類、調整きのこ、保存処理をしたきのこ及びしいたけ以外の乾燥きのこを集計項目に追加した。
(*59)財務省「貿易統計」
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219