第2章 林業と山村(中山間地域)









1.林業の動向
(1)林業生産の動向
林業産出額は近年増加傾向。2023年は5,563億円
➢ 我が国の林業産出額は増加傾向で推移。2023年は、製材用素材等の価格の低下や生産量の減少などから、前年比4.0%減の5,563億円
➢ このうち約6割を占める木材生産は前年比9.6%減の3,257億円
(2)林業経営の動向
1林業経営体当たりの素材生産量は増加し、林業経営体の規模拡大が進行

➢ 林家69万戸のうち保有山林面積が10ha未満の林家が88%を占め、小規模・零細な所有構造
➢ 林業経営体による素材生産量の約8割は森林所有者からの受託や立木買い。また、民間事業体や森林組合が素材生産全体の約8割を担っている状況
➢ 1林業経営体当たりの平均素材生産量は増加。年間素材生産量が1万m3以上の林業経営体による生産量が約7割を占めるまで伸展し、規模拡大が進行
➢ 森林組合数は607(2022年度)。森林整備の中心的な担い手であるが、規模の小さい組合も存在し経営基盤の強化が必要

事例 6つの森林組合が合併し「滋賀県森林組合」を設立
➢ 2024年6月に、滋賀県内の8つの森林組合のうち6つが合併し、組合員の保有する森林面積が約10万7,500ha(全国1位)の規模となる「滋賀県森林組合」を設立
➢ 合併により財政基盤や執行体制を強化し、ICT等の新技術の導入による効率的な施業や新たな事業展開に取り組むとともに、皆伐・再造林を促進。また、広域化による供給力の強化と併せて、近隣地域との連携により原木の安定供給に向けた取組を実施
(3)林業労働力の動向
労働力の確保に向けて「緑の雇用」事業等を推進
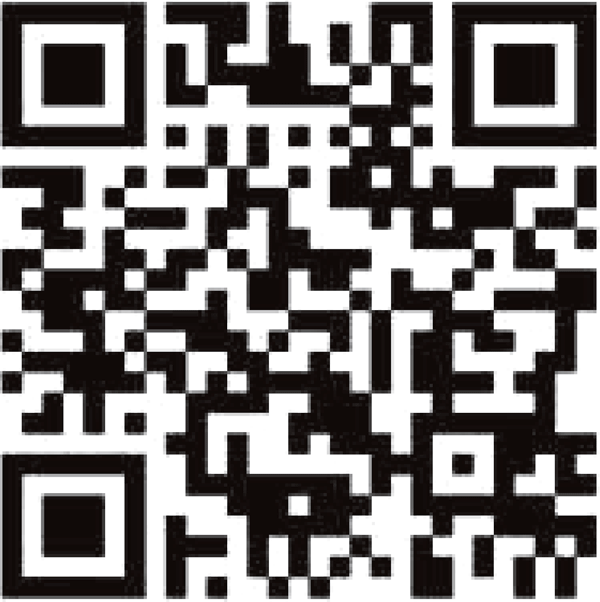
➢ 林業従事者数は、⾧期的には減少傾向であったが、近年横ばいに転じ、2020年は4.4万人。全産業の若年者率が低下する中、横ばいで推移
➢ 「緑の雇用」事業により新規就業者の確保・育成を図っており、これを活用した2023年度の新規就業者は778人。同事業による3年後の定着率は69.9%
➢ 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる特定技能制度について林業が対象分野として追加
➢ 林業の労働災害発生率は他産業に比べて高いため、安全衛生装備・装置の導入や、安全巡回指導等を推進
➢ 林業従事者の通年雇用化が進展し、年間平均給与も361万円(2022年)まで上昇しているが、全産業平均より100万円程度低い状況にあり、施業集約化や販売力強化等による経営体の収益力向上や技能検定を含む能力評価による処遇の改善等を推進
➢ 林業に従事する女性は2,730人(2020年)。女性が働きやすい環境整備の推進は、男性も含めた「働き方改革」にも貢献
(4)林業経営の効率化に向けた取組
生産性向上のための施業の集約化や収支をプラス転換する「新しい林業」に向けた取組を推進
施業の集約化


➢ 生産性向上やコスト低減等を図るためには、複数の所有者の森林を取りまとめ、路網整備や間伐等を一体的に実施する「施業の集約化」が必要
➢ 森林経営計画制度等により施業の集約化を推進
➢ 境界明確化に向けてはリモートセンシングデータを活用した測量等を支援
➢ 所有者が不明な森林に対しては、森林経営管理制度により、一定の手続を経て市町村が経営管理権を設定できる所有者不明森林等における特例措置を、2024年度末までに12市町において活用
➢ 所有者や境界の情報等を一元的に管理する林地台帳の活用や、都道府県での森林クラウドの導入など、林業経営体に対して施業の集約化に必要となる森林情報を提供する取組を推進
➢ 提案型集約化施業を行う「森林施業プランナー」の育成を支援
➢ 主伐・再造林の増加や木材の有利販売等の林業経営上の課題に対応して持続的な経営を実践する「森林経営プランナー」の育成を支援

「新しい林業」に向けて


➢ 林業は、造林から収穫まで⾧期間を要し、自然条件下での人力作業が多いことから、低い生産性や安全性の改善が課題
➢ 高性能林業機械の導入による生産性の向上等の従来の取組に加えて、新技術の活用により伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」に向けた取組を推進
➢ 収益性の向上につながる経営モデルの実証により、「新しい林業」の経営モデルの構築・普及の取組を支援
➢ 「新しい林業」を支える先端技術等の導入に向けて、自動運転や遠隔操作の機能を有する林業機械の開発・実証を推進
➢ 2023年度から、多様な関係者で構成される地域コンソーシアムが主体となり、地域一体で森林調査から原木の生産・流通に至る林業活動にデジタル技術をフル活用する「デジタル林業戦略拠点」の取組を3地域(北海道・静岡県・鳥取県)で支援

2.特用林産物の動向
(1)きのこ類等の動向
特用林産物は林業産出額の約4割。産出額の9割以上がきのこ類。
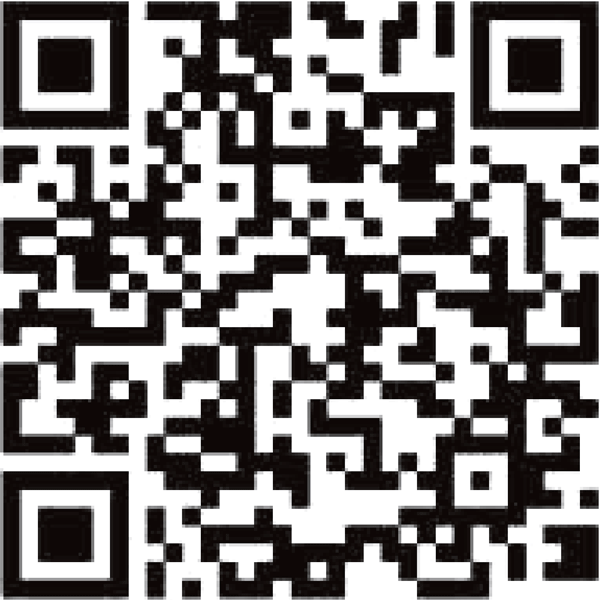
➢ 特用林産物は林業産出額の約4割。地域経済の活性化や山村地域における所得の向上等に大きな役割
➢ 特用林産物の産出額の9割以上がきのこ類で、2023年の生産量は天候不順や需要減を見込んだ生産調整等により前年比5.1%減の43.6万トン
➢ きのこ類は国内需要の89%を国内で生産。近年、燃油・電気代に加え、原木やおが粉の価格高騰等により生産資材の安定的・効率的な調達が困難な状況となっていることから、省エネ化等を図る施設整備や生産資材費の一部を支援。きのこ生産者の経営安定化に向け、おが粉の需給マッチング等も支援
➢ きのこ類の輸出量は海外における和食の普及や健康的な食生活への関心の高まりに伴い増加傾向だが、2024年は鮮度保持の課題等により前年比24.9%減の1,154トン
(2)薪炭・竹材・漆の動向
2023年の木炭、竹の生産量は前年より増加、薪の生産量も増加傾向で推移
➢ 2023年の木炭の生産量は、飲食店需要の回復等により、前年比19.9%増の2.0万トン。薪の生産量は、増加傾向で推移しており、2023年は前年比9.5%増の6.3万m3
➢ 竹材の生産量は、2017年以降減少傾向にあったが、2023年は前年比8.5%増の90万束。近年は、家畜飼料、土壌改良材、メンマ、洗剤など、竹資源の有効利用に向けた取組が進展
➢ 2023年の漆の生産量は、1.7トン。岩手県等の主要産地を中心にウルシ林が造成・整備
3.山村(中山間地域)の動向
(1)山村の現状
山村の地域資源に対し都市住民や地方移住希望者、外国人観光客から大きな関心
➢ 山村は、林業を始めとする様々な生業が営まれる場であり、森林の多面的機能の発揮に重要な役割
➢ 山村振興法に基づく「振興山村」は国土面積の約5割、林野面積の約6割。過疎化・高齢化が進行し、森林の荒廃等の問題が発生
➢ 山村の豊富な森林・水資源、景観、文化等に対しては、都市住民や地方移住希望者、外国人観光客から大きな関心
(2)山村の活性化
林業・木材産業の成⾧発展に加え、地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を支援


➢ ⼭村地域での⽣活を成り⽴たせていくためには、地域資源を活かした産業の育成等を通じた⼭村の内発的な発展が不可⽋。森林資源を活⽤して、林業・⽊材産業を成⻑発展させるほか、特⽤林産物、広葉樹、ジビエ等の地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を⽀援
➢ コミュニティの維持・活性化のため、地域住⺠や地域外関係者(関係⼈⼝等)による⾥⼭林の継続的な保全管理や利⽤等の協働活動を促進
➢ 林業⾼校・林業⼤学校等への進学、「緑の雇⽤」事業によるトライアル雇⽤等を契機とした移住・定住を促進
➢ 健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を利⽤しようとする動きを受け、森林空間における体験プログラムの提供等により、⼭村地域に収⼊・雇⽤の機会を⽣み出し、関係⼈⼝の創出・拡⼤にもつながる「森林サービス産業」の創出を推進
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219














