第1章 森林の整備・保全









1.森林の適正な整備・保全の推進
(1)我が国の森林の状況と多面的機能
森林の多面的機能がSDGsや2050年ネット・ゼロ等の目標達成、GXの実現、国土強靱化に寄与

➢ 森林面積は国土面積の約3分の2。このうち約4割を占める人工林は、約6割が50年生を超え、本格的な利用期
➢ 森林蓄積は人工林を中心に年々増加し、2022年3月末時点で約56億m3。森林は、水源涵養、山地災害防止・土壌保全、地球温暖化防止、林産物の供給等の多面的機能を通じて、国民生活・国民経済に寄与
➢ 森林の多面的機能がSDGsや2050年ネット・ゼロの目標達成に貢献。木材を建築物等で利用することで⾧期間炭素が貯蔵される効果も
➢ クリーンエネルギー中心の産業構造・社会構造に転換するグリーントランスフォーメーション(GX)の実現に向けて、吸収源の機能強化と森林由来素材を活かしたイノベーションを促進
➢ 災害に対する国土強靱化に向けて、きめ細かな治山ダムの配置等による土砂流出の抑制や再造林の確実な実施等を行うことで、森林の国土保全機能の維持・発揮を推進
(2)森林の適正な整備・保全のための森林計画制度
全国森林計画等により、森林の整備・保全を計画的に推進


➢ 森林・林業基本計画(2021年6月閣議決定)では、森林の整備・保全や林業・木材産業等の事業活動等の指針とするための「森林の有する多面的機能の発揮」並びに「林産物の供給及び利用」に関する目標や、森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を規定
➢ 森林法に基づく全国森林計画(2023年10月策定)、森林整備保全事業計画(2024年5月策定)、地域森林計画、市町村森林整備計画等により、森林の整備・保全を計画的に推進
➢ 2024年5月に策定された森林整備保全事業計画では、2024年度から2028年度までの5年間における森林整備や治山事業の実施の目標及びその達成状況を測定する成果指標等を設定

(3)研究・技術開発及び普及の推進
「林業イノベーション現場実装推進プログラム」に基づき、林業イノベーションを推進
➢ 「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略」において、造林等の省力化・低コスト化、気候変動への対応、CLTの利活用技術の開発等、研究・技術開発における対応方向等を明確化
➢ 「林業イノベーション現場実装推進プログラム」に基づき、自動運転や遠隔操作の機能を有する林業機械の開発・実証、エリートツリー等の開発・普及等を推進。同プログラムを推進するため、必要な組織・人材・情報が集まる場として、2023年に「森ハブ・プラットフォーム」を設置。林業だけでなく、製造業やサービス業などの異分野を含む幅広い業種が参画
➢ 自動運転や遠隔操作の機能を有する林業機械の実用化及び普及に向けて安全対策検討会を設置し、2025年4月に「林業機械の遠隔操作に関する安全性確保ガイドライン~Ver. 1.0~」を公表
➢ 各都道府県に配置された林業普及指導員は、森林所有者への技術・知識の普及等を行い、森林総合監理士(フォレスター)は地域の森林づくりの全体像を示すとともに、市町村林政の技術的支援等を実施


事例 林業普及指導員によるリモートセンシングデータの活用支援
➢ 鳥取県では、市町村の森林経営管理制度の実務を支援するため「鳥取県森林経営管理支援センター」を設置
➢ 林業普及指導員が中心となり、森林境界明確化の効率化や地籍調査に資するリモートセンシングデータの活用を推進。同データを活用した森林境界明確化や地籍調査に取り組む市町村が増える中、森林経営管理制度の更なる進展に向け、林業普及指導員による市町村への支援が期待
2.森林整備の動向
(1)森林整備の推進状況
森林の多面的機能の発揮に向け、間伐や再造林等の森林整備を推進
➢ 森林の多面的機能の発揮に向け、間伐や主伐後の再造林等の森林整備を確実に行うことが必要。また、自然条件等に応じて針広混交林化等を推進するなど、多様で健全な森林への誘導も必要
➢ 2023年度の主な森林整備の実施状況は、人工造林面積3.5万ha、保育、間伐等の森林施業面積44万ha
➢ 適正な森林施業を確保するため、市町村森林整備計画において、標準的な森林施業等の方法を示すとともに、伐採造林届出制度を運用
(2)再造林の着実な実施
再造林の省力化・低コスト化や成⾧に優れた種苗の供給を推進
➢ 森林の有する公益的機能の発揮や森林資源の持続的な利用を確保していくためには、適正な伐採と再造林を着実に進めていくことが必要。2050年ネット・ゼロに向けて、中⾧期的な森林吸収量の確保・強化が必要となっている一方で、二酸化炭素吸収量は減少傾向にあり、再造林が進んでいないことが課題
➢ 再造林の省力化と低コスト化に向けて「伐採と造林の一貫作業システム」や、低密度植栽、下刈りの省略等を推進。2023年度の省力・低コスト造林実施面積の割合は54%
➢ 再造林の推進には、苗木の安定供給が重要。2023年度の苗木の生産量は、約6,600万本と近年横ばい傾向。このうち、コンテナ苗は5割
➢ 成⾧に優れたエリートツリー等のうち、成⾧量、材質、花粉量が一定の基準を満たすものを特定母樹として、573種類(2025年3月末時点)を指定。特定母樹を増殖する事業者の認定や採種園・採穂園の整備を推進
(3)花粉発生源対策
花粉発生源対策に数値目標を設定し、対策を加速化

➢ 2023年、政府は「花粉症対策の全体像」を決定し、「花粉症対策初期集中対応パッケージ」を取りまとめ
➢ 花粉発生源対策の目標として、2033年度に花粉発生源となるスギ人工林を約2割減少。将来的(2023年度から約30年後)には花粉発生量を半減
➢ そのため、伐採・植替え等の加速化、スギ材の需要拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、生産性向上と労働力の確保等の対策を総合的に推進する必要
➢ 重点的に伐採・植替え等を実施する区域(スギ人工林伐採重点区域)約98万haを設定し、森林の集約化を進め、伐採・植替えの一貫作業の実施やそのために必要な路網整備を推進
➢ 2023年度の花粉の少ないスギ苗木の生産量は約1,800万本で、2012年度から大幅に増加(スギの苗木の生産量の約6割)
(4)路網の整備
森林整備の基盤となる路網の整備とともに、路網の強靱化・⾧寿命化を推進
➢ 効率的な森林施業や木材の安定供給に対応した林道など、森林整備の基盤となる路網整備を推進
➢ 山地災害の激甚化や走行車両の大型化等に対応するため、路網の強靱化・⾧寿命化を推進

(5)森林経営管理制度及び森林環境税・森林環境譲与税
森林経営管理制度による取組や森林環境譲与税の活用は増加
森林経営管理制度
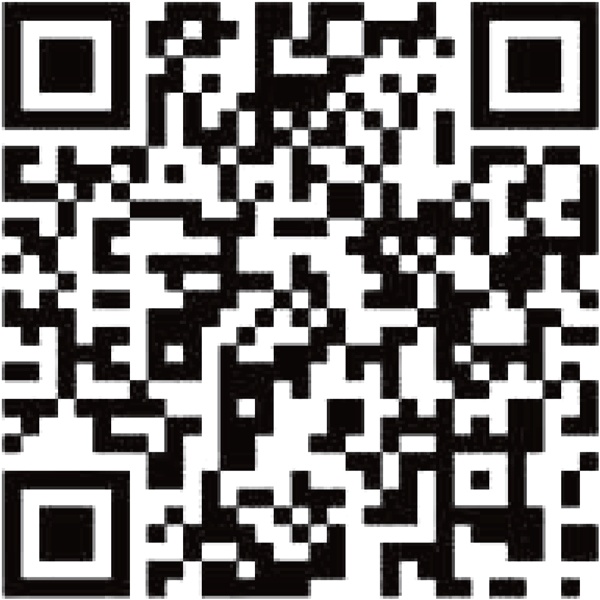
➢ 2019年4月に森林経営管理法が施行され、森林経営管理制度が導入
➢ 市町村が行う森林所有者への意向調査を踏まえ、経営管理の委託を受けた場合には、林業経営に適した森林は、地域の林業経営者に再委託され、主伐・再造林も含む森林整備を実施。林業経営に適さない森林は、市町村が自ら管理
➢ 制度の推進に当たっては、周辺市町村の関係者との連携による体制整備や都道府県等による市町村支援等、地域の状況に応じて様々な取組が展開
森林環境税・森林環境譲与税

➢ 2019年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設。森林環境税は2024年度から課税開始、森林環境譲与税については、2019年度から先行して市町村及び都道府県へ譲与開始
➢ 森林環境譲与税の譲与額は段階的に引き上げられ、2024年度以降は平年度で約600億円
➢ 活用額は年々増加してきており、2023年度は464億円。2023年度の間伐等の森林整備面積は初年度の約9倍となるとともに、上下流などの地方公共団体間が連携した取組も進展
➢ 譲与基準については、2024年度から私有林人工林面積の譲与割合を5/10から55/100、人口の譲与割合を3/10から25/100に見直し
市町村に対する⽀援
➢ 国は地域林政アドバイザー制度の活用推進等により市町村の体制整備等を支援
(6)社会全体で支える森林(もり)づくり
多様な主体による森林(もり)づくりや、森林分野のクレジット化等の取組を推進

➢ 「第74回全国植樹祭」は岡山県、「第47回全国育樹祭」は福井県で開催
➢ 「森林×ACT(アクト)チャレンジ」により、カーボンニュートラルへの貢献や生物多様性保全等の観点から企業等による森林(もり)づくりを促進
➢ J-クレジット制度における森林管理プロジェクトの登録件数の累計は261件、クレジット認証量の累計は139.6万CO2トン(2025年3月末時点)となり、前年度より77.1万CO2トン増加の大幅な伸び
➢ J-クレジットは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく算定・報告・公表制度(通称:SHK制度)における報告やカーボン・オフセット等に利用可能
➢ 森林と人々の生活や環境との関係についての理解と関心を深める森林環境教育の取組が推進


事例 森林由来J-クレジットの創出から販売まで一気通貫でサポートするプラットフォームを提供
➢ 全国森林組合連合会及び農林中央金庫は、森林由来J-クレジット創出をサポートするプラットフォーム「FC BASE-C」に続いて、2024年3月に、同クレジットの販売をサポートするプラットフォーム「FC BASE-M」を開設
➢ FC BASE-C及びFC BASE-Mにより、森林由来J-クレジットの創出から販売まで一気通貫によるサポートが可能
➢ FC BASE-Mの第一号案件として、大阪府森林組合及び一般社団法人大和森林管理協会が創出した森林由来J-クレジットが、西日本旅客鉄道株式会社が展開するカーボンオフセットプログラムと連携させる形で販売
3.森林保全の動向
(1)保安林等の管理及び保全
保安林制度等を適切に運用するとともに、盛土等による災害防止に向けた取組を推進

➢ 公益的機能の発揮が特に要請される森林を保安林に指定し、伐採、土地の形質の変更等を規制。保安林以外の民有林において一定規模を超える開発が行われる場合は、林地開発許可制度を適切に運用
➢ 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)により、土地の用途(宅地、森林、農地等)や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制
(2)山地災害等への対応
早期復旧に向けた迅速な対応を行うとともに、防災・減災、国土強靱化に向けた取組を推進
➢ 治山事業は、森林の維持・造成を通じて森林の機能を維持・向上させ、山地災害等から国民の生命・財産を守ることに寄与
➢ 気候変動の影響により、短時間強雨の増加や、線状降水帯の発生等による総降水量の増加に伴い、山地災害が激甚化。2024年の主な山地災害は、令和6年能登半島地震や梅雨前線による大雨。山地災害等に伴う被害額は約1,759億円。
➢ 大規模な被害が発生した際には、早期復旧に向けて、ヘリ等を活用した被害状況調査を行うとともに、職員派遣等による技術的支援及び災害復旧等事業を実施
➢ 令和6年能登半島地震により発生した大規模な山腹崩壊の復旧のため、2024年3月から林野庁直轄による復旧事業を開始
➢ 流域治水とも連携しつつ、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(2020年12月閣議決定)等に基づき、土石流等の山地災害等リスクが高い山地災害危険地区の実施率向上等をKPIとして設定し、治山対策を計画的に推進
(3)森林被害対策の推進
野生鳥獣被害や、松くい虫被害、ナラ枯れ被害等への対策を実施
➢ 野生鳥獣による森林被害は依然として深刻であり、約6割がシカによる被害
➢ 防護柵の設置やシカの捕獲等の対策を実施。2023年度は72.3万頭(前年度比0.8%増)のシカを捕獲したが、2028年度までの半減目標達成(2011年度比)に向けて、シカの生息頭数が増加している地域等を中心に捕獲を強化
➢ 松くい虫被害は、⾧期的に減少傾向にあるものの、我が国最大の森林病害虫被害。2023年度は夏季の高温少雨等により前年度比26.7%増の31.5万m3。薬剤等による予防、被害木の伐倒による駆除、抵抗性マツの植栽等を推進
➢ ナラ枯れ被害は2023年度に北海道、2024年度に愛媛県で初確認されるなど被害区域が拡大しており、特に守るべき樹木及びその周辺において、粘着剤の塗布やビニールシート被覆等による侵入予防、被害木くん蒸による駆除等を推進
➢ 2025年2月から3月にかけては、岩手県大船渡市を始めとして、岡山県岡山市や愛媛県今治市などの各地で林野火災が相次いで発生
コラム 岩手県大船渡市における林野火災への対応
➢ 2025年2月下旬に発生した岩手県大船渡市における林野火災は、約2,900ha(2025年3月28日時点調査中)の林野が焼損する甚大な被害。林野庁では、岩手県に対して迅速な情報収集や技術支援のためのMAFF-SATを派遣したほか、森林被害の状況確認のため、岩手県と合同でヘリコプター調査を実施
➢ 被災者の生業の再建に向けては、被災した高性能林業機械及び特用林産施設の整備等への支援等を実施していく方針
➢ 被災した森林の再生に向けては、激甚災害に指定されたことから、森林災害復旧事業により、被害木等の伐採・搬出、被害木等の伐採跡地における造林等に対して支援等を実施していく方針
4.国際的な取組の推進
(1)持続可能な森林経営の推進
世界の森林面積は依然として減少傾向、我が国は持続可能な森林経営に向けた取組を推進

➢ 2020年の世界の森林面積は41億ha(陸地面積の31%)で、アフリカ、南米等の熱帯林を中心に依然として減少
➢ 我が国は、国連森林フォーラム(UNFF)、「モントリオール・プロセス」等の国際的議論に参画。「G7広島サミット」等において、持続可能な森林経営のみならず、木材利用の促進の重要性についても認識
➢ 持続可能な森林経営がされていることを認証する森林認証は、国際的な「FSC認証」と「PEFC認証」、我が国独自の「SGEC認証」(PEFC認証と相互承認)等が存在。我が国の認証森林の割合は1割程度であり、認証面積は増加傾向
(2)地球温暖化対策と森林
地球温暖化対策計画の目標達成に向け、森林吸収源対策を推進

➢ 2050年ネット・ゼロの実現に向け、地球温暖化対策計画(2025年2月閣議決定)では、2035年度及び2040年度の我が国の温室効果ガス排出削減目標をそれぞれ60%削減、73%削減(2013年度排出量比)に設定
➢ 森林吸収量については、算定方法を国際的な標準に合わせ、全国レベルの森林調査(NFI)データを活用した直接推計による方法へ見直し。これにより、2040年度の目標は同上比5.1%確保
➢ この目標の達成に向け、森林の適切な整備、管理・保全、木材利用の推進が重要
➢ 開発途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減等(REDD+)の取組や、気候変動適応計画(2023年5月閣議決定)等に基づく取組を推進

(3)我が国の国際協力
JICAを通じた技術協力、国際機関を通じたプロジェクト等の支援を実施
➢ JICAを通じた技術協力・研修等や、資金協力による造林、人材の育成等の活動支援、森林管理のための機材整備等の実施のほか、生態系を活用した防災・減災機能の強化の技術開発等を推進
➢ 国際機関(FAO、ITTO)を通じたプロジェクトの支援等により、対象国及び世界における森林減少抑止、持続可能な森林経営や木材利用、気候変動対策等を推進


事例 パプアニューギニアにおける森林の減少と劣化に由来する温室効果ガス排出削減のための支援
➢ パプアニューギニアにおいては、商業伐採等による森林の減少と劣化が温室効果ガスの主な排出源となっており、持続可能な森林経営の実施が必要
➢ 2022年開始のJICA技術協力プロジェクトでは、専門家を派遣し、(ア)商業伐採における伐採関連規則の遵守、(イ)伐採後の森林資源の回復、(ウ)伐採事業により排出される炭素量のモニタリング手法開発の3つの分野で技術協力や研修等を実施
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219
















