第1部 特集 第3節 生物多様性を高める林業経営と木材利用に向けて(3)
(3)持続的な経営から生産される木材の利用に向けて
(民間企業に持続可能な木材利用への配慮を求める動き)
生物多様性を高める林業経営が持続的に行われていくためには、そこから生産される木材が需要者に評価され、利用されていくことが重要である。近年、持続可能な開発目標(SDGs)の認知度の向上やESG投資の拡大など、消費者を含めた社会全体に環境意識が浸透しつつあり、建築物への木材利用(*36)による地球温暖化防止への貢献等の効果に対して期待が高まっている。このような中、2023年9月のTNFD提言等の動きを受けて、民間企業においては、自らの自然資本への依存度を評価した上で、企業活動に必要な原材料の調達の際に生物多様性の保全や持続可能な木材利用に配慮することが求められている。
建築物等に木材を利用する事業者等においては、建築資材等として使用する木材について、違法伐採木材であるなどのリスクを回避するため、輸入材から国産材に転換を図る動きもみられる(資料 特-25)。また、「気候変動」や「生物多様性」の課題への対応として、建築物の木質化や国産材の活用に取り組んでいることを企業が情報開示する例もある(資料 特-26)。このように企業における建築物等への木材利用の拡大により、木材利用への関心が更に広がることも期待される。
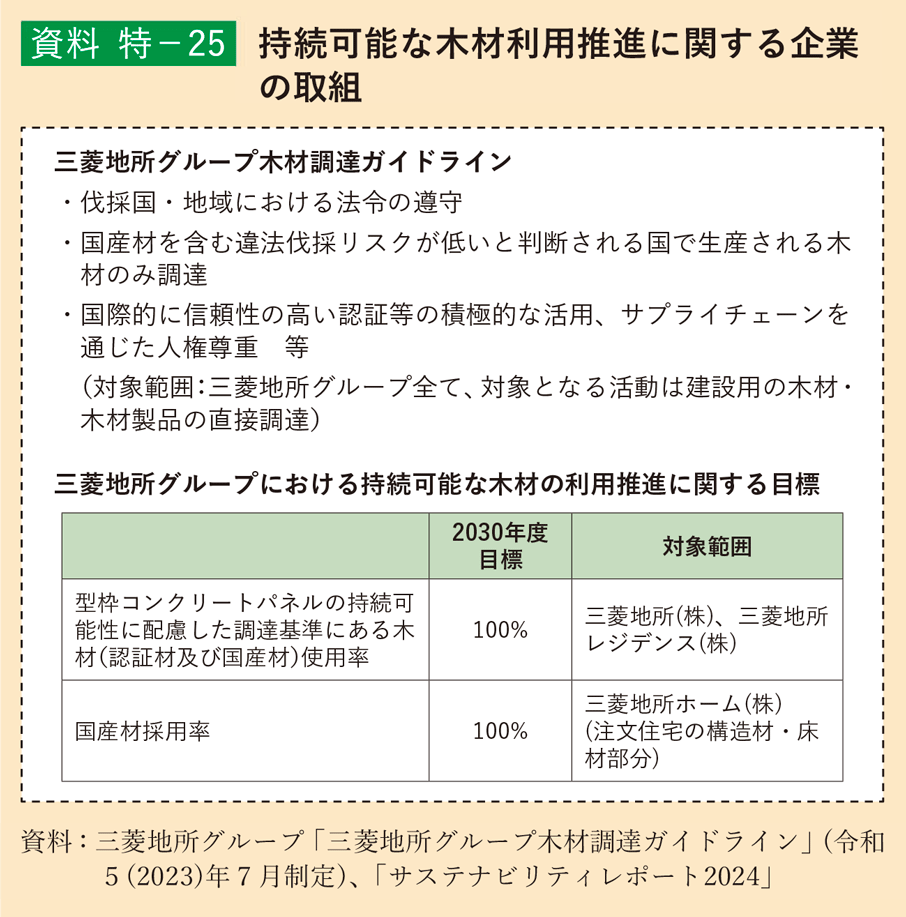
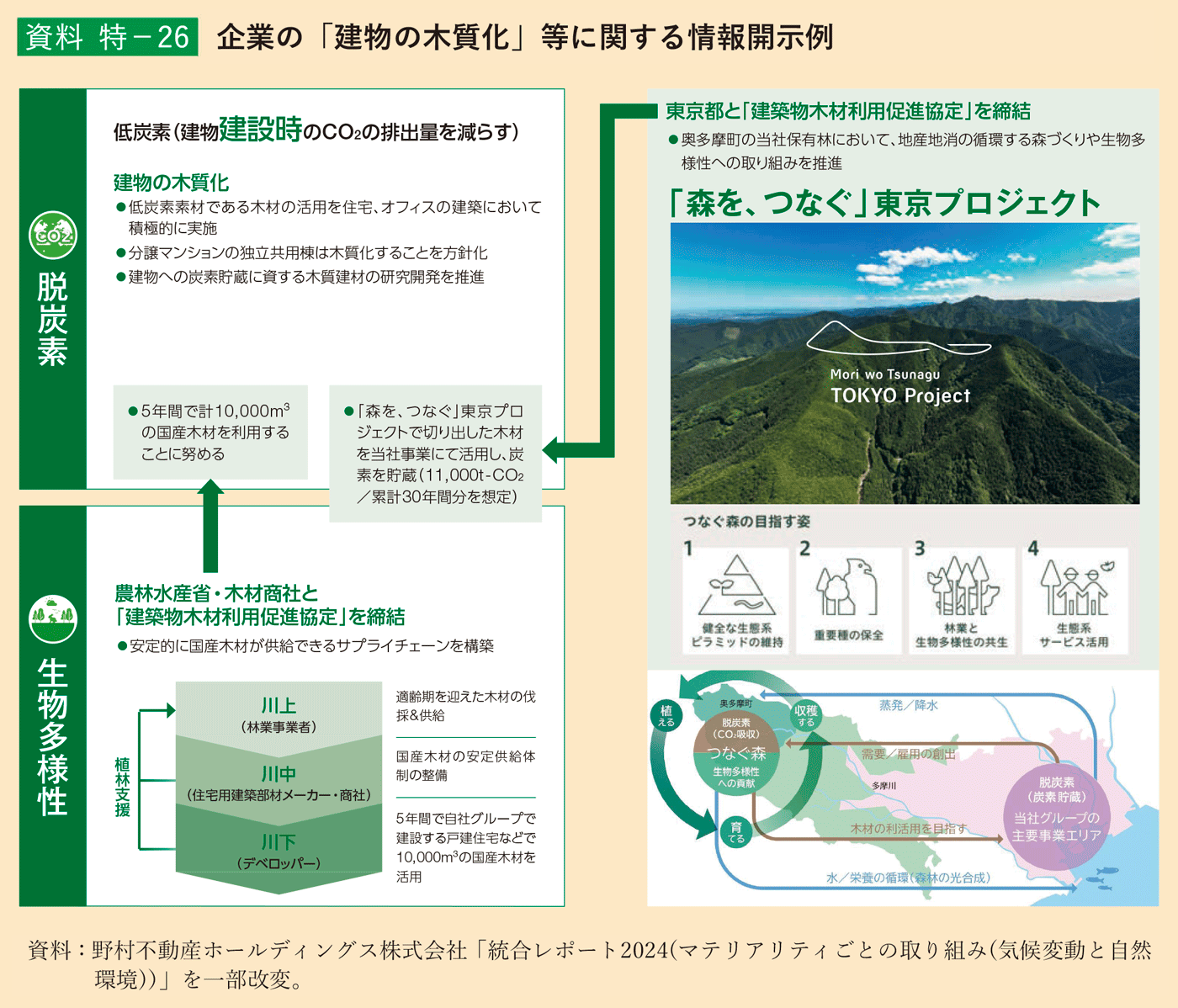
林野庁では、令和6(2024)年3月に「建築物への木材利用に係る評価ガイダンス」を作成・公表し、建築物に木材を利用する企業等が情報開示において木材利用の効果を評価し訴求する際の参考となる評価項目・評価方法を示した(*37)。ガイダンスでは、評価項目として、デュー・デリジェンス(*38)の実施による「持続可能な木材の調達」を挙げており、評価方法として、利用する木材について、合法性と共に森林の伐採後の更新の担保を確認できるものであること、又は、森林認証制度(*39)に基づき認証・評価されたものであることのいずれかであることなどを提示している。
他方で、林業事業体等が持続的な経営を実現していくためには、主伐後の再造林や保育に係る経費を賄えるだけの木材販売収入が必要であり、それに対する川中・川下の関係者を含めた相互理解も重要である。中には、川上から川下までの事業者が、再造林等の費用を織り込んだ水準で木材の取引価格を設定し、再造林に係る費用や負担を透明化した形で協定を締結している例もみられる(*40)。
(*36)木材利用の意義については、第3章第2節(1)150-151ページを参照。
(*37)建築物への木材利用に係る評価ガイダンスについては、第3章第2節(2)161ページを参照。
(*38)木材に関するデュー・デリジェンスは、利用する木材が合法性、生物多様性、人権などに配慮した持続可能な方法で生産・流通されたものであることを確認することを指す。「企業又は事業者が果たすべき注意義務」や「要求される相当の注意」のように訳されることが多い。
(*39)森林認証については、第1章第4節(1)92-93ページを参照。
(*40)具体例については、「令和5年度森林及び林業の動向」第3章第2節(2)の事例3-2(137ページ)を参照。
(持続可能な木材利用に向けて)
サプライチェーンの中で、生物多様性の観点も含めて持続的な経営が行われている森林から生産される木材を選択的に利用できることは、林業経営側・木材利用側の双方からみて重要である。
「建築物への木材利用に係る評価ガイダンス」では、持続可能な木材の調達に関する評価に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(以下「クリーンウッド法」という。)(*41)を活用できることとしており、同法では、木材関連事業者(*42)が木材を調達する際に合法性を確認するために活用できる書類として、伐採及び伐採後の造林の届出書や森林経営計画の認定書等が位置付けられている。今後はクリーンウッド法に基づく合法性確認への対応に加え、森林経営計画において生物多様性に関連する取組事項を示すことにより、木材の流通過程でその情報を伝達していくことも、生物多様性の確保と森林経営の持続可能性が図られている木材として選択的利用を促す有効な手段となり得る。
また、同ガイダンスでは、森林認証制度についても評価に活用できるものとしている。そのうち、我が国独自の森林認証制度である「SGEC認証」では、持続可能な森林管理の要求事項として、「森林生態系における生物多様性の維持、保全及び適切な増進」や「森林の社会的・経済的機能の維持及びその適切な増進」等の6つの基準と、「モニタリングによるパフォーマンス評価と改善」等が定められており、生物多様性と森林経営の持続可能性を一体のものとして評価している。
このように、生物多様性の観点も含めて持続的な経営が行われている森林から生産される木材が、需要者に評価され、その利用が拡大していくことは、山元の利益の確保や伐採後の再造林等にもつながり得るものであり、我が国の森林の生物多様性を更に高めることに貢献する。
(*41)クリーンウッド法については、第3章第1節(4)147-148ページを参照。
(*42)木材等の製造、加工、輸入、販売等を行う者。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219




