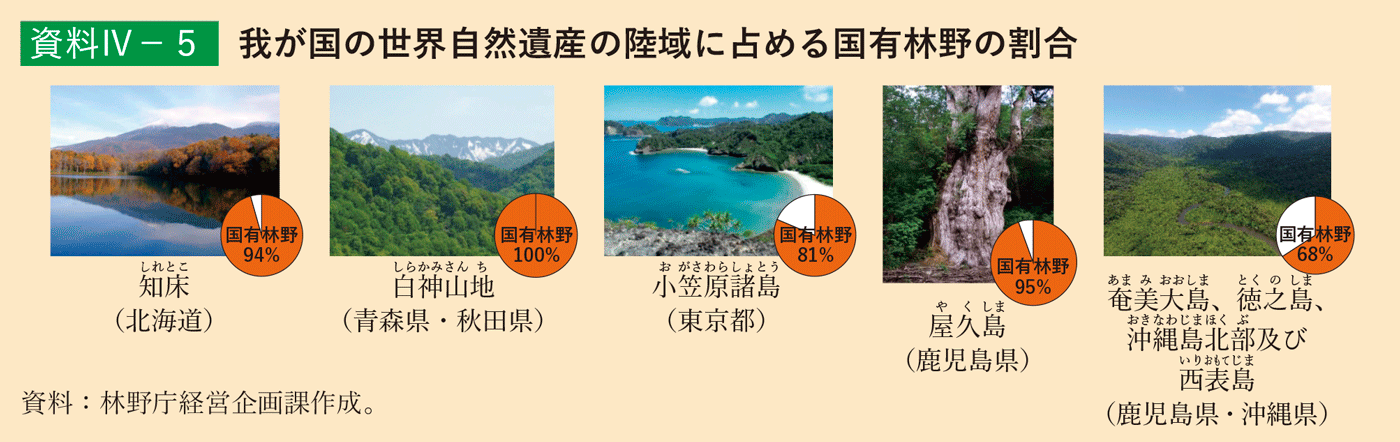第1部 第4章 第2節 国有林野事業の具体的取組(1)
(1)公益重視の管理経営の一層の推進
(ア)重視すべき機能に応じた管理経営の推進
(機能類型区分に応じた森林施業等の推進)
国有林野事業では、管理経営基本計画に基づき公益重視の管理経営を一層推進するという方針の下、国有林野を、重視すべき機能に応じて「山地災害防止タイプ」、「自然維持タイプ」、「森林空間利用タイプ」、「快適環境形成タイプ」及び「水源涵(かん)養タイプ」の5つに区分している(資料4-3)。木材等生産機能については、これらの区分に応じた適切な施業の結果として、計画的に発揮するものと位置付けている。
また、間伐の適切な実施や主伐後の確実な更新を図るほか、複層林への誘導や針広混交林化を進めるなど、多様な森林を育成するとともに、林地保全や生物多様性保全に配慮した施業及び花粉発生源対策に取り組んでいる。
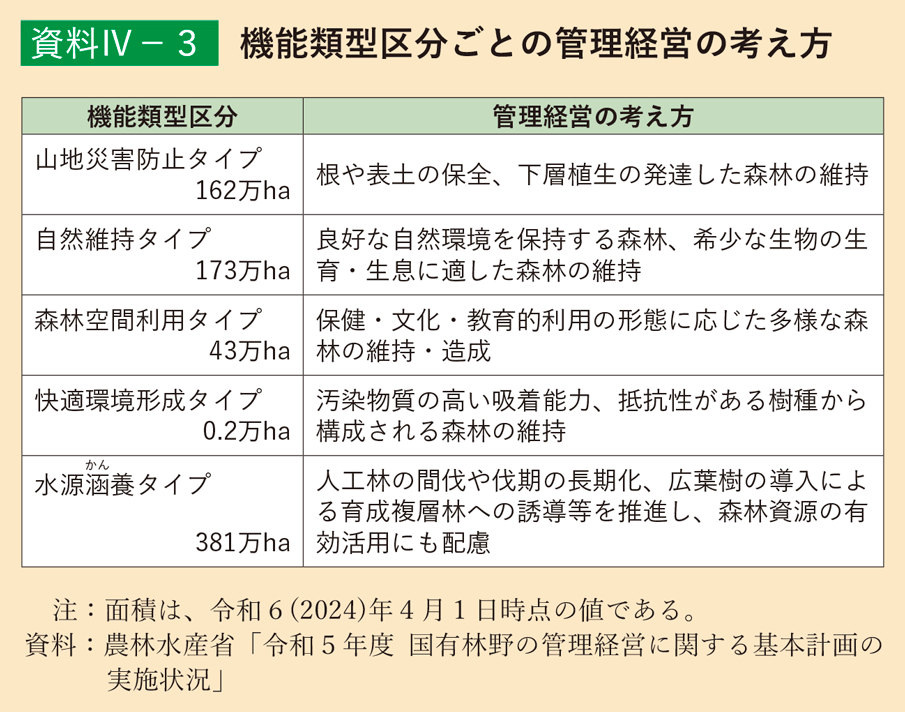
(治山対策の推進)
国有林野には、公益的機能を発揮する上で重要な森林が多く存在し、令和5(2023)年度末時点で面積の約9割に当たる686万haが水源かん養保安林や土砂流出防備保安林等の保安林に指定されている。これら保安林において、森林の造成等を通じて森林の機能を維持・向上させ、山地災害等から国民の生命・財産を守ることに寄与するため、機能の低下した森林の整備、集中豪雨や台風等により被災した山地の復旧整備等を推進する「国有林治山事業」を行っている(事例4-1)。
さらに、民有林野においても、事業規模の大きさや高度な技術の必要性を考慮し、国土保全上特に重要と判断されるものについては、都道府県からの要請を踏まえ、「民有林直轄治山事業」を行っており、令和6(2024)年度は16県22地区の民有林野でこれらの事業を行っている。
このほか、大規模な山地災害が発生した際には、専門的な知識・技術を有する職員の被災地派遣やヘリコプターによる被害調査等を実施し、地域への協力・支援に取り組んでいる。
事例4-1 令和6年7月25日からの大雨における治山施設の効果
秋田県湯沢(ゆざわ)市の南部に位置する峠(とうげ)の沢(さわ)は、直下に、秋田県と山形県をつなぐ重要な幹線である国道13号とJR奥羽本線が並走している。平成30(2018)年8月に発生した豪雨により当該渓流が荒廃し鉄道付近まで土砂が押し寄せたため、秋田森林管理署湯沢支署は、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により下流の国道・鉄道等の保全に寄与する復旧治山工事を実施し、令和4(2022)年までに2基の治山ダムを完成させた。
その後の令和6(2024)年に発生した令和6年7月25日からの大雨では、北日本を中心に土砂災害や河川氾濫などの被害が発生した。秋田県においても、県内77か所で山地災害が発生する中、峠の沢では、設置した2基の治山ダムが渓岸・渓床の侵食を防止し、渓流を安定させるとともに下流への土砂流出を抑制した結果、国道や鉄道等への被害が防止された。
(路網整備の推進)
国有林野事業では、機能類型に応じた適切な森林の整備・保全や林産物の供給等を効率的に行うため、自然条件や作業システム等に応じて林道及び森林作業道を適切に組み合わせた路網の整備を進めている。このうち、基幹的な役割を果たす林道については、令和5(2023)年度末における路線数は1万3,498路線、総延⾧は4万6,248kmとなっている。
(イ)地球温暖化対策の推進
国有林野事業では、中⾧期的な森林吸収量の確保・強化に向けて、主伐後の確実な再造林や、適切な保育等の森林施業に取り組んでおり、令和5(2023)年度には約0.9万haの植栽や約13万haの保育等の森林施業を実施した。
(ウ)生物多様性の保全
(国有林野における生物多様性の保全に向けた取組)
国有林野における生物多様性の保全を図るため、国有林野事業では「保護林」や「緑の回廊」を設定し、モニタリング調査等を通じて適切な保護・管理に取り組んでいる(資料4-4)。また、地域の関係者等との協働・連携による森林生態系の保全・管理や自然再生、希少な野生生物の保護等の取組を進めている。
なお、我が国が目指す30by30目標の達成に向けては、保護地域(*1)としての国立公園等の新規指定・拡張への対応を進めるとともに、保護地域以外でも生物多様性の保全に資する管理経営を行っており、今後、保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域(OECM)の設定等について適切に対応することとしている。
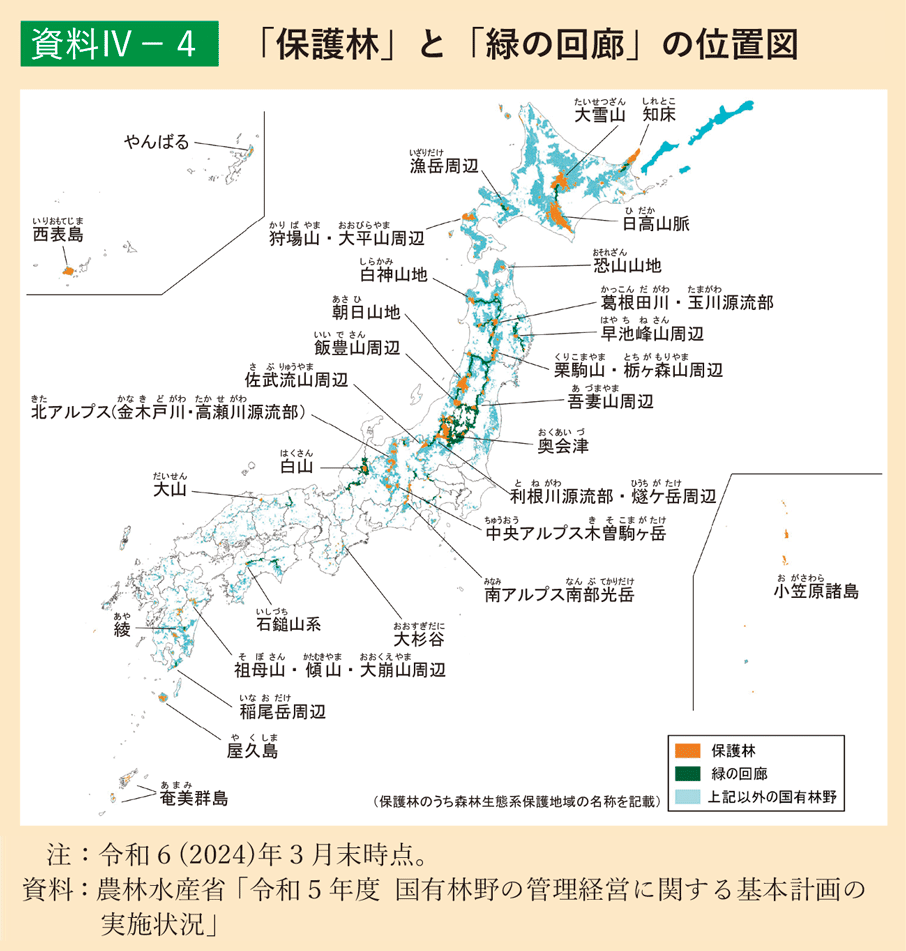
(*1)陸域については自然公園、自然海浜保全地区、自然環境保全地域、鳥獣保護区、生息地等保護区、近郊緑地特別保全地区、特別緑地保全地区、保護林、緑の回廊、天然記念物、都道府県が条例で定めるその他保護地域。
(保護林の設定)
国有林野事業では、我が国の気候又は森林帯を代表する原生的な天然林や地域固有の生物群集を有する森林、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を「保護林」に設定し厳格に保護・管理している。令和6(2024)年3月末時点の保護林の設定箇所数は658か所、設定面積は101.6万haとなっており、国有林野面積の13.4%を占めている。
(緑の回廊の設定)
野生生物の生育・生息地を結ぶ移動経路を確保することにより、個体群の交流を促進し、種の保全や遺伝的多様性を確保することを目的として、国有林野事業では、保護林を中心にネットワークを形成する「緑の回廊」を設定している。令和6(2024)年3月末時点で、国有林野内における緑の回廊の設定箇所数は24か所、設定面積は58.3万haであり、国有林野面積の7.7%を占めている。
(世界遺産等における森林の保護・管理)
我が国の世界自然遺産は、その陸域の86%が国有林野であり、国有林野事業では、遺産区域内の国有林野のほとんどを「森林生態系保護地域」(保護林の一種)に設定し、関係する機関と共に厳格に保護・管理している(資料4-5)。
例えば、「白神山地(しらかみさんち)」(青森県及び秋田県)の国有林野では、世界自然遺産地域への生息範囲拡大が懸念されるシカや、その他の中・大型哺乳類に関する生息・分布調査のため、センサーカメラによる調査を実施している。また、「屋久島(やくしま)」(鹿児島県)の国有林野では、植生等のモニタリング調査、ヤクシカによる植生への被害対策、湿原の保全対策やヤクスギの樹勢診断等に取り組んでいる。このほか、「小笠原諸島(おがさわらしょとう)」(東京都)の国有林野では、アカギやモクマオウなどの外来種の駆除を実施した跡地に在来種の植栽や種まきを行うなど、小笠原諸島固有の森林生態系の修復に取り組んでいる。
世界遺産のほか、我が国では令和7(2025)年3月時点で、みなかみユネスコエコパーク(群馬県及び新潟県)等10地域が「ユネスコエコパーク(*2)」に登録されており、国有林野事業では、ユネスコエコパークが所在する国有林野の適切な保護・管理等を行っている。
(*2)生物圏保存地域(Biosphere Reserve)の国内呼称。生態系の保全と持続可能な利活用の調和(自然と人間社会の共生)を目的として、「保全機能(生物多様性の保全)」、「経済と社会の発展」、「学術的研究支援」の3つの機能を有する地域を登録。
(希少な野生生物の保護等)
国有林野事業では、希少な野生生物の保護を図るため、野生生物の生育・生息状況の把握、生育・生息環境の維持・改善等に取り組んでいる。また、自然環境の保全・再生を図るため、地域、ボランティア、NPO等と連携し、生物多様性についての現地調査、荒廃した植生回復等の森林生態系の保全等の取組を実施している。
さらに、国有林野内の優れた自然環境や希少な野生生物の保護などを行うため、環境省や都道府県の環境行政関係者との連絡調整や意見交換を行いながら、自然再生事業実施計画(*3)や生態系維持回復事業計画(*4)等を策定し、連携した取組を進めている。
(*3)自然再生推進法に基づき、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とし、地域の多様な主体が参加して、森林その他の自然環境を保全、再生若しくは創出し、又はその状態を維持管理することを目的とした自然再生事業の実施に関する計画。
(*4)自然公園法に基づき、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るために、国又は都道府県が策定する計画。
(鳥獣被害対策等)
シカ等の野生鳥獣による森林被害は依然として深刻であり、希少な高山植物等、他の生物や生態系への脅威にもなっている。このため、国有林野事業では、防護柵の設置のほか、GPSや自動撮影カメラ等によるシカの生息・分布調査や被害調査、委託事業や職員による捕獲、効果的な捕獲技術の実用化や捕獲後の処理の効率化等の対策に取り組んでいる(事例4-2)。また、職員が考案した「小林式誘引捕獲法」については、各森林管理局で開催する現地検討会等を通じて普及を図っている。さらに、地域の関係者等と協定を締結し、国有林野内で捕獲を行う地域の猟友会等にわなを貸し出して捕獲を行うなど、地域全体で取り組む対策を推進している。このほか、松くい虫等の病害虫の防除にも努めている。
事例4-2 大型排水管を用いたシカ捕獲個体の埋設処理の効率化
ニホンジカについては、農林業被害対策として全国的に積極的な捕獲が進められている。一方で、山中で捕獲しジビエ利用等されない個体については、捕獲者自らが搬出して焼却施設に持ち込むか、その場で穴を掘り埋設処理する必要がある。これらが捕獲を実施する上での大きな負担となっており、その解消が喫緊の課題となっている。
こうした状況を踏まえて、和歌山森林管理署では、埋設処理の効率化に向け、林道脇のスペースに大型排水管(直径1m、⾧さ4m)を縦置きで埋設し、その中に捕獲個体と発酵促進剤(ぼかし剤)を投入し、自然分解により減容化してから残渣さを埋設する実証試験に取り組んでいる。これまでの実証結果では、残渣(さ)のかさ高は捕獲個体を累計で約100頭投入した場合でも1m程度となっており、個体処理の効率化が期待できる。また、従来の埋設処理と違い、クマやイノシシなどに掘り返されることがないという利点もある。
このような大型排水管を用いた残渣(さ)減容化については、多くの地方公共団体等が注目している取組であるものの事例は少ないことから、和歌山森林管理署では、今後、排水管を抜き取り、土を埋め戻す作業のコストや周辺の土壌水成分への影響についても調査を行うなど、実証を重ねつつ更なる改良と普及を目指すこととしている。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219