第1部 特集 第3節 花粉発生源対策の加速化と課題(4)
(4)花粉の少ない苗木の生産拡大
スギ人工林の伐採・植替えに併せて、植替えに必要となる花粉の少ない苗木の生産拡大が必要である。「花粉症対策の全体像」では、10年後には花粉の少ないスギ苗木の生産割合をスギ苗木の生産量の9割以上に引き上げることを目指している。
(種穂の供給及び苗木の生産体制の整備)
山林に植栽する苗木を生産するには、(ア)林木育種センターが原種園(*34)等で管理している樹木から挿し木等により原種苗木を増殖し、都道府県等へ配布する、(イ)都道府県等はこの原種苗木を採種園・採穂園に植栽・育成して母樹とし、その母樹から採取した種穂を苗木生産事業者へ供給する、(ウ)苗木生産事業者はこの種穂から苗木を生産する、という工程が必要となる(資料 特-22)。
花粉の少ない苗木の生産拡大のためには、これらの各生産過程における生産量を増加させる必要があることから、林木育種センターにおける原種苗木増産施設、都道府県等における採種園・採穂園、苗木生産事業者におけるコンテナ苗生産施設の整備を進めるなど、官民を挙げて花粉の少ない苗木の生産体制の強化を進めている。
さらに、国有林野事業においては、花粉の少ない苗木の生産拡大を後押しする観点から、苗木生産の関係者等に対し、数年先までの花粉の少ない苗木の必要数の見通しを提示するなどの取組を推進している。
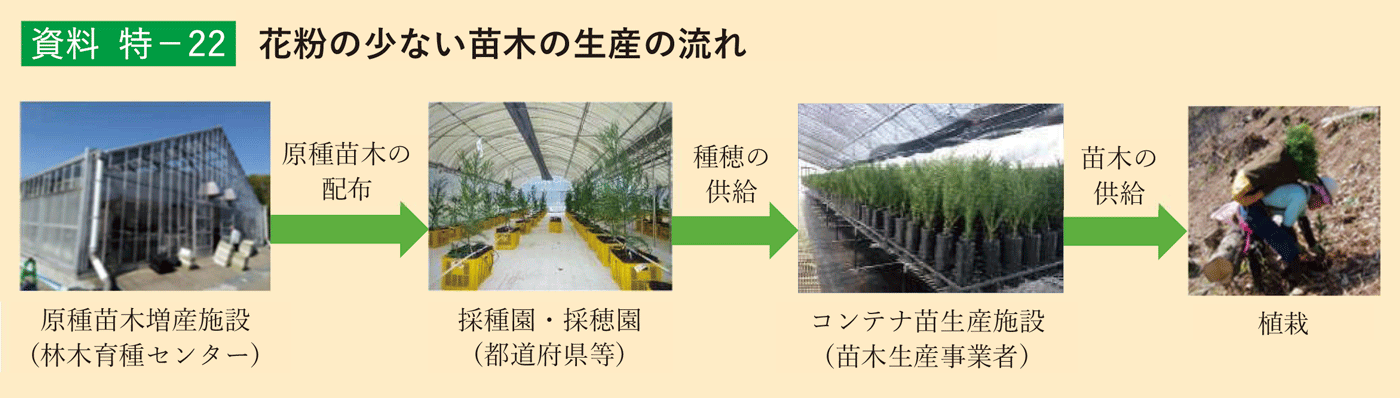
(*34)花粉の少ない品種等の原種を管理・保存するために整備された圃場。
(その他の技術開発の取組)
無花粉スギ品種については、種子により生産する手法と挿し木により生産する手法がある。種子により生産する場合、無花粉品種同士では種子を生産できないため、無花粉スギを種子親、無花粉遺伝子を持つ有花粉のスギを花粉親として交配させる。無花粉の特性は潜性遺伝であるため、この交配により得られた種子は50%の割合で無花粉スギになる。この手法では、花粉親の候補木が無花粉遺伝子を持つかをあらかじめ判別する必要があるが、無花粉遺伝子の有無を判別するDNAマーカー(*35)が開発されており、それを用いることでこれまでよりも判別が容易かつ広範に行えるようになり、無花粉遺伝子を持つ精英樹が全国で20以上新たに発見されている。それらの無花粉遺伝子を持つ精英樹を花粉親とすることにより、成⾧等に優れた無花粉スギの更なる開発が期待されているほか、多数の花粉親の候補木があることで、日本各地の多様な気候条件に適応した無花粉スギ品種の開発が見込まれている。
さらに、花粉の少ない苗木を早期に大量に得るために、細胞増殖技術を活用してスギの未熟種子からスギ苗木を大量増産する技術の開発を推進している。
(*35)DNA鑑定において、個体間の差異を調べることができる目印となる特定のDNA配列。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219




