第1部 特集 第3節 花粉発生源対策の加速化と課題(3)
(3)スギ材需要の拡大
スギ人工林の伐採・植替えを加速化する上で、スギ材の需要を拡大することは不可欠である。「花粉症対策の全体像」では、住宅分野におけるスギ材製品への転換の促進や木材活用大型建築の新築着工面積の倍増等の需要拡大対策を進め、スギ材の需要を現状の1,240万m3(*24)から10年後までに1,710万m3に拡大することを目指すとしている。
(*24)平成31(2019)年から令和3(2021))年におけるスギの素材生産量の平均。
(住宅分野)
我が国の木造戸建住宅の工法で最も普及している木造軸組工法において、スギを用いた製材や集成材は柱材等に一定のシェアを有し、スギを用いた構造用合板は面材に高いシェアを有している。一方、例えば、梁(はり)や桁といった横架材では、スギよりも曲げヤング率(*25)の高い米(べい)マツの製材やヨーロッパアカマツの集成材等が好んで利用されていることなどにより、スギ材製品の利用は低位となっている。また、国内の木造の新設住宅着工戸数の約2割のシェアを占める枠組壁工法(ツーバイフォー工法)においても、枠組材としてのスギ材製品の利用は低位となっている(*26)。
このため林野庁では、国産材率の低い横架材やツーバイフォー工法部材等について、スギ材の利用拡大に向けた技術開発を進めるとともに、スギ材を活用した集成材、LVL(*27)(単板積層材)、製材の柱材や横架材等を効率的かつ安定的に生産できる木材加工流通施設の整備を推進することとしている(資料 特-17)。あわせて、スギJAS構造材(*28)等の利用を促進することとしている。
さらに、国土交通省、林野庁及び関係団体が連携して、国産材を多く活用した住宅であることを表示する仕組みの構築や、住宅生産者による花粉症対策の取組の見える化等により、2050年カーボンニュートラルの実現や花粉症対策に関心のある消費者層への訴求力を向上していくこととしている(資料 特-18)。


(*25)ヤング率は材料に作用する応力とその方向に生じるひずみとの比。このうち、曲げヤング率は、曲げ応力に対する木材の変形(たわみ)のしにくさを表す指標。
(*26)住宅分野における木材利用の動向については、第3章第2節(2))130-132ページを参照。
(*27)「Laminated Veneer Lumber」の略。単板を主としてその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着したもの。
(*28)JAS構造材については、第3章第3節(2))152-153ページを参照。
(非住宅・中高層建築分野)
林野庁では、製材やCLT(*29)(直交集成板)、木質耐火部材等に係る技術の開発・普及や、公共建築物の木造化・木質化、木造建築に詳しい設計者の育成、標準的な設計や工法等の普及によるコストの低減等を推進している(資料 特-19)。また、国土交通省では、耐火基準の見直しなど、建築物における木材利用の促進に向けた建築基準の合理化を進めている。
さらに、施主の木材利用に向けた意思決定に資する取組として、林野庁では、建築コスト・期間、健康面等における木造化のメリットの普及や、建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量を表示する取組を推進するとともに、国土交通省では、建築物に係るライフサイクルカーボンの評価方法の構築を進めている(*30)。
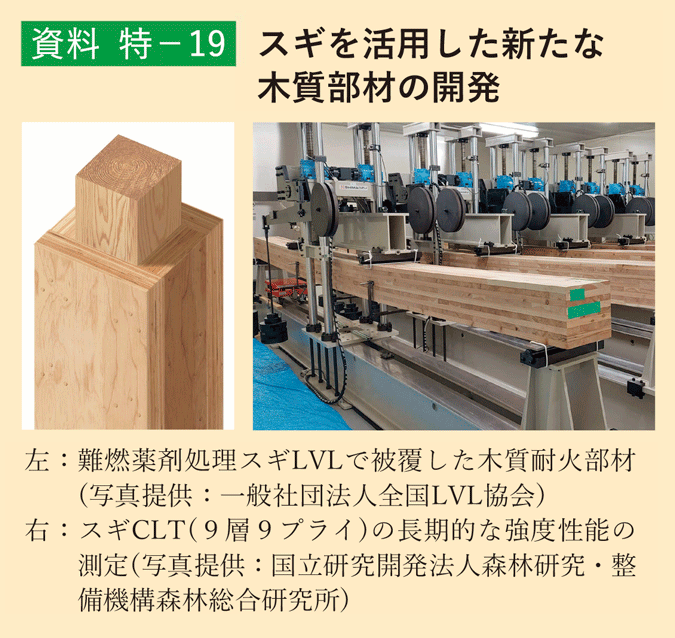
(*29)「Cross Laminated Timber」の略。一定の寸法に加工されたひき板(ラミナ)を繊維方向が直交するように積層接着したもの。
(*30)非住宅・中高層建築分野における木材利用の動向については、第3章第2節(2)132-137ページを参照。
(内装・家具等への対応や輸出の拡大)
このほか、スギ材の需要拡大に資する取組として、スギ材の持つ軽さ、柔らかさ、断熱性、調湿作用、香り等の特性を活かして建築物の内外装や家具類等にスギ材を活用する取組もみられる(*31)(資料 特-20、資料 特-21)。また、情報発信や木材に触れる体験の提供等により、スギ材を含めた木材の良さや木材利用の意義を消費者等に普及する取組も行われている(*32)。
さらに、農林水産省では、製材及び合板を重点品目として、海外市場の獲得に向けた輸出先国・地域の規制やニーズに対応した取組により輸出を促進することとしている(*33)。
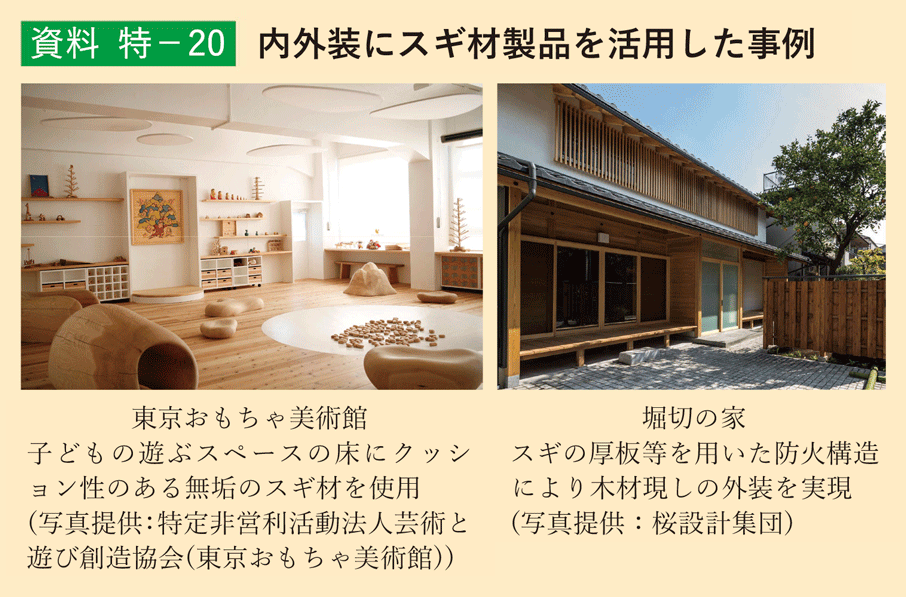

(*31)内装・家具分野における需要拡大については、第3章第3節(3)157-158ページを参照。
(*32)消費者等に対する木材利用の普及については、第3章第2節(4)144-147ページを参照。
(*33)木材輸出の促進については、第3章第2節(5)147-148ページを参照。
(需給の安定化)
スギ材の供給量の増加により、一時的に木材需給の安定性に影響が生じることも想定されるため、上記の需要拡大策に加え、ストック機能強化に向けた製品保管庫や原木ストックヤードの整備を促進することとしている。また、林地残材を含む地域内の低質材の需要確保に資する木質バイオマスエネルギーの利用拡大に取り組むこととしている。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219




