第1部 特集 第3節 花粉発生源対策の加速化と課題(1)
(1)これからの花粉発生源対策
(関係閣僚会議が「花粉症対策の全体像」を決定)
これまで各省庁で様々な取組が行われてきたが、今もスギ花粉症の有病率は高く、多くの国民が悩まされ続けている状況となっている。
そのため、令和5(2023)年4月、政府は「花粉症に関する関係閣僚会議」を設置し、同年5月に「花粉症対策の全体像」を決定した。その中では、花粉の発生源であるスギ人工林の伐採・植替え等の「発生源対策」や、花粉飛散量の予測精度向上や飛散防止剤の開発等の「飛散対策」、治療薬の増産等の「発症・曝(ばく)露対策」を3本柱として総合的に取り組み、花粉症という社会問題を解決するための道筋を示している。
同年10月には、花粉症に関する関係閣僚会議において、「花粉症対策の全体像」が想定している期間の初期の段階から集中的に実施すべき対応を「花粉症対策 初期集中対応パッケージ」として取りまとめた(資料 特-13)。
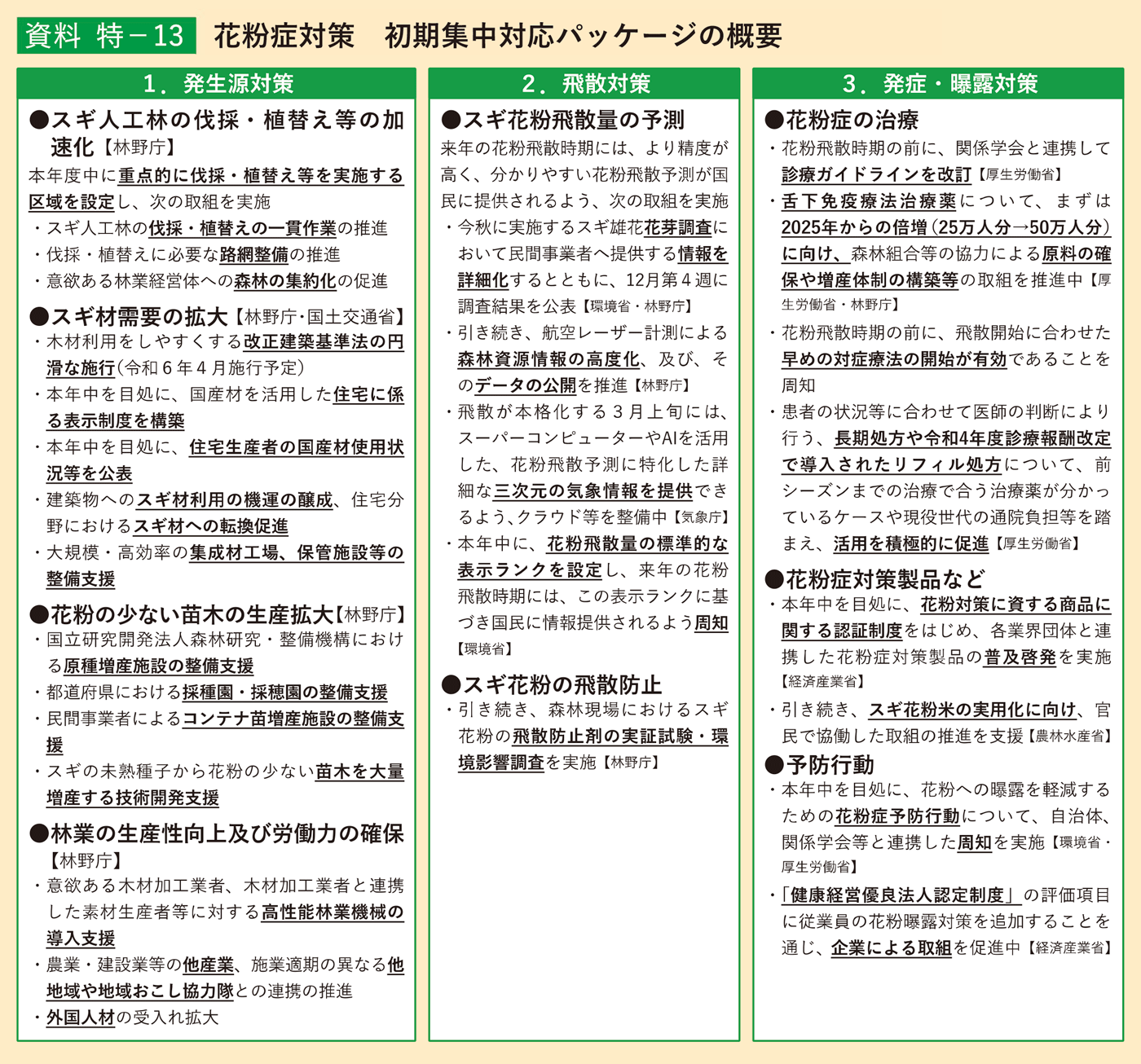
(花粉発生源対策の目標)
「花粉症対策の全体像」において、10年後の令和15(2033)年には花粉発生源となるスギ人工林を約2割減少させることを目標としている(資料 特-14)。これにより、花粉量の多い年でも過去10年間(平成26(2014)年~令和5(2023)年)の平年並みの水準まで減少させる効果が期待される。また、将来的(約30年後)には花粉発生量の半減を目指すこととしている。
これを実現するため、スギ人工林の伐採量を増加させるとともに、花粉の少ない苗木や他樹種による植替えを推進することとしている。
花粉を発生させるスギ人工林の減少を図っていくためには、伐採・植替え等の加速化、スギ材の需要拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、生産性向上と労働力の確保等の対策を総合的に推進する必要がある(資料 特-15)。
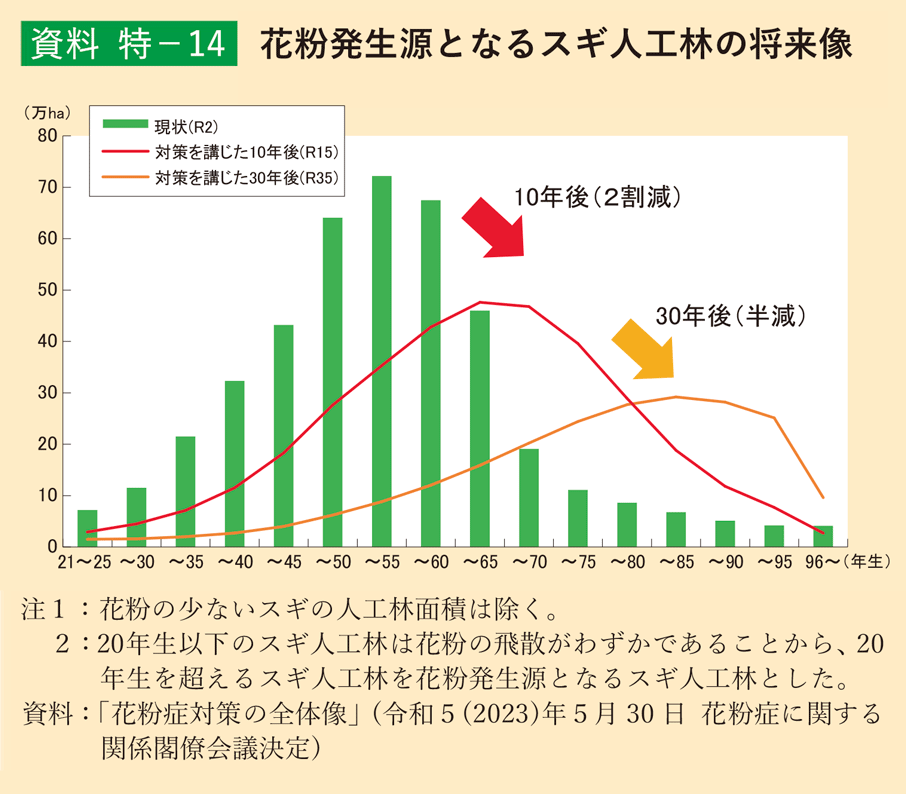
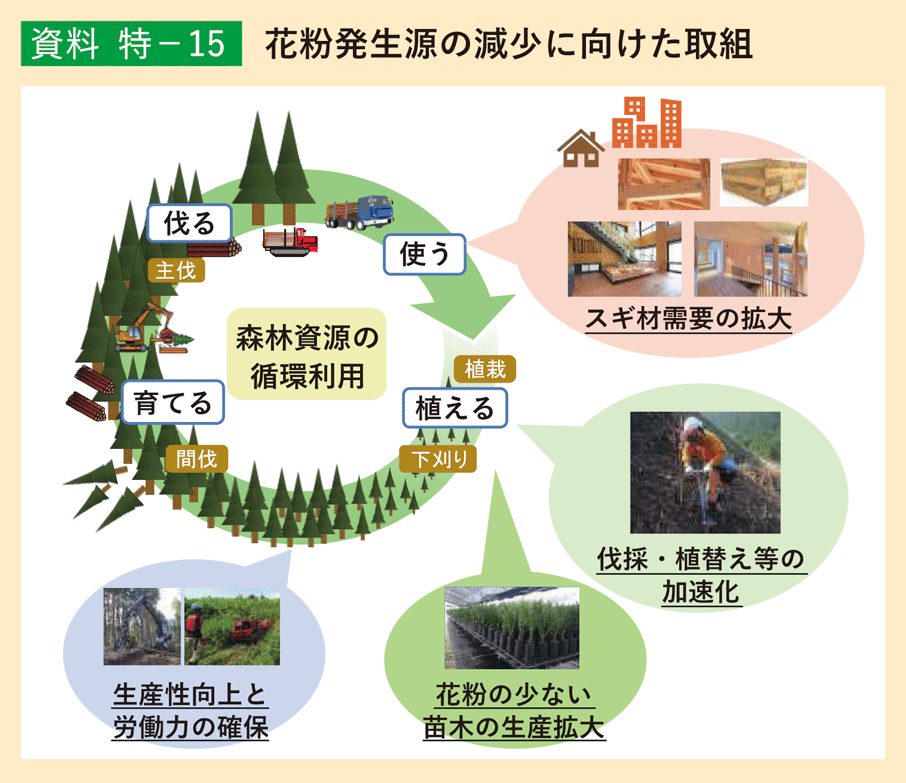
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219




