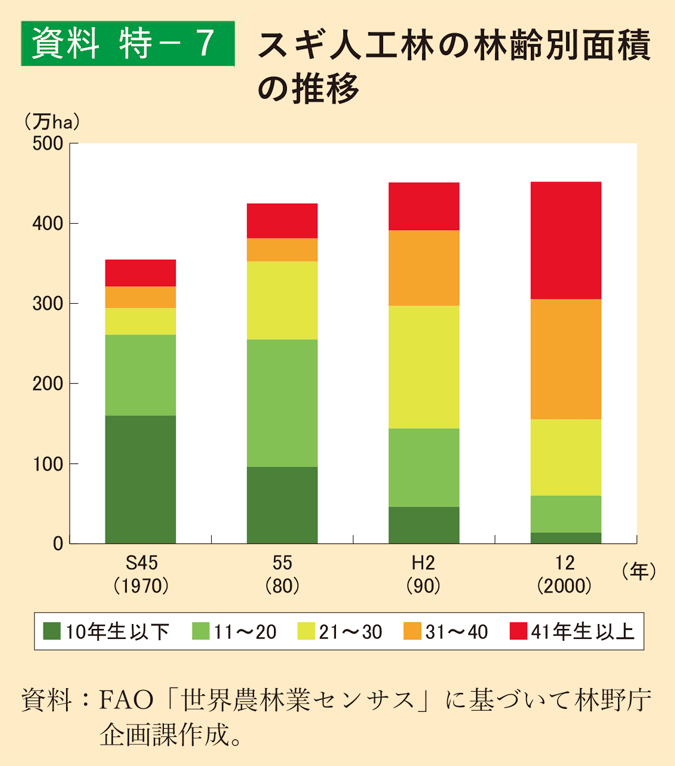第1部 特集 第2節 スギ等による花粉症の顕在化と対応(1)
(1)顕在化してきたスギ等の花粉症
(世界における花粉症の発見)
19世紀の英国において、夏に目のかゆみなどの結膜炎症状や、くしゃみ、鼻水等の鼻炎症状を発症する例が報告された。この症状は新しい干し草の匂いによって発症するとの説によって干し草熱(hay fever)と呼ばれるようになり、その後の研究によってイネ科の牧草等の花粉が症状を引き起こすことが確認された。また、同時期の米国では、秋に同様の症状を発症する者がみられるようになり、研究の結果、開拓地等の荒地に繁茂するようになったブタクサ等の花粉が原因であることが確認された(*4)。
その後、シラカバやハンノキ等のカバノキ科、ブナやナラ等のブナ科の樹木等も花粉症を引き起こすことが知られるようになり、現在はこれらの草本及び樹木による花粉症がヨーロッパや米国で人々の生活に影響を与えている。また、世界各国で様々な植物の花粉を原因とする花粉症が報告されるようになっている(*5)。
(*4)斎藤洋三・井出武・村山貢司「花粉症の科学」(2006)、小塩海平「花粉症と人類」(2021)
(*5)Björkstén B Clayton T, Ellwood P, Stewart A, and Strachan D and the ISAAC Phase III Study Group. Worldwide timetrends for symptoms of rhinitis and conjunctivitis: Phase III of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Pediatric Allergy and Immunology 2008; 19(2): 110-124.
(我が国におけるスギ花粉症の初確認と増加)
我が国においても、明治時代には花粉症は枯草熱の名称で紹介されていたが、日本人における症例は⾧く報告されなかった。日本初の花粉症患者の報告はブタクサ花粉症について昭和36(1961)年に報告されたものである(*6)。最初のスギ花粉症の報告は昭和39(1964)年になされ、栃木県日光地方で春にくしゃみ等を発症した患者を研究した結果、スギ花粉をアレルゲンとする花粉症であると結論付けられた(*7)。
スギ花粉症患者の数を正確に把握することは困難だが、耳鼻咽喉科医及びその家族約2万人を対象とした全国的な疫学調査によれば、有病率は平成10(1998)年の16%から約10年ごとに約10ポイントずつ増加し、令和元(2019)年には39%に達していると推定された(資料 特-5)。
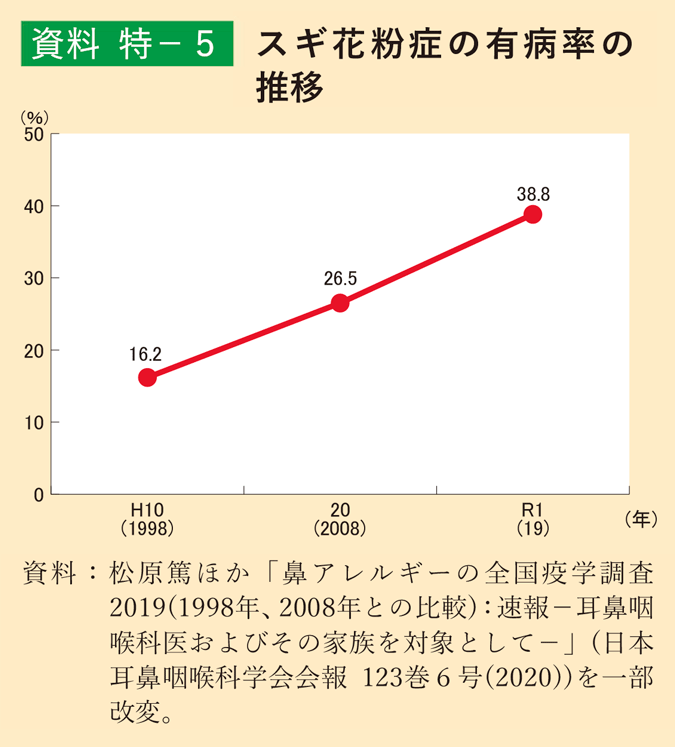
(*6)荒木英斉「花粉症の研究2 花粉による感作について」(アレルギー 10巻6号(1961))
(*7)堀口申作・斎藤洋三「栃木県日光地方におけるスギ花粉症 Japanese Cedar Pollinosisの発見」(アレルギー 13巻1-2号(1964))
(花粉症を引き起こす仕組み)
花粉症は、花粉によって引き起こされるアレルギー疾患の総称であり、体内に入った花粉に対して人間の身体が抗原抗体反応を起こすことで発症する。花粉が粘膜に付着すると表面や内部にあるタンパクを放出し、アレルギー素因を持っている人の体内ではこれが抗原となって抗体が作られ、粘膜上の肥満細胞(マスト細胞)に結合する。人によって異なるが数年から数十年花粉を浴びると抗体が十分な量になり、抗原が再侵入すると抗体がそれをキャッチして(抗原抗体反応)、肥満細胞が活性化しヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質が放出され、それらが花粉症の症状を引き起こす(*8)。
同じ季節・場所でも症状が起こる時期や症状の強さは人によって変わるが、一般には体内に取り込む花粉の量によって症状の強さが変わり、短期的にみれば症状の強さや新規有病者数はその年の花粉飛散量の影響を強く受ける(*9)。
⾧期的な花粉症有病率の増加の背景としては、花粉症は一度発症すると自然に症状が消えることが少ないために有病者が蓄積していくことに加え、花粉飛散量の増加(資料特-6)や、食生活の変化、腸内細菌の変化や感染症の減少などが指摘されている。また、症状を悪化させる可能性があるものとして、空気中の汚染物質や喫煙、ストレスの影響、都市部における空気の乾燥などが考えられている(*10)。
花粉飛散量の増加の要因としては、昭和45(1970)年以降、スギ人工林の成⾧に伴い、雄花を付け始めると考えられる20年生以上のスギ林の面積が増加してきていることが考えられる(資料 特-7)。
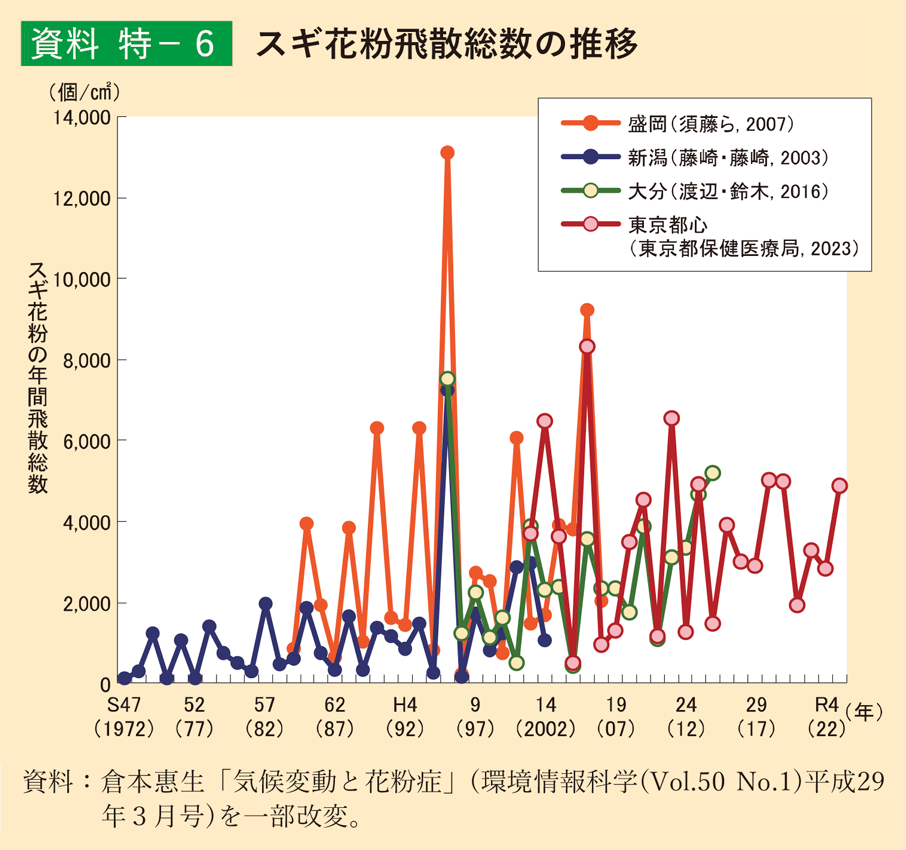
(*8)日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会編「鼻アレルギー診療ガイドライン-通年性鼻炎と花粉症-2020年度版」(令和2(2020)年7月改訂)
(*9)大久保公裕監修「的確な花粉症の治療のために」(2011)
(*10)環境省「花粉症環境保健マニュアル2022」(令和4(2022)年3月改訂)
(その他の花粉症の状況)
スギとヒノキはともにヒノキ科であり、花粉中の主要な抗原となる物質の構造が似ていることから、ヒノキ花粉症はスギ花粉症と併発することが多い。ヒノキは関東以西に多く植えられており、それらの地域でヒノキ花粉飛散量が多い傾向にある。
北海道においては、スギは道南など限られた地域のみに植栽されていることからスギ花粉症患者の割合は低く、代わりにシラカバやイネ科の花粉症患者が多い(*11)。
(*11)環境省「花粉症環境保健マニュアル2022」(令和4(2022)年3月改訂)
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219