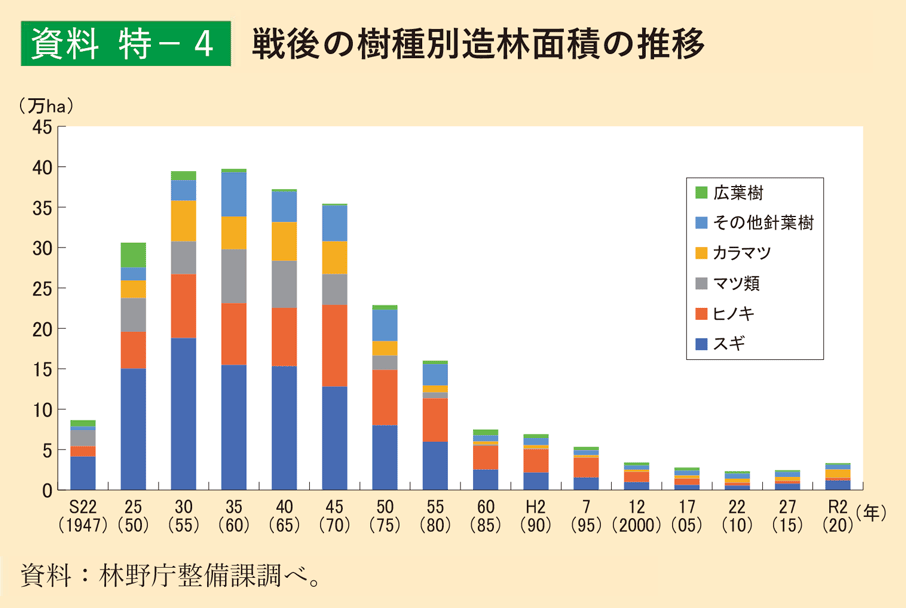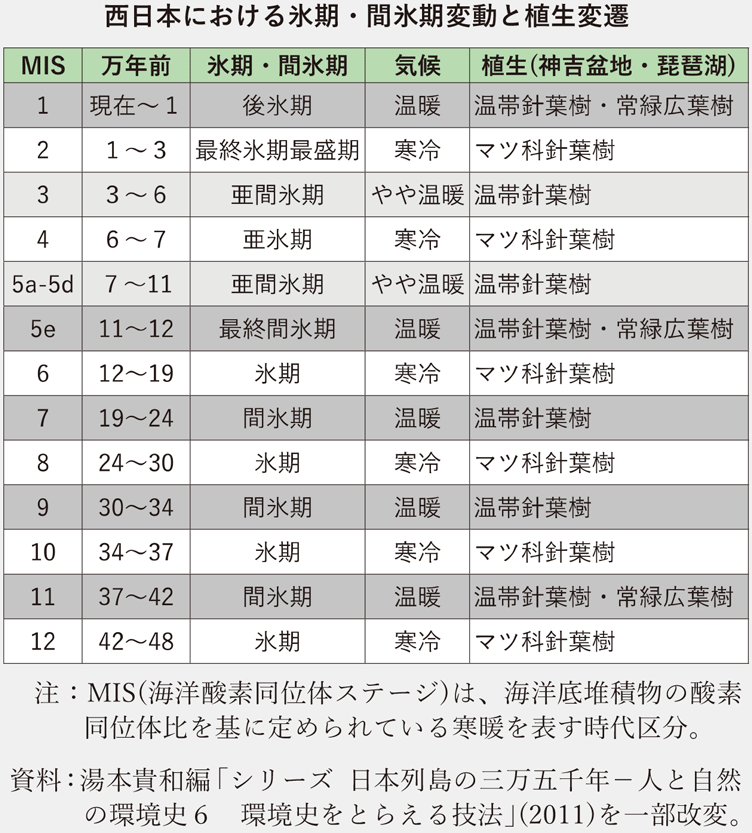第1部 特集 第1節 森林資源の利用と造成の歴史(2)
(2)戦後の人工林の拡大
(国土保全に向けた復旧造林の実施)
昭和10年代には第二次世界大戦の拡大に伴い、軍需物資等として森林の伐採が進んだ。また、戦後も復興のために我が国の森林は大量に伐採された。一方、食料その他多くの物資の不足から食料生産や生活必需品の確保が優先され、造林を行う余力が少なかったため、造林面積は低位となった。これらの結果、昭和24(1949)年における造林未済地は約150万haに上り、我が国の森林は大きく荒廃した状況にあった。また、昭和20年代には、各地で大型台風等による大規模な山地災害や水害が発生した。
こうした中で、国土保全の面から早急な国土緑化の必要性が国民の間で強く認識されるようになり、育苗・造林技術の確立していたスギ等を用いた復旧造林が各地で実施された。このような復旧造林の取組は、引揚者も含め人口が多かった山村における雇用対策の側面もあった。さらに、昭和25(1950)年には「荒れた国土に緑の晴れ着を」をスローガンに第1回の全国植樹祭が山梨県で開催され、以後国土緑化運動の中心的行事として毎年開催されている。こうした一連の施策により、戦後約10年を経た昭和31(1956)年度には、それまでの造林未済地への造林がほぼ完了した。
(旺盛な木材需要に対応した拡大造林の進展)
昭和25(1950)年頃から我が国の経済は復興の軌道に乗り、住宅建築等のための木材の需要は急速に増大し、木材価格も大幅に上昇した。一方、昭和30年代以降は、石油やガスへの燃料転換や化学肥料の使用が一般化したことに伴い、里山の広葉樹林等の天然林がそれまでのように薪炭用林や農用林として利用されなくなってきた。このような経済状況から、国内における木材の大幅な増産、そのための天然林の伐採と人工林化を望む声が大きくなった。
また、パルプ用材については、原料の大部分を占めていたマツ類の原木の調達が困難になっていたことを背景に、原料を広葉樹に転換するための設備投資が急速に行われたことにより、広葉樹の利用が後押しされた。このようにして里山の薪炭林や奥地の天然広葉樹林が伐採された跡地には、早期の森林回復と将来の高い収益を見込み、成⾧が早く建築用材等としての利用価値が高いスギ等の針葉樹を植栽する拡大造林が進展した(資料 特-3)。昭和40年代半ばまで、伐採跡地等においてスギを中心として毎年40万ha弱の造林が行われ、その後、拡大造林は急速に減少した(資料 特-4)。その要因としては、造林対象地が少なくなったこと、残っているのは権利関係が複雑で造林を進めにくい森林であったこと、外材輸入の増加等による木材価格の先行き不安、労賃や苗木代等の経費の増大などがあった。
このように、昭和20年代後半から40年代にかけて集中的にスギ等の人工林が造成されたことにより、人工林面積は昭和24(1949)年の約500万haから現状の約1,000万haまでに達するとともに、スギはそのうちの約4割を占める主要林業樹種となった。

コラム 花粉からわかる過去の森林の変化
花粉は、種や属ごとに特徴的な形態を持ち、湖底等の堆積物中では⾧期間保存されることから、過去の植生の変遷を解明する有効な手段の一つとして、花粉の含有量や割合を分析する手法が用いられる。
寒冷な氷期や温暖な間氷期を繰り返してきた過去40万年の日本列島の植生の変遷を調べると、氷期にはマツ科のトウヒ類やモミ類が増え、間氷期にはスギやヒノキ等の温帯性針葉樹が優勢だったと考えられている。また、各間氷期においても、広葉樹の出現率が異なるなど、様々な植生が成立していたことが明らかになってきている。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219