第1部 特集 第1節 森林資源の利用と造成の歴史(1)
(1)森林資源の利用拡大と造林技術の発達
(森林資源の利用拡大の歴史)
有史以前の日本列島は、日本の固有種であるスギやヒノキ等の針葉樹が、気候に応じて落葉広葉樹のブナや常緑広葉樹のシイ・カシ類等と様々な割合で混交し、広葉樹林の樹冠層を針葉樹が突き抜けるような林相の森林によって広く覆われていたと考えられている(*1)(資料 特-1)。例えば静岡県の登呂遺跡では建築物や道具類、田や畔を区画する矢板などにスギ材が使われていたとともに、周囲でスギやシラカシ等の埋没林が発見されたことからも、低地にも天然のスギ林が広く分布していたと考えられている(*2)。なお、現在、日本各地に残されている原生的な森林のうち、広葉樹や針葉樹がそれぞれ純林の様相を呈している森林の中には、人間が針葉樹や広葉樹を選択的に伐採したことが関係しているところも多いと考えられている(*3)。
奈良時代に入ると、大規模な建築物の造営等により、建築用材として優れた特性を持つスギやヒノキ等の針葉樹の伐採が進んだ。時代を追って大径の良材は減少し、伐採の範囲は畿内から次第に拡大していった。
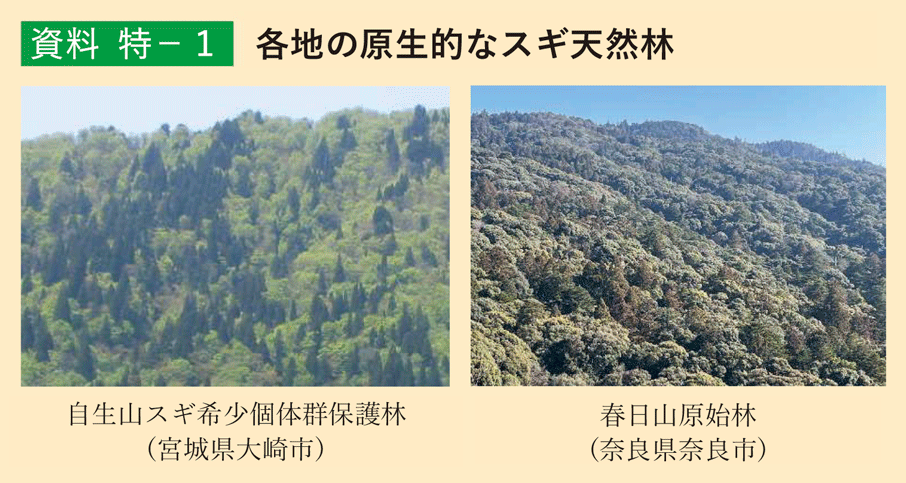
(*1)湯本貴和編「シリーズ 日本列島の三万五千年-人と自然の環境史6 環境史をとらえる技法」(2011)
(*2)鈴木三男「日本人と木の文化」(2002)
(*3)堤利夫編「造林学」(1994)
(造林技術の発達)
江戸時代を迎える頃になると、森林の荒廃による災害の発生が深刻となり、幕府や各藩によって留山(とめやま)など森林を保全するための規制や公益的機能の回復を目的とした造林が推進されたほか、スギやヒノキの天然資源が減少してきた中で積極的に資源を造成する観点から、山城国(京都府)の北山地域や大和国(奈良県)の吉野地域、遠江国(静岡県)の天竜地域等で、スギやヒノキを植栽する人工造林が開始された。さらに、その他の河川での流送が可能な地域でも、大都市等での需要に対応して木材生産を目的とする造林が拡大し、現在に至る伝統的な林業地が形成された(資料 特-2)。
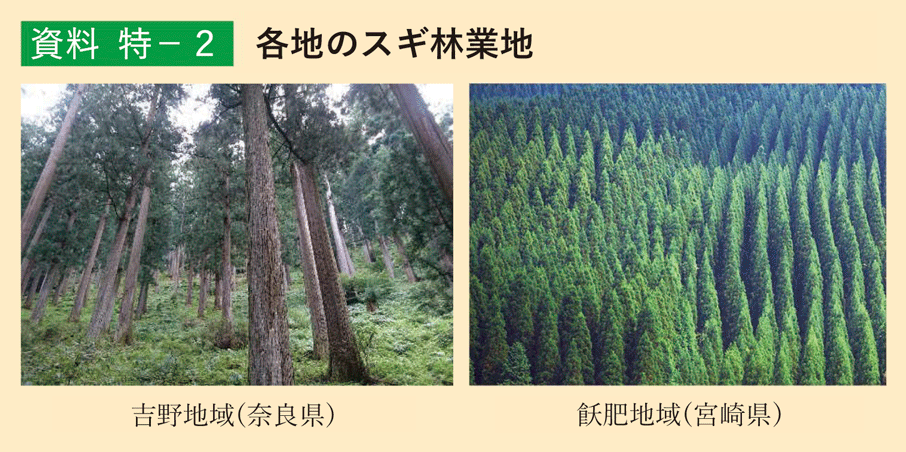
このような経緯の中で、スギやヒノキの育苗、植栽、保育等の技術の発達及び普及が進んだ。特にスギは、各地域の地理的・気候的な特徴に合った多様な品種系統が存在したことや、幅広い立地で生育が可能であること、成⾧が早い、面積当たりの収穫量が多いといった利点があるとともに、通直で柔らかいため加工しやすく、建築物や船、生活用具等の幅広い用途に利用できることから、全国各地で造林された。
スギの施業方法は一定の区域をまとめて伐採して植栽し同齢林を造成するものが多く、目的とする木材の形状や性質に応じて、植栽本数や間伐の回数、伐期(植栽から最終的な伐採までの期間)は多様なものとなった。例えば、吉野地域ではスギを密植(1万本/ha程度)し、間伐を繰り返すことで、様々な太さの丸太を生産して各種の需要に応えるとともに、⾧期間をかけて育成された大径材は年輪が細かく完満で無節の材が採れることから日本酒等を運搬する樽の材料として使われた。日向国(宮崎県)の飫肥(おび)藩では、油脂分に富み弾力性のある飫肥スギの特徴を活かして、単木の成⾧に重点を置いた疎植により成⾧を促して造船用の大径材を生産していた。
明治時代に入ると、近代産業の発展に伴って建設資材や産業用燃料等の様々な用途に木材が使われるようになり、国内各地で森林伐採が盛んに行われたため、森林の荒廃は再び深刻化し、災害が頻発した。その後、明治30(1897)年に森林法が制定され、保安林制度の創設等によって森林の伐採を本格的に規制するなど森林の保全を図る措置が講じられた。さらに、民有林において吉野地域などの先進林業地を模範とした林業技術の改良・導入の意欲が高まり、特に日清・日露戦争後は、木材需要の増大を背景に各地で林業生産が盛んとなり、新たな林業地も生まれた。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219




