令和元年度森林総合監理士育成研修日記1日目
令和元年度の森林総合監理士育成(後期)1研修を8月6日から9日の4日間、北海道森林管理局と小樽市にある塩谷国有林において実施しました。
森林総合監理士とは広域的・長期的な視点に立って林業の成長産業化や地域の活性化を構想し、実現に向けて中立的な立場で地域の森林・林業関係者の合意形成を図りつつ、制度や予算を活用しながら具体的な取組を進めていく中心的な役割を担っていく人材であり、林業普及指導員資格試験「地域森林総合監理区分」に合格した者に与えられる国家資格です。
森林総合監理士には森林づくりに関する科学的な知見や木材の生産から利用まで基本的な知識に加えて、こちらを地域の振興に結びつけていく構想力や合意形成に必要なプレゼンテーション能力が求められます。
本研修は平成23年から准フォレスター研修の名称で始まりました。カリキュラムの前期は林野庁森林技術総合研修所(八王子市)で座学を、後期は北海道・関東・九州の3ブロックで演習を中心に実施しています。
森林総合監理士とは広域的・長期的な視点に立って林業の成長産業化や地域の活性化を構想し、実現に向けて中立的な立場で地域の森林・林業関係者の合意形成を図りつつ、制度や予算を活用しながら具体的な取組を進めていく中心的な役割を担っていく人材であり、林業普及指導員資格試験「地域森林総合監理区分」に合格した者に与えられる国家資格です。
森林総合監理士には森林づくりに関する科学的な知見や木材の生産から利用まで基本的な知識に加えて、こちらを地域の振興に結びつけていく構想力や合意形成に必要なプレゼンテーション能力が求められます。
本研修は平成23年から准フォレスター研修の名称で始まりました。カリキュラムの前期は林野庁森林技術総合研修所(八王子市)で座学を、後期は北海道・関東・九州の3ブロックで演習を中心に実施しています。
1日目
研修初日、会場となった北海道森林管理局に北海道、東北各県、遠くは関西から27名の研修生が集まりました。所属も林野庁、都道府県、林業事業体とさまざまです。
本研修では5~6人のグループに分かれてその中で与えられた課題に対して議論して解決していく演習が中心ですが、研修生のみなさんの多くは初対面。いきなり議論を始めるのは難しいのでまずは準備運動のために簡単なゲームをしました。
行ったのは「ペーパータワー」。
A4のコピー用紙をどれだけ高く積み上げられるかを競うゲームです。「ペーパータワー」では作戦を考えたり役割分担をしたりとグループの中での議論や協力が必要となります。

こちらの班はM字に折って積み上げる作戦のようですね。

優勝はこちらの班でした!しっかり話し合って作戦を立てたことが勝因のようです。
このあとは研修の中身に入ります。
森づくりの構想
この演習の目的は最終的にどのような森林をつくるかという「目標林型」を考え、そこに向けた間伐や主伐を行う時期やその方法をどうするかという森林施業を決定することができるようになることです。演習では対象となる森林を実際に調査して次のことを検討します。
・現況評価・・・求められる機能を発揮しているかの判断
・将来の目標林型、途中の目標林型、木材生産を行うかの判断、その場合の生産目標
・施業方法・・・次回行う間伐の時期や方法、主伐の時期や伐採方法、更新方法
演習に先立ち、北海道大学大学院 渋谷教授より森林づくりの基本的な考え方、目標林型、施業方法の選択に関する科学的・技術的知見についての講義をいただきました。
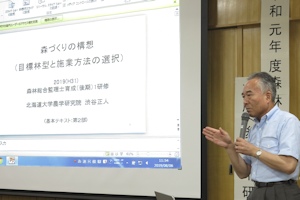
北海道のカラマツ人工林の施業や育林の低コスト化、長伐期施業による大径材の生産についてなど、さまざまな考え方や事例を教えていただきました。
本州からの研修生のみなさんにとって主要な樹種の違いやそこから来る考え方の違いは興味深かったようです。
つづいて現地実習で行う調査の内容や現地の概要について北海道森林管理局計画課職員が講師として説明しました。
ドローンで撮影した動画や全天球カメラで撮影した画像なども使って現地の状況を紹介しました。

この日はこれらの資料を基に目標林型や森林施業の案を作成し、翌日の現地実習では対象となる森林を実際に調査してそれを修正します。
資源循環利用構想
木材の流通・販売の動向を踏まえた販売戦略、マーケットを踏まえた木材の生産目標を立てること、森林の科学的な評価と循環的な木材生産の戦略を用いて森林・林業の将来ビジョンを描くことが目標です。ここでいうビジョンとは地域振興や地域の林業を活性化するために森林資源をどのように活用していくか、そこに至るためにどのような方向性で事業を行っていくか、具体的にはどのようなことを行うかという森林経営の構想です。
この演習では1000haの区域を対象に、
- 林況、路網を把握→10年間の間伐計画を立て、
- これによる所得、雇用効果等を計算、
- 首長に対してビジョンをプレゼン
まずは林業専用道の設計、作業システムの選択、森林作業道の作設、該当地域の木材関連産業、道内の木質バイオマス発電施設の動向、現地の情報について、北海道森林管理局講師から説明しました。
ここからはグループワーク。
まずは仮のビジョンを考えます。
今回は小樽市の国有林を民有林に見立てて検討します。小樽市の産業、周辺の木材加工工場や需要先となる木質バイオマス発電施設の稼働状況、気候や地形などの情報を基に考えます。
次に10年間の間伐箇所や林業専用道の配置を考えます。


北海道森林管理局の職員が講師として演習をサポート
翌日の現地実習では図面ではわからないところを現地で実際に確認したり、現地で新しい情報を得たりして今日つくった案を修正します。事前に現地のどこを確認するのかを決めておくことも重要です。
案が完成したところで1日目終了。
お疲れ様でした!
→2日目へ
お問合せ先
森林整備部 技術普及課
民有林連携・人材育成担当
ダイヤルイン:011-622-5245




