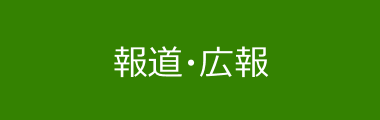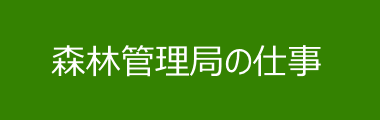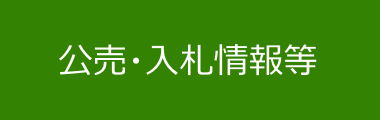やんばる森林生態系保護地域
1.概要

やんばる森林生態系保護地域内(45林班近景)
やんばる森林生態系保護地域内(40林班遠景)
2.目的
このように、本保護林は面的な広がりを持つスダジイ林やオキナワウラジロガシ林などの亜熱帯常緑広葉樹林地帯、山地の稜線部に発達する雲霧林、渓流添いの渓流植生など生物多様性に富む原生的な天然林を有し、地史に由来する大陸遺存固有種、新固有種などこの地域を特徴付ける動植物の固有種、希少種が多数生息・生育している。これらの多様で貴重な森林生態系を良好な形で維持・保存し将来にわたって、確実に引き継いでいくことが極めて重要である。
3.所在地
沖縄県国頭郡東村平良国有林1い3林小班外
やんばる森林生態系保護地域全体図(PDF : 940KB)
4.設定年月日
平成29年12月25日
5.面積
森林生態系保護地域総面積:3,007.04 ha (保存地区:2,769.01ha 保全利用地区:238.03ha)
6.関係森林管理署等
沖縄森林管理署
7.概況(成因、現況、地形、森林生態系保護地域の区域等)
ア 成因と現況
南西諸島は琉球弧とも呼ばれる島嶼域で、ユーラシアプレートの縁・境界に位置し、活発な地殻変動、数次の氷河期などを経て、陸地の海進、海退が繰り返され、地形の大変動が起こって、ユーラシア大陸と陸続き(大陸島といわれる所以)となったことや沖縄トラフの形成、古い地層を持つ高島の形成、珊瑚礁の発達による低島の形成など多様な成因からなる島々で構成される琉球弧(薩南諸島、沖縄諸島、先島諸島)が形成された。さらには、琉球諸島の西海上を北上し、トカラ海峡を経て太平洋へ流れる暖かい黒潮暖流は、島々に温暖な気候と多量の降水をもたらして、我が国でも希少で多様な生態系を有する最大級の亜熱帯多雨林が成立した。
このように、沖縄本島北部は山原(やんばる)とも呼ばれ、中琉球の持つ特異で多様な地史や気候等の影響を受けて、生物多様性豊かな亜熱帯多雨林を有することとなった。
イ 地形
国有林も本島北部のやんばる地域にあり、中央部の山域は起伏に富み本島最高峰の与那覇岳(503m)をはじめ、伊湯岳(446m)など複数のピークを持ち、与那覇山地は、標高400m以上の山稜が北東-南西方向に走る脊梁山地となっています。全体に20~30 度の急傾斜の山腹斜面があり、深い谷がある。その小起伏山地を取り囲んで標高100~200mの丘陵地が発達し、浅く細かい谷となり、海岸付近において、深く大きな峡谷となっている。海岸周辺には、断続的に海岸段丘が分布し、低地は全般的に極めて少ないのが特徴である。
ウ 森林生態系保護地域の区域
先に記した地殻変動等の地史、湿潤温暖な気候などのため、当該地域にしか生息しない希少な動植物が生息・生育している。このうち、森林生態系保護地域は、北側にある辺野喜ダムの伊集湖や周辺に位置する県営林(勅令貸付地)に取り巻かれ、我地地区の我地林道をほぼ境として、南西側に39,40,46,45林班を北端として、北東-南西方向に走る標高400m前後の脊梁山地の分水嶺、照首山、伊湯岳、玉辻山などをピークにしながら、東側、太平洋側一帯を含んでいる。未返還地域の米軍訓練場を挟んで、福地ダムの福上湖の北側湖岸までの連続的に長く連なる一体の地域のうち大きく2団地が含まれ、今般、返還された国有林の大部分が森林生態系保護地域として設定されている。
(別添図 やんばる森林生態系保護地域全体図(PDF : 940KB)参照)
エ 地質
本島北部地域の基盤は、主に中古生代国頭層群の名護層、嘉陽層からなり、沖縄島の代表的山地を形成している。名護層は、脊梁山地の両側に分布し、主として千枚岩からなるが、砂岩と千枚岩が互層をなす部分もあって、嘉陽層に整合漸移する。嘉陽層は、国頭村から名護岳付近の脊梁山地に分布し、主に砂岩からなり、粘板岩の葉理・破片を含み一部礫岩や泥岩も認められる。国頭礫層も分布し、一般には、数m以下の薄層である。
オ 土壌
この地域の林野土壌は、大別して赤色土(R)、黄色土(Y)、表層グライ系赤黄色土(gRY)に区分できる。標高300m以上の山地帯及び段丘内斜面、谷底面には黄色土が、標高90-300mの段丘免状には赤色土が分布する。表層グライ赤黄色土は,赤色土分布周辺の表層が帯水しやすい平坦~微凸地形に出現し、100-200mの段丘面状に広く分布している。
カ 水系
沖縄北部地域の主な河川は、福地川、安波川、普久川、新川、我地川等が太平洋に注いでいる。東シナ海側に注いでいるのは、大保川、源河川,羽地大川,辺野喜川等がある。主な水系は、福地川水系、新川水系、安波川水系、普久川水系、我池川水系があり、我池川水系以外は、ダムが建設されており、重要な水源地域となっている。
キ 気象
沖縄本島は、海洋性亜熱帯気候区に属し、年間を通じて温暖で気温変化も少ない。国頭村、東村では、年間平均気温が20℃、年降水量が2,000~2,500mmに達し、季節風が明瞭であり、冬季には北東風、夏季には南風が卓越する。
8.法指定等
やんばる国立公園(特別保護地区、第1種特別保護地区)、国指定やんばる(安田)鳥獣保護区(希少鳥獣生息地)、国指定やんばる(安波)鳥獣保護区(希少鳥獣生息地)、水源かん養保安林
9.取り扱い方針
【管理と利用に関する事項】
森林生態系保護地域に係る保護・管理及び利用に関する基本的な事項については、保護林設定管理要領(平成27年9月28日付け27林国経第49号)に定められた取扱方針に従う。
平成29年12月の保護林設定後、平成30年度に「やんばる森林生態系保護地域の森林基礎調査」が、令和元年度に追加調査が行われた。植物相については、基礎調査結果と既往の調査結果等から、沖縄島北部の自然を代表する林分として、大経木の分布、林床植生、後継樹等概ね健全な状態で天然林の森林環境が維持されていると評価された。動物相については、マングース等外来種対策が進み、希少種を含む在来種が本来の生息地まで回復する傾向が認められ、安定的生息環境に戻りつつある。
保護林の保全管理については、保護林設定管理要領に加えて保護林の保護・管理及び適切な利用を行うための総合的指針「やんばる森林生態系保護地域保全管理計画」に基づき具体的に取り組まれることとなる。以下、その内容について概括する。
保存地区及び保全利用地区ともに、基本的に自然の推移に委ねることとし、保全利用地区内の人工林は森林施業を行わないものとする。
希少種・固有種の取り扱い並びに外来種については、モニタリング調査による状況把握を行い、森林生態系保全に係る普及啓発に努め、巡視活動、外来種の侵入監視や駆除、さらに、松くい虫等病害虫対策も含めて、森林管理署と関係機関が密に連携し役割分担のもとで柔軟に対応し、必要に応じて生息環境改善、回復措置を講じるものとする。
また、保護林内における利用については、森林生態系への影響を考慮し、利用ルールの確立を図るとともに、地域住民等による利用については、管理主体が明確な道または従前から利用されている既存ルートに限定し、保護地域の保全に係る知識と経験を有するなど必要な資質を備えた案内者の動向を促すなど森林生態系の保全に配慮して取り扱うものとする。
今後は、基礎調査時に設定したプロット(8プロット)及び平成31年度の追加調査箇所(4プロット)を加えて、今後の調査拠点(計12プロット)として引き続き定期的にモニタリング調査を継続することとしており、他の保護林と同様にモニタリング調査結果を踏まえて、必要な対応策を講じることとなる。
【その他留意事項】
モニタリング実施間隔 5年(暫定)
なお、世界遺産地域に登録されたことから、モニタリング調査については、基礎調査、各種モニタリング調査項目や調査のあり方も含め、科学委員会等における審議や専門家意見等を経て、今後検討されていくものと思われる。
10.特徴
植物相
植生の特徴
沖縄北部国有林の森林植生は、常緑広葉樹からなるヤブツバキクラスに位置づけられ、高木層にイタジイ、オキナワウラジロガシ、イスノキ、イジュ等が優占し、亜高木層以下には、コバンモチ、ヒメユズリハ、タイミンタチバナ、シシアクチ、ボチョウジ、アオノクマタケラン、ササクサ等の常緑植物が繁茂する。
また、特徴的自然植生としては、イタジイ林やオキナワウラジロガシ林に加え、標高の高い山地に発達する雲霧林と渓流沿いの岩上に発達する渓流植生があげられる。沖縄北部国有林に生育する維管束植物は800種以上に上るとされ、貴重な植物の多くが雲霧林と渓流域に集中する傾向があり、環境省レッドリスト掲載の希少植物、国内希少野生動植物種など多数生育している。
動物相
1 哺乳類
やんばる地域に生息する陸生哺乳類は5目9科17種(人為的移入5種を含む)とされ、沖縄県全体の土着哺乳類は20種であり、このうち12種が沖縄本島北部に生息することになる。やんばる地域の哺乳類相の特徴は、大半が南西諸島の固有(亜)種であること、森林に強く依存する種が多いこと、大型種はリュウキュウイノシシのみで他は小型種のみであること、土着の食肉(ネコ)目がいないことが挙げられる。
土着哺乳類12種のうち、ケナガネズミ、オキナワトゲネズミの2種は国の天然記念物に指定され、7種が環境省レッドリスト、9種が沖縄県レッドデータブックに記載されている。
オキナワトゲネズミは沖縄北部のごく一部のみに生息する在来齧歯類であり、沖縄県レッドデータブックでは絶滅危惧種に選定されている。一時、絶滅が危惧されたが、平成20年に自動撮影カメラにより生息が確認された。生息範囲は非常に狭く、個体数もわずかとされている。
また、沖縄島南部で放獣された外来種マングースは沖縄北部地域に生息するヤンバルクイナなど地上を利用する鳥類、小動物の生息分布に大きな影響を与えている。このため、これ以上の北上を防止するため、名護市以北に2つの防止柵が設置され、また、その北側での集中的駆除事業により、マングース個体数は順調に減少していると考えられている。
一方で最近は、ノイヌやノネコの生息が確認されており、在来種への影響が懸念されており、それらへの対策も実施されている。
2 鳥類
沖縄北部地域の鳥類相については13目24科(4亜科)54種が確認されている。そのうち、ノグチゲラは国の特別天然記念物、ヤンバルクイナ、ホントウアカヒゲ、カラスバト、オシドリは国の天然記念物、アマミヤマシギは県の天然記念物に指定され、さらに、ノグチゲラ、ヤンバルクイナ、ホントウアカヒゲ、アマミヤマシギは国内希少野生動植物種に指定されている。

ノグチゲラ
3 爬虫類
やんばる地域の爬虫類は、2目12科19種が確認されている。このうち土着種が17種、移入種が2種である。リュウキュウヤマガメが国の天然記念物、クロイワトカゲモドキが県の天然記念物に指定されており、これにオキナワキノボリトカゲ、バーバートガゲ、オキナワトカゲ、アマミタカチホヘビ、ハイを加えた7種が環境省レッドリスト及び沖縄県レッドデータブックに記載されている。

オキナワハイ
ヒメハブ
キノボリトカゲ
4 両生類
やんばる地域の両生類は、2目6科15種が確認されている。このうち、土着種が12種、移入種が3種である。オキナワイシカワガエル、ホルストガエル、ナミエガエル、イボイモリの4種が県の天然記念物に指定され、これにハナサキガエル、シリケンイモリ、リュウキュウアカガエルを加えた7種が環境省RL、さらに、ハロウエルアマガエルを加えた8種が沖縄県レッドデータブックに記載されている。

オキナワイシカワガエル
シリケンイモリ
5 魚類(淡水魚)
やんばる地域に生息する淡水魚類は、河川延長が短いことなどもあって純淡水産魚の種数、個体数は著しく少ない。海と河川を行き来する両側回遊型の魚類と、汽水域や海水域に生息する種が一時的、偶発的に淡水域に侵入する周縁性魚類が淡水魚類相の90%以上を占めるのが特徴である。これらのうち、キバラヨシノボリは琉球列島の固有種で、アオバラヨシノボリはやんばる地域の固有種であり、これらに加えてタナゴモドキ、タメトモハゼが環境省レッドリスト及び沖縄県レッドデータブックに記載されている。また、ヒラヨシノボリは、沖縄島では沖縄北部国有林内のみでしか確認されていない。かつて生息したリュウキュウアユは、本島内では絶滅したが、奄美大島からの放流で一部水系(福地ダム)に定着が確認されている。
6 無脊椎動物相
やんばる地域に生息する無脊椎動物(昆虫類、陸産貝類、甲殻類)に関しては、沖縄本島及び奄美諸島の固有種等、貴重とされるものだけでも150種前後に達する。このうちヤンバルテナガコガネは国の天然記念物及び国内希少野生動植物種、フタオチョウ、コノハチョウは県の天然記念物に指定されている。環境省レッドリスト及び沖縄県レッドデータブックでは、これらに加え、昆虫類が23種、陸産貝類が18種、サワガニ類が5種記載されている。
お問合せ先
計画保全部計画課
担当者:生態系保全係
ダイヤルイン:096-328-3612