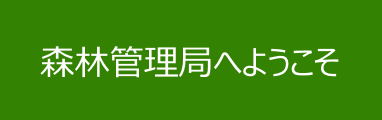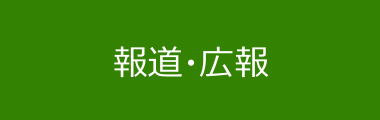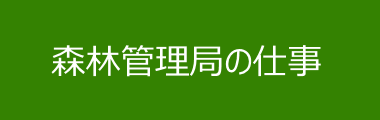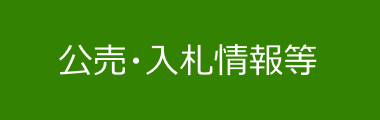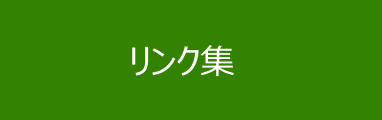令和4・5年度国有林モニター会議
国有林モニター見学会について
- 関東森林管理局では、国有林野事業について幅広いご意見をいただき、国有林野の管理経営に役立てていくため、国有林モニター制度を設けています。国有林モニターの皆様には、広報誌や森林・林業に関する資料を毎月お送りするとともに、国有林野事業への理解をより深めてもらうため、現地見学や意見交換等を行う国有林モニター会議に参加していただいています。
令和5年度現地見学会概要
- 今年度は12月5日に群馬県利根郡川場村で現地見学会を開催し、21名の国有林モニターの方々にご参加いただきました。治山工事箇所では、コンクリートの表面に木材を使用した(木製残存型枠)治山ダムを見学していただき、UAVの活用も含め災害復旧に向けた森林管理署の対応を説明しました。皆さんからは、「通常の治山ダムと比べコストはどうか」といった質問、「UAVを活用した新しい取組を知ることができ良かった」などの意見が出されました。
- また、川場ウッドステーション(製材所)では、川場村内で伐採されたスギやヒノキなどの丸太を製材品に加工する機械、ウッドチップを製造する機械を見学していただきました。川場村役場の担当者から、森林資源の循環利用を進めるため、村内の温泉施設やバイオマス発電所、役場の冷暖房などとしてウッドチップを利用しているとの説明がありました。国有林モニターからの「広葉樹はウッドチップにしないのか」との質問に対して「村内にある豊富な資源であるスギ、ヒノキの間伐材で、製材品として利用出来ない部分を利用している」などの説明がありました。地域循環型の木材利用について理解を深めたようでした。
- 次に、今年11月に完成したばかりの川場村役場の新庁舎を見学していただきました。川場村産のスギやカラマツなどの木材が各所に使われており、木のぬくもりを感じとれる建物となっています。ウッドチップを燃料とした冷暖房施設や太陽光などの再生可能エネルギーが導入されています。役場庁舎としての機能のほか、村民が安心して生活ができる拠点施設「kawaba BASE」としても利用しているそうです。
- 最後に、道の駅(川場田園プラザ)内の会議室で意見交換を行いました。「災害から短い期間で治山ダムが完成しており驚いた」、「木製残存型枠を利用した治山ダムを初めて見た」、「景観にも配慮されており大変良い取組みなので、このような治山ダムがどんどん増えると良い」、「このような治山は国有林のPRにもなる」との意見をいただきました。 また森林・林業行政に関して、「令和6年度から森林環境税の課税も始まるので、森林・林業に関心がもたれるように、その趣旨や活用状況をもっとPRすべき」との意見をいただきました。
- これらのご意見・ご要望は、今後の国有林野事業等に活かすとともに、より一層の情報発信に努めてまいります。
令和4年度現地見学会概要
- 今年度は、10月27日に群馬県利根郡みなかみ町の国有林で現地見学会と意見交換会を開催し、24名の国有林モニターの方々にご参加いただきました。
- 午前中は、チェーンソーでのスギの伐採、大型林業機械(プロセッサ)による枝払い、玉切り作業を見学していただきました。国有林モニターの皆さんは、木が倒れる様子や初めてみる林業機械に驚かれており、伐採の方法や林業機械の仕組み等についての質問がありました。
- 午後は、生物多様性の保全に取り組む「赤谷の森プロジェクト」について、イヌワシの狩場創出のために伐採された試験地を見学しながら説明をしました。残念ながらイヌワシが飛んでいる姿を見ることはできませんでしたが、なぜ狩場が必要なのか、どのような効果があるのかなどの質問があり、取組の必要性についてご理解を深めていただきました。
- 最後に、JR上毛高原駅前にあるビルで、意見交換を行いました。国有林モニターの皆さんからは、普段は入ることができない国有林の現場を見ることができ良かった、木材利用の現場を次は見たい、もっと一般の方々へアピールした方が良いなどのご意見・ご要望をいただきました。
- これらのご意見・ご要望は、今後の国有林野事業に活かすとともに、分かりやすい情報発信に更に努めてまいります。
- ご参加していただきました国有林モニターの皆様、ありがとうございました。
お問合せ先
総務企画部 企画調整課
担当者:林政推進係
代表:027-210-1150(内線293)
E-mail:ks_kanto_kikaku@maff.go.jp
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。