![]()
ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の概要 > 下越森林管理署 > 下越森林管理署の概要 > Ⅲ 公益重視の管理経営の推進
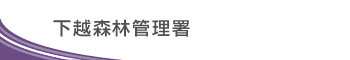
国有林ではこれまで主に発揮させる森林に機能に応じて3つの機能に類型化して管理経営を行ってきましたが、これまでも国有林の大部分は公益林に位置付けられてきました。
森林・林業基本計画などに基づき、平成25年に機能類型を5つに見直しましたが、公益重視の管理経営を行うことには変わりがありません。
|
(図6)国有林野の機能類型の見直し
|
我が国の森林は、流域を単位として158の計画区に区分されており、それぞれの流域において森林づくりや林業・木材産業の振興を図る「森林の流域管理システム」が、平成4年度から民有林と国有林の連携の下で進められています。
この流域管理システムの一層の推進を図るためには、国有林が先導的かつ積極的に取り組むことが必要であり、この推進に当たっては、国有林に対する地域の要望やニーズを的確に把握し、優先的に取り組むべき課題を絞り込んで重点的に実施していくことが必要ですが、現在、国有林では流域管理システムを推進するため、次のような取り組みを進めています。
民有林・国有林が連携して流域の森林の整備等を進めるために、下越流域で流域森林・林業活性化協議会を設けています。この協議会には、当署のほか、県の地方振興局、流域内の市町村をはじめ、多くの関係者が参画して、森林・林業の活性化に努力しています。
森林に対するニーズは多様化かつ増大しており、これらに適切に対処し各流域においてニーズを的確に反映した効率的な事業運営に努めるとともに、一定の理念を共有可能なNPOや団体等の外部組織との連携、協力を強化していくことも重要です。
平成13年度から、流域管理推進アクションプログラムを流域単位で作成し、下越流域ではこれに基づくメニューを実施してきました。
県下での民・国連携を進めるため、平成25年から新潟県との間で「新潟県民国連携連絡会議」を組織し、情報共有と連携の強化に努めています。その他、民有林との交流を進め、情報収集や情報提供などを行っています。
民・国連携を進めるための具体的施策として、民有林との間で全国的に「森林共同施業団地」の設定が行われています。
当署では、平成27年2月に新発田市田貝地区をエリアに、新発田市、さくら森林組合、田貝山生産森林組合及び当署の4者によって、「二王子森林整備推進協定」が締結され、民国連携による林業及び地域振興などへの寄与が期待されています。
その他の地域においても、森林共同施業団地の設定や、国有林の介在地を対象とした「公益的機能維持増進協定」の設定に向けた検討を行っています。
|
(写真19)森林整備推進協定締結式
|
当署が管理経営する広大かつ多様な国有林を新潟大学の教育や研究に活用していただき、当署が直面する様々な課題に対して新潟大学から学術的助言を受けるために、平成27年3月に新潟大学農学部との間で連携協力協定を締結しました。
|
(写真20)連携協力協定締結式 |
治山事業は、森林法に基づき森林の維持造成を通じて、山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、水資源の涵養、生活環境の保全・形成等を図る極めて重要な国土保全政策の一つです。また、広義の治山事業には、地すべり等防止法に基づく地すべり防止事業や、保安林の整備事業、山地災害復旧事業なども含まれます。
当署では、国有林内の荒廃地などを対象に国有林野内直轄治山事業を計画的に実施しているところですが、近年では地球温暖化に伴う集中豪雨の発生頻度が高まっており、昭和42年には「羽越大水害」による被害を被っていることから、山地災害に対する備えを怠らないよう努めています。
|
(写真21)木製型枠使用の治山ダム
|
路網とは、林道など森林内に開設された道路の総称であり、木材などの搬出のほか、適切な森林整備を合理的かつ効率的に行う上で不可欠の施設です。
林道(平成23年からは林業専用道。)は森林計画に基づいて計画的に開設されるほか、既設路網の維持修繕や改良も必要に応じて施工しています。
林道や林業専用道のような恒久的に維持される路網のほか、近年では低コストで効率的な間伐等の森林整備を行うための作業道など、林内路網の整備も積極的に進めています。
|
(写真22)計画的に進める路網整備
|
森林・林業や国有林及び森林並びに環境の重要性に対する理解と認識を深め、協力と支援をいただくために、学校や市民を対象とした森林環境教育に積極的に取り組んでいます。
具体的には、森林環境教育に関するプログラムやツールの提供、森林環境教育の場としての国有林の活用などを行っています。
|
(写真23)森林教室
|
(写真24)森林整備のボランティア
|
健全で機能の高い森林を維持、育成するため、森林動物や病害虫に対する対策を講じることが必要です。
最近では、主な造林樹種であるスギに対するツキノワグマによる剥皮被害が地域的に深刻となっています。このため、スギの幹に、剥皮防止用のテープを取り付けることを行っています。また、ニホンザルの被害防止対策についても、国有林内に電気柵を設置することを許可しています。
マツノマダラカミキリによって運ばれたマツノザイセンチュウによるマツ枯れは、以前から、海岸や平地丘陵部を主体に蔓延しています。
特に海岸近くの乙地区の保安林では、その被害が深刻であることから、従来から薬剤散布、被害木の伐倒駆除を行ってきましたが、今後の森林再生について、学識経験者による、検討を行い、天然力を活用しながら将来的には広葉樹林に誘導していくこととしています。
また、カシノナガキクイムシによって伝播される、いわゆるナラ枯れについても、近年、被害が奥地まで及びましたが、被害量は減少しています。
|
(写真25)薬剤散布
|
(写真26)被害木の伐倒駆除
|
トキ(学名Nipponia nipponn)は国内種は絶滅しましたが、佐渡島を中心に中国産トキ及び後継個体の保護・増殖が国の事業として取り組まれています。
佐渡島の国有林は、元々トキの保護のために民有林を買い上げたもので、トキの営巣候補木を確保するため、官行造林を含め、アカマツなどの調査や保護などを実施しています。
|
(写真27)トキ
|
(写真28)営巣候補木への樹幹注入
|
![]()
下越森林管理署
ダイヤルイン:0254-22-4146
FAX:0254-22-4148