第1部 第3章 第3節 木材産業の動向(2)
(2)木材産業の競争力強化
(国際競争力の強化)
大手住宅メーカー等は、品質・性能の確かな木材製品の大ロットで安定的な調達を重視しており、主に、JASによる格付がされた製品や、人工乾燥材等の一般流通材を調達している。輸入材や他資材との競争がある中、輸入材に対抗できる品質・性能の確かな製品を低コストで安定供給できる体制整備が進められており、主に国産材を原材料とする年間原木消費量10万m3以上の製材・合板等の工場が全国各地で増加してきている。年間原木消費量の最も大きい工場は、製材で65万m3、合板で49万m3の工場となっている(*68)。これまで大規模な製材工場等がなかった地域でも、新たに大規模工場が進出したり、地元の製材工場等が連携して新たに工場を整備したりするなど、大規模化・集約化が進展している。
製材工場について、令和5(2023)年における年間国産原木消費量5万m3以上の工場数とその国産原木消費量を平成16(2004)年と比べると、いずれも増加している(資料3-33)。規模拡大の手法としては、工場が単独で規模を拡大する例に加え、製材と集成材の複合的な生産、輸出向け製品の生産等に取り組む例がみられる。
合板工場においても、令和5(2023)年における年間国産原木消費量10万m3以上の工場数とその国産原木消費量を平成16(2004)年と比べると、いずれも増加している(資料3-34)。従来、合板工場の多くは原木を輸入材に依存するため、沿岸部に整備されてきたが、国産材への原料転換に伴い、内陸部に整備される動きがみられる(資料3-35)。


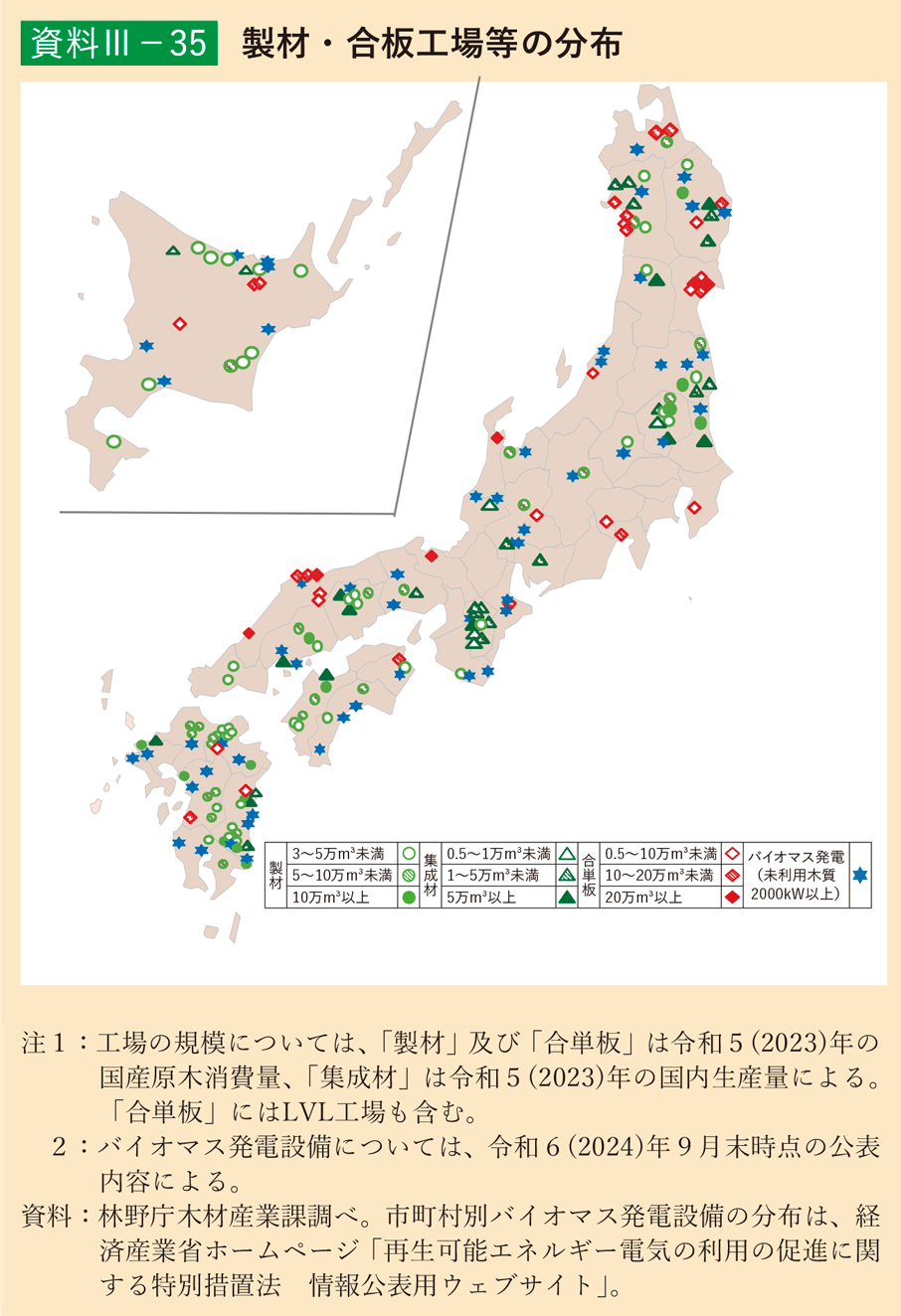
(*68)林野庁木材産業課調べ。
(地場競争力の強化)
中小規模の製材工場等は、地域を支える産業として重要な存在であり、地域の工務店等のニーズに対応し、優良材や意匠性の高い製材品等の生産に取り組む例がみられる。
例えば、国産材の使用割合が高く、木材を現(あらわ)しで使うなど意匠性の高い木造住宅を作り続ける工務店に対して、川上から川中の関係者が連携して優良材を提供する取組がみられる。また、需要者のニーズに合わせて付加価値の高い内外装や家具等を製造する取組などもみられる(*69)。
林野庁は、こうした地場競争力を強化するため、平角、柱角など多品目の製品を生産する取組や、地域の素材生産業者、製材工場、工務店等の関係者の連携による、付加価値の高い製品の企画・開発・プロモーションの取組等を支援している。
(*69)地場競争力の強化に関する取組については、「令和3年度森林及び林業の動向」特集2第3節(1)34-36ページを参照。
(品質・性能の確かな製品の供給)
現在、木材の新たな需要先として期待されている中大規模建築物は、設計時に構造計算が必要であるほか、小規模な木造建築物においても、令和7(2025)年4月の改正建築基準法の施行に伴い、構造関係の審査が必須となる範囲が拡大されることなどから、強度等の品質・性能の確かな部材としてのJAS構造材の供給の必要性が高まっている(事例3-8)。
一方、令和5(2023)年度において、国産材の主要な仕向け先である製材のJAS格付率は12%であり、住宅等の構造部に用いられる構造用製材に限っても25%にとどまる(*70)。また、JAS構造用製材を供給する国内の製材工場数について、令和元(2019)年度末と令和5(2023)年度末を比較すると、機械等級区分構造用製材(*71)の認証工場数は85工場から104工場へ増加したものの、目視等級区分構造用製材(*72)の認証工場数は268工場から227工場へ減少している(*73)。林野庁では、木材加工流通施設の整備を支援しており、機械等級区分構造用製材の認証工場数について、令和7(2025)年度までに110工場とすることを目標としている。
また、林野庁では、JAS構造材の積極的な活用を促進するため、平成29(2017)年度から「JAS構造材活用宣言(*74)」を行う建築事業者等の登録・公表による事業者の見える化とJAS構造材の利用実証の支援を実施している。JAS構造材活用宣言を行った事業者数は、平成30(2018)年度末は380社であったが、令和5(2023)年度末には2,065社に増加している。利用実証においては、令和5(2023)年度末時点までに1,025件のJAS構造材を活用した建築物が整備された。
さらにJAS構造材の供給拡大に向けて、令和6(2024)年度から、品質管理等に必要な人材の育成等への支援を新たに措置するとともに、製材工場等におけるグレーディングマシン等の導入への支援を強化した。このほか、製材工場に対してJAS認証取得を促すパンフレットを作成し、都道府県や業界団体に広く配布している。
JASについては、農林水産省において、科学的根拠を基礎としつつ、利用実態に即した区分や基準の合理化等の見直しを行っており、令和7(2025)年1月には、製材のJASについて、1)目視等級区分における材面の欠点の測定方法にカメラ撮影等による材面測定機器の利用を追加、2)含水率20%以下の構造用製材の木口におけるマイナス寸法(*75)を許容、3)曲げヤング係数について上限値と下限値による管理から平均値と下限値による管理への変更等、製造者と利用者に配慮した改正を行った。
事例3-8 大径材にも対応できるJAS製材工場
宮崎県日南(にちなん)市、都城(みやこのじょう)市、高原町(たかはるちょう)の3か所において年間の原木消費量9万m3規模の製材事業を行っている株式会社高嶺木材では、飫肥(おび)杉の大径材を製材できる強みを活かし、平角等のJAS製品等を効率的に製造している。
大径材の製材に当たっては、木取りの工夫により、平角に加え、間柱や筋交いなどの羽柄材を製材することで歩留りの向上を図っている。また、平角の製造において重要となる乾燥技術については、宮崎県木材利用技術センターからの技術的な助言を受け、粗挽(び)き材への散水による表面割れ防止の技術や乾燥スケジュールなどを工夫することで、JAS機械等級区分構造用製材の生産につなげている。
このように同社が製造したスギの平角は県内外の施設等で使用されており、例えば令和5(2023)年10月にオープンした「道の駅きたごう」(日南市)においては、梁(はり)・桁として62本(5.5m3)が使用されている。
今後は、飫肥杉の大径材の更なる活用に向け、JAS枠組壁工法構造用製材のうち幅広のツーバイエイト(2×8)材やツーバイテン(2×10)材の製造に取り組むこととしている。
(*70)林野庁木材産業課調べ。
(*71)構造用製材のうち、機械によりヤング係数を測定し、等級区分するもの。
(*72)構造用製材のうち、節、丸身等材の欠点を目視により測定し、等級区分するもの。
(*73)一般社団法人北海道林産物検査会「JAS認証事業者及び工場」、一般社団法人全国木材検査・研究協会「製材等JAS認証工場名簿」に基づいて林野庁木材産業課が試算。
(*74)JAS構造材の供給又は活用の拡大等に意欲を有する者が、JAS構造材の普及と利用に向けた目標を掲げて行う宣言。宣言を行う事業者は、JAS構造材実証支援事業事務局により登録・公表される。
(*75)基準値より大きくなる「プラス寸法」に対し、基準値より小さくなる寸法。今回の改正では、表示された寸法と測定した寸法との許容差を「+2.0mm~0mm」から「+2.0mm~-0.1mm」に見直し(木口の寸法が75mm以上の場合)。
(原木の安定供給体制の構築に向けた取組)
原木の安定供給体制の構築に向けては、製材・合単板工場等と、森林組合連合会や素材生産業者等、木材流通業者等(木材市売市場や木材販売業者等)との間で協定を締結して、一定の規格及び数量の原木を、年間を通じて安定的に取引する取組が行われている。
製材・合単板工場等が調達する原木のうち、素材生産業者等から直送されたものの割合は、平成30(2018)年は44.3%、令和5(2023)年は41.8%であり、ほぼ横ばいで推移している。また、木材流通業者が原木を購入後、自社等に運ばず、山土場や中間土場等から製材・合単板工場等へ直送する取組もみられる(*76)(資料3-36)。
林野庁では、川上と川中の安定供給協定の締結を推進するとともに、国有林野事業においても、国有林材の安定供給システムによる販売(*77)を進めている。
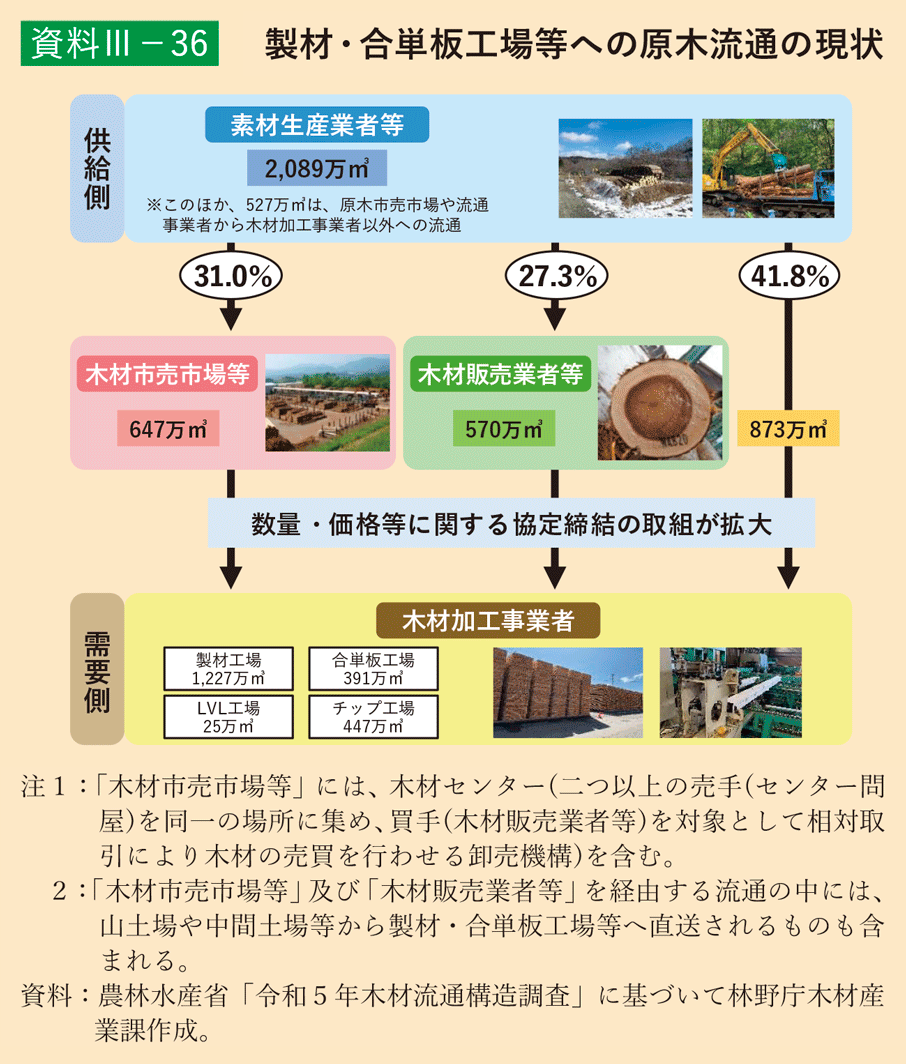
(*76)例えば、林野庁「国産材の生産・流通」(林政審議会資料(令和2(2020)年11月16日)資料1)3ページを参照。
(*77)国有林材の安定供給システム販売については、第4章第2節(2)203ページを参照。
(木材産業における労働力の確保と生産性の向上)
国産材の供給力強化に向けては、木材産業における労働力の確保も重要となる。木材・木製品製造業(家具を除く。)における従業者数は、近年減少傾向で推移しており、令和5(2023)年6月1日時点の従業者数は92,631人(*78)となっている。
このような中、生産性向上や国内人材確保を行ってもなお不足する労働力の確保に向けて、令和6(2024)年3月に、一定の専門性、技能を有する外国人を受け入れるための特定技能制度の対象分野として木材産業分野の追加が決定され、同年9月に運用が開始された。
また、開発途上国等への技術移転を目的とした技能実習制度に関しては、令和5(2023)年10月に、技能実習2号への移行対象職種に木材加工職種・機械製材作業が追加され、1号から通算して最大3年の実習が可能となった(*79)。
なお、木材加工の高効率化、省人・省力化、安全性の向上に向けては、画像処理やAIなどの最新技術を活用した検査装置の開発や、省人化と生産性向上を両立するための無人化ラインの導入等が進みつつある(*80)。
(*78)総務省・経済産業省「2023年経済構造実態調査 製造業事業所調査」(産業別統計表)における「木材・木製品製造業(家具を除く)」(全事業所)の数値。
(*79)特定技能制度及び技能実習制度については、第2章第1節(3)110-112ページを参照。
(*80)木材加工の高効率化、省人・省力化、安全性の向上に向けた取組については、「令和5年度森林及び林業の動向」第3章第3節(2)の事例3-8(154ページ)を参照。
(木材産業における労働災害の防止)
木材産業の労働力を確保し、持続可能な産業とするためには、働きやすく安全な労働環境を整備することが不可欠である。木材産業における死傷者数は⾧期的に減少傾向にあるものの、ここ数年の年間死傷者数は約1,000人と横ばい傾向である。また、木材産業における労働災害発生率は、令和5(2023)年の死傷年千人率でみると11.9で、林業、漁業に次ぐ高い水準であり、製造業全体の平均(2.7)の約4.4倍となっている(*81)。
木材産業における労働災害は、木材加工用機械等を用いた作業に起因する「はさまれ・巻き込まれ」や「切れ・こすれ」の事故が全体の約半数を占めており、大規模な事業所であっても他の製造業より労働災害発生率が高いなどの特徴がある。
農林水産省は令和3(2021)年2月に「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定し、周知及び啓発に取り組んでいる。林野庁では、専門家による安全パトロールや研修等の実施、製材工場等における「安全診断・評価マニュアル」の作成等を支援している。
また、木材産業は、可燃物である木材を扱うことから、工場火災の危険性が高い。令和5(2023)年における木材産業の火災件数は103件(*82)で、ここ数年は横ばい傾向にあるが、1,000事業所当たりの火災発生件数は16.5で、製造業全体(8.1)の約2倍となっている(*83)。
林野庁では、木材産業における効果的な火災対策の在り方を検討するため、令和6(2024)年に、製材工場等を対象とするアンケート調査を実施した。この調査結果(*84)を踏まえて、1)出火防止、2)早期発見、3)初期消火の3点の徹底を呼び掛ける資料を作成・配布して、工場火災に対する注意喚起に取り組んでいる。
(*81)厚生労働省「労働災害統計(令和5年)」
(*82)消防庁調べ。
(*83)総務省「経済構造実態調査 製造業事業所調査」(産業別統計表)に基づいて林野庁木材産業課が算出。
(*84)林野庁「工場火災に関するアンケート調査の結果について」(令和6(2024)年12月)
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219






