第1部 第5章 第2節 原子力災害からの復興(1)
(1)森林の放射性物質対策
(ア)森林内の放射性物質に関する調査・研究
(森林においても空間線量率は減少)
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、環境中に大量の放射性物質が放出され、福島県を中心に広い範囲の森林が汚染された。福島県は、平成23(2011)年から、帰還困難区域を除く県内各地の森林において、空間線量率等のモニタリング調査を実施している。令和5(2023)年3月の空間線量率の平均値は0.17μSv/hとなっており、森林内の空間線量率は、放射性物質の物理的減衰による予測値とほぼ同様に低下している(資料5-3)。
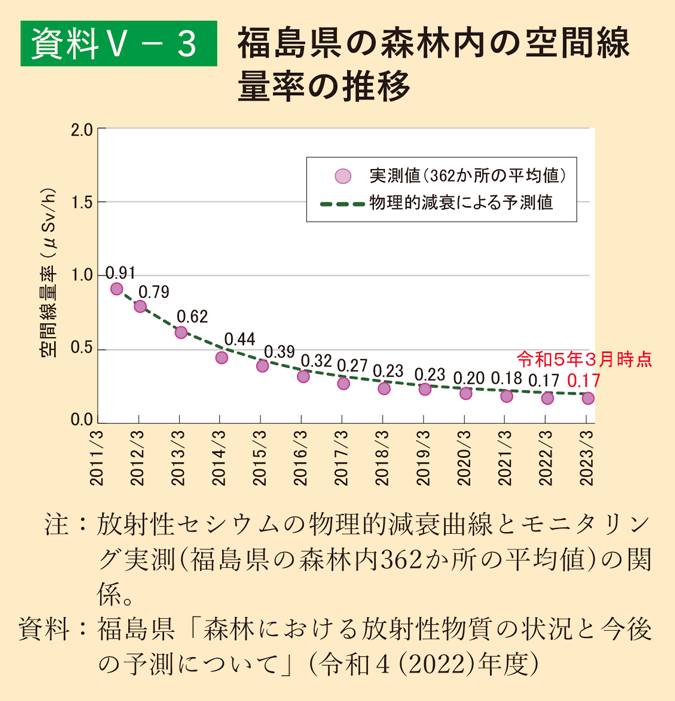
(森林内の放射性物質の分布状況の推移)
森林・林業施策の対応に必要な基礎的知見として、林野庁は、福島県内の森林において、放射性セシウムの濃度と蓄積量の推移を調査している。
森林内では、事故後最初の1年で葉、枝、落葉層の放射性セシウムの分布割合が大幅に低下し、土壌の分布割合が大きく上昇した。令和5(2023)年時点では、森林内の放射性セシウムの90%以上が土壌に分布し、その大部分は土壌の表層0~5cmに存在している。なお、森林全体での放射性セシウム蓄積量の変化が少なく、かつ大部分が土壌表層付近にとどまっていることなどから、森林外への流出は少ないと考えられる(*12)。
(*12)林野庁ホームページ「令和4年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について」
(森林整備等に伴う放射性物質の移動)
林野庁は、平成24(2012)年から平成29(2017)年にかけて福島県内の森林に設定した試験地において、落葉等除去や伐採等の作業を実施した後の放射性セシウムの移動状況調査を行った。その結果から、間伐の際に林床を大きく攪(かく)乱せず、土砂の移動が少なければ、森林外への放射性セシウムの移動は抑えられることが明らかにされている(*13)。
(*13)林野庁「平成28年度森林における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業報告書」(平成29(2017)年3月)
(ぼう芽更新木等に含まれる放射性物質)
放射性物質の影響によりきのこ生産に用いる原木の生産が停止した地域において、将来的にしいたけ等原木の生産を再開する上で必要な知見を蓄積するため、林野庁は、平成25(2013)年度から、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に伐採した樹木の根株から発生したぼう芽更新木について調査している。これらの取組に加えて、林野庁では、福島県及び周辺県のしいたけ等原木林の再生に向け、伐採及び伐採後のぼう芽更新木の放射性セシウム濃度の調査等について支援している。
(情報発信等の取組)
これまでの国、福島県等の取組により、森林における放射性物質の分布、森林から生活圏への放射性物質の流出等に係る知見等が蓄積されており、林野庁では、これらの情報を分かりやすく提供するため、シンポジウムの開催や動画の制作、パンフレットの作成・配布等の普及啓発を実施している。
(イ)林業の再生及び安全な木材製品の供給に向けた取組
(福島県における素材生産量の回復)
福島県全体の素材生産量は、震災が発生した平成23(2011)年には大きく減少したが、森林内の空間線量率が低下したことや、放射性物質対策に関する知見の蓄積や制度の整備に伴い、帰還困難区域やその周辺の一部の地域を除き、おおむね素材生産が可能となり、平成27(2015)年には震災前の水準まで回復している。
(林業再生対策の取組)
放射性物質の影響による森林整備の停滞が懸念される中、森林の多面的機能の維持・増進のために必要な森林整備を実施し、林業の再生を図るため、平成25(2013)年度から、福島県や市町村等の公的主体により間伐等の森林整備と放射性物質対策(*14)が一体的に実施されている。令和5(2023)年3月末までの実績は、汚染状況重点調査地域等に指定されている福島県内44市町村(既に解除された市町村を含む。)の森林において、間伐等14,110ha、森林作業道作設1,705kmとなっている。
(*14)急傾斜地等における表土の一時的な移動を抑制する筋工の設置等。
(里山の再生に向けた取組)
平成28(2016)年3月に復興庁、農林水産省及び環境省によって取りまとめられた「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」に基づく取組の一つとして、平成28(2016)年度から令和元(2019)年度にかけて、里山再生モデル事業を実施した。平成30(2018)年3月末までに14か所のモデル地区を選定し、林野庁による森林整備、環境省による除染、内閣府による線量マップの作成等、関係省庁が県や市町村と連携しながら、里山の再生に取り組んだ(*15)。
令和2(2020)年度からは、里山再生事業として森林整備等を行っており、令和6(2024)年3月末までに7市町村13地区において実施している。
(*15)平成28(2016)年9月に川俣町、葛尾村、川内村及び広野町の計4か所、同年12月に相馬市、二本松市、伊達市、富岡町、浪江町及び飯舘村の計6か所、平成30(2018)年3月に田村市、南相馬市、楢葉町及び大熊町の計4か所を選定。
(林内作業者の安全・安心対策の取組)
避難指示解除区域において、生活基盤の復旧や製造業等の事業活動が行われ、営林についても再開できることを踏まえ、林内作業者の放射線安全・安心対策の取組が進められている。
林野庁では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」に基づき、森林内の個別作業における判断に資するため、「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について(Q&A)」を作成し、森林内作業を行う際の作業手順や留意事項を解説している。
また、平成26(2014)年度からは、避難指示解除区域等を対象に、試行的な間伐等を実施し、平成28(2016)年度には、それまでに得られた知見を基に、林内作業者向けに分かりやすい放射線安全・安心対策のガイドブックを作成し、森林組合等の林業関係者に配布し普及を行っている。
(木材製品や作業環境等の安全証明対策の取組)
林野庁では、消費者に安全な木材製品が供給されるよう、福島県内において民間団体が行う木材製品や木材加工施設の作業環境における放射性物質の測定及び分析に対して、継続的に支援している。これまでの調査で最も高い放射性セシウム濃度を検出した木材製品を使って、木材で囲まれた居室を想定した場合の外部被ばく量を試算(*16)すると、年間0.049mSvと推定され、国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告にある一般公衆における参考レベル下限値の実効線量1mSv/年と比べても小さいものであった(*17)。福島県においても、県産材製材品の表面線量調査を定期的に行っており、専門家からは、環境や健康への影響がないとの評価が得られている。
(*16)国際原子力機関(IAEA)の「IAEA-TECDOC-1376」による居室を想定した場合の試算に基づいて算出。
(*17)木構造振興株式会社、福島県木材協同組合連合会、一般財団法人材料科学技術振興財団「安全な木材製品等流通影響調査・検証事業報告書」(令和元(2019)年)
(樹皮の処理対策の取組)
木材加工の工程で発生する樹皮(バーク)は、ボイラー等の燃料、堆肥、家畜の敷料等として利用されるが、バークを含む木くずの燃焼により、高濃度の放射性物質を含む灰が生成される事例が報告されたことなどから、利用が進まなくなり、製材工場等に滞留するようになった。
このため、林野庁では、製材工場等から発生するバークの廃棄物処理施設での処理を支援しており、バークの滞留量は、ピーク時(平成25(2013)年8月)の8.4万トンから、令和5(2023)年11月には約2,000トンへと減少した。
また、発生したバークを農業用敷料やマルチ資材に用いる方法の開発等、利用の拡大に向けた実証が進められている。
(しいたけ等原木が生産されていた里山の広葉樹林の再生に向けた取組)
震災前、福島県は全国有数のしいたけ等原木の生産地であり、全国のしいたけ原木の生産量の約1割、都道府県境を越えて流通するしいたけ原木の約5割を福島県産が占めていた。事故後、放射性物質の影響により、しいたけ等原木の生産が停滞し、原木となる広葉樹の伐採・更新が進んでいない。林野庁では、伐採・更新による循環利用が図られるよう、計画的な原木林の再生に向けた取組を「里山・広葉樹林再生プロジェクト」として、令和3(2021)年4月より福島県、市町村、福島県森林組合連合会、福島県木材協同組合連合会等と連携して推進している。同プロジェクトでは、市町村が、再生すべき原木林の面積や実行体制等を定めたほだ木(*18)等原木林再生のための計画(再生プラン)を作成し、令和4(2022)年度から広葉樹の伐採を本格的に実施している。また、福島県がぼう芽更新木の放射性物質の調査を行うとともに、伐採した広葉樹の利用拡大等に関係者が連携して取り組んでいる。これらの伐採や調査は、林野庁の実証事業を活用して行われている。
(*18)原木にきのこの種菌を植え込んだもの。
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219




