2014年8月
2014年8月31日(日曜日)
羅臼湖巡視
お盆が過ぎて、秋の気配漂う羅臼湖を巡視しました。
巡視のポイントは、入り込み状況(6組12名以上)、降雨後の歩道の状況、植物の生育状況などです。

4日ほど晴天が続くと歩道面は歩きやすくなりました。

ワタスゲは花が終わり、白い綿毛状となり、風になびいて種子を運び始めました。

ウラジロナナカマドは、果実が楕円状球形で真っ赤に色付き始めました。

オトギリソウは、咲いている花が黄色で、咲き終わった花は赤く丸みをおびています。

ミツガシワは、太い根茎が沼底を這い、開花時期の6月には白い花をつけていましたが、
この日は茎が水面に浮かぶ個性的な姿を見せていました。

サワギキョウは、野山の水辺や湿地に生育する秋に似合うキキョウ科の植物です。
2014年8月29日(金曜日)
羅臼中学校の英嶺山登山の同行、ガイド
夏の終わり、晴天に恵まれた英嶺山へ、羅臼町立羅臼中学校の第1学年の生徒31名と教職員引率のもと、
野外活動学習の一環としての登山です。
GSSは、今年も羅臼中学校からのガイド要請を受け登山を行いました。
先頭は知床半島探検隊にも参加している健脚グループ、中程はテニス部など部活別グループ、そして、
のんびりグループなどに別れ登山開始です。

出発式

元気に登っています。

樹木について質問タイムです。

横一列になってひと休みです。

羅臼の町並みと根室海峡がくっきり見えました。
羅臼中学校もよく見えています。

山頂で全員ニッコリ集合写真。

膝に負担をかけない下り方のコツを聞きながら下山しました。
2014年8月28日(木曜日)
春松小学校の羅臼湖遠足同行
今日は羅臼町立春松小学校6年生の遠足に同行し、16名の生徒さんと4名の教職員の皆さんと
一緒に羅臼湖を目指して歩いてきました。

天気もよく、気持ちのいい日となりました。

バスを降りていざ出発!
 
植生保護のため、全員長靴を着用しての参加です。
また、道中出会った方にはきちんと挨拶をするなど、公共のマナーを学ぶ良い機会となりました。

目的地の羅臼湖に到着です。
GSSも一緒にハイ・チーズ!

先生がゴールの記念写真を撮っていました。
今回の遠足は離脱者が出ることなく全員が無事に帰ってくることができました。
2014年8月22日(土曜日)
羅臼湖巡視

モウセンゴケ
天候の優れない日はマクロの世界が綺麗です。

ウメバチソウ

今年はハイマツの球果が多いと感じます。

ミズバショウを食べたと思われるヒグマの食痕がありました。

新しいと思われるクマ糞が歩道上に!
クマ鈴やクマスプレーを携行しましょう。

長靴は必須です。

終点の展望ポイントです。この日の羅臼湖は濃霧でした。
2014年8月18日(月曜日)
羅臼湖巡視
夏から秋にかけての羅臼湖も魅力的で連日利用者が訪れています。
また、学校の野外活動の一環としての利用も計画されています。
このため、安全かつ快適な利用が図られるよう巡視を行いました。

三の沼から見た羅臼岳は、大きなひさしのある帽子を被っていました。

遊歩道の一部には、路面に水道(みずみち)ができていました。

ぬかるんだ所には、枯れたダケカンバの幹を並べ応急的処置を施しましました。

秋を象徴する山のアクセント一つであるゴゼンタチバナの赤い実です。

ヤマハギが咲き、秋が近づいていることを感じさせていました。
2014年8月16日(土曜日)
イチイの森巡視
知床においては、エゾシカの食害が森林生態系保全の観点からの課題の一つとなっており、
いろいろな方策が講じられています。
今日は、エゾシカの食害を受けたイチイの森林床の巡視に行きました。
エゾシカが好んで食べる植物とされる、イタヤカエデ、キタコブシなどの稚樹は、わずかに見る事が
出来るだけでした。
 
林床において大きな存在感を持って生育していたのは、コバノイラクサでした。

ミミコウモリは高さ60~70センチメートルで、総状花序に多くの花をつけていました。

水辺にはミゾソバ(別名ウシノヒタイ)が生育していました。

クルマバソウはエゾシカが好きな植物の一つといえますが、林床にまとまりをもって生育していました。
 
アオカナブン、ミヤマクワガタ(大型)は、必死に樹液を吸い続けていました。
2014年8月15日(金曜日)
羅臼岳・ラウス側草刈り
知床が最も賑わいを見せるシーズンの一つであるお盆の中日、羅臼岳・羅臼温泉歩道入口(登山口)
ルートの巡視を行いました。
先日、草を刈り残した箇所を4人総出で行います。

知床森林生態系保全センターに隣接する早朝の国設野営場は、国内外からの
キャンパーであふれていました。

 
羅臼岳等への入山者は、2つあるルートのうち岩尾別歩道入口(登山口)ルートを利用する方が約8割を占めるとされ、残りの2割は健脚者が主体となっている羅臼温泉歩道入口ルートであり、たくさんの登山者に利用されています。このため、安全で快適な利用が図られるよう、かかり木のチェック、覆いかぶさったササ類の刈り払いなどを行いました。
 
木かくれの滝」の前では草が盛大に伸びていました。だいぶすっきりしました。
看板も半分隠れてしまっています。
 
お盆を過ぎる頃からどこかで秋の気配を感ずるという知床では、ベニナギナタタケなどのキノコが歩道脇にて
目に付くようになっていました。
花の開花も終盤を迎えつつあります。
夏の終わりの花がひっそりと咲いていました。
 
ツルリンドウ ハナイカリ
2014年8月14日(木曜日)
カムイワッカの湯の滝、ポンホロ沼巡視

今日はこの時期に一番賑わっているだろうと思われるカムイワッカ湯の滝への巡視です。
流れる水温はちょっとぬるめの27度でした。

「一の滝」はたくさんの人で大賑わいです。
滝の上部へ向かう所も譲り合いながら、楽しんでいる様子です。

その大賑わいの中には大学生のラグビー部50名ご一行様がいました。
なんだか今日の水温は2、3度高くなっていそうです…。

カムイワッカ湯の滝巡視の後はポンホロ沼の巡視へ行きました。
こちらは私たちの他に入林者は誰もおらず、ひっそりとしていました。

小さくなったポンホロ沼の周りにはヒメシダが生い茂っています。
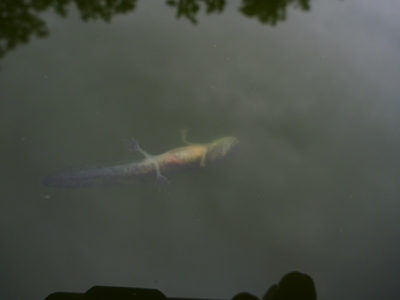
その小さな沼の中にエゾサンショウウオが浮いていました…。
気になってちょっとつつくと慌てて水の中に潜っていってしまいました。

ヒゲナガカミキリがトドマツの木で休憩中です。
ヒゲの部分も含めるとかなり大きいです。
2014年8月10日(日曜日)
羅臼岳歩道(登山道)ラウス側巡視

今日は2人で羅臼岳のラウス側の歩道(登山道)へ剪定バサミを持ち草刈りへ行ってきました。
道中、かわいいキノコがいたるところで生えていました。

歩道の入り口付近は地面がやわらかく、また、中途半端な長さの草が生えている箇所が多いです。
この場合、剪定バサミでは刈りづらいので、後日鎌で刈ることにし前へ進みます。

7月の山開き前に草刈りをした場所は新しい笹が勢いよく伸びていたのでもう一度短く刈りました。
植物の力強さを感じます。

第一の壁近辺の日当たりがいい所ではヨツバヒヨドリと笹が歩道を覆い尽くしている所がありました。
これだけの量の草刈りを2人だけで行ったら時間切れとなってしまいますので後日の課題となりました。

エゾライチョウが歩道を歩いていたのですが、私たちに気がつくと体を重たそうに飛んで逃げてしまいました。
本日、歩道沿いで確認できたお花です。
 
キツリフネ カワミドリ
 
ホタルサイコ オオヤマサギソウ
2014年8月9日(土曜日)
今日は羅臼湖巡視班と相泊・アメリカオニアザミ駆除班に分かれました。
羅臼湖巡視

雪渓が残っていた涸れ沢はすっかり雪も溶け、今日は水の流れは少しだけありました。
涸れ沢から眺める羅臼岳は曇り空のため見られませんでした。

笹をハサミで刈っていると、こんな変わった芽を見つけました。

四の沼では、サワギキョウが水際にちらほらと咲いていました。

五の沼です。
木道の付け替え作業が終わり、とても歩きやすくなっていました。
五の沼の標識付近までは歩いて行けそうに見えますが、植生保護のため
木道から降りないようにお願いいたします。

仮設の展望台から見た旧木道(写真中央)と、付け替えられた新しい木道(写真右側)の様子です。
今後、旧木道は撤去されて立ち入り禁止となります。

今日の羅臼湖です。
今日の入林者は5組17名でした。
相泊・アメリカオニアザミ駆除

崩れた斜面の途中に他の草陰などに隠れたオニアザミが、緑のつぼみ状態からピンクの花へと熟し始め、
あらためて目に付くようになりました。
極力、花が開花する前に手バサミで摘み取りを行います。

オジロワシが木の枝に止まっていました。
近くにある番屋の方のお話では『いつもあの枝で休憩をして飛んでいくんだ』と教えてくれました。
今日、海岸線で見られたお花です。
 
エゾモメンヅル ツリガネニンジン
2014年8月2日(土曜日)~3日(日曜日)
知床連山巡視
今回の巡視は知床連山の縦走路巡視です。
知床連山には、羅臼岳から知床硫黄山までの稜線上に縦走路が繋がっていて、
道中には羅臼平、三ツ峰、二ツ池、第一火口の野営指定地があります。
各野営地にはヒグマ対策のためのフードロッカーが設置されており、
一般的には一泊二日から二泊三日の行程で利用されます。

約25キロメートル長い行程なので夜明け前からの行動です。

大沢の雪渓はまだ長さ30メートルほど残っていました。

三ツ峰の水場は涸れそうな状況です。

サシルイのオッカバケ側の雪渓はまだだいぶ残っていました。

オッカバケから望む二ツ池、硫黄山方面
二ツ池のうち、天の池のほうは涸れているようでした。

第一火口もまだ雪渓がたっぷりありました。
水に困ることは無さそうですが、キツネがうろうろしていたのが気になります。

第一火口のテント場近くにあるフードロッカーです。
これは野営地にヒグマを寄せ付けないための食料保管庫です。
羅臼平、三ツ峰、二ツ池、第一火口の野営指定地にそれぞれ設置されています。
知床連山縦走路でキャンプをする際、テント内に食料は持ち込まず、このフードロッカーを利用しましょう。
近年では羅臼平のフードロッカーにリュックが丸ごと入っていた事例がありました。
使用時は食料のみを小さくまとめて、他の方も気持ちよく使えるように入れましょう。

硫黄山近辺の砂れき地にさしかかるとシレトコスミレを多く見かけますが、
今あるのは花が終わり結実した株ばかり…

…しかし!なんとか今年も開花している株を見つけることができました!
シレトコスミレはとても小さく、うっかり踏みつけてしまいそうな植物です。
シレトコスミレに限らず、歩道(登山道)を歩く際は足もとをよく見て植生にも気をつかいましょう。

硫黄沢にわずかに残る雪渓です。
硫黄沢でこのように残る雪渓は全部で2カ所ありましたが全体的に残り少なく、
雪渓の踏み抜きが懸念されますので雪の部分は避けて歩いたほうがいいと思います。
このあたりまで標高が下がると暑さが徐々に増してきます。
知床は連日の猛暑で消費する水の量と体力は相当なものです。
沢水などがあるところでは水を多めに補給するなどし、荷物は多少重くなりますが熱中症対策もお忘れなく!

道中、ヒグマのものと思われる毛が折れた枝にびっしりと挟まっていました。
ヒグマにとっては狭い道だったのかもしれません。
今回、縦走路で見られたお花です。

チシマノキンバイソウ

アオノツガザクラ

最後にカムイワッカに設置されている硫黄山歩道入り口(登山口)~カムイワッカまでの
区間(約600メートル)の道路通行許可の申請書(道路特例使用承認申請書)を記入し、
1泊2日のテント泊縦走巡視は無事に終了しました!
~入林者の皆さまへ~
平成26年度の硫黄山歩道入り口~カムイワッカまでの区間は登山者に限り通行が可能です。
期間は6月21日から9月23日までの95日間となり、すでにオホーツク総合振興局 網走建設管理部に「道路特例使用承認申請書」を提出済みの方は、あらためて記入することや写しの提出は不要ですが、やむを得ず事前に提出できなかった方は、記載台備え付けの申請書用紙に必要事項を記載のうえ、投函箱に入れてください。
なお、上記の方法は、すでに通行を終えた方(知床連山縦走をして下山した方)にも該当しますので、申請忘れのないようにお願いします。
2014年8月2日(土曜日)
羅臼岳巡視
8月2日(土曜日)薄曇りの中、岩尾別歩道入り口(登山口)より羅臼岳山頂まで日帰りで巡視を行いました。
今回の巡視のポイントは植生の保護を基本において、植物の生育および開花状況などを標高や土壌、岩場や水辺などの生息場所に注目しながら行いました。
標高に応じた植生

岩尾別登山口(標高230メートル)
針広混交林の林床は、エゾシカの食害の影響が少ないエゾユズリハが一面に生育していました。

オホーツク展望付近(標高560メートル)
ほぼ直立したダケカンバが生育し、薄い霧の中に知床五湖、オホーツク海が展望できました。

標高650メートル付近
ヒグマも好んで食べる低木のクロウスゴの実がなっていました。

横向きダケカンバ
重い積雪の影響により、太い幹のこのダケカンバさえも横向きに生育しています。

弥三吉水の付近(標高790メートル)
弥三吉水は、約900万年前に始まる海底火山活動により形成された半島基盤岩類と約50万年前からの
陸上火山活動により形成された溶岩層との間から通年的に涸れることなく流れ落ちる水です。

銀冷水付近(標高1050メートル)
銀冷水の水は、いわゆる表流水として流れている沢の水です。
その年により涸れることもありますが、今年の夏は涸れることなく健在で、近くには
水辺を好む植物が生育しています。
また、銀冷水より標高が上がるところからダケカンバに代わりハイマツやミヤマハンノキが
目立つようになります。

今日の大沢雪渓(標高1130メートル付近)
その年の雪解けの状況に応じて生育状況が異なりますが、
 
チングルマエゾコザクラ
 
エゾノツガザクラアオノツガザクラ
その他多くの可憐な高山植物が顔を見せていました。

アメリカオニアザミが生息域を拡大する中で、ここ標高1000メートルを越える付近では
エゾアザミが健在でした。

イワブクロが高山のれき地や岩場に生育していました。

羅臼平(標高1345メートル)には、岩の上に人工花である赤青リュックが咲いていました。

岩清水です。
岩場から貴重な水がぽたりぽたりと落ち、近くにはエゾノツガザクラ、チングルマなどが咲いていました。
2014年8月1日(金曜日)
知床五湖外来種駆除
今日は知床五湖に生える外来種のアメリカオニアザミ刈りを環境省のウトロ保護官事務所職員と行いました。

高架木道の周辺にはキオンがたくさん咲いていました。

この日は天候も良く観光客も多く見られました。

高架木道から見える範囲にはアザミはいくつか見られましたが、
少し離れたところには咲き始めたアザミがいくつもありました。
 

キオンの中にもオニアザミが…

遠くの海には観光船もみられました。

エゾシロチョウがキオンの密を吸っていました。

エゾカワラナデシコがちらほら見られました。

笹の中にはモイワシャジンが隠れていました。
 
作業終了です。
本日の駆除は土のう袋10袋となりました。
|