第2回研修が始まりました~研修1日目(平成24年8月20日)
本日から、平成24年度 東北ブロック林業専用道技術者研修の第2回目が、岩手県盛岡市の「ホテルエース盛岡」において始まりました。
今回は、福島県を除く東北5県から森林土木工事等を担当している県職員11名、市町村職員1名、大学職員2名、森林組合職員1名、森林管理署等職員13名、計28名が参加しています。受講者は、3日間の日程で講義・現地実習等の研修を受講します。
開講に当たり、東北森林管理局 青山指導普及課長から、「森林・林業再生プランが昨年からスタートとしているが、プランの主要な柱として、路網整備、森林施業の集約化、人材育成の3つを掲げている。基盤整備としての路網整備をいかに進めていくかが再生プラン推進の重要な鍵となっている。皆さんには、林道の技術を活かして新たな概念である林業専用道についても一層のプロ意識を持って取り組んでいくことを期待しています。」との挨拶がありました。
オリエンテーション
日程説明、資料確認、講師・スタッフの紹介が行われました。
 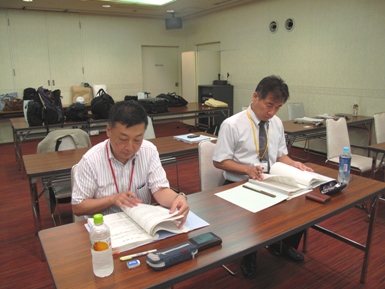
斉藤・佐藤・岡本の各講師 寺岡 林野庁業務課企画官 ・ 壁村 研修運営委員
林業専用道作設指針等の概要(講義)
なぜ、今、路網整備が必要なのか?どんな路網が必要とされているのか?林業専用道とは何か?林道とは何が違うのか?を理解するために、森林・林業再生プラン、路網整備の現状、路網整備の考え方、林業専用道の作設指針、林業専用道の設計上・管理上の留意点等について講義が行われました。
 
講師:東北森林管理局 斉藤林道実行係長
《森林・林業再生プラン》
平成21年12月に、今後10年間を目途に、森林・林業に向けた中長期的な施策の方向性を示すため、「森林・林業再生プラン」が作成されました。
再生プランが作成された背景は、
(ア) 国内の森林資源が、これまで整備してきた1千万haの人工林を主体に充実し、活用する時期に来ていること、
(イ) 外材輸入をめぐる情勢が、新興経済国における木材需要の増大、輸出国における輸出税の引き上げの動きなど、先行きが不透明なこと、
(ウ) 国内において国産材専門の大規模な製材工場や合板工場が増加し、これら工場に原木の安定的な供給が求められていること、
(エ) しかし国内林業は、長期的な材価の低迷等から、採算性の悪化、所有者の施業意欲の低下、林業所得の減少、就業者の減少・高齢化等の悪循環となっていること、
このような背景から、再生プランを作成し、林内路網の整備や機械化、施業の集約化などにより、生産性を向上させ、儲かる林業を展開するものです。再生プランでは、直ちに取組を開始する事項として、林業専用道の普及を図ることとなっており、この取組の一環として、林業専用道技術者研修を実施しています。
《路網整備水準の目安》
地域の諸条件にとらわれない普遍的な因子として林地の傾斜度に着目して、作業システムに必要となる路網密度の目安が示されました。
再生プランに掲げた、10年後の木材自給率50%の実現に向け、充実した人工林資源の活用にあたって、森林施業に主眼を置いた路網を早急に整備していくことが課題です。 そのためには、森林施業に使い勝手の良い道(森林作業道が分岐して林地へ入れる道)が必要であり、また簡易な構造とするなど、林道開設コストの低減が必要です。
搬出間伐が原則となるため、B材C材と言われている曲がり材や根元の材で一般の製材に仕向けられない安価な材を搬出するためには、搬出・輸送コストを含めたトータルコストの縮減が必須であり、 搬出・輸送コストの低減のためには、導入する作業システムに応じた高密度の路網整備が必要です。
今後の路網整備の課題等を踏まえ、林業専用道作設指針が示されました。
指針のポイントは、(ア) 地形に沿った線形とする、(イ) 土構造を基本とする、(ウ) 波形勾配と横断排水による分散排水です。このポイント を果たすため、詳細な規格・構造等を定めています。
平均傾斜30度程度以下としたのは、山地の地形は一様でないため平均傾斜としたものです。また、 土構造を原則としているため、30度を目安とし、地質条件や一定の構造物の設置を踏まえて程度以下としたものです。
排水は、可能な範囲で縦断勾配を波形とすることにより、路面水を分断します。また、簡易な横断排水工により、きめ細かに排水します。起点終点の関係から、路線全体が上り勾配にする必要がある場合でも、一律の上り勾配とせず、緩急をつけることで分散を検討します。
線形は、必要に応じてR=12mを活用しつつ地形に沿った屈曲線形、波形勾配とし、曲線部の片勾配や横断勾配を設ず、路面水はきめ細かな横断排水による分散排水を行います。
切土高は極力低く抑え、法面勾配は土砂の場合6分を標準とし、法面整形・保護は原則として行いません。盛土高は極力低く抑え、法面勾配は1割2分を標準とします。 路面は砂利道とし、必要に応じて侵食防止の路面工を行います。
林業専用道の工事施工に当たっては、施工業者にも林業専用道の主旨を理解してもらい、発注者と共により良い専用道を造るという意識を共有する必要があります。設計図書、仕様書に基づき施工管理を行いますが、現地と設計図書を確認する起工測量がその第一歩です。
林業専用道の目的は、林業ができる道づくりであり、現地に照らし当該設計がこの目的に合致しない場合は、監督員と相談して対応します。具体的には、地形の変化に応じた線形の微調整、森林作業道の取付部の確保、林業作業用施設(土場)の確保等についての変更協議です。
林業専用道の設計に当たっては、ボーリング調査等による土質調査は行っていないため、工事施工の段階で想定と異なる土質が出現する場合が多々あります。特に、切り土のり勾配について、監督員と相談して臨機に対応する必要があります。
林業専用道については、路面水を分散排水により処理することとしていますが、横断排水溝の設置を予定した現地が、盛り土区間であったりした場合は、洗堀防止対策の検討や横断溝の設置箇所の移動等について、監督員と相談して臨機に対応する必要があります。
林業専用道の調査設計(演習)
明日の藪川林道における現地実習の準備として、班ごとに藪川林道周辺の5千分の1の図面上で林業専用道の路線検討と、平面図や縦横断面図等から見直すべき線形、工法等について検討を行いました。
講師:(株)森林テクニクス 岡本青森支店長 演習方法等の説明
この演習や明日の実習により、林業専用道の適正な線形の選択や適切な施工管理の知識を習得します。
<1班> <2班>
 
<3班> <4班>
|
![]()

![]()