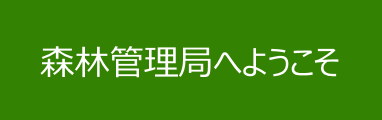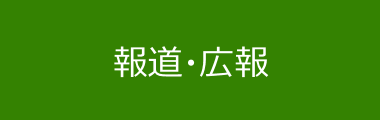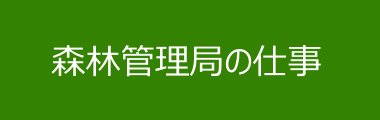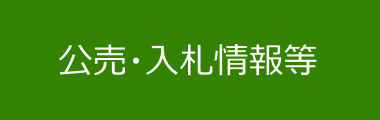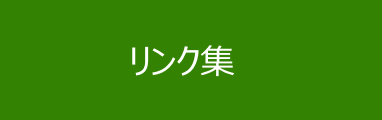令和2年度保護林モニタリング調査評価等部会の概要
1開催方法
持ち回りによる開催(令和3年3月3日、5日)
Web会議システムを使用した個別説明により実施。
2議題及び委員からの意見
(令和2年度の保護林モニタリング調査について)
- 調査方法を踏査主体に変更したことによって、保護林の状況がよく分かるようになった。来年度以降も問題の予見される保護林を重点的に調査してほしい。
- 生物多様性の観点からは、保護対象種となっているブナやミズナラよりもむしろ希少な草本植物などの方が重要である。こうしたものも保護の対象に位置づけ、順応的管理を行っていくことが重要。
- 沖ノ山と扇ノ山でシカ被害が顕著であるので、地域ボランティアの協力も得ながら、植生保護のためのシカ柵の設置等の対策を急いでほしい。
- 山王谷の保護林についてはトチ等の一部の保護対象種が確認できていないため、次回に向けて調査方法の見直しが必要。
- モニタリング調査の結果を踏まえ、植生が衰退しつつある保護林については有効な対策を検討すること。
- 現在シカの被害が発生していない保護林は次回調査まで10年間の期間が空くことになるが、その間にシカ被害が急速に進展することも考えられる。何かあった時にすぐ対応できる監視体制にしておく必要があるのではないか。
(令和2年度の緑の回廊モニタリング調査について)
- 主伐をしたことによってシカが侵入してくるかもしれないといったリスクも想定しながら、モニタリングしつつ事業を進める必要がある。
- 植栽する広葉樹の種類については、同じような取組をしている森林組合などから情報収集しながら検討してほしい。遷移初期の樹種を植栽すればいいという考えもあれば、遷移を早く進めるために遷移中後期の樹種を一緒に植えるという考えもある。
- シカ被害が軽微な地区で主伐を進めることとしているが、主伐を進められるほどではないと思われる。列状伐採程度の規模でないと難しいのではないか。
- 標高が高く尾根筋に位置する緑の回廊において、大面積の皆伐を行うのは問題があると思うが、列状間伐や択伐ではイヌワシが狩場として利用しにくい。施業を計画する際には、どの程度の伐採とするか調整が必要となる。
- イヌワシが緑の回廊をどのような目的で利用しているのかを把握し、狩場を作るのがよいのか、又は別のことをした方がよいのか考えるようにした方がよい。イヌワシの利用範囲は広範囲であるので、狩場はどこか別の場所にあって、森林は別の目的で使いたいから来ているというケースも考えられる。しっかりと情報収集することでイヌワシに利用してもらえる森林を残すことができる。
説明資料一覧、委員名簿、委員会等設置要領(PDF : 141KB)
資料1 令和2年度保護林モニタリング調査結果(PDF : 11,007KB)
資料2 東中国山地緑の回廊 (1)行動指針(案)(2)モニタリング調査における「基準・指標」及び「調査項目・調査手法」 の作成についての報告(PDF : 7,197KB)
お問合せ先
計画保全部計画課
担当者:森林施業調整官
ダイヤルイン:050-3160-5696