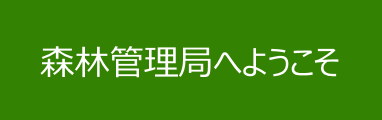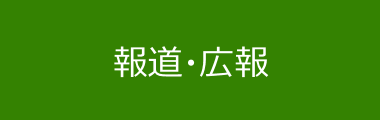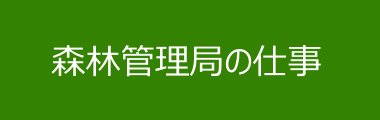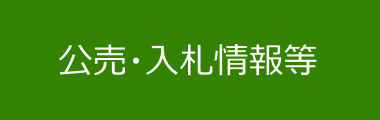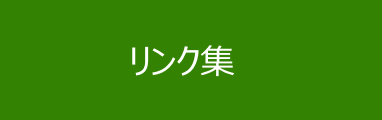令和元年度 国有林の森林計画に関する地域懇談会の概要
令和3年度を始期とする「地域管理経営計画」を策定するに当たり、国有林の管理経営について広く国民の皆さまから意見をお聴きするため、令和元年9月19日から10月30 日までの間において、対象となる7森林計画区において「国有林の森林計画に関する地域懇談会」を開催しました。懇談会での主な意見や質問の概要は以下のとおりです。
○越前森林計画区(福井県)
- 開催日
令和元年10月29日(火曜日)
- 開催場所
福井県総合グリーンセンター(福井県坂井市)
- 主な意見等
県内では、林業の人材確保が必要な状況にあり、仕事の量が多く手が回りきれていないように見受けられる。次の計画ではそのような状況を考慮して計画量を決める必要があるのではないか。
今回の計画区は隣接する若狭地域と協調した計画内容となっているのか。
低コスト化に向けて今後はすべてコンテナ苗を使用して事業を実施していく方針か。
|
 |
○北伊勢森林計画区(三重県)
- 開催日
令和元年10月24日(木曜日)
- 開催場所
いなべ市北勢庁舎(三重県いなべ市)
- 主な意見等
公益的機能を発揮する森林整備として、どのような森林を目指していくのか。森林環境教育の場、レクリエーションの森など気軽に入れる箇所や事例の情報を共有しやすくしてほしい。
次期計画の事業箇所や伐採数量等は現行の計画との連続性をどのように考慮したものとなるのか。
地域の林業を発展させ、林業技術者の育成を進めていくため、国有林がリーダーシップをもって活動してほしい。
台風で千葉県を中心に高圧鉄塔や送電線の被害が報道されたが、電力会社との協力はどのように進めるのか。
|
 |
○由良川森林計画区(京都府)
- 開催日
令和元年10月11日(金曜日)
- 開催場所
宮津市福祉・教育プラザ(京都府宮津市)
- 主な意見等
次期計画において基本的な考え方に変更点はあるのか。主伐は今後増加していく傾向にあるのか。
舞鶴市でバイオマス発電が開始されることから、木質バイオマスを優先して地元に供給していただきたい。
早生樹の導入に向けた検討は行われているのか。
森林経営管理制度が施行されたが、条件の不利な森林でどのように利益を確保するかが課題と考えている。
コンテナ苗の成績はどのような状況か。
一貫作業システムにより、どの程度のコスト削減が可能となるのか。また、川上へ利益が還元されるよう、国有林が中心となり川中・川下を含めたコスト削減を考えていただきたい。
列状間伐はどの程度導入されているのか。また、どのような森林で導入しているのか。
獣害対策については、防護柵等による被害防除に加え、シカの生息密度の管理も重要ではないか。山林で駆除すると里山で被害が増加する傾向があるので、餌となる実を付ける広葉樹を植栽するなど、シカを山林に留まらせる方策も考えてほしい。
遺伝子保存林については、今後どのような管理を行っていくのか。
丹後縦貫林道を観光資源として活用するため整備を進めているので協力してほしい。
|
 |
○北山・十津川森林計画区(奈良県)
- 開催日
令和元年10月10日(木曜日)
- 開催場所
ホテル野迫川(奈良県吉野郡野迫川村)
- 主な意見等
県南部地域では林業従事者が多いことから、林業事業体の育成等の対策に取り組んでほしい。
参詣道と一体となった森林景観とは、具体的にどのようなものか。
レクリエーションの森で修景伐採の要望に対し、以前より臨機応変に対応した施業をしているように思う。
不成績人工林については、今後、針広混交林への施業を検討するのか。
国有林だからできる試験的な取組をしてほしい。
次期計画での素材生産の方向性と十津川村内への出材量を教えてほしい。また、今回の計画の中で岡山のような広葉樹活用の取組が検討されるのか。
民国連携として森林ボランテイア活動を村を挙げて一緒にやっていきたい。
村の材の評価はどの程度なのか。
低コスト化を進めているが、山が急峻で機械化に手を付けられないのが現状である。急峻な山でも使用できる林業機械を開発してほしい。
奈良県南部は急峻な箇所が非常に多くコストがかかるので、事業単価はこうした地域性に配慮してほしい。
|
 |
○紀中森林計画区(和歌山県)
- 開催日
令和元年10月30日(水曜日)
- 開催場所
美山温泉愛徳荘(和歌山県日高郡日高川町)
- 主な意見等
民国連携については、これからどのような取組を行っていくのか。
虫害により材価が下がり深刻な被害を受けている。森林管理署が先頭になって虫害対策に取り組んでほしい。
低コスト化でどの程度コスト削減ができるのかを具体的に示していただきたい。
木材自給率の将来目標はどうなっているのか。また、自給率を上げるため国有林からの出材を増やすこととなるのか。
保護林を拡大することは検討されているのか。
材価が低迷している状況にあり、国有林の生産は価格調整に配慮する必要があるのではないか。
マイクロプラスチックが問題となっており、防護柵の撤去を検討する必要があるのではないか。
林道開設する際の希少生物等の調査は、どのように行っているのか。
国有林のフィールド提供として、観光やショートステイなど新たな活用方針はないのか。
近年、大きな災害が多発しており、応急復旧住宅等の建設資材として国有林材を無償で提供することはできないのか。
|
 |
○高梁川下流森林計画区(岡山県)
- 開催日
令和元年9月19日(木曜日)
- 開催場所
新見商工会議所(岡山県新見市)
- 主な意見等
合板やチップ、バイオマス用材といった低価格な材の需要が増えている中で、山主が収入をあげるためには低コストで材を搬出することが必要であり、林道等の基盤整備が重要である。
国有林で行っている施業や技術開発の取組が民間には知られていない。もっと多くの人に国有林の取組を知ってもらえる機会を設けていただきたい。
近年自然災害が多く発生している中で、木を伐ったら災害を誘発するのではないかといった伐採に否定的な意見もある。自然環境に配慮した施策・計画はあるのか。
|
 |
○高梁川上流森林計画区(広島県)
- 開催日
令和元年9月26日(木曜日)
- 開催場所
油木協働支援センター
(広島県神石郡神石高原町)
- 主な意見等
新たな森林管理システムの下で、意欲と能力のある林業事業体を育成するためには安定的な事業量の確保が必要であり、民有林を補完する形で国有林が長期に安定的に事業や素材を供給できる仕組みを拡充することが必要である。
低コスト林業を進める上で、林道の拡充は重要と考えており、民国連携を進めるのであれば、15tから20tトラックが通れる高規格林道を計画してほしい。
花粉症対策苗木への転換促進が必要であり、少花粉や無花粉のコンテナ苗作成や造林を進めてほしい。
計画されている主伐や間伐が実行できなかった場合は、次の計画に計上されるのか。また、間伐と主伐を変更する場合があるのか。
岩等によって路網整備が困難な場合など計画と現地が乖離している場合があるので、事業発注時に精査してほしい。
|
 |
お問合せ先
近畿中国森林管理局 計画課
担当者:計画調整官
ダイヤルイン:050-3160-6700
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。