第1部 第3章 第3節 木材産業の動向(4)
(4)木材産業の各部門の動向
(ア)製材業
(製材業の概要)
我が国の製材工場数は、令和5(2023)年末時点で3,749工場であり、前年より55工場減少した。出力階層別にみると、75.0kW未満の階層で減少し2,131工場、それ以外の階層では横ばいの1,618工場となっている(*94)。
令和5(2023)年の出力階層別の原木消費量をみると、出力規模300.0kW以上の工場の消費量の割合が78.3%、うち出力規模1,000.0kW以上の工場の消費量の割合は39.6%となっており、製材品の生産は大規模工場に集中する傾向がみられる(資料3-38)。
(*94)農林水産省「木材需給報告書」
(製材品の動向)
国内の製材工場における製材品出荷量は、令和5(2023)年は、前年比7.4%減の797万m3であった。令和5(2023)年の製材品出荷量の用途別内訳をみると、建築用材(板類、ひき割類、ひき角類)が648万m3(81.4%)、土木建設用材が32万m3(4.0%)、木箱仕組板・こん包用材が93万m3(11.7%)、家具建具用材が5万m3(0.7%)、その他用材が18万m3(2.2%)であった。建築用材に占める人工乾燥材の割合は60.7%であった(資料3-39)。
また、国内の製材工場における製材用原木入荷量は令和5(2023)年には1,506万m3となっており、このうち国産材は前年比5.1%減の1,227万m3で、全体に占める国産材の割合は81.5%であった。輸入材は前年比18.6%減の279万m3であり、このうち米材(べいざい)が228万m3、ニュージーランド材が31万m3、北洋材が12万m3であった(資料3-40)。
これに対し、製材品の輸入量は前年比32.0%減の315万m3であり(*95)、製材品の供給量(*96)に占める輸入製材品の割合は28.4%であった。
(*95)「令和5年分貿易統計」による製材品の輸入量333万m3から「令和5年木材需給報告書」による半製品入荷量を控除した数量。
(*96)製材品出荷量797万m3と製材品輸入量315万m3の合計。
(イ)集成材製造業
(集成材製造業の概要)
集成材は、一定の寸法に加工されたひき板(ラミナ)を複数、繊維方向が平行になるよう集成接着した木材製品である。狂い、反り、割れ等が起こりにくく強度も安定していることから、プレカット材の普及を背景に、住宅の柱、梁(はり)及び土台に利用が広がっている。我が国における集成材工場数は、令和5(2023)年末時点で143工場であった(*97)。
(*97)農林水産省「令和5年木材需給報告書」
(集成材の動向)
国内での集成材の生産量は、令和5(2023)年は前年比1.0%増の168万m3となった。令和5(2023)年の集成材生産量(*98)を用途別にみると、構造用が159万m3、造作用等その他が9万m3となっており、構造用が大部分を占めている(*99)。また、国内の集成材生産量のうち国産材を原料としたものの割合は、⾧期的には上昇傾向にあり、令和5(2023)年は45.9%(77万m3)であった(資料3-41)。
集成材の製品輸入量は、令和5(2023)年には65万m3で、集成材の供給量に占める割合は28.0%であった。そのうち構造用集成材の輸入量は56万m3であった。構造用集成材の主な輸入先国及び輸入量は、フィンランド(24万m3)、ルーマニア(8万m3)、オーストリア(6万m3)等であった(*100)。
(*98)農林水産省「令和5年木材需給報告書」
(*99)構造用とは、建築物の耐力部材用途のこと。造作用とは、建築物の内装用途のこと。
(*100)財務省「令和5年分貿易統計」
(ウ)合板製造業
(合板製造業の概要)
合板は、木材を薄く剝いた単板を3枚以上、繊維方向が直角になるよう交互に積層接着した板である。狂い、反り、割れ等が起こりにくく強度も安定しており、また、製材品では製造が困難な大きな面材が生産できることから、住宅の壁・床・屋根の下地材やフロア台板、コンクリート型かた枠わく等、多様な用途に利用される。
我が国の合単板工場数は、令和5(2023)年末時点で、前年比9工場増の164工場であり、単板のみを生産する工場が27工場、普通合板(*101)のみが31工場、特殊合板(*102)のみが102工場、普通合板と特殊合板の両方を生産する工場が4工場であった(*103)。また、LVL(*104)(単板積層材)工場は3工場増の15工場であった(*105)。
(*101)表面加工を施さない合板。用途は、コンクリート型枠用、建築(構造)用、足場板用・パレット用、難燃・防炎用等。
(*102)普通合板の表面に美観、強化を目的とする薄板の貼り付け、オーバーレイ、プリント、塗装等の加工を施した合板。
(*103)農林水産省「令和5年木材需給報告書」
(*104)Laminated Veneer Lumberの略。単板を主としてその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着したもの。本報告書では合板の一種として整理。
(*105)農林水産省「令和5年木材需給報告書」
(合板の動向)
普通合板の生産量は、令和5(2023)年は前年比17.2%減の253万m3であった。このうち、針葉樹合板は全体の98.0%を占める248万m3であった。また、厚さ12mm以上の普通合板の生産量は全体の82.9%を占める210万m3であった。令和5(2023)年におけるLVLの生産量は23万m3であった(*106)。
用途別にみると、普通合板のうち、構造用合板が223万m3、コンクリート型枠用合板が2万m3等で、構造用合板が大部分を占めている(*107)。コンクリート型枠用合板では、製品輸入が大きなシェアを占めており、国産材利用の拡大が課題となっているが、海外における丸太輸出規制等の影響により、合板の原料をスギ、カラマツ、ヒノキを中心とする国産針葉樹に転換する動きがみられる。
令和5(2023)年における合板製造業への原木供給量は前年比22.7%減の414万m3であった(*108)。このうち、国産材は前年比20.4%減の391万m3、輸入材は前年比48.5%減の23万m3であった。国内の合板生産における国産材割合は上昇傾向で推移しており、令和5(2023)年は94.5%であった。国産材のうち、スギは55.3%、カラマツは18.7%、ヒノキは15.9%、アカマツ・クロマツは3.9%、エゾマツ・トドマツは5.1%であった(*109)。
製品での輸入量は前年比25.3%減の334万m3であった(*110)。製品輸入を含む合板用材需要量全体に占める国産材割合は⾧期的には上昇傾向にあり、令和5(2023)年は52.3%であった(資料3-42)。
(*106)農林水産省「令和5年木材需給報告書」
(*107)農林水産省「令和5年木材需給報告書」。コンクリート型枠用合板の数値は、月別調査でのみ調査実施しており、12か月分の合計となる。
(*108)LVL分を含む。
(*109)農林水産省「令和5年木材需給報告書」。LVL分を含む。
(*110)数値は丸太材積に換算したもの。
(エ)木材チップ製造業
(木材チップ製造業の概要)
木材チップのうち、原木や工場残材等を原料とするものは、主に製紙用や燃料用として利用される。一方、廃材等を原料とするものは、主にボイラー等の燃料及び木質ボードの原料として利用される。我が国の木材チップ工場数は、令和5(2023)年末時点で、前年比9工場増の1,119工場であった。このうち、製材又は合単板工場等との兼営が792工場、木材チップ専門工場が327工場であった(*111)。
(*111)農林水産省「令和5年木材需給報告書」
(木材チップの動向)
木材チップ工場における木材チップの生産量(*112)(燃料用チップを除く(*113)。)は、令和5(2023)年は前年比0.3%減の526万トンであった。原材料別の生産量は、原木は前年比1.4%増の241万トン(生産量全体の45.9%)、工場残材は前年比3.5%減の208万トン(同39.6%)、林地残材は前年比2.2%減の5万トン(同0.9%)、解体材・廃材は前年比3.4%増の72万トン(同13.7%)であった。
原材料のうち、木材チップ用原木の入荷量(燃料用チップを除く。)は、令和5(2023)年は前年比5.5%増の447万m3であり、そのほとんどが国産材であった。国産材のうち、針葉樹は285万m3(63.8%)、広葉樹は162万m3(36.2%)であった。国産材の木材チップ用原木は、近年では針葉樹が増加し、広葉樹を上回っている(資料3-43)。
一方、木材チップの輸入量(*114)(燃料用チップを含む。)は、令和5(2023)年には前年比1.7%減の1,112万トンであり、木材チップの供給量(*115)に占める輸入の割合は67.9%であった。
(*112)農林水産省「令和5年木材需給報告書」
(*113)燃料用チップについては、第2節(3)167-168ページを参照。
(*114)財務省「令和5年分貿易統計」
(*115)木材チップ生産量526万トンと木材チップ輸入量1,112万トンの合計。
(オ)パーティクルボード製造業・繊維板製造業
(パーティクルボード製造業・繊維板製造業の概要)
パーティクルボード(削片板)、繊維板(ファイバーボード)等の木質ボードは、建築解体材、工場残材(*116)、間伐材、林地残材等を原料としている。
パーティクルボードは、細かく切削した木材に接着剤を添加して熱圧した板製品である。遮音性、断熱性及び加工性に優れることから、家具や建築用に利用されている。
繊維板は、原料を繊維化してから成型した板状製品である。密度によって種類があり、高密度繊維板(ハードボード)は建築、こん包、自動車内装等に、中密度繊維板(MDF(*117))は建築、家具・木工、キッチン等に、低密度繊維板(インシュレーションボード)は畳床(たたみどこ)等に利用される。
(*116)製材業や合板製造業等において製品を製造した後に発生する端材等。
(*117)Medium Density Fiberboardの略。
(パーティクルボード・繊維板の動向)
令和5(2023)年におけるパーティクルボードの生産量(*118)は前年比5.0%減の94万m3、輸入量(*119)は前年比30.5%減の24万m3であった。
令和5(2023)年における繊維板の生産量(*120)は、前年比13.2%減の62万m3であった。
(*118)経済産業省「2023年生産動態統計年報」
(*119)財務省「令和5年分貿易統計」
(*120)経済産業省「2023年生産動態統計年報」における「繊維板換算値合計」。
(カ)プレカット製造業
(プレカット材の概要)
プレカット材は、木造軸組住宅等を現場で建築しやすいよう、柱や梁(はり)、床材や壁材等の継手や仕口といった部材同士の接合部分等をあらかじめ一定の形状に加工したものである。
(プレカット材の動向)
プレカット加工率は上昇しており、令和5(2023)年には、木造軸組工法におけるプレカット加工率は95%に達している(*121)。
プレカット工場における材料入荷量は、令和5(2023)年は平成30(2018)年比27.1%減の560万m3で、その内訳は、国産材が246万m3(43.9%)、輸入材が314万m3(56.1%)であった。材料入荷量のうち、人工乾燥材は270万m3(48.2%)、集成材は244万m3(43.6%)であった(*122)。
(*121)一般社団法人全国木造住宅機械プレカット協会「プレカットニュース Vol.115」(令和7(2025)年1月)
(*122)農林水産省「令和5年木材流通構造調査報告書」
(キ)木材流通業(*123)
(木材流通業の概要)
木材流通業者は、地域内又は地域をまたいで木材産業の川上・川中・川下をつなぎ、原木や木材製品への多種多様な需要に応ずる事業者で、木材市売市場や木材販売業者等がある。
木材市売市場は、原木市売市場(*124)と製品市売市場に区分できる。原木市売市場は、主に原木の産地に近いところに立地し、素材生産業者等から原木を集荷し、製材工場等が必要とする規格(樹種、径級、品質、⾧さ等)や量に仕分けた上で、土場に椪積(はいづみ)して、セリ等により販売する。製品市売市場は、主に木材製品の消費地に近いところに立地し、自ら又は市売問屋が実需者のニーズに応じた木材製品を集荷し、セリ等により販売する。令和5(2023)年における木材市売市場の数は431事業所となっている。
木材販売業者は、原木又は木材製品を仕入れた上で、これを必要とする者に対して販売を行う。原木を扱う木材販売業者には商社等があり、素材生産業者等から原木を買い付け、製材工場等の実需者に販売する。また、木材製品を取り扱う木材販売業者には木材問屋や材木店・建材店等があり、製材工場等から直接、又は商社や市場等の様々なルートから製品を仕入れ、最終的には工務店やプレカット工場等の実需者に販売する。令和5(2023)年における木材販売業者の数は6,860事業所となっている。
(*123)木材流通業の数値は、農林水産省「令和5年木材流通構造調査報告書」による。
(*124)森林組合が運営する場合は「共販所」という。
(木材流通業の動向)
令和5(2023)年における原木市売市場の原木取扱量(*125)は1,009万m3、製品市売市場の製材品取扱量(*126)は268万m3、木材販売業者の原木取扱量(*127)は1,707万m3、製材品取扱量(*128)は645万m3であった(*129)。
同年に国内で生産された原木の製材工場等への入荷量のうち、素材生産業者等から製材工場等へ直接販売されたものは41.8%、木材市売市場等を経て販売されたものは31.0%、木材販売業者等を経て販売されたものは27.3%であった。
(*125)木材市売市場における素材の入荷先別入荷量の計。
(*126)木材市売市場における製材品の販売先別出荷量の計。
(*127)木材販売業者における素材の入荷先別入荷量の計。
(*128)木材販売業者における製材品の販売先別出荷量の計。
(*129)原木取扱量(入荷量)及び製材品取扱量(出荷量)のいずれも、木材販売業者間の取引も含めて集計された延べ数量である。
コラム 木材の価格形成に関する理解の醸成
木材価格には、製材品等の木材製品価格と素材価格、山元立木価格がある。概念的には、木材製品価格から製材加工や流通にかかるコストを減じ、素材1m3当たりの価格に換算したものが素材価格、素材価格から素材生産や流通にかかるコストを減じたものが山元立木価格と整理できる。
木材製品については、平成7(1995)年に発生した阪神・淡路大震災以降、住宅の品質・性能への要求が高まり、平成12(2000)年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されたこともあいまって、寸法安定性の高い製品を供給するための人工乾燥に必要な経費が増加した。また、品質の確かな製品を選別することにより、原料として入荷した丸太の量に対して製材品等として出荷できる製品の割合(製品歩留まり)が低下した。このように、製品加工コストが増加し、製品歩留まりが低下する一方で、令和2(2020)年までは、住宅需要の減少等を背景に製品価格が一定の水準で推移したことなどから、素材価格や山元立木価格も上昇しにくい状況にある。
このような中、我が国においては、地域によってばらつきはあるものの、立木の販売による森林所有者の収入に対して、主伐後の造林初期費用が高いことから、森林所有者の再造林意欲の減退、ひいては森林の多面的機能の発揮に支障を及ぼすことが懸念されている。
森林資源の持続性を確保し林業・木材産業を持続可能な産業とするためには、川下の木材需要を高め、川上においても適切な利益を確保することが重要である。また、素材生産が間伐主体から主伐主体に移行しつつある中、木材の販売者と購入者の双方が、再造林を含む森林の育成にかかるコストへの理解を深めた上で、木材価格が形成されることが重要である。
このため、林野庁においては、低層住宅に加えて、非住宅・中高層建築物における木材需要拡大の取組等を進めている。また、木材の価格形成に関する理解を促進するため、川上から川下までの幅広い関係者が参加する国産材の安定供給体制の構築に向けた需給情報連絡協議会の開催や、適正な価格形成を呼び掛ける資料の作成、公正取引委員会と連携した取引ルールの周知等に取り組んでいる。
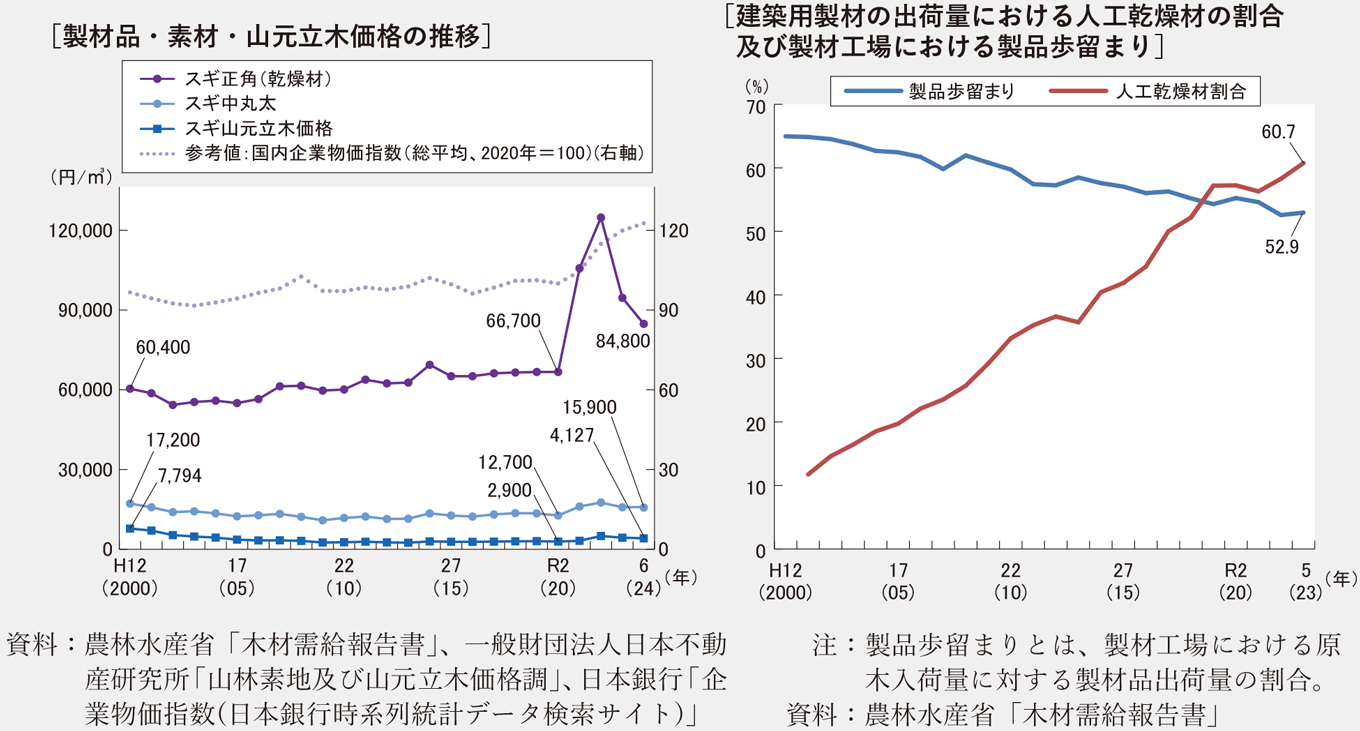
お問合せ先
林政部企画課
担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219










