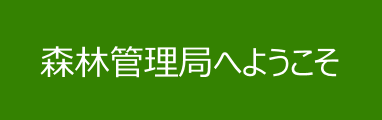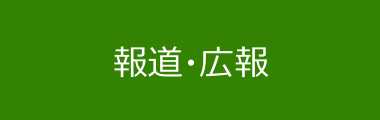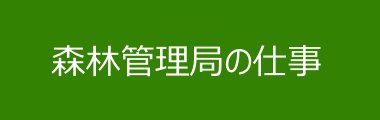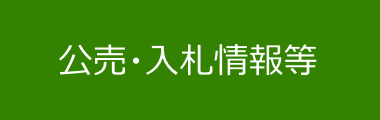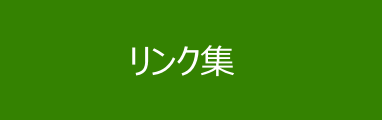「安全な伐木作業のための講習会」を開催しました
掲載日:令和7年7月4日
香川森林管理事務所
令和7年7月2日(水曜日)、香川県立農業大学校の教室をお借りして、「安全な伐木作業のための講習会」を開催しました。
香川県内では、ヒノキ人工林を中心とした森林資源の充実を背景に県産木材利用に向けた機運が高まっています。今後も、安定的な木材供給を担う現場従事者の皆様に安心して働いていただけるよう、林業・木材製造業労働災害防止協会(林災防)香川県支部及び香川県立農業大学校のご理解を得て、7月1日から展開されている全国安全週間における取組の一環として本講習会を企画したものです。
なお、本講習会は林災防香川県支部の令和7年度伐木時における労働災害防止のための集団指導会を兼ねて実施しています。
講習会には、林業事業体関係者、香川県立農業大学校林業・造園緑化コースの学生、香川・徳島両県の行政担当者のほか森林管理局署職員ら、69名の皆様にご参加いただきました。
本講習会では、まず、林災防 教育支援課 中国・四国地区担当 安全管理士の山本正晴氏から、林業労働災害の発生状況と傾向等についてご説明いただいた後、
林業の現場は他者の目が届きにくいため、安全のための基本的事項が守られない傾向が強い
作業者自身、現場責任者、林業事業体の幹部、外部(行政)の4つの視点からのチェックが必要
法令や災防規程に定められた基本的事項を遵守し、イレギュラーな作業方法を常態化しない
災害事例や現場でのヒヤリハット事例を共有し、危険予知能力を高めることが重要
といったお話をいただきました。
続いて、伐木技術に関する研究の第一人者であり、労働安全衛生規則の改正やチェーンソー特別教育用テキストの作成にも係わっておられる(国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 林業工学研究領域 主任研究員の上村巧氏から、「伐木の安全のために」と題してご講演いただきました。
油圧ショベルをベースマシンとする林業機械作業に当たっては、
履帯の向きと作業方向や旋回動作によっては、機械の安定性が変化し転落等の危険がある
ブーム・アームを伸ばし切った状態で持ち上げる能力はさほど大きくない
全木など長いものを扱う場合は、危険範囲が広くなる
オペレーターからは死角が多いため、接近・近接作業は注意する
ことなどをお話しいただいたほか、近年、災害が多発傾向にあると推測されるトップハンドルチェーンソーについては、
両手でしっかり保持して作業することが原則
特に、キックバックの発生に注意して作業する
といったことについて、アドバイスをいただきました。
また、伐木作業に関しては、
受け口の斜め切りと下切りは必ず一致させる
受け口深さは伐根直径の4分の1~3分の1
追い口高さは受け口の下切りより2.5センチ以上高くすることが望ましい
ツル幅は均等に、長さはなるべく長く設ける
といった基本の伐倒方法について、力学的な解析結果のアニメーションや実際の伐倒時の動画を例示いただきながら、わかりやすく解説いただきました。加えて、退避行動をとること、伐倒方法は樹種や木の状態などにより一様ではないため適切な伐倒方法を選択すること、起こりうるリスクを予知して備えることなど、知識に基づく応用力や総合的な技能の高さの重要についてもお話いただきました。
参加者からは、「写真や動画を交えた説明で、危険性が良く理解できた」「作業前のリスクマネジメントに活用したい」「年に一度はこのような講習会を開催していただきたい」といったご意見をいただいたほか、「繁忙期前の暑い時期に涼しい部屋での研修はありがたい」とのコメントも寄せられ、主催者が当初想定していなかった熱中症対策としても役立てていただけた模様です。
本講習会が、日々の作業に不安全要素が含まれていないかを振り返るきっかけとなり、皆様の今後の業務における安全意識の向上と労働災害の未然防止につながることを願っています。
なお、今回の講習会内容と同旨の講習会が、10月20日、21日の2日間、別途厚労省委託事業として企画されています。
詳細は下記ページをご確認ください。
令和7年度 厚生労働省委託事業
伐木等作業安全対策推進事業 チェーンソーを用いた伐木作業安全マニュアル安全対策講習会
|
林災防山本講師 |
森林総研上村講師 |
|
講習会の模様 |
|
お問合せ先
香川森林管理事務所
担当:森林技術指導官
ダイヤルイン:087-866-6622