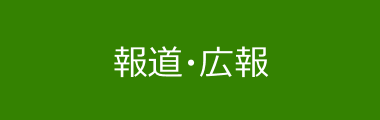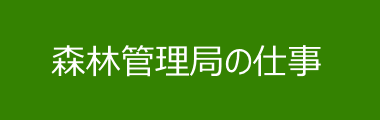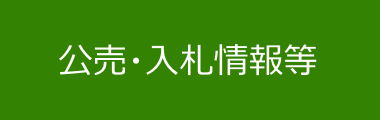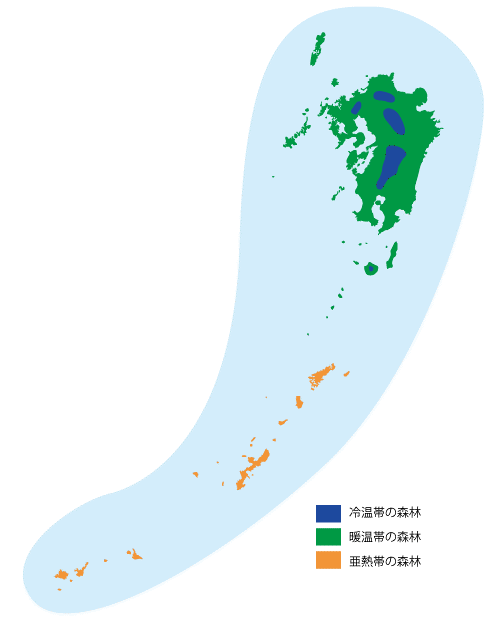九州・沖縄に広がる森林
|
九州・沖縄は、北緯25度から35度までの南北約1,200kmにわたる中・低緯度の温暖な地域に位置する一方で、標高1,000mを超える山岳地帯が連なっていることから、亜熱帯の森林、暖温帯の森林、冷温帯の森林の3つの森林帯が連なる世界でも珍しい地域です。 また、日本海流と対馬海流の二つの暖流や季節風がもたらす温暖湿潤な気候、急峻な地形等によって、シイ・カシ等からなる照葉樹林、ブナ・シラキ等からなる落葉広葉樹林、モミ・ツガ(針葉樹林)と広葉樹の混交林のような多様な森林が形成されています。 さらに、本地域は、気候帯が亜熱帯から温帯へと移行する地域に位置するため、両方の気候帯に属する生物が入り交じり、珍しい分布や生態系がみられます。 |
|
|
九州・沖縄の森林帯分布 「森林の百科事典」(丸善株式会社1996)より作成 |
暖温帯の森林
九州に広く分布する森林で、厚く光沢のある葉をもつ樹木からなる照葉樹林が分布。海岸付近から標高が上がるに従い、それぞれウバメガシ、シイ、カシを中心とした森林へ移行する。
|
|
|
|
|
綾の照葉樹林(宮崎県綾町) |
照葉樹林内(鹿児島県稲生岳周辺) |
海岸部の照葉樹林(長崎県対馬) |
冷温帯の森林
九州中央山地など標高の高い地域には、冬に葉を落とす落葉広葉樹林が分布。九州ではブナ、シラキが中心となっている。また、暖温帯との移行部にはモミやツガを中心とした常緑の針葉樹林も見られる。
|
|
亜熱帯の森林
西表、沖縄、奄美大島などの島嶼部を中心に分布しており、熱帯アジアから続く植生の北限であり、日本で最も豊富な種類の動植物が生息。暖温帯の構成種に加え、ヘゴ、ガジュマルなど本土とは異なる植物が生育している。淡水と海水が混ざる河口付近にはマングローブの森が広がっている。
|
|
|
|
|
マングローブ林(西表島) |
サキシマスオウノキの板根(西表島) |
木生シダのヒカゲヘゴ(奄美大島) |
人工林
木材生産を目的として、人の手で苗を植えて育てたスギやヒノキを中心とした森林。スギは日本の固有種で、九州では700年以上前から植林。海岸には防風・防潮林としてクロマツなどが植林されている。
|
|
|
|
海岸のクロマツ林 (虹の松原、佐賀県唐津市) |
スギ人工林(大分県湯布院町) |
お問合せ先
計画保全部計画課
担当者:生態系保全係
ダイヤルイン:096-328-3612