8月の日記
准フォレスター研修
林業専用道技術者研修
過去の日記
平成23月7月
森林・林業再生プランを実行する人材の育成
森林・林業再生プランのポイントは、戦後造成し、現在充実しつつある森林資源を有効に活用するとともに、無秩序な伐採の抑制や適切な更新を確保し、持続可能な森林経営を実現していくため、新たな森林計画を実効あるものとすることです。
そのためには、市町村森林整備計画の策定や森林経営計画(仮称)の認定・実行監理など森林計画制度の運用を現場で担う市町村を技術面から支援する新たな人材として、高度な知識・技術と豊富な実務経験を有するフォレスターの育成と活用が不可欠なものとなっています。
また、対象区域内の森林所有者をまとめ森林経営計画(仮称)を作成するキーパーソンになる森林施業プランナーや森林作業道を地形、地質等の現地の条件に応じて開設したり高性能林業機械を操作したりするオペレーターなどの現場の技術者・技能者の育成が不可欠となっています。
このような中、平成23年度以降、北海道森林管理局は、森林・林業再生プランを踏まえ、国有林野の多様な立地を活かして、北海道における森林経営のニーズに最も適した研修フィールドや技術を提供することなど集合研修(准フォレスター研修、林業専用道技術者研修)等を実施し、人材を計画的に育成していく予定です。
フォレスターとは
「フォレスター」は、市町村森林整備計画の策定支援を通じて、地域の森林(もり)づくりの全体像を描くとともに、市町村が行う行政事務の実行支援を通じて、森林所有者等に対する指導等を行う人材です。
フォレスターの育成には一定の期間を要するため、平成25(2013)年度からの資格認定を目指し、それまでの間は、「准フォレスター研修」を受けた者が市町村森林整備計画への支援業務を行うこととしています。
准フォレスター研修
准フォレスターとは、フォレスターが認定され本格的に始動するまでの間、都道府県職員や国職員等のうち森林計画制度に関する研修(准フォレスター研修)を受けた者を認定するものであり、市町村森林整備計画の策定等の支援業務を行います。
研修では、市町村森林整備計画の概要、市町村森林整備計画演習、路網と作業システム、路網線形計画、森林施業の集約化、森林経営計画の概要、森林経営計画作成演習、森林整備企画演習(路網整備等効率的な施業構想の策定)、森林施業における労働安全、木材流通・販売等の多岐にわたるカリキュラムを受講し、准フォレスターとして必要な知識と技術を習得します。
林業専用道技術者研修
林業専用道とは、森林づくりを進めていく上で欠かす事のできない路網づくりにおいて、幹線となる林道を補完し、森林作業道と組み合わせて、森林施業の用に供する道路をいい、従来の林道と比較して、地形に沿った屈曲線形及び波形勾配を採用して土工量の軽減を図り、簡素な構造を目指す新たな林道です。
研修では、林業専用道を作設していくために必要な知識、技術を講義、演習及び現地での検討等を通じて習得します。
関連情報リンク
|
准フォレスター研修(第1週・第2コース)
研修第2週に向けた課題の設定~5日目(平成23年8月5日)
准フォレスター研修第1週目の最終日は、第2週(10月24~28日)に向けた課題(宿題)の設定、目指すフォレスター像についての発表、一週間の振り返りなどを行いました。
第2週に向けた課題の設定
1講目は、昨日行った市町村森林整備計画の演習について振り返るとともに、研修第2週(10月24~28日)の中で行う「市町村森林整備計画作成演習」と「森林経営計画作成演習」に向けた課題(宿題)についての説明がありました。

研修生は次回までに、市町村森林整備計画演習については、演習の対象とする市町村を選び、図面などの資料を集め、森づくりの構想・木材生産方法・合意形成手法などの計画のたたき台の準備。
森林経営計画作成演習については「森林施業プランナー」との合同研修になることから、参加するプランナーと打ち合わせながら計画を立てる森林を選定し、その森林の計画図や森林簿などの資料を収集するなどの準備を行います。
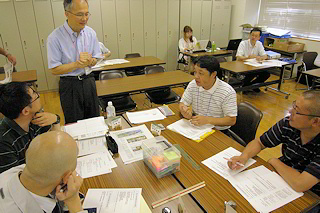
持ち帰っての「宿題」は、これまで数日かけて学んだ成果をもっての実践演習です。
課題の作成は、同じ地域に勤務する道と国の研修生がチームになって行うことになっており、職場に戻ってからの連絡調整方法などについても打ち合わせが行われていました。
普段は民有林の経営指導、国有林の管理運営といった異なる仕事をしている両者ですが、森づくりを進めて行く同士として、さらに連携が深まることが期待されています。
目指すフォレスター像について考える
(進行:プロセスマネージャー 山口氏)

2講目は、どのようなフォレスターを目指していくべきかについてグループ討論などが行われました。
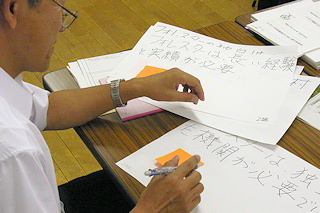
そして、グループ毎にとりまとめた「目指すフォレスター像」をフリップに書き込んでいきました。

作業が終わると、グループ毎に発表です。
「人々に夢を与えるフォレスター」、「地域に根ざして活動するフォレスター」、「地域に対して説明し理解を得ることのできるフォレスター」、いろいろなフォレスター像が発表され、その実現のためには「自己研鑽に励まなければならない」、「今までの仕事では木を育て、どのように伐っていくという事が中心だったが、今後は川上から川下まで、つまり木材の流通まで学んでいかなくてはならない」などの意見も出されました。

最後に一人一人5日間の感想や2週目に向けた今後の抱負などを発表しました。
「山を持っていて良かった」と思える環境作り。これができれば、山を売ってしまおうという人はいなくなる。みなさんと一緒にがんばっていきたい。
地域の林業経営や林産業、そして生物多様性の保全について勉強していかなければならない。
研修前はフォレスターになった後の事ばかり考え不安だったが、今回の研修でかなりの部分が解決できた。
職場に戻ってすぐに今回習ったことの実践が待っているが、非常に役に立つ内容だった。
グループ討議などでいろいろな情報や知見を共有でき、視野がかなり広がった。
研修生からはこのような声が多く聞かれました。
研修委員からの講評
研修の最後に研修委員からの5日間の講評をいただきました。

「提案型集約化施業」などの講師も務めていただいた石山委員(株式会社森林環境リアライズ専務取締役)からは、「今、我々が参考にしているドイツのフォレスターだが、ドイツも50年前は今の日本林業と同じような状況だったと聞いている。そのような中で、人材育成を進めて今のドイツ林業がある。
みなさんは日本の森林・林業再生を担う日本型フォレスター候補の第1期生である。いろいろな人たちとの関係を造り、そしてコーディネートしていく中心人物となってほしい」とのお話がありました。

「森林施業検討会」などの講師も務めていただいた酒井委員(東京大学教授)からは、「フォレスターの仕事は空間と時間のマネージメント。みなさんは時間軸の流れに責任を持つことになる。
フォレスターに求められるものは「想像力」。森林が5年後10年後どうなるのかという想像力を養うために日々、訓練を続けていくことが、森林・林業の明るい未来につながる」とのお話がありました。
第1週・第2コース閉講式

閉講式では、北海道森林管理局の平野計画部長から、「皆さんが職場に戻ると「市町村森林整備計画」の策定作業が待っていますが、その作業チームの中心となり、この研修の成果を存分に発揮していただきたい。また、第2週目に向けての研鑽に努めてもらうとともに、課題(宿題)の作成にあたっては、北海道の職員と国有林の職員が技術を持ち寄り、協力・連携する中からより良いものを作り出せるようがんばってほしい」との挨拶があり、5日間の研修を終了しました。
|
10月24日から始まる研修(第2週)では、市町村森林整備計画(案)によるワークショップ、木材の流通・販売、森林経営計画の作成演習などが行われる予定です。
研修日記は、引き続きこのブログで紹介していきます。
|
|
![]()
