![]()
ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 津軽森林管理署 > わぃはぁ通信 > 五所川原農林高等学校の現地実習について(7月27日)
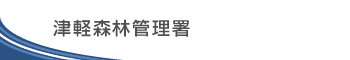
青森県立五所川原農林高等学校による現地実習は昨年度から実施しておりますが、今年度は7月14日と7月27日の2回実施しました。
今回は7月27日の様子をお知らせします。
7月27日の現地実習は、昨年度から引き続き実施されている、後長根沢治山工事(土石流対策)の遷移を見学し、治山工事の目的、対策、効果について勉強していただくことに加え、現在、効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを進めるための手法として注目されているコンテナ苗についても勉強していただくことにしました。
見学月日 平成27年7月27日(月曜日)
見学者 青森県立五所川原農林高等学校 森林科学科 1年生 30名 教諭3名
見学箇所 青森県弘前市大字百沢字東岩木山国有林33林班 後長根沢治山工事
青森県弘前市大字湯口字一ノ下がりやま87 種沢種苗園
見学にあたって、当署総括治山技術官、治山技術官より「後長根沢治山工事」の目的や概要、国有林の治山工事などについて説明し、その後、実際の工事現場を見学しました。
「後長根沢治山工事」の概要や工事経過については、「岩木山・後長根沢の土石流対策について」、「治山事業による岩木山・後長根沢の土石流対策について」をご覧ください。
 |
まずは、現在工事施工中の3号治山ダム工事現場に移動します。 当日は、この時期としては涼しく、さわやかな天候で、生徒のみなさんも気持ち良さそうに工事用道路を上っていきます。 |
 |
3号ダムの工事状況です。 コンクリート打設後、継ぎ増しするコンクリートとの付着性をよくするためのレイタンス(コンクリートや骨材に含まれる不純物)の除去を行った状態で、この後、残存式型枠を設置し、コンクリートを打設します。
|
 |
3号ダムの工事進行状況や工法について説明しています。 3号ダムは一番上流に設置されたダムですので、その上流には土石流の形跡が残されています。
|
 |
場所を2号治山ダムに移して、「治山ダムのできるまで」と題して、荒廃した渓間に治山ダムが完成するまでの作業順序を当署の治山技術官より説明しました。1年生には少し難しい説明かと思われましたが、真剣に聞いていただきました。 ちなみに、2号ダムは床堀作業中でした。 |
 |
2号ダムでは、工事に使用する機械を使用して、2種類の岩石を破砕する作業を見ていただきました。 同じような岩石でも簡単に割れる性質のものと、なかなか割れない性質のものがあることがわかりました。 この作業を見た生徒の皆さんは機械の凄さに驚いた様子で、中には、機械のオペレーターになりたいという生徒もいました。 |
 |
最後に昨年度完成している1号ダムに移動し、国有林で行われている治山事業について説明しました。 国有林の治山事業は治山ダムを設置するだけでなく、災害で崩れた山を森林に戻す事業や海岸防災林の整備など、様々な事業で国土の保全を行っていることなどについて実例を示しながら説明しました。 |
 |
当日、地元の新聞社2社が取材にきており、生徒代表に今回の現地実習について質問していました。 生徒代表は「土石流の現場は見たことがなく、自然災害の脅威に圧倒された。災害を防ぐ森林の機能があらためて分かった。自然と関わりながら人の命を守る仕事に就きたい」と将来の目標を掲げていました。 |
午後は弘前市湯口に所在する種沢種苗園に場所を移して、これからの林業に欠かせないものになると思われるコンテナ苗について勉強していただきました。
実習プログラムは次のとおりとして行いました、
1 コンテナ苗を見て触れてみる。
2 コンテナ苗を植えてみる。
3 コンテナ苗を作ってみる。
 |
まずはコンテナ苗について知ってもらうため、生徒の皆さんに実際にみてもらいました。 今回の実習で使用したコンテナ苗は岩手県の横田樹苗さんが、高校生の勉強のためであれば是非協力したいとの申し出があり、教材として、スギ、カラマツ、ヒノキのコンテナ苗とカラマツの幼苗、移植用に培土を詰めたコンテナ苗を送っていただきました、たいへんありがたいお話でした。 見てもらったのは、スギの普通苗とコンテナ苗です。スギの普通苗は種澤さんの苗畑にあったものをお借りしました。 コンテナ苗と普通苗では、根の部分が違うこと、このコンテナ苗の根鉢が植付する作業とどのように関係してくるのか、またこの根鉢を形成させるために専用容器のコンテナを使用していることなどについて実物を示しながら説明しました。
|
 |
次に実際にコンテナ苗の根鉢に触ってもらいました。 生徒の皆さんからは、「コンテナ苗の根鉢が予想したよりも堅く形成されている」「根鉢の根が下に真っ直ぐ伸びている」などの感想をいただきました。 |
 |
コンテナ苗を見たあとは実際にコンテナ苗と普通苗を植えて作業性の違いを実感してもらいました。 生徒の皆さんは入学してまだ3ヶ月あまりということで植付した経験がないことから、当署の総括治山技術官から普通苗の植付け指導を行ってから植付を行いました。 生徒の皆さんは慣れない唐鍬で土をおこし植付穴を掘っていました。 植付した場所は種沢種苗園の一部で行いました。 |
 |
次にコンテナ苗を植付けてもらいました。 コンテナ苗は植栽専用器具(ディブル)を植付ける場所に差し込み、少し穴を広げるだけで植付穴が完成します、その穴にコンテナ苗の根鉢を入れるだけで植付が完成します。 生徒の皆さんからは、「早くて簡単に植付できる」と言う感想をいただきました。 |
 |
当日は偶然に弘前地方森林組合の皆さんが種澤種苗園を訪れておりましたので、森林組合のみなさんにもコンテナ苗を植付けていただきました。 植付作業を行うと、コンテナで苗木を育て、一定の大きさの根鉢を形成させる意味がわかっていただけるものと思います。 |
 |
最後のプログラム「コンテナ苗を作って見る」です。
今回の実習に際して横田樹苗さんから培土を詰めたコンテナとカラマツの幼苗を送っていただいたこと、また、種澤さんでもコンテナと培土を準備していただいておりましたので、コンテナに幼苗を移植する作業を説明しながら体験してもらいました。
最初に、コンテナに培土を詰める作業です、種澤種苗の方に実際に作業をしていただきながら説明していきます。 培土を詰める時に注意することは、コンテナ全体に均一に土を詰めること、コンテナの中の培土を締め固めることだそうです。 コンテナを持ち上げて落とし、培土を加えるといった作業を数回繰り返します。 |
 |
コンテナに培土を詰めたら移植する穴を空けます、このあなを空ける道具は種澤さんのオリジナルで、150ccのコンテナの場合は1回で10穴空けることができます。 |
 |
移植するコンテナが完成したらいよいよ苗の移植です。 まず、先生が移植作業をしながら、生徒の皆さんに作業方法を教えています。 後で先生に聞いたところ「コンテナ苗の必要性は理解していたが、なかなか体験できる場面がなく、まず自分で植えてみたかった」とのことでした。
|
 |
いよいよ生徒の皆さんも作業開始です、すぐにコツがつかめたようで、楽しそうに移植しています。 移植した幼苗はカラマツの幼苗です、種澤さんオリジナルの移植へらを使って、苗の根の先端を移植穴の奥の方に押し込み、培土で埋めていきます。 |
 |
中には、一人で何本も移植する生徒もおり、「座ってできるので作業が楽」「根を押し込む作業が楽しい」との感想をいただきました。 移植するコンテナの数も少なかったことから、移植実習はあっという間に終了しました。
|
 |
移植したカラマツの幼苗です。 今回生徒の皆さんが移植したコンテナは学校に持ち帰っていただき、育ててみることになりました。 |
今回は、森林科学科の1年生ということで、入学してから3ヶ月あまりの生徒の皆さんでしたので、治山工事、種苗事業を見たことがない生徒がほとんどで、理解するのにたいへんだったと思います。
実習後に生徒のみなさんには、国民の皆様が安心して安全に暮らせるように、森林の持つ様々な機能を十分に発揮させることが森林管理署の仕事であることを説明し、森林管理署の仕事に興味を持っていただき、是非、将来の進路として森林管理署を考えていただきたいとお願いしました。
五所川原農林高等学校森林科学科では、平成28年の春からコンテナ苗の育苗実習を行いたいとのことで、この実習については、津軽流域林業活性化センターが中心となり、青森県産業技術センター林業研究所、種沢種苗園など関係者の協力を得ながらすすめることにしております。今後の活動を楽しみにしていただきたいと思います。
今回の現場実習が生徒の皆さんの今後の進路に少しでも役立っていただければありがたいと考えております。また、今後もこのような現場実習を継続していきたいと考えております。
![]()
津軽森林管理署
ダイヤルイン:0172-27-2800
FAX:0172-27-0733