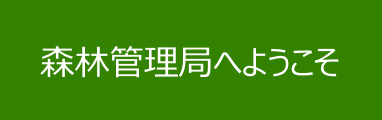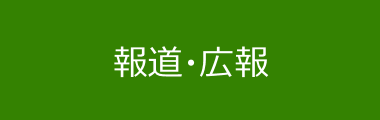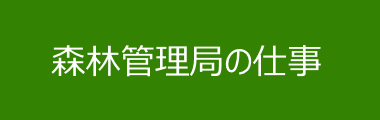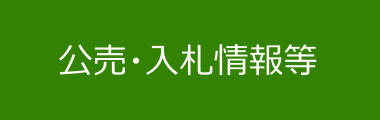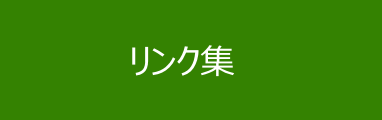プレスリリース
電子版「木曽式伐木運材図会の解説」等の発行について
|
|
「木曽式伐木運材図会の解説」等については、以下のURLをクリック!
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/koho/kisosikibatuboku.html
1.「木曽式伐木運材図会の解説」について
中部森林管理局が所蔵する絵巻「木曽式伐木運材図会」につきましては、年間を通して、教育関連の出版社やテレビ番組制作会社などから取材や画像使用の依頼があるところです。
この資料に関して、さらに広く知っていただくため、当局広報誌「中部の森林」において「木曽式伐木運材図会の解説」の連載を令和2年5月から令和3年4月まで1年間で、12回掲載しました。今回この連載に大正~昭和初期の古写真を追加し、小冊子(電子データ版)としてまとめました。
2.昭和29年発刊「木曽式伐木運材図会」について
同図絵については昭和29年に長野営林局(現中部森林管理局)が発刊した解説本がありますが、現在絶版となっており再販する予定もないことから、今回スキャニングにより、電子データ化し公開しました。
〈参考〉
中部森林管理局が所蔵している「木曽式伐木運材図会」は、江戸時代後期頃の木曽地方や飛騨地方で行われていた伐木・運材の技術についての絵巻物二巻からなっています。
奥山で大木を伐採するところから、造材、搬出・集材、木曽川でのいかだによる流送、熱田白鳥貯木場(愛知県名古屋市)での集積、大型船による海上輸送までの工程が、作業順に図絵と詞書(ことばがき)で説明されています。
本「図会」の作者、製作時期、製作目的、中部森林管理局に保管されている経緯等については、それらを明らかにする文献等が見つかっていないことから明確ではありませんが、現在の岐阜県高山市で江戸時代後期に製作された図絵をオリジナルとし、林業・木材産業に関する博覧会への出展や皇族・政府高官などへの説明用として、明治時代に製作されたものであろうと推測されています。類似の絵図や版画が複数存在しますが、本「図会」は、これらの中で最も丁寧に描き込まれ、豪華につくられた最上級の美品となっています。
|
|
|
| 実物の絵巻物2巻 | 絵巻物を広げた様子 |
※「木曽式伐木運材図会」は、一般公開は行っていません。
「木曽式伐木運材図会」のサイトにある画像を使用したい場合には、「木曽式伐木運材図会使用申請書」の提出が必要です。