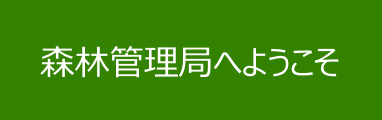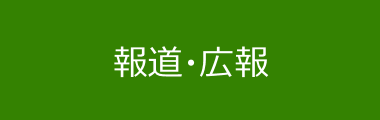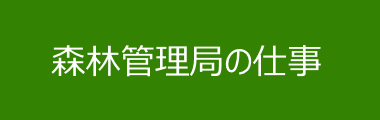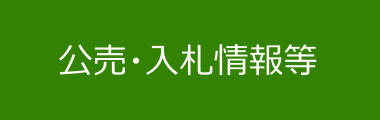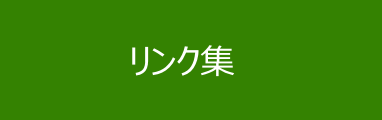2025年1月20日(193号)
中部森林管理局メールマガジンでは、広報誌「中部の森林」の記事を基に、国有林で行われている森林づくりに関する様々な話題をはじめ、管内各地からのお便りなど、森林・林業に対しご関心をお持ちの皆様方に情報を提供させていただいております。
また、ご購読いただきました皆様方からのご意見やご要望などを事業の参考にさせていただきます。
さて、今回のメールマガジンですが、中部森林管理局次長(名古屋事務所長)からのメッセージなどを記載しています。
最後までお読みいただければ幸いです。
INDEX
1.森林管理局からのメッセージ
2.広報「中部の森林」1月号(第250号)
3.公売・入札情報
☆編集長だより
1.森林管理局からのメッセージ
「森林の所有区分から見えてくるもの」 中部森林管理局次長(名古屋事務所長)井口真輝
あけましておめでとうございます。
新年早々、型苦しいタイトルで読む気がしないって?まあ、そうおっしゃらずに、しばらくお付き合いください。
林野庁の出先機関である森林管理局・署では、森林面積の3割を占める国有林を管理しています。これ以外の森林は民有林と呼ばれ、その内訳は、地方公共団体が所有する公有林が1割、個人・会社などが所有する私有林が6割となっています。んっ? 民有林の中に公有林が含まれている・・・。これって、ちょっと変じゃない?
永田信氏が著した「林政学講義」によると、次のように説明されています。明治時代になって間もない頃、当時の政府は地租改正によって土地(森林)と所有者を紐づけする必要が生じました。税金をキッチリと納めてもらうためです。これにより、従来の幕藩有林は官有地(国有林)に、有力武士や豪農の山は民有地第一種となり、薪などを採取する山として集落ごとに共同利用していた入会林(いりあいりん)については、民有地第二種として区分されました。このとき、利用実態を証明できず官有地に区分されてしまった入会林も少なくなかったようです。
その後、市町村制の施行により、いくつかの集落が合併して行政区としての市町村となるのですが、その際、入会林の多くは市町村に引き継がれました。また、一旦官有地になったものの、あらためて利用実態が証明できた箇所については下戻しが認められ、一部は県有林などになりました。お気づきでしょうか。公有林が民有林の一部として区分されているのは、このような経緯があるからです。
今回焦点を当てた入会林は、かつて農山村地域では生活に不可欠な資材を採取する森林として各地で見られましたが、戦後、化石燃料や化学肥料の普及などにより大きく減少しました。また、本来の利用目的が失われた入会林は、そのまま放置すると荒れてしまいますので、権利関係を整理した上で、個人に分割したり、生産森林組合などに移行したりしました。しかしながら、いずれの場合も社会情勢の変化などにより、以前のような形での地域住民と森林との関わり方は随分と希薄となりました。
けれども、こうした流れの中で森林が持っている様々な機能が失われたわけでも、変わったわけでもありません。私たちは、今でも様々な森の恵みを享受し、また大きく依存しています。ですから、森林所有者が誰になったとしても、これらの機能がきちんと発揮されるよう所有者は一定の管理をしなければならないのは言うまでもありません。このことは、森林に関する根本の法律である森林・林業基本法にも謳われています。
国有林を管理する中部森林管理局・各署では、今後とも利用と保全の両立を図りながら森林を適切に管理経営し、健全な状態で将来に引き渡していけるよう取り組んでまいります。
読者の皆さまには、本年も引き続きの応援をいただきますよう、よろしくお願いします。
2.広報「中部の森林」1月号(第250号)
各地からの便りなどを掲載しています。
シリーズ「私の森語り」、「今は昔の林業」なども掲載中です。
年頭のご挨拶
【各地からのたより】
〇森林ボランティア・NPO連携推進会議を開催
〇近隣市町村職員に向けた無人航空機操作講習会を開催
〇地域住民を対象とした治山見学会
〇小林式誘引捕獲法の現地検討会
〇木曽ヒノキが繋ぐ木の文化
〇こども園で森林教室を開催
【シリーズ】
〇中部の保護林【西岳・フウキ沢ヤツガタケトウヒ希少個体群保護林】
〇「森林官からの便り」【北信森林管理署 水内森林事務所 森林官 古田 誠】
〇「私の森語り」【名古屋学院大学 現代社会学部 教授 今村 薫】
〇「秘蔵写真・今は昔の林業」【「裏木曽」その九】
〇「木曽悠久の森」管理委員会を開催
〇「木曽悠久の森」設定10周年記念シンポジウム開催のご案内
☆詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/koho/koho_si/index.html
3.公売・入札情報
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/index.html
中部森林管理局では、より多くの事業者の皆さまに入札情報をお届けするため、中部森林管理局及び森林管理署が発注する各種工事や、造林事業、素材生産事業、物品等の調達情報についてのメールマガジンを毎週水曜日に配信しています。
ご登録をお願いいたします。
☆メールマガジン「調達情報」のご登録はこちらから
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/koho/mailmaga/tyoutatuzyouhou.html
過去の中部森林管理局メールマガジン「中部の森林」はホームページからもご覧いただけます。
★中部森林管理局メールマガジン「中部の森林」バックナンバーはこちらから
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/koho/mailmaga/backnumber/index.html
編集長だより
明けましておめでとうございます。お正月にはおせち料理、年末は黒豆・田作り・数の子・紅白なます・松前漬け・筑前煮・ぶりの照り焼きなどの準備に勤しみました。それぞれの食材に縁起を担ぐいわれがあり、買うにせよ作るにせよ、習わしとして、年初を祝う気持ちとともに大切にしたいと思います。
近くの神社では材料確保と技術の伝承が困難となり、しめ縄飾りが全て合成繊維製となりました。しめ縄づくりの技術としては継承されていても身近とは言えなくなる、おせち料理もいずれ同じようになる(すでになっている?)のでしょうか。
巳年は新たな挑戦や変化に前向きになる年だそうです。どんな年にするかは自分次第!今年もどうぞよろしくお願いします。
★中部森林管理局メールマガジン「中部の森林」バックナンバー https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/koho/mailmaga/backnumber/index.html
♢メールアドレス等の配信変更はこちら↓↓
https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
♢メールマガジンの配信解除はこちら↓↓
https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/can.html
このメールマガジンの登録及び購読は無料です。
お問合せ先
中部森林管理局 総務課広報
〒380-8575
長野県長野市大字栗田715-5
MAIL:migoro@maff.go.jp
URL:https://www.rinya.maff.go.jp/chubu