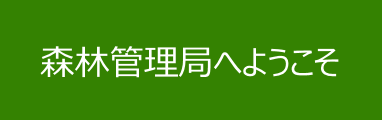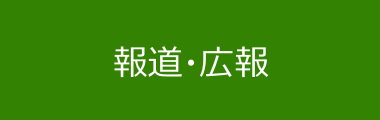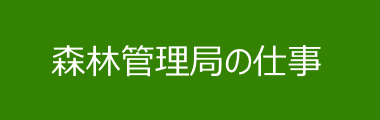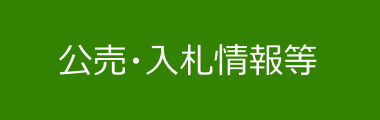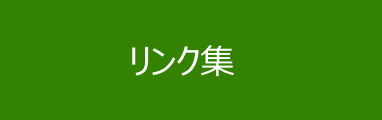国土を守る治山事業
治山事業は、森林の維持造成を通じて山林に起因する災害から国民の生命・財産を保全すると共に、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る極めて重要な国土保全施策の一つです。由利森林管理署における治山事業
由利森林管理署では以下のような治山事業を行っています。防災林造成事業
海岸防災林造成事業
海岸防災林は海岸からの飛砂や強風から人家や農地等を守るためのものです。
当署管内においても、由利本荘市の水林海岸、西目海岸、田尻海岸といったクロマツを中心とする海岸防災林が存在し、長年、海岸からの強風や飛砂から人々の生活を守ってきました。
ところが、当署の海岸防災林でも、全国で問題となっていたマツクイムシの被害(マツ材線虫病)が、昭和58年頃に確認されるようになりました。そのため、被害木の伐採や薬剤処理を行い被害の拡大防止に努めていましたが、豪雪や台風により、松食い虫被害で弱った海岸防災林は甚大な被害を被りました。
そこで、当署では、治山事業における海岸防災林造成事業により、海岸防災林の復旧・再生を行っています。
また、私たち森林管理署だけでなく、市民の皆さんの参加も得ながら、身近な自然を守っています。
 |
○海岸防災林の育成 |
| 本数調整伐 海岸のクロマツは山に植えるスギなどに比べて密に植栽します(スギが1ヘクタールあたり3000本なのに対してクロマツは1万本を植栽)。 そのため、一定の生長過程で、生育の悪いものなどを間引く作業は健全な海岸防災林造成には不可欠です。 |
|
 |
○海岸林を守る |
| 木製防風柵設置工 主に冬季の日本海から海岸へ吹き付ける強い季節風から植栽したクロマツを保護します。この防風柵に守られたクロマツがやがて、強い季節風から後方の住宅や農地等を守ります。 |
|
 |
県立矢島高等学校の生徒さんによる林業体験 当署職員から森林や海岸林の意義について説明を受けた後、水林海岸のクロマツ林の本数調整伐を行ってもらいました。 今自分たちが行っている作業が、数十年、もっと先の未来の人たちの生活を守ることになるかもしれないと説明を受け、生徒の皆さんも、一所懸命に作業しました。 |
なだれ防災林造成事業
なだれ防災林造成事業は、主に山腹急斜面において発生するなだれを抑止し、直下の人家や道路、農地等を守るためのものです。当署では秋田県由利本荘市鳥海町において、なだれ防止柵を設置しました。
 |
○雪から生活を守る |
| なだれ防止柵工 毎年のように発生するなだれが、雪と一緒に土砂を削り、直下の農業用水路を埋めてしまったり、農地に土砂や雪が堆 積し農作業に支障を生じさせていました。 当署では、それを防ぐためのなだれ防止柵を設置し、雪や土砂による被害を抑止しました。 |
渓間工
渓流の浸食を防止することにより、土石流等から下流に位置する人々の生活を守るとともに、荒廃した森林を復旧し、水源のかん養など多様な森林の機能の発揮を図ります。
 |
○渓流を保全する |
| 山腹崩壊などで土石が渓流に流れ込んだり、渓流の傾斜が急すぎると、土石が渓流の岸や川底を削り、さらに大量の土石が発生することとなったり、場合によっては、新たな山腹の崩壊を引き起こすことになります。 そのため、治山ダムを築き、渓流の土砂の動きを止め、山腹を安定させます。 それが長い目で見ると、荒廃した森林の復旧に資することになります。 |
山腹工
融雪や豪雨等により崩壊した山腹(山の斜面)を放置すれば、被害が拡大し、やがて渓流に土石等が流下し、下流に住む人々の生活にも被害を及ぼす恐れがあります。そのため、山腹工事を施し、速やかに森林への復旧を図ります。
 |
○被害の拡大を未然防止 |
| 融雪、豪雨により、山腹が崩壊し、直下の渓流に大量の土砂が流れ込んでしまった現場です。 放置しておけば、この崩壊地から、さらに新たな崩壊が発生し、下流の農地等に被害を招く恐れがありました。 |
|
 |
法枠工による緑化 山腹面上部の不安定な部分を掘削し安定させ、その上で崩壊面を、法枠工という工法により固定します。枠の内側は工事用の種子を用いて早期に緑化することとし、それにより新たな災害が発生しにくいようにしました。 最終的には、周りから樹木が法枠工の中に侵入し、周囲の森林と区別がつかないようにするのが目的です。 |
山地災害危険地区について
お問合せ先
林野庁 東北森林管理局由利森林管理署
〒 015-0885 秋田県由利本荘市水林439
TEL : 0184-22-1076