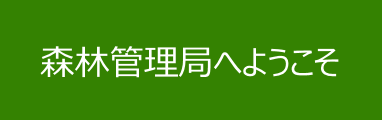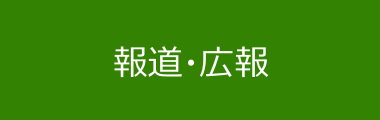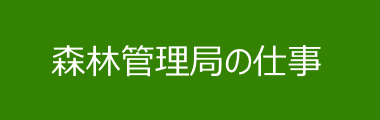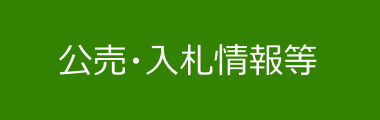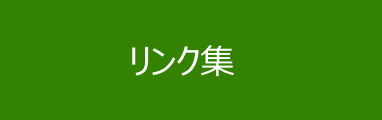【ヒバに携わる人】建築(寺社・住宅):角野勝德さん、恭平さん
 |
角野建築・建築工房 角野 勝德 さん 木の個性を活かした建物づくり 青森県むつ市で一般家屋や社寺仏閣の建築業を営み、ヒバを用いた社寺仏閣を建築・修復も精力的に行う。左の写真は作業中の恭平さん。 |
ヒバの特産地である青森県内各地では、昔はヒバを扱う大工が数多くいました。しかし、ヒバが以前より貴重になってしまったことや安定的に入手が可能なプレカット材の流通が増加したことによりヒバを扱う大工の数もめっきり減ってしまいました。
そんななか、角野さんはヒバを用いて社寺仏閣の建築・修復を行う青森県でも数少ない大工の一人として、青森県むつ市でお仕事をしています。
木はそれぞれ育った環境やそれぞれが持つ形質により、人と同様に個性を持ち合わせています。例えば斜面に生えている木は太陽の向きにまっすぐ伸びるため根元が曲がってしまいます。その部分は木の形状が曲がってしまうだけでなく、一度加工したあとも乾燥などによって変形してしまうこともあるため、一般的には使うことが難しく敬遠されます。しかし、角野さんは「あて木(ひねくれているもの)もあるが適材適所だ」と言い、そんな“ひねくれているもの”も曲線が必要な箇所の部材に上手に使っています。
築170年の神社ともなると、柱の表面は年月の経過によって色あせてしまいます。そんな柱も、少し表面を削ると新しい木材に遜色のないきれいな木肌があらわれます「これは職人の手による優れた技術のお陰だ」と角野さんは言います。
木材表面の組織に傷がついてしまうと、木材の外から水が入り、防腐性のあるヒバの揮発油成分も外にでていきやすくなります。しかし、木材表面の組織をつぶさないような上手なかんながけをすることで、木材を長持ちさせることができます。「部材は上手にかんながけして上手に使えば、100年以上たっても、何度でも使い続けることができ、ヒバは他の材よりも値は張るがそれだけの価値のある木だ」と角野さんは言います。現に一度解体したヒバの部材を社寺材として使い直すこともあるそうです。
 材の曲がりが活かせる使い方を考える。写真に写っているのは角野さんと長年関わりの深い宮大工の道地則之さん。 |
 年月の経過で色あせた部材(中央)も、優れたかんながけをすることできれいになる。 |
ヒバを用いて建てられた数多くの社寺が今でもその姿をとどめているのは、ヒバ本来の丈夫さに加えて、宮大工により守り続けられた技がヒバのもつ個性や持ち味を活かしているからではないでしょうか。
お問合せ先
下北森林管理署
ダイヤルイン:0175-22-1131